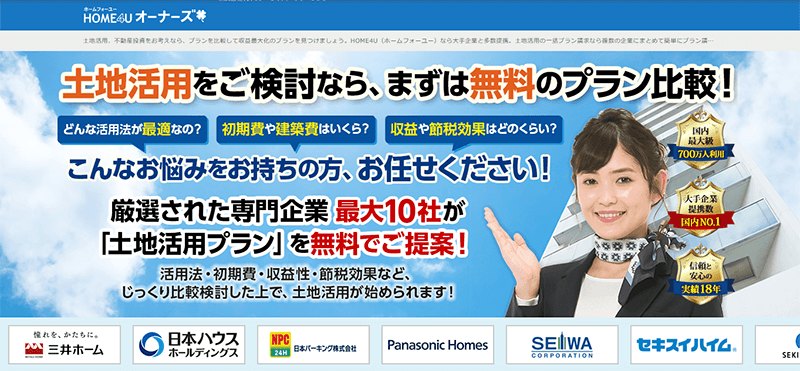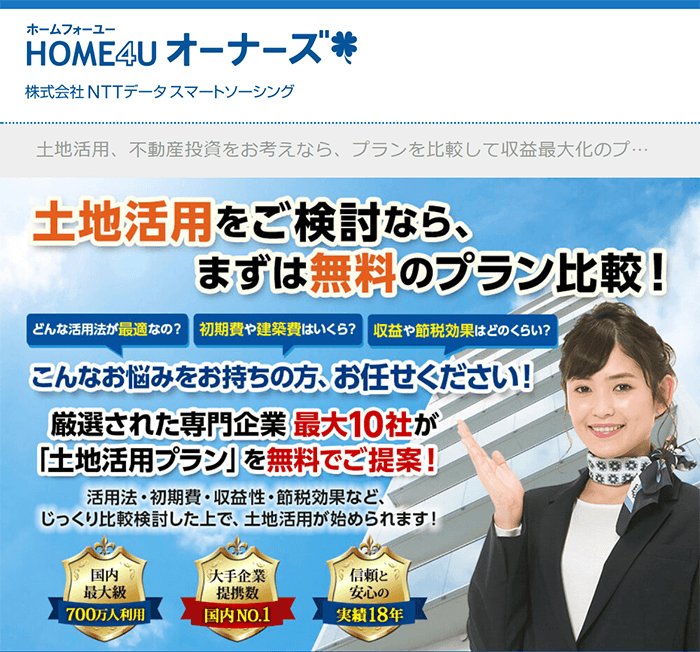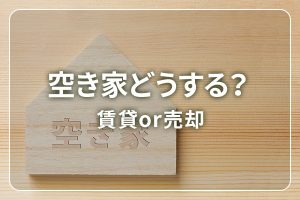ビル建築に向いている土地条件は3つあります。
- 都心部にある
- 駅から近い・大通りに面している
- ある程度の土地面積がある
それぞれの土地条件に向いている、ビル建築のタイプ(種類)は以下のようになります。
| 都心部にある |
|
|---|---|
| 駅から近い・大通りに面している |
|
| ある程度の土地面積がある |
|
この記事では、ビルの建築費の目安や、各ビル建築の費用規模、難易度などを解説します。
ビル建築について、向いている土地かどうかも直接プロに相談したい方は、以下のボタンから簡単に土地活用プランの請求ができます。ぜひご利用ください。
ビルの建築費用を計算するには?
ビルにはどんな種類がある?
この記事では、代表的なビルのタイプを4種類紹介し、それぞれの難易度も解説しています。
- 商業系ビル
- オフィス系ビル
- 賃貸住居系ビル
- 介護・保育・メディカル系ビル
詳細は「おすすめビル建築4タイプ 難易度別土地活用方法」をご一読ください。
ビルの運営方法は?
目次
1.ビル建築費用の算出方法と目安
ここではビル建築費用が、具体的にいくらなのかをご紹介します。
1-1.ビル建築費用の算出方法
ビルの建築費用の算出方法には、以下のような方程式があります。
・(ア)延べ床面積(のべゆかめんせき)
延べ床面積とは、建てたビルの広さの合計のことです。
例)6建てビルを建築する予定 1~6階までが全く同じ形のビルの場合
ワンフロアが100坪だった場合は、100坪の6階分で600坪の延べ床面積になります。
・(イ)坪単価
坪単価とは、1坪当たりにかかる建築工事費用のことです。
この金額には資材や人件費など工事をする際にかかる費用のおおよそが含まれています。
ビル建築の場合、以下のビル建築の3種の構造タイプから、建築したいビルのタイプ・規模・利用目的によって専門家が建築方法を判断して設計プランにして提案したものをオーナーが選択します。
【ビル建築 3種類の構造タイプ】
- S造(鉄骨造)
-
SはSteel、鉄骨のことです。柱や梁などの骨組に鉄骨を使用しています。普通の木造の柱をそのまま鉄にしたイメージです。
S造には重量鉄骨造と軽量鉄骨造の2種類があり、鋼材の厚みが6mm以上のものを「重量鉄骨構造」、6mm未満のものを「軽量鉄骨造」と言います。重量鉄骨はビルや高層マンションなどの大規模なビル建築に使い、軽量鉄骨は一般住宅や小規模店舗などに使っています。
- RC造(鉄筋コンクリート造)
-
Reinforced Concreteの略で、「鉄で補強(Reinforced)されたコンクリート」構造です。鉄筋を組んだ型枠の中にコンクリートを流し込んで固め、建物の柱や梁、床・壁を作ります。
縦横に張る力は強いがサビやすく熱に弱い性質を持つ鉄と、縦横に張る力は弱いが熱や寒冷差に強いコンクリートの良いとこ取り構造のため、耐久性・遮音性・耐震性が高く、日本ではほとんどのマンションでこの構造が採用されています。
- SRC造(鉄筋鉄骨コンクリート造)
-
Steel Reinforced Concreteのことで、鉄骨で作った柱の周りに鉄筋を組み、そこにコンクリートを打ち込んだものです。
大型マンションや高層ビルなどの大規模な建物に使われます。最も耐火性・耐震性が高いため、10階以上のビル建築で採用されます。
1-2.ビル建築費用の目安
ビル建築における構造別の「坪単価」は次の通りです。
| 構造 | 実際の坪単価相場 |
|---|---|
| S造(鉄骨造) | 約107.2万円 |
| RC造(鉄筋コンクリート造) | 約106.7万円 |
| SRC造(鉄筋鉄骨コンクリート造) | 約107.1万円 |
出典:国土交通省「最新版建築工事費デフレーター」
建築着工統計調査 工事費予定額
たとえば、以下の条件での建築費を算出してみましょう。
条件:ワンフロアが100坪 6階建てビルを建築予定
(ア)ビルの延べ床面積 600坪
(イ)構造 SRC構造平均坪単価 107.1万円
約6億4,260万円=(ア)600×(イ)107.1万円
あなたがお持ちの土地にどのくらいの規模のビル建築が出来るものか、ビル建築ではどのような構造を選ぶべきなのか等は、プロに聞いて確認してみるのが一番です。
NTTデータグループが運営する「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」を使えば、ビル建築設計プランに強い会社に一括プラン請求できます。TVCM等でおなじみの大手企業を中心に最大10社まで選択が可能です。
なるべく多くの企業のプランを比較して、あなたの土地に最適なプラン、信頼のできるパートナーを見つけてください。
具体的なビル建築費について知りたい方は「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」を使えば、最大10社から無料で建築プランが手に入れられます。
2.おすすめビル建築4タイプ 難易度別土地活用方法
- 商業系ビル
- オフィス系ビル
- 賃貸住居系ビル
- 介護・保育・メディカル系ビル
2-1.商業系ビル
ビルの中に、オフィス(事務所)タイプ以外のテナントを入れるタイプです。
| ビルの種類 | 収益性の高さ | 初期投資額の多さ | ビル経営の難易度 |
|---|---|---|---|
| 商業ビル(雑居ビル) | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| ロードサイド店舗 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ |
| 駅前商店街ビル | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ |
2-1-1.商業用ビル(雑居ビル)
都心部の駅前で、有名な繁華街にあるような、ビルの中にいろんなタイプの業種が入っているビルです。
都内または都心部の一等地と呼ばれる場所であれば、1階部分には有名なブランド店やファッション店の入店が期待できます。地方都市は駅前であれば大手のパチンコ・カラオケ・居酒屋・消費者金融などが入店します。
家賃設定を高くできるため、収益性は高いといえます。ただし、初期費用は多くなる傾向があります。また、相当に立地条件が良くないと、テナントの入れ替わりが激しくなる傾向があるため、安定経営にはテクニックが必要です。
将来、周辺環境の変化などにより、路面店以外のテナントが決まらなくなるケースを想定し、配管などを住居などほかの目的としても使用できるようにしておくことも建築計画の段階で盛り込んでおきましょう。
2-1-2.ロードサイド店舗
ロードサイド店舗とは、国道や車通りの多い通りに面したビルで、例えば大通り沿いのスーパーマーケットと医療施設が入った駐車場付きの建物のことです。
車付けが良いことから商業ビルとしても、複合施設としても利用できます。土地の条件としてはある程度の駐車場数が確保できる広さが必要なため、300~500坪はあると理想的です。
また土地が大型道路に面していることが重要です。
ビル建築には頑丈な作りと、どのようなテナントにも対応できるビル設備が必要なので初期投資はかかりますが、スケルトンというがらんどうの状態でテナント募集が出来ますので経営管理は比較的ラクと言えます。
2-1-3.駅前商店街のビル
大規模な繁華街ではないが、駅前に隣接した商店街にあるビルのことです。
路面店はすぐ埋まりますが2階以上はテナント入居が難しいため、4階以下の低層ビルでもエレベーター設置をし、ゲストを流入させるための入り口付近の作り方(バギーや車いす対応など)などにも工夫やアイデアが必要になります。
大規模な繁華街と違って歩行者用道路を大きくとってはいないため、商店街の中で遠くからお店を見つけることが難しく、2階以上にテナントが入る可能性は低くなります。
2-2.オフィス系ビル
ビジネス用のオフィス、事務所などをビルに入居させるタイプです。
| ビルの種類 | 収益性の高さ | 投資額の多さ | 経営の難易度 |
|---|---|---|---|
| シェアオフィス・スモールオフィス | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| テナントオフィス | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
2-2-1. シェアオフィス・スモールオフィス
ネット普及とコロナ禍によるリモートワーク推進によって、一気に需要が増えてきたタイプのオフィスです。
一昔前のスモールオフィスは、スモールと言っても30坪程度の広さがありましたが、これから必要とされるのはカラオケボックスの個室レベルの広さで、更に衛生環境の良い小さなオフィスです。
1オフィスあたりの面積が小さいため家賃設定も低く、テナントの経営状態にも大きく左右されません。
2-2-2.テナントオフィス
いわゆる昔からあるオフィスビル経営のことです。
都心部ではオフィスビルはすでに供給過多気味ですので、今からの参入はかなり難しいと言えます。
小~中規模のオフィスビルで低層階にクリニック、中層階以上はオフィスにするようなタイプであれば、地域によっては需要があるでしょう。
ただし、経営状態が少しでも悪くなると早期に退去する傾向がありますので、オフィステナントの長期安定確保は難しく、経営も難しいでしょう。
2-3.賃貸住居用ビル
ビルであるものの、賃貸マンションにもなっているタイプです。
| ビルの種類 | 収益性の高さ | 投資額の多さ | 経営の難易度 |
|---|---|---|---|
| 1棟賃貸駅前 ワンルームマンションビル |
☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| ビジネスホテル | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆ |
2-3-1.1棟賃貸駅前ワンルームマンション
駅前にあるビルですが、全室がワンルームになっているタイプのマンションです。
部屋を住居専用に指定しているわけではないので、入居者が自室としても、小型のオフィスなどとしても使える点がマンションと違います。
1階部分にコンビニやコインランドリーなどが入っていて利便性を重要視しています。
ビル階数を高くする場合は、ある程度の土地面積がないと、エレベーター設置と非常階段の確保で実際に使用できる部分はほとんどなくなってしまいます。
駅の周辺はワンルームマンションも供給過多気味のため、駅前という便利さ以外で、設備の良さや防音やセキュリティなどの付加価値をつける必要があるため、初期投資額は多くなる傾向がありますが、入居状況はその投資額に見合うことになります。
2-3-2.ビジネスホテル
電車・空港などから近い、近隣に有名な観光地があるなど、ある程度の宿泊客数が見込めるならば、ビジネスホテルでのビル経営も検討の価値があります。
旅館業法の規定でホテルの部屋は、公衆衛生の確保に1室あたり9平米(約3坪)以上、安定経営の確保のために部屋は10室以上用意する必要があります。
10室で約27~30坪程度の延床面積が必要になり、部屋以外にフロント・ロビー・廊下・階段・共用トイレ、場所によっては駐車場数台の必要もありますので、最低でもおおよそ50~60坪の広さの土地が必要です。
参考:厚生労働省「旅館業に関する規制について」
運営する部屋数が多いほどビル建築の総費用はかかりますが、同時に費用対効果も良くなりますので、最低で30室、理想は100室以上ある方が経営は楽になります。
部屋数を何個用意できるかは土地の容積率でわかります。
ビル建築後の運営方法は、土地オーナーであれば以下の3つのどのタイプでも選択できます。
- 一括借り上げ(サブリース)
-
ビル建築の総工費をオーナーが負担し、運営は専門会社に任せます。土地建物を全て賃貸に出すことになり、その賃料をオーナーが得るタイプの不動産賃貸業になります。
- オーナー直営
-
ビル建築と運営方針をオーナー決定で行います。ホテル運営そのものは専門会社に代行をしてもらいます。ホテル運営が軌道に乗った場合、オーナーの資産は飛躍的に増えていきます。
- コンサルティング方式
-
ホテル会社のフランチャイズに加盟して自分で運営をする方式です。コンビニエンスストアのフランチャイズと似ています。
すでに名前の通ったホテル名とそのブランド力、ホテル運営ノウハウなどを使えますので、比較的経営は楽です。しかし年間フランチャイズ契約料を支払う必要があり、運営がうまくいかないと、契約料が重くのしかかります。ただし、世界情勢などによってはビジネス利用や観光客の流入が少なくなることもあるため、ビジネスホテルの需要が冷え込む時期があることも想定しておく必要があります。
2-4.介護・保育・メディカル系ビル
| ビルの種類 | 収益性の高さ | 投資額の多さ | 経営の難易度 |
|---|---|---|---|
| メディカルビル | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ |
| 保育園 幼稚園 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ |
2-4-1.メディカルビル
外科・内科などの医療クリニック、眼科、歯科、調剤薬局などの医療系テナントを入れるタイプのビルです。
一つのビルに入ったクリニック同士が総合病院のように互いにビル全体の機能を補完しあうため、利用者も入居者にもメリットがあります。
また、医療系は一度開業すると場所を転々とはしない傾向があり、比較的安定したテナント運営になります。
クリニック系はすべて、精密機械・重量機材などを使用しますので、しっかりした作りのビルを建築しておく必要があります。
特に大きな重量の機材を置いても安心な床と、医療器具のための大容量電源、耐震免震対策は重要です。
また、身体に不調がある方が車いすや担架キャスターで移動できる広めのエレベーター設置、車での送迎、救急車搬送が出来る駐車場が必要です。
そのため、ビル建築の初期投資としては大きめですが、代わりに一度入居して患者さんがつくと、テナントが移動をしなくなりますので経営は安定します。
2-4-2.保育園や私立の塾
私立の保育園や私立の塾などをビル内で運営します。
保育園には認可保育園と無認可保育園、塾には塾以外の学童保育のような機能を持つものがあります。
特に、保育園は中程度の都市部であれば常に需要があります。
- 認可保育園
-
国の認可を受けている保育園です。
都心部では慢性的に保育園不足ということもあり、多少、立地が悪くても人が殺到します。
いったん、入園すれば次の候補も少ないため、撤退リスクも低く安定したテナントです。ただし、認可保育園は補助金事業のため、土地条件が良くても高額家賃設定はできず、収益性はそれほど高くはありません。
- 無認可保育園や私立の塾
-
認可の保育園同様に「子供を一定時間預かる場所」ではありますが、補助金などもないので普通のテナント入居と同じ扱いになります。都心・駅近などの立地条件が揃えば、周辺相場と同等のテナント収入が期待できます。
土地活用を検討している地域に、未就学児が多いかは判断の重要なポイントになります。また、地域全体に保育園が不足していれば、複数の認可保育園の誘致や、私塾形式の預り所などをテナントとして入れることが出来ます。
また、ビルのすべてをテナントにしなくても、低層階に保育所や私立塾などを入れ、中~上層階を小規模ファミリー向けの住居にするなど、地域の需要に合ったことを時代に沿って適宜にやっていけば、経営はそこまで難しくありません。
どのタイプのビル経営が向いている土地かどうか判断したいときは「HOME4U オーナーズ」をご活用ください。最大10社から経営プランが手に入ります。
3.ビルのタイプ別の初期費用シミュレーション
ここでは、前章でご紹介したビルタイプのうち、商業系ビル、オフィス系ビル、賃貸住居用ビルの初期費用をシミュレーションします。
なお、介護・保育・メディカル系のビルについては、初期費用が規模や設備によって大きく異なるため割愛しますが、建物の建築費などは参考になるかと思いますのでご覧ください。
3-1.商業系ビル
商業系ビルの坪単価の目安は、次の通りです。小規模のビルの場合、構造はRC造かS造が一般的です。
| 構造 | 坪単価 | |
|---|---|---|
| RC造 | 鉄筋コンクリート造 | 75~90万円/坪 |
| S造 | 鉄骨造 | 65~80万円/坪 |
例えば、70坪で3階建てのオフィスビルを鉄骨造で建てた場合、建築費は1億3650~1億6800万円です。
諸経費を建築費の10%程度見込むと、初期費用は1億5000~1億8500万円程度となります。
3-2.オフィス系ビル
通常のオフィスビルの坪単価の目安は、次の通りです。
| 構造 | 坪単価 | |
|---|---|---|
| SRC造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 90~110万円/坪 |
| RC造 | 鉄筋コンクリート造 | 80~100万円/坪 |
| S造 | 鉄骨造 | 70~90万円/坪 |
通常のオフィスビルの坪単価の目安は、次の通りです。
例えば、50坪で10階建てのオフィスビルを鉄骨造で建てた場合、建築費は3億5000~4億5000万円です。
諸経費を建築費の10%程度見込むと、初期費用は3億8500~4億9500万円程度となります。
3-3.賃貸住居用ビル
ビル全体がワンルームマンションになっている場合、坪単価の目安は次のようになります。
| 構造 | 坪単価 | |
|---|---|---|
| RC造 | 鉄筋コンクリート造 | 90~120万円/坪 |
| S造 | 鉄骨造 | 80~120万円/坪 |
| 木造 | 鉄骨造 | 77~100万円/坪 |
100坪でRC造、7階建てのマンションの場合、建築費は6億3000~8億4000万円です。
諸経費を建築費の10%程度見込むと、初期費用は6億9500~9億2000万円程度となります。
4.ビル建築の運営方法
ビル建築のための資金調達から出来上がったあとの管理まで、どのようなビルの運営方法があるのかもあらかじめ把握しておきましょう。以下に、タイプ別ビル建築と運営方法をまとめました。
4-1.ご自分で経営するタイプ
ビル建設予定地のオーナー自身が、資金を調達します。
オーナーが指定した建設会社に施工させ、入居者・テナント募集は不動産会社に任せてビル運営する方式で、最も一般的な方法です。
ビル建築の目的と収益計算さえハッキリしていれば、お持ちの土地の大小を問わずにビル建築がスタートでき、なおかつ成功しやすいタイプです。
4-1-1.ご自分で経営するタイプのメリット
- オーナーはビル建築の企画から事業運営までの全てに関わることができ、決定権もオーナーにある
- ビル経営の収益はすべてオーナーのものであり、ビル経営が順調にいけば、オーナーの資産が増える
4-1-2.ご自分で経営するタイプのデメリット
- ビル建築と運営の全てのリスクをオーナーが負うことになる
<デメリット対策>
施工経験が豊富で、信頼できる不動産会社と建設会社から設計プランをもらいます。また、金融機関を説得できるだけのしっかりした事業プランも必要です。想定するテナント特定はビル建築後の事業運営の要になりますので、お持ちの土地周辺のマーケティングなどをもとに、しっかりしとした収支計画を提案できるプランを選べば、大きなリスクを回避できます。
4-2.借り上げて運営してもらうタイプ
サブリースと言われる運営スタイルです。
オーナーが自分で資金を調達してビルを建築し、その後は不動産会社などのサブリース専門会社がオーナーのビル物件全てを一括で借り上げ、その代りにオーナーには一定収入を保証する方法です。
一定収入の保証額はビルが満室になった時の8~9割くらいになります。
自分で経営するタイプのオーナーと比べると、プランの段階でサブリース専門会社の意見も取り入れておく必要があるため、総じて建築費が高くなる傾向があります。
また収入保証は長期保証ではなく、数年ごとに運営状態によって保証額の見直しによって徐々に減額されていく傾向があります。
4-2-1.借り上げて運営してもらうタイプのメリット
- 保証額が長期保証であれば、ビルの建築後は一定収入がサブリース会社から支払われ続けるので、比較的長期の安定収入を得られる
- サブリース会社によるビル一括借り上げなので、ビル建築後にオーナーが入居者募集・賃貸管理などのビル運営に関する事業をする必要がなく非常に楽です。
4-2-2.借り上げて運営してもらうタイプのデメリット
- サブリースだと、満室経営でも手取りは8~9割程度に減る
- 経営状態に関係なく、ビルの経年や減価償却率などを基準に、保証賃料が定期的に減額される傾向がある
- サブリース会社の指示通りにメンテナンス・修繕を行わないと、保証賃料の減額、契約解除になることがある。さらに、違約金を請求されるリスクもある
<デメリット対策>
ビルを建築する場所が1章で説明をしたようなビル建築に向いている環境の場合は、ビルの建築後は常に満室になる可能性があります。
そのような土地をお持ちの場合は、サブリースにするよりもオーナーがご自身でビル経営をし、管理だけを不動産管理会社にお任せする方がよいかもしれません。
サブリース契約を前提にビル建築をする場合は、賃料保証を長期(10~20年単位)で更新が出来るように先に交渉提案をしてみてください。
5.ビル建築について相談できる建築会社を選ぶ方法
ビル建築は投資期間が高額且つ長期間にわたって経営する事になるため、建築会社を慎重に選ぶことになると思います。
選ぶ際の基準はズバリ
- 長期的に安定したアフターフォローが受けられる、経営の安定した建築会社
- お持ちの土地の立地に合ったタイプのビルを建築・経営支援した経験が豊富な建築会社
です。
「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」は、お客様がお持ちの土地の立地や、その他の事情に合った「実績豊富な」建設会社をお客様毎に厳選して、無料で複数社ご紹介いたします。
是非ご活用ください。
関連記事
-
-
-
- 2025.01.09
- アパート・マンション建築
- ノウハウ
- 空室改善
-
- 2025.01.23
- アパート・マンション建築
- 経営ノウハウ