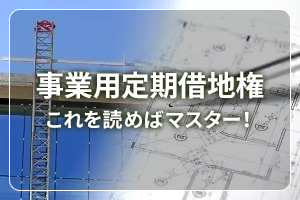トランクルーム経営は「初期費用が安い」「高利回り」といわれることが多いです。そのため、使っていない土地を活用するためにトランクルーム経営が気になっておられる土地オーナー様も多いでしょう。
「トランクルーム経営は自分の土地に合うかどうか?郊外でもできるのか?」
「トランクルーム経営のリスクは何?どういうことに気を付ければいいの?」
「トランクルーム経営で、実際どのくらい収益をあげられるのか?」
など、わからないことばかりでお困りではないでしょうか。
この記事ではトランクルーム経営の事情を知りたい方のために、トランクルーム経営の全体像、型式・運営形態、事業リスクと対策について説明します。トランクルーム経営で土地活用を始める足掛かりとして役立ててください。
また、トランクルームを含むさまざまな土地活用について検討するなら、以下のボタンから、土地活用プランを手に入れられます。ぜひご利用ください。
目次
1. トランクルーム経営とは
トランクルーム経営とは、コンテナハウスと呼ばれる建物を建築し、収納スペースとして貸し出すことで賃料を得る事業です。賃貸アパートやマンション経営と比べて、初期費用・ランニングコストが安く済むため、比較的リスクを抑えて空いている土地を活用できます。
ここでは、トランクルーム経営のメリットとデメリット、それぞれの運営方式の違いについて説明します。
1-1. トランクルーム経営とレンタル収納ビジネスとの違い
トランクルーム経営とレンタル収納ビジネスはしばしば混同されますが、似て非なるものです。倉庫事業者として契約し、保管している荷物を保証するかしないかという利用形態に大きな違いがあります。
トランクルーム = 倉庫業者(倉庫を貸す、運営する)
レンタル収納スペース = 不動産賃貸業者(場所を貸す)
端的に言うと、「倉庫を貸す」か「場所を貸す」かの違いです。
-
トランクルーム経営
トランクルーム経営では、利用者に倉庫を貸すときに「寄託契約」を結び、物品の保管・保証義務を負います。そのため、単に場所を貸すレンタル収納スペースと比べて、防犯対策がしっかりしているという特徴があります。
一定の基準を満たした優良トランクルームは、国土交通大臣の認定を受けることができ認定マークを申請できます。参考:「倉庫業法第25条(トランクルームの認定)」
-
レンタル収納ビジネス
一方レンタル収納ビジネスは、あくまでも「場所を貸す契約」にとどまります。物品の保管は利用者の自己責任で管理することになります。
定の基準を満たした優良レンタル収納スペースには、レンタル収納スペース推進協議会から「RS推奨マーク」が付与されます。
1-2. 「屋外型」「屋内型」2つのトランクルームの型式と特徴
トランクルームには「屋外型」「屋内型」の2つの型式があり、それぞれ特徴が違います。それぞれの特徴とメリット・デメリットを紹介します。
「屋外型」「屋内型」の違い
「屋外型」「屋内型」は、それぞれ「コンテナ型」「ルーム型」とも呼ばれ、違いは明確です。
屋外型(コンテナ型) = 更地にコンテナを置く、建てる
屋内型(ルーム型) = 建物内の各室に倉庫を割り当てる
更地にコンテナを設置する「屋外型」は、主に郊外に多いと言われています。一方、建物内の各室に倉庫を割り当てる「屋内型」は、市中心部で見られる傾向があります。賃貸マンションの1階部分を改修して倉庫として貸し出すケースが多いようです。
それぞれのメリットとデメリット
同じトランクルーム経営でも、屋外型(コンテナ型)か屋内型(ルーム型)かで、メリット・デメリットが大きく変わってきます。違いは、以下の2つに大別できます。
- 初期投資額の大小
- 温度・湿度調整の難易度
屋外型(コンテナ型)
メリット:コンテナを設置するだけなので、新築するよりも初期投資を抑えられる。
デメリット:屋外にコンテナを積むため、温度・湿度調整が難しい。
屋内型(ルーム型)
メリット:建物内で保管するため、温度・湿度管理が用意、多種多様な収納ニーズに応じられる
デメリット:新築だと初期投資額がかさんでしまう。
なお、屋外型のコンテナは、観光地や住宅などでは景観を損なう恐れがあり、クレームにつながることもあるため、周辺エリアに合わせた選択が求められます。
1-3. トランクルーム経営の3つの運営方式
トランクルームに「屋外型(コンテナ型)」「屋内型(ルーム型)」の2つの型式があることは前述の通りですが、さらにそこから3つの運営方式にそれぞれ枝分かれします。
- 事業用定期借地方式
- リースバック方式
- 業務委託方式
運営方式によって運営・管理方法、契約形態、収益の仕組みが大きく変わります。個々の事情に合った選択が必要になります。それぞれの特徴を下記の通り説明します。
事業用定期借地方式
「事業用定期借地方式」とは、自分の土地をあらかじめ定めた期間だけトランクルーム事業者に貸し、そこから地代を得る方式です。上物(トランクルーム)の経営主体はトランクルーム事業者になるので、地主の懐に入ってくるのは「地代」のみです。トランクルームの賃料収入は入りません。
トランクルームの賃料収入が入らない代わりに、地主は土地を貸すだけなので、「土地活用に時間と労力を費やしたくない」という人に向いているといえます。
リースバック方式(一括借り上げ方式)
「リースバック方式(一括借り上げ方式)」とは、自分のトランクルームを専門企業に借り上げてもらうことで安定収入を図る方式です。先の「事業用定期借地方式」と異なり、土地を貸すのではなく、自分の土地に自分で設備投資してトランクルームを借り上げてもらうことで、稼動の有無にかかわらず賃料収入を得ることができます。土地・建物はオーナー名義ですが、経営主体は専門企業になります。
リスクを吸収してくれる分、一室あたりの手数料が割高になりため、その分収益が目減りします。「賃料収入は多少目減りしてもリスクは極力避けたい」といった方におすすめできる運営方式です。
業務委託方式
「業務委託方式」は、集金や清掃など最低限の業務のみを事業者に委託するやり方です。経営主体は土地オーナーになります。
リースバック方式と比べて事業者に払う手数料は安くなる代わりに、オーナーは空室リスクを負うことになります。「自分で経営したい」「リスクを負ってなるべく多くの収入がほしい」といった方におすすめできるといえます。
トランクルーム経営の収益シミュレーションを知りたい方は「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」を使えば、最大10社から無料で収支プランが手に入れられます。
2.トランクルーム経営のメリットとデメリット
ここでは、トランクルーム経営を行う際のメリット・デメリットを紹介します。
2-1.トランクルーム経営の7つのメリット
トランクルーム経営のメリットは、次のとおりです。
- 初期投資費用がアパート・マンション経営など住居系の土地活用に比べて安い
- 土地の転用が容易
- 修繕費があまりかからない
- 利用者とのトラブルが少ない
- 屋外型の場合、コンテナを置くだけなので始めやすい
- 管理の手間や修繕などの保守点検がほぼ不要
- 立地条件にかかわりなく、多くの土地で活用できる
トランクルーム経営における最大の魅力として、初期投資費用の少なさが挙げられます。特にコンテナ型のトランクルームは、更地にコンテナを設置するだけで電気・水道・ガス工事すら不要なケースがほとんどです。低コスト、低リスクで土地活用を始めたい方におすすめです。
それ以外も、修繕費用や管理点検の手間が不要であること、やめたいと思ったときに転用がしやすいこと、用途地域など条件がクリアできれば始められることなど、土地活用の初心者にも向いているといえるでしょう。
2-2.トランクルーム経営の5つのデメリット
トランクルーム経営のデメリットは、次のとおりです。
- 収益化までに時間がかかる可能性がある
- 相続税などの節税効果が低い
- 金融機関の融資を受けにくい
- アパート・マンション経営よりも収益が少ない
- 保管物の盗難・破損のリスクがある
新築物件の価値が高い賃貸用不動産と違い、トランクルームには新規開設による付加価値は見込めません。また居住用物件のメリットである相続税の節税効果などもありません。初期投資費用が安価なため、比較的空室リスクは低いといえますが、収益化に時間がかかり空室が長く続くと利回りは悪くなります。
リスク回避のためには、トランクルーム経営に詳しい事業者へ相談して立地やニーズについて調査してもらい、活用プランを提示してもらうとよいでしょう。よくある失敗例と対策については4章で紹介しています。
3.トランクルームの市場規模と収益性
トランクルーム市場が沸いている背景には、日本の住まい事情とライフスタイルの変化が関係しています。ここでは、トランクルームの市場規模と、収益が高くなる理由を説明します。
3-1.トランクルームの市場規模は右肩上がり
トランクルームの市場規模は右肩上がりです。トランクルーム大手のキュラーズ(東京都品川区)が2020年7月に公開した「市場規模調査」によると、トランクルームの国内店舗数は約10,000を超えています。また市場規模は約650億円と試算されています。
店舗数が増えた理由は、市中心部への人口流入が加速したことが原因と考えられています。東京なら都心部へ人口が集中したことにより、新築されるマンションの戸当たりスペースが狭くなりました。収納スペースを満足に確保できない住民が、次第にトランクルームを使うようになったと推測できます。
また、新型コロナウイルスの影響により、テレワーク、オンライン授業など、従来とは大きく異なる生活様式が浸透したことも大きいでしょう。居住環境の変化に伴い、生活スペースを改善するための収納ニーズが高まっています。
一方、従来の労働環境では必須だったオフィススペースが、在宅ワークの広がりとともに不要となるケースも多いようです。オフィスのダウンサウジングによって出る什器の置き場として、トランクルームへのニーズが顕在化したことも一因と考えられます。
このような市場動向から、トランクルーム経営は注目を集めている土地活用の一つといえます。
3-2.トランクルーム経営が有利な場所・不可能な場所
トランクルーム経営に有利な場所として、以下が目安となります。
郊外 コンテナ型で、利用者の居住エリアから車で5~10分程度の場所
都市 ルーム型で、利用者の居住エリアから徒歩で5~10分程度の場所
トランクルームの商圏は比較的広いと言われています。後は需要と供給のバランス次第です。競合が少なければ少ないほど、またマンション戸当たりの居住スペースが小さいエリアであるほど商機が高まります。
ただし、トランクルームはどこでも始められるわけではないため、注意が必要です。用途地域によって、「可能なエリア」「不可能なエリア」が存在します。これは都市計画法で定められています。トランクルーム経営が「不可」の地域は、以下のとおりです。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域(2階以下は可)
自分の土地がどの用途地域に当てはまるか、事前に調べておきましょう。市役所や区役所などの自治体の窓口で照会できますが、ウェブサイト上で検索サービスを実施している自治体もあります。
3-3.トランクルーム経営における集客方法
トランクルームの集客にあたっては、インターネット、紙媒体が主に使われます。周辺住民に認知してもらうためには、「チラシの配布」「看板設置」といった古典的な集客も奏功します。
- 自社サイト
- 紙の広告(チラシ配布など)
- 看板
なお、多くは運営会社が代行してくれます。どのように広告を行うのか、土地オーナーは上記をおさえておき、必要に応じて運営会社に問い合わせるとよいでしょう。
3-4.収益化までにかかる期間
収益化までの期間は一概に言えませんが、一般的に、満室稼動までには一定の時間がかかると言われています。トランクルームを収益化するためにはいち早く稼働率を高めなければいけませんが、稼働率を上げるためには周辺住民に認知してもらう必要があり、その認知にタイムラグが生じます。
近年、トランクルームの認知度は高まりつつあるものの、郊外ではまだ低い傾向にあります。その代わり、一度使ってもらうと長きにわたって契約が続きます。認知してもらいさえすれば安定経営が望めるところが、トランクルームのメリットと言えるでしょう。
トランクルーム経営について相談したい方は「HOME4U オーナーズ」をご活用ください。複数社から無料で収支プランを手に入れられます。
4.はじめてのトランクルーム経営でよくある失敗例と対策
アパート・マンション経営と比べて「ローリスク」と言われるトランクルーム経営にも、少なからずリスクはつきまといます。ここでは代表的な失敗例を紹介します。
4-1.賃料設定を見誤ってしまう
賃料設定を見誤ると、稼働率が低くなり、利回りに影響します。賃料設定は慎重に行いましょう。
特に注意が必要なのは、エリアの料金相場が「月2万円」だからといって、安易に合わせないことです。月2万円のトランクルームが多くても、もし空室が多ければ、その2万円は「需要を満たしていない」と考えられるからです。
【対策】
エリアの料金と空室状況を調査しましょう。調査することでニーズを可視化でき、「安くするか」「設備を追加投資してグレードアップするか」といった戦略が立てられます。
4-2.温度や湿度の調整で用途が制限されてしまう
トランクルームの設備仕様によっては、利用用途が限られてしまいます。特に空調設備をつけにくい「屋外型(コンテナ型)」の場合、温度・湿度調整が大変難しいため、季節によっては預けられない物品がでてきます。
例えば日当たりのよいコンテナ型の場合、書籍・衣服の保管には湿度管理がかかせません。温度で質が左右されるワインなどは、コンテナ型には不向きと言えるでしょう。
【対策】
利用者がどんな物を預けようとしているのか、需要をきちんと見極める必要があります。
4-3.集客に時間がかかってしまう
3章でも説明したとおり、トランクルームそのものの認知度が高くない郊外の場合、新設したトランクルームの認知に多少のタイムラグが生じると言われています。チラシ配布や看板、ネットを使って周知したものの「満室までに半年かかった」としたら、その間の賃料は入って来ません。
【対策】
運営会社にサブリースしてもらうことで、その間のリスクを軽減するのも一つのやり方です。専門企業によって集客の仕方は若干の差がありますので、気になる方は複数の専門企業に聞いてみるといいでしょう。
4-4.盗難・破損・災害のリスクを軽視する
「倉庫事業者」としての登録を以て行うトランクルーム経営では、オーナーは利用者の物品の保管・保全に責任を持たなければなりません。これが無策だと、盗難、破損、災害の際に争いに発展する危険が伴います。
また、セキュリティが万全でないことが露呈した場合、周辺住民に敬遠されやすくなります。利回りの高低に直結する要素なので、軽視せず、対策を練りましょう。
| 盗難のリスク | トランクルームが物品を預けるスペースである以上、盗難のリスクは常につきまといます。セキュリティ設備を備え、必要最低限の投資を行うことが必要です。また「利用者の責任で管理してください」と注意書きを記すのも一案です。ひとつのリスクヘッジになるでしょう。 |
|---|---|
| 破損のリスク | 高温多湿による物品の劣化、災害による破損などのリスクがあることも、契約時に利用者に説明しておきましょう。物品を預かる以上、外部要因による悪影響がないとも言い切れないからです。事前に注意喚起をすれば、万が一のトラブル抑止が期待できます。 |
| 災害のリスク | 災害による建物損壊リスクも念頭におきましょう。災害が多いエリアなら、地震や台風に強い屈強なコンテナを使うなど事前に出来ることをしておきましょう。 |
5.トランクルーム経営は複数の専門企業に相談する
利用ニーズが底堅いトランクルーム経営ですが、何も考えなくても稼げるビジネスというわけではありません。エリアごとの詳しいニーズや、土地にあった型式・設備・仕様を見誤らないよう、まずは複数の専門企業に相談することをおすすめします。
おすすめは、NTTデータグループが運営している土地活用のプラン一括請求サイト「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」です。
トランクルーム経営を検討している人に、専門企業が最適なプランを提示します。一括請求なので、必要事項を一度入力すれば、お持ちの土地の所在地に対応した企業からプランが届く仕組みになっています。
「HOME4U オーナーズ」を上手に活用して、最適なトランクルーム経営のプランをみつけてください。
まとめ
いかがでしたか。この記事では、トランクルーム経営について解説しました。
アパート・マンション経営と比べて「ローリスク、ローリターン」と言われるトランクルーム経営は、その中にも複数の型式、運営方法があり、選び方次第で成否が左右されます。自分の土地に合うか合わないかを照らし合わせ、さらに運営リスクを考慮しながら、専門企業と一緒に組み立てることが成功の近道と言えるでしょう。
土地活用も「彼を知り己を知れば百戦危うからず」です。自分の土地・エリアを知り、トランクルーム経営をよく勉強すれば、失敗のリスクは自然と低くなります。この記事が、トランクルーム経営の成功への第一歩となることを願っています。
関連キーワード
関連記事
-
-
- 2025.01.23
- アパート・マンション建築
- 費用
-
【自分の建築費がすぐわかる】アパート建築費の坪単価相場について
- 2025.01.23
- アパート・マンション建築
- 費用