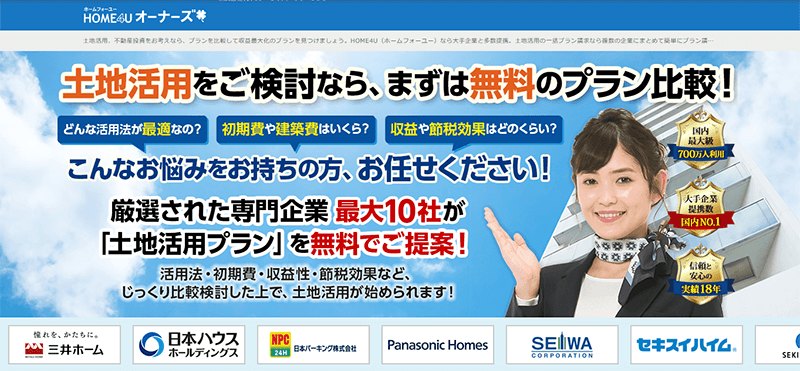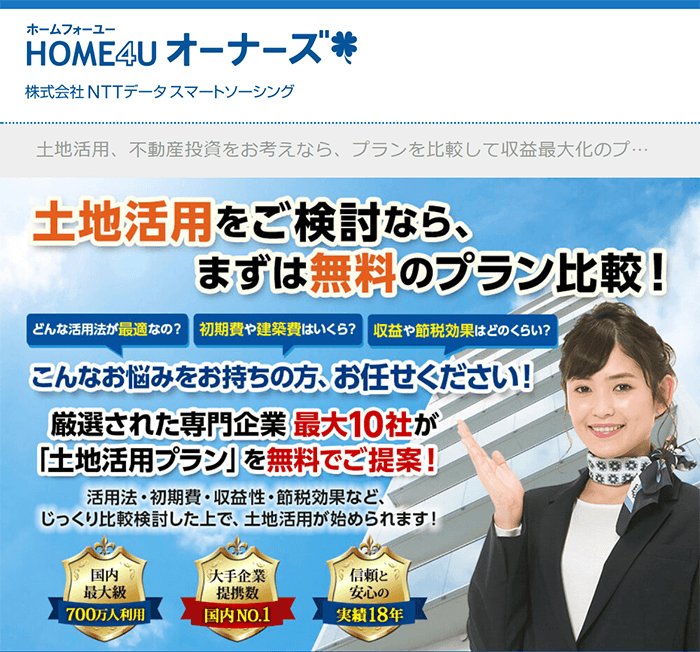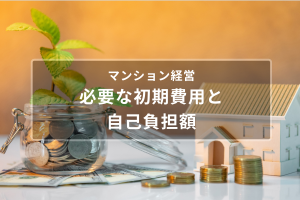2022年になると生産緑地の指定期間の終了を迎えることから、生産緑地の今後の取り扱いが話題となっています。
指定期間終了時に生産緑地の所有者が取り得る選択肢としては、「農地としての継続利用」、「売却」、「土地活用」の3つです。
マスコミでは「売却」の選択肢のみが取り上げられ、2022年に一気に生産緑地が売却され、宅地が大量供給されて土地価格が下がるのではないかという懸念も騒がれています。
これは俗に「2022年問題」と呼ばれています。
2022年問題は売却ばかりがフォーカスされますが、売却は1つの選択肢であり、最終手段といえます。
生産緑地はポテンシャルが高く、手放すのはもったいないので、土地活用を最優先に考えてください。
そこで、この記事では生産緑地の選択肢の中で「土地活用」に着目して解説したいと思います。
この記事をお読みいただくと、生産緑地の土地活用なら何ができるのか分かるようになります。
特に先代からの土地をしっかり継承したいとお考えの方には、ぜひお読みいただきたい内容となっています。
この記事を参考にして、お持ちの生産緑地を上手に活用し、収益化に繋げてください。
目次
1.生産緑地は活用のポテンシャルが高い
2022年問題が話題となった理由に、生産緑地のポテンシャルの高さがあります。
最初に生産緑地のポテンシャルの高さについて解説します。
1-1.生産緑地ができた経緯
生産緑地とは、生産緑地法に基づき市街化区域内において、一定の要件を満たす土地が自治体から指定された土地または森林のことを指します。
まず、生産緑地がある場所は「市街化区域内」であるということです。
市街化区域とは「既に市街化を形成している区域、またはおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」です。
市街化とは街づくりのことを指し、市街化区域は建物を建て、人が住んだり、働いたりすることを積極的に行うことを目的とした地域になります。
市街化区域は、土地活用がしやすい都市部のことを指し、生産緑地はその都市部の中にある農地や山林です。
ただ、都市部においても、災害の防止の観点から、緑地が持つ地盤保持や保水の機能は必要になります。
都市の中にもある程度このような緑地帯を残しておかなければなりません。
全てを宅地化すると、農地や緑地の持つ地盤保持や保水の機能が失われてしまうことから、都市部にも農地等を残しておく必要がでてきました。
そこで、営農を条件に30年間の期限付きで農地を宅地並み課税としないこととし、農地を維持する政策が取られました。
それが1992年のことであり、30年目の期限が2022年ということになります。
生産緑地は、都市部において緑地を保全しておく必要性があったというのが誕生した経緯になります。
1-2.指定を受けなかった土地の当時の状況
1992年当時、同じ農地でも生産緑地の指定を受けず、宅地並み課税をされてしまった土地もあります。
このような土地は、固定資産税が上がってしまったため、農業を止めてしまう土地が徐々に増えていきました。
ただし、農業を止めて休耕田のようになってしまったわけではなく、そのほとんどはマンションや建売住宅の敷地等の宅地転用が行われました。
理由としては、生産緑地の指定を受けなかった土地も市街化区域内にあるため、宅地にしたらすぐに活用できる状況にあったからです。
国土交通省の統計「都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況」によると、2016年3月時点の生産緑地の都道府県別指定面積は以下のようになっています。
| 都道府県 | 生産緑地面積(ha) | 割合 |
|---|---|---|
| 東京都 | 3,223.7 | 24.4% |
| 大阪府 | 2,029.5 | 15.4% |
| 埼玉県 | 1,764.8 | 13.4% |
| 神奈川県 | 1,360.7 | 10.3% |
| 千葉県 | 1,147.3 | 8.7% |
| 愛知県 | 1,126.0 | 8.5% |
| 京都府 | 820.4 | 6.2% |
| 奈良県 | 598.8 | 4.5% |
| 兵庫県 | 518.7 | 3.9% |
| 静岡県 | 238.0 | 1.8% |
生産緑地は全国で13,187.6haですが、そのうち東京都が最大で3,223.7ha(全体の24.4%)となっています。
6位までが首都圏と大阪府と愛知県になりますが、6位の愛知県までの合計が全体の8割以上の割合を占めます。
生産緑地は市街化区域に指定されていますが、中でも土地活用のポテンシャルの高い三大都市圏に集中しています。
生産緑地は広くて都心部にある良い土地が多いです。
売ってしまうのはもったいないので、まずは活用を考えることをおススメします。
1-3.指定解除の条件とは
生産緑地の指定解除には、以下の3つの要件のうち、いずれかを満たす必要があります。
- 生産緑地指定から30年後
- 病気などの理由で主たる従事者が営農することが困難になったとき
- 主たる従事者が死亡し、相続人等が営農しないとき
1992年に生産緑地の指定を受けた農地が多かったため、2022年には一気に生産緑地が解除されることが懸念されています。
2.宅地並み課税が引き起こす2022年問題
 生産緑地は、生産緑地指定から30年後に解除されるという制度です。
生産緑地は、生産緑地指定から30年後に解除されるという制度です。
指定されてから30年を過ぎると所有者が市町村に対して買い取りの申出をすることができます。
所有者から買い取りの申出があると、市町村は1ヶ月以内に買い取るかどうかの通知を行います。
市町村が買い取らないということになれば、市町村は農業従事者へのあっせんを務めることになっています。
買い取りもあっせんも無理という話になると、生産緑地は解除されます。
現在、各市町村は財政的に余裕のないことから、買い取りの申出があっても買い取りはできないだろうと予想されています。
生産緑地が解除されてしまえば、現況の農地が宅地並み課税となり、維持費の負担が重くなることから、土地所有者に活用か売却かの選択が迫られます。
売却を選択する人が増えると、一挙に宅地が売りに出されることになり、土地価格が暴落するのではないかという懸念も出ています。
現行の生産緑地は指定時の面積要件が500平米以上であったため、マンションや戸建分譲の素地となる大きな土地がボンボン売りに出されることになります。
新築マンションや建売戸建ての価格にも影響を与えていくため、景気の低迷を引き起こす要因となりかねません。
仮に売却が本当に増えてしまうようであれば問題は大きくなるものと予想されます。
3.「2022年問題」を受けての国の施策
2022年に生産緑地が大量放出される懸念もあることから、国も黙ってみているわけではありません。
実はきちんと対策がなされていますので、この章では国の施策でご紹介します。
3-1.特定生産緑地制度の導入
2017年6月に生産緑地法が一部改正され、新たに特定生産緑地制度が導入されました。
簡単に言うと、2022年に生産緑地の指定が切れても、特定生産緑地に指定されれば、再度10年間の期限延長が可能となります。
元々、生産緑地は地盤保持や保水の機能として都市に必要なものです。
その必要性は2022年になっても突然、消滅するわけではありません。
生産緑地法の改正により、都市農地の位置付けは、「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」へと考え方が大きく転換しています。
都市農地は農産物の供給だけでなく、今は農業体験の場や災害時の避難場所、良好な景観を生む機能があると再認識されており、国としては都市農地をなるべく保全する方向へと舵を切っています。
尚、2018 年9月1日より「都市農地貸借法(都市農地の貸借の円滑化に関する法律)」が制定されました。
都市農地貸借法により、今後は生産緑地の農地の貸出がしやすくなります。
3-2.田園住居地域の創設
2022年問題を受け、都市計画法および建築基準法の改正も行われ、2018年4月から「田園住居地域」と呼ばれる新たな用途地域が創設されました。
用途地域とは、エリアごとに建築可能な建物の用途を指定した地域のことを指します。
ここは住居だけ、ここは工場だけ等々、エリアで建てられる建物を規制しているため、土地活用をする際、大きな影響を与えます。
田園住居地域とは、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定められる地域を指します。
田園住居地域は、主に生産緑地を対象に指定されていくことが想定されています。
田園住居地域では、現行の第一種低層住居専用地域にプラスアルファの建物が建てられるというイメージの地域です。
第一種低層住居専用地域とは、「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域」のことであり、土地活用をするとアパートや老人ホームなどの、主に住居系の低層の建物しか建てられません。
しかしながら、田園住居地域に指定されると、以下のような用途も建築することが可能となります。
つまり、住宅以外の土地活用も考えられるわけです。
- 農産物の生産・集荷・処理・貯蔵に供するもの
- 農協の生産資材の貯蔵に供するもの
- 店舗、飲食店等※
※地域で生産された農産物の販売等を主な目的とするものは床面積500平米以内。その他は床面積150平米以内。いずれも3階以上の部分をその用途に供するものは除かれる。
4.生産緑地の土地活用の選択肢
 生産緑地の土地活用方法としては、「農地として継続利用」、「 一部生産緑地を更新しつつ、新たな活用」、「用途地域に応じた活用」の3つになります。
生産緑地の土地活用方法としては、「農地として継続利用」、「 一部生産緑地を更新しつつ、新たな活用」、「用途地域に応じた活用」の3つになります。
この章では生産緑地の3つの土地活用方法について解説します。
4-1.農地として継続利用する
1つ目の活用方法としては、農地として継続利用するという方法があります。
生産緑地は、営農の継続意向を示せば、特定生産緑地として再度指定され、10年間は宅地並み課税となることが回避できます。
都市農地貸借法ができたことにより、今後は自分で農業をするだけではなく、農地を農業法人やNPOなどに貸し出すこともしやすくなります。
従来は、農地の賃借は農地法の制限を受けていたため、一度貸してしまうと二度と返ってこないかもしれないという不安があるという問題がありました。
しかしながら、都市農地貸借法では農地法は適用されず、契約期間満了時に農地が返ってくるため、安心して農地を貸すことができるようになります。
4-2.生産緑地を更新しつつ、新たな活用方法に挑戦する
2つ目としては、生産緑地を更新しつつ、一部の土地を新たに活用する方法です。
生産緑地は、今後、田園住居地域に指定される可能性があります。
田園住居地域の建築可能用途で、注目したいのは「店舗、飲食店」です。
第一種低層住居専用地域では店舗、飲食店を作ることは原則できませんが、田園住居地域であれば作ることが可能です。
例えば、生産緑地の一部の土地をレストランとして貸し出し、自分が作った農作物をレストランで利用してもらうこともできるようになります。
自分が作った農作物の仕様や販売を目的とすれば、床面積が500平米までの店舗や飲食店にすることができます。
500平米もあると十分大きなレストランや販売所ができますので、都内などは借手がすぐに見つかるものと思われます。
都会では顔の見える農家からの新鮮な野菜の提供に対するニーズが高いため、田園住居地域を踏まえた土地活用は都市部の生産緑地の活用にマッチしています。
用途地域に関しては、今後、順次、田園住居地域への指定が増えていくものと思われます。
田園住居地域に指定されるかどうかは、土地活用の方向性を決める大きなポイントとなります。
今後の都市計画決定について注視し、用途地域が決まってから活用方法を考えるのがおススメです。
4-3.用途地域に応じた建物を建てる
3つ目としては生産緑地をすべて解除し、用途地域に応じた建物を建てる方法があります。
生産緑地は最低面積が500平米であるため、全部解除すると広い土地となります。
広い土地ですので、まず第一にはアパートやマンションの土地活用が考えられます。
アパート、マンション経営は、その収益性の高さから、あらゆる土地活用の種類の中でも特に人気があります。
例えば、新築マンション・アパートの需要は高いため、空くことなく満室になれば、毎月安定した高収益が期待できます。
また、マンションやアパートといった住宅系土地活用では、土地に課せられる固定資産税や土地計画税も軽減されるため、節税対策としても有用です。
アパート・マンション経営の最大の魅力は、毎月の家賃収入があるだけでなく、固定資産税や相続税の節税効果も得られる点です。
とりわけ都内や大都市圏の住宅地なら、少し駅から離れていても学校や病院など、環境が整っていることが多いため、賃貸住宅の需要は安定傾向です。
これらのことから、まずは、土地活用の王道「アパート・マンション経営」を検討するのが賢明といえます。
とはいえ、大都市圏から少し外れていたり、周辺環境的にどうしてもアパートやマンション経営が厳しいケースもあるかと思います。
そのような場合は、老人ホーム等の介護施設を検討してみてください。
老人ホームは、駅から徒歩圏外であっても、バス停から5分以内の立地だと、事業者が出店する可能性があります。
土地所有者は老人ホームを建設し、老人ホーム事業者に一棟貸しで貸し出す活用となります。
老人ホームは一棟貸しであるため、手間もほとんどかからないというメリットがあります。
周辺にまだ介護施設がないようなエリアであれば、十分に可能性はあるでしょう。
所有している土地がどのような用途地域に当てはまるかなど、用途地域については「そんな規制あったんだ!土地活用で重要な用途地域を徹底解説」という記事も参考にしてください。
5.新しいアイディアをいっぱい集めることが重要
生産緑地の土地活用は、田園住居地域に指定される可能性もあり、様々な可能性も秘めています。
生産緑地は、元々がポテンシャルの高い土地であるため、アパートなどの土地活用も検討できます。
しかしながら、レストランや老人ホーム等の事業系の土地活用の可能性も出ていることから、幅広く活用のアイディアを集めることが一層重要になっていきます。
土地活用のアイディアを幅広く集めるには、「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」がおススメです。
「HOME4U土地活用」には、アパートだけでなく、事業系の土地活用の実績もある大手ハウスメーカーが揃っているためです。
生産緑地は都市部にある広い土地なので、用途の多様性があり、ありきたりな土地活用では少しもったいないこともあります。
力あるハウスメーカーから幅広い土地活用提案を受ければ、納得のいく土地活用が見つかります。
土地は、一度手放すと取り戻せません。
売却ではなく「HOME4U オーナーズ」を使って、生産緑地を有効に活用することをおススメします。
まとめ
いかがでしたか。
生産緑地の土地活用について解説してきました。
生産緑地は市街化区域内の土地であるため、土地活用のポテンシャルは高いです。
建物を建てる土地活用については、生産緑地が田園住居地域に指定されると、活用の幅が広がります。
また、全部指定解除して広い土地で活用するには、アパートや老人ホームなども考えられます。
生産緑地は、従来にはない収益性の高い土地活用もできる可能性があるため、「HOME4U オーナーズ」で幅広い活用プランの提案を受けると、そのポテンシャルを十分に生かした土地活用をし、収益を得ることができます。
新しいアイディアをたくさん集め、生産緑地を有効に活用してください。
関連記事
-
-
- 2025.01.29
- ノウハウ
-
面白い土地活用方法全28選。意外な賃貸経営方法とユニークな土地活用
- 2025.01.24
- アパート・マンション建築
- ノウハウ
-
- 2025.01.23
- アパート・マンション建築
- 費用