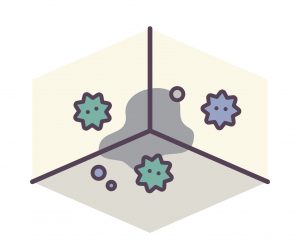Q
お悩みQ&A
洗面所の床が腐った。明らかに入居者さんの過失だと思うが…
- 2025.06.10
- Q&A
- 修繕費
ケンさん
アパート大家です。
洗面所やキッチンの床を腐らせた入居者の方がいます。退去時に気づいたのですが、最低でも張り替えるレベルです。
明らかに入居者さんの過失だと思うのですが、かたくなに認めません。
こちらが泣き寝入りするしかないですか?
福岡県/50代
A 回答順に表示

後藤 謙治さん
賃貸借契約における原状回復義務や過失責任の立証が問題となる場面です。
入居者による「通常使用を超える損耗・毀損」であり、過失や故意による損害と判断できる場合には、原状回復費用を請求可能です。
ただし、入居者が過失を否定している場合、立証責任は大家側にあるため、証拠をどうやって集めるかがポイントになります。
1. 原状回復の基本原則―国交省のガイドラインを参考に
大前提として、賃貸借契約書の記載が問題にはなりますが、一般的には、賃借人は退去時に原状回復しなければならない(「原状回復義務」と呼ばれます。)と定められていることがほとんどですので、以下ではそのような前提でご説明します。
過去の判例で、通常損耗と経年変化(劣化)については、原状回復義務には含まれないと判断されています。つまり、賃借人は「通常使用による損耗・経年劣化」については原則として修繕義務を負いません。
もっとも、故意・過失、善管注意義務違反(善良な管理者としての注意義務)に基づく損耗や損傷については、原状回復費用を負担する義務が生じます。
ここであげたように、通常損耗と経年変化については、賃料に含まれる部分と解されるので、基本的には大家さんの負担ということになります。
どのようなケースで大家さんの負担になり、どのようなケースで賃借人の負担となるかは、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」が参考になります(https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf)。
2. 対応の流れ
(1) 証拠資料の確保と記録
賃借人が修繕費を任意に支払うことを拒む場合、請求の根拠となる資料を確保することが大切です。具体的なには以下のような資料です。
・退去時の損傷状況の写真や動画:複数の位置から残しておくと安心
・入居時の現場状況の写真や動画:入居中の損傷であると特定するために必要
・修理業者の見積書:修理内容と金額の特定に必要
・損傷原因の調査報告書:賃借人の故意・過失の判断に必要(必要に応じて)
(2) 説明と交渉
まずは、上記のような資料を提示しつつ、賃借人が負担すべき費用であることを説明して、修繕費用の負担を求めます。各種資料については、コピーを渡してしまった方が賃借人側の検討材料になるので望ましいケースが多いです(個人情報等には配慮が必要です。)。必要に応じて、国交省のガイドラインの該当箇所も参考資料として送ることも有益です。また、受領を確認する意味でも、配達記録郵便やレターパックを利用することが望ましいです。
電話や対面でやり取りする場合は、交渉経過を残す意味で、できる限り録音・録画を残しておくとよいでしょう(録音・録画にあたって相手方の了解を得る必要はありません。)。
(3) 話合いで解決しない場合は
話合いで解決しない場合、内容証明郵便による請求、調停や訴訟などの法的措置に進む必要があります。いずれかの段階では、弁護士に相談・依頼する必要が出てくると思います。
3. 泣き寝入りしないために
以上のとおり、床の損傷部分の修繕費を賃借人に請求できるかどうかは、損傷の状況や程度と、それに対して有益な証拠資料を確保できるかが重要なポイントになります。
そもそも賃借人に請求できる損傷なのか、できるとしてどのような証拠資料が必要か、など、法的に複雑な問題が含まれるケースも多いです。
弁護士であれば、必要な証拠資料の提案や交渉の進め方の助言も可能です。依頼するか否かにかかわらず、早めにご相談いただくことが望ましいと思います。
入居者による「通常使用を超える損耗・毀損」であり、過失や故意による損害と判断できる場合には、原状回復費用を請求可能です。
ただし、入居者が過失を否定している場合、立証責任は大家側にあるため、証拠をどうやって集めるかがポイントになります。
1. 原状回復の基本原則―国交省のガイドラインを参考に
大前提として、賃貸借契約書の記載が問題にはなりますが、一般的には、賃借人は退去時に原状回復しなければならない(「原状回復義務」と呼ばれます。)と定められていることがほとんどですので、以下ではそのような前提でご説明します。
過去の判例で、通常損耗と経年変化(劣化)については、原状回復義務には含まれないと判断されています。つまり、賃借人は「通常使用による損耗・経年劣化」については原則として修繕義務を負いません。
もっとも、故意・過失、善管注意義務違反(善良な管理者としての注意義務)に基づく損耗や損傷については、原状回復費用を負担する義務が生じます。
ここであげたように、通常損耗と経年変化については、賃料に含まれる部分と解されるので、基本的には大家さんの負担ということになります。
どのようなケースで大家さんの負担になり、どのようなケースで賃借人の負担となるかは、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」が参考になります(https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf)。
2. 対応の流れ
(1) 証拠資料の確保と記録
賃借人が修繕費を任意に支払うことを拒む場合、請求の根拠となる資料を確保することが大切です。具体的なには以下のような資料です。
・退去時の損傷状況の写真や動画:複数の位置から残しておくと安心
・入居時の現場状況の写真や動画:入居中の損傷であると特定するために必要
・修理業者の見積書:修理内容と金額の特定に必要
・損傷原因の調査報告書:賃借人の故意・過失の判断に必要(必要に応じて)
(2) 説明と交渉
まずは、上記のような資料を提示しつつ、賃借人が負担すべき費用であることを説明して、修繕費用の負担を求めます。各種資料については、コピーを渡してしまった方が賃借人側の検討材料になるので望ましいケースが多いです(個人情報等には配慮が必要です。)。必要に応じて、国交省のガイドラインの該当箇所も参考資料として送ることも有益です。また、受領を確認する意味でも、配達記録郵便やレターパックを利用することが望ましいです。
電話や対面でやり取りする場合は、交渉経過を残す意味で、できる限り録音・録画を残しておくとよいでしょう(録音・録画にあたって相手方の了解を得る必要はありません。)。
(3) 話合いで解決しない場合は
話合いで解決しない場合、内容証明郵便による請求、調停や訴訟などの法的措置に進む必要があります。いずれかの段階では、弁護士に相談・依頼する必要が出てくると思います。
3. 泣き寝入りしないために
以上のとおり、床の損傷部分の修繕費を賃借人に請求できるかどうかは、損傷の状況や程度と、それに対して有益な証拠資料を確保できるかが重要なポイントになります。
そもそも賃借人に請求できる損傷なのか、できるとしてどのような証拠資料が必要か、など、法的に複雑な問題が含まれるケースも多いです。
弁護士であれば、必要な証拠資料の提案や交渉の進め方の助言も可能です。依頼するか否かにかかわらず、早めにご相談いただくことが望ましいと思います。
回答者
後藤 謙治さんプロフィール
数万件規模の物件を管理する賃貸管理会社を顧問先として複数有する事務所にて執務。退去・隣地・承継問題など大家さんに関わる様々な法律問題に対応した実績がある。
中小企業から上場企業まで、多数の企業事案を経験しており、クレーム対応にも豊富な実績がある。
相続や離婚・交通事故など一般民事にも幅広く対応可能。
弁護士向けの研修や市民向けセミナー、経営者向けの勉強会などの講師実績あり。
お問合せは下記より。
中小企業から上場企業まで、多数の企業事案を経験しており、クレーム対応にも豊富な実績がある。
相続や離婚・交通事故など一般民事にも幅広く対応可能。
弁護士向けの研修や市民向けセミナー、経営者向けの勉強会などの講師実績あり。
お問合せは下記より。

木﨑 海洋さん
張り替えるレベル、とはよほどひどい状況ですね。
経年劣化か入居者の過失か…原因の究明が何よりの解決策ですね。
多少の水がはねることは想定できますが、おそらくこのような通常使用を超えたものでしょう。
入居の際の「室内確認書」や「写真」があるでしょうか。
入居時と退去時の比較になり、入居者の過失を認めさせやすくなります。
また、まだ敷金の清算をしていなければ専門業者に状況を確認してもらい、原因の特定をしてもらえば入居者も認める可能性があります。
経年劣化か入居者の過失か…原因の究明が何よりの解決策ですね。
多少の水がはねることは想定できますが、おそらくこのような通常使用を超えたものでしょう。
入居の際の「室内確認書」や「写真」があるでしょうか。
入居時と退去時の比較になり、入居者の過失を認めさせやすくなります。
また、まだ敷金の清算をしていなければ専門業者に状況を確認してもらい、原因の特定をしてもらえば入居者も認める可能性があります。
回答者
木﨑 海洋さんプロフィール
相続専門の行政書士と不動産取引・FP業務を行う。
同時に「こころ亭久茶」として「落語で学ぶ相続と不動産」などセミナー講師をする。
落語形式の講演は珍しく、難しい話を笑いながら学習できると評判となり全国で年間140回の講演をする。
著作物に、「家の光(農協グループ月刊誌)タイトル:こころ亭久茶の相続&マネー高座」「全国商工会議所:資金繰りは企業の生命線」がある。そのほか、新聞や雑誌のコラムも手掛ける。
同時に「こころ亭久茶」として「落語で学ぶ相続と不動産」などセミナー講師をする。
落語形式の講演は珍しく、難しい話を笑いながら学習できると評判となり全国で年間140回の講演をする。
著作物に、「家の光(農協グループ月刊誌)タイトル:こころ亭久茶の相続&マネー高座」「全国商工会議所:資金繰りは企業の生命線」がある。そのほか、新聞や雑誌のコラムも手掛ける。

藤井 健太郎さん
重要なのは、その破損が「経年劣化」なのか、それとも「入居者の不適切な使用・管理によるもの」なのかを明確にすることです。
賃貸借契約における原状回復義務は、通常損耗や経年劣化を除いた部分に適用されます。
つまり、今回の床の腐食が、単なる年月の経過によるものではなく、例えば水漏れを放置したなど、入居者の過失によって引き起こされたことを認めさせる必要があります。
今後のトラブルを避けるためにも、入居時のキッチンの床の状態がわかる写真などを必ず保管しておくことをおすすめします。
そうすることで、「入居時にはこんな状態ではなかった」という明確な証拠となり、万が一の際にスムーズな解決につながります。
賃貸借契約における原状回復義務は、通常損耗や経年劣化を除いた部分に適用されます。
つまり、今回の床の腐食が、単なる年月の経過によるものではなく、例えば水漏れを放置したなど、入居者の過失によって引き起こされたことを認めさせる必要があります。
今後のトラブルを避けるためにも、入居時のキッチンの床の状態がわかる写真などを必ず保管しておくことをおすすめします。
そうすることで、「入居時にはこんな状態ではなかった」という明確な証拠となり、万が一の際にスムーズな解決につながります。
回答者
藤井 健太郎さんプロフィール
祖父母の代から続く三代目大家。
200戸の物件を自主管理し、原状回復やリフォームも自ら手がけてきました。新築から築古、単身からファミリー向けまで幅広い物件を運営する中で、夜逃げ、孤独死、火災、訴訟、デッドクロス、資金ショートなど、数々の困難を経験。
これらの経験から賃貸業の厳しさを痛感し、物件分析、市場分析、月次・年次分析を取り入れた経営に転換。
キャッシュフローを改善させ、現在は自身の経験を活かし、不動産管理やコンサルティングを通じて大家さんの支援を行っています。
200戸の物件を自主管理し、原状回復やリフォームも自ら手がけてきました。新築から築古、単身からファミリー向けまで幅広い物件を運営する中で、夜逃げ、孤独死、火災、訴訟、デッドクロス、資金ショートなど、数々の困難を経験。
これらの経験から賃貸業の厳しさを痛感し、物件分析、市場分析、月次・年次分析を取り入れた経営に転換。
キャッシュフローを改善させ、現在は自身の経験を活かし、不動産管理やコンサルティングを通じて大家さんの支援を行っています。
※回答内容は、すべてのケースに該当するものではありません。
より詳細な回答を求められる場合は、個別で専門家に相談することをお勧めいたします。
関連記事
-
-
-
- 2025.06.25
- アパート・マンション建築
- Q&A
-