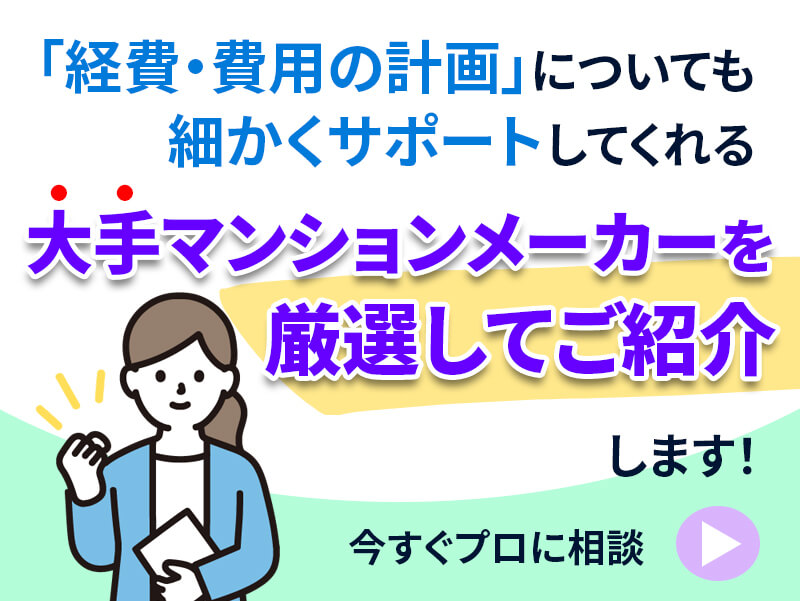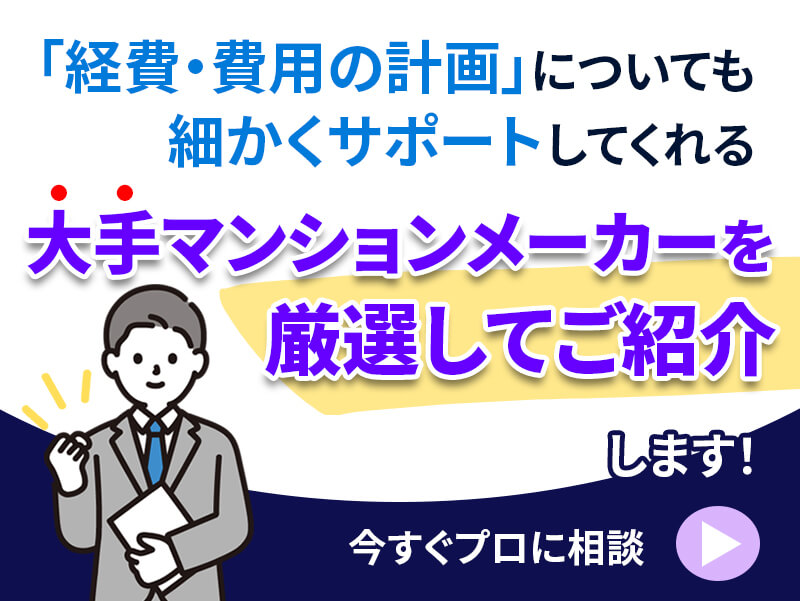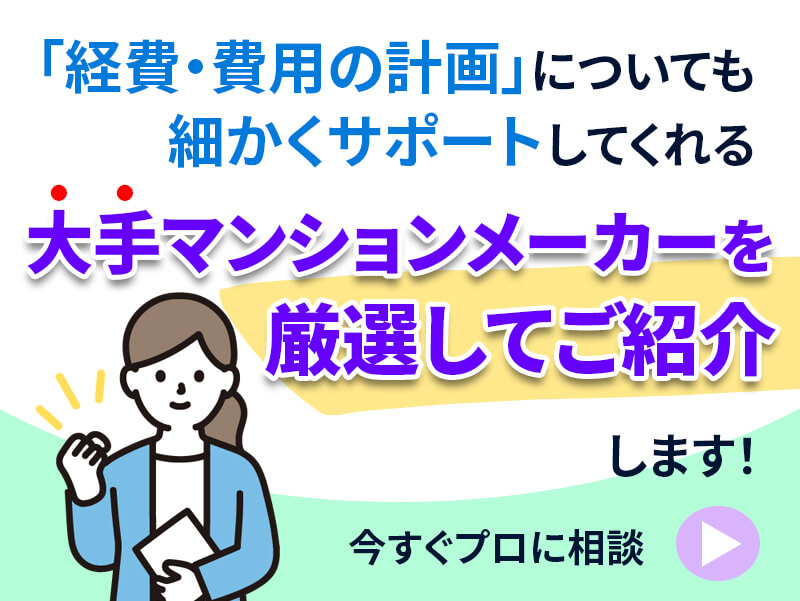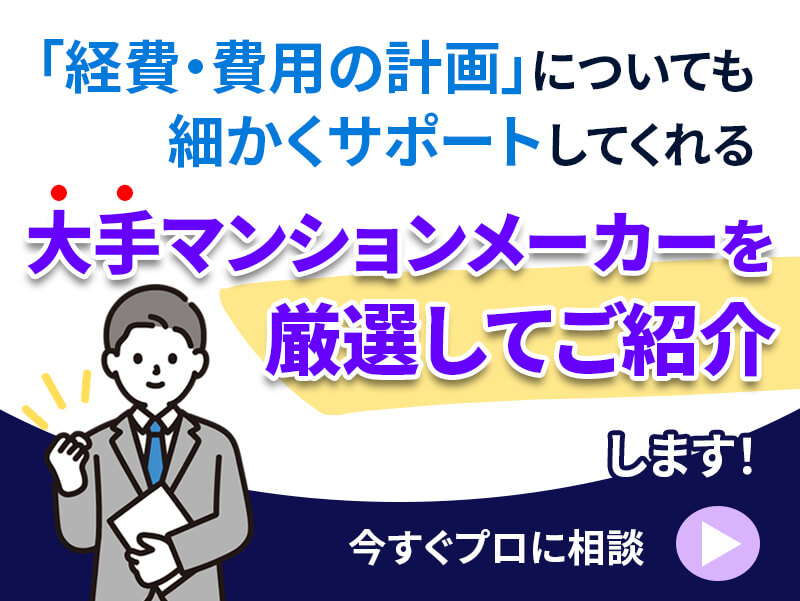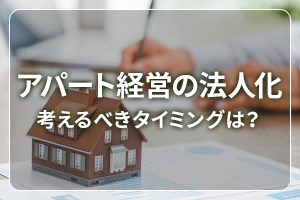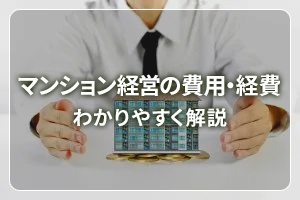
この記事では、現在土地を持っている人向けに、マンション経営で必要となる費用の費目とその概要について解説します。
「マンション経営の費用と経費の百科事典」としてご活用ください。
また、以下のボタンから土地情報を入力すると、最大10社のハウスメーカーがあなたの土地に合った、建築費の見積もりや、収支計画を無料診断いたします。
「うちの土地にはいくらでマンションが建つの?」「いくら儲かるのか知りたい」という方はご活用ください。
マンション経営においての経費とは?
マンション経営の経費は、あくまでも「マンション経営で収益を生み出すために要した費用」だけです。
マンションの収益化につながらない、個人として消費した通信費や交通費などの“プライベート上の支出”は、経費として認められません。
マンション経営上の経費にあたらないものは?
「会計上の損益でないもの(例えば不動産投資用ローンの返済)」や「資本的支出(資産の価値を増やすための支払い)」は、経費として計上することができません。」
「資本的支出」については、発生した年は経費として一括計上できないものの、翌年以降に「減価償却費」という形で経費として計上することができます。
マンション経営上の出費で、経費として計上できるもの・できないものは?
マンション経営に必要となる費用の中で、経費として計上できるものは、以下の通りです。
- 不動産取得税
- 登記費用
- 印紙税
- 火災・地震保険料
- (ローン関連の)事務手数料
- (ローン関連の)保証料
- 固定資産税及び都市計画税
- 事業税
- 修繕費
- 管理委託料
- (入居者募集のための)仲介手数料
- 広告宣伝費
- 給料・賃金
- 水道光熱費
- 通信費
- 交通費
- 接待交際費
- 新聞図書費
- 消耗品費
- 地代・家賃
- ローン金利
- 減価償却費
- 解体費・立退料
一方で、マンション経営に必要な費用のうち、経費として計上できないものとしては以下が挙げられます。
- 物件の購入代金
- (不動産購入の際の)仲介手数料
- 団体信用生命保険特約料
- 固定資産税清算金
上記の全27種類の費用は、それぞれ発生するタイミングが異なります。
「経費・費用の計画」についても細かくサポート
詳しい解説は以下
目次
1.マンション経営における経費の基本的な考え方
マンション経営における「経費になるもの」と「経費にならないもの」をおおまかに区別できるようになるために、まずは「経費とはどんなものか」を理解しましょう。
個人でマンション経営を行う場合、生活費などの「プライベートの支出」と「マンション経営のために要した費用」を明確に分ける必要があります。
経費の中には「接待交際費」や「交通費」「通信費」「新聞図書費」「消耗品費」などプライベート支出と混同されやすい費目もありますが、「マンション経営のために要した支出のみが費用である」ことを念頭に、経費と経費以外(プライベート)の支出を明確に分けましょう。
2.マンション経営で経費にならない支出について
マンション経営の経費として認められない支出としては、前章でお話しした「プライベートの支出」の他に
- 会計上の損益でないもの
- 資本的支出
の2種類があります。
以下、この2種類が経費計上できない理由について解説します。
2-1.会計上の損益でないもの
支払ったお金が経費として認められる要件としては、「会計上の損益」に該当する必要があります。
例えば、借入金の場合を考えてみましょう。
お金を借りると手元に現金が入ってきますが、お金を借りることで「利益が生まれた」わけではありません。
(会計上は、借入金の分増えたお金は「損益計算書上の利益」ではなく「貸借対照表上の資産および負債の増加」にあたります。)
一方で、お金を返すことで手元から現金が減りますが、これも上と同じ考え方をします。
つまり、お金を返すことで現金が減ったとしても「損失が生じた」わけではありません。(会計上は「資産および負債の減少」にあたります。)
上記の借入金の例以外にも「会計上の損益」ではなく「貸借対照表上の資産・負債の増減」にあたる支払いは経費として計上できません。
2-2.資本的支出
資本的支出は「新たに資産を構築したとみなされる支出」を意味します。
一ヶ所あたりの工事が20万円以上となると、経費ではなく資本的支出として扱われます。
資本的支出は「新たな資産を作ったこと」と同じ扱いになるため、そのお金はいったん資産として計上され、減価償却の対象となります。
つまり、資本的支出となると「支出したお金を一括して費用計上すること」はできません。経費として一括計上できない代わりに、耐用年数の期間にわたって「減価償却費」として費用計上することができます。
具体的には、資本的支出をおこなった年の翌年以降、一定の割合で「減価償却費」を計上していきます。
3.マンション購入・経営にかかる初期費用
マンション購入や経営に着手した直後から発生する費用についてリストアップしました。
| 費用の名称 | 経費計上の可否 | |
|---|---|---|
| 1 | 不動産取得税 | ◯ |
| 2 | 登記費用 | ◯ |
| 3 | 印紙税 | ◯ |
| 4 | 火災・地震保険料 | ◯ |
| 5 | (ローン関連の)事務手数料 | ◯ |
| 6 | (ローン関連の)保証料 | ◯ |
| 7 | 物件の購入代金 | ✕ |
| 8 | (不動産購入の際の)仲介手数料 | ✕ |
| 9 | 団体信用生命保険特約料 | ✕ |
| 10 | 固定資産税清算金 | ✕ |
3-1.不動産取得税
不動産取得税は、土地や建物を取得した際に課される税金です。経費として計上できます。
土地・建物を購入すると同時に税を支払うわけではなく、購入後、所有権移転の登記から3ヶ月〜1年ほどしたタイミングで、行政から納付書が送られてきます。
不動産取得税の計算式
不動産取得税=固定資産税評価額×4%
上の式の「固定資産税評価額」は取得時の時価とは異なります。
一般的には時価よりも固定資産税評価額のほうが低く、土地の評価額は時価の7割、建物の評価額は時価の5〜6割程度の水準です。
例えば、3,000万円で取得した土地の場合、不動産取得税は以下のように計算します。
不動産取得税の事例
不動産取得税=固定資産税評価額(3000万円×70%)×4%=84万円
上記の計算例のように、不動産取得税は一度に数十万円を超える支払いとなるのが一般的なので、オーナーにとっては大きな金銭的負担がかかる費用ですが、幸い経費として計上できます。
また、戸建て以外の貸家(マンション等)については、住宅部分の床面積が、40平米以上240平米以下であると、不動産取得税の軽減措置を受ける事が出来ます。
具体的には、固定資産税評価額から1200万円を控除できます。
不動産取得税の軽減措置の効果は大きく、面積要件を満たすと木造や軽量鉄骨造のマンションでは不動産取得税がゼロになることもあります。
この様に1戸あたりの面積を意識すると、不動産取得税を節税することができます。
3-2.登記費用
登記費用は、取得した不動産について「この不動産の所有者は私です」というふうに、不動産の所有権を登記する際にかかる費用です。
登記の手続きは司法書士に代行してもらうのが一般的です。
登記にかかる費用には、登記の手続きに課せられる「登録免許税」という税金と、代行手続きを代行してもらう司法書士へ払う報酬の2種類があります。
登録免許税・司法書士への報酬ともに、経費として計上できます。
- ◎登録免許税
-
【登録免許税のかかる登記の種類】 登記の種類 税率(土地) 税率(建物) 所有権移転登記 評価額×税率2.0% 課税額×税率2.0% 所有権保存登記(新築建物) – 評価額×税率0.4% 抵当権設定登記
(住宅ローン借り入れ)借入額×税率0.4% 借入額×税率0.4% 例えば、2022年4月に2000万円で新築建物を購入し、また1500万円の住宅ローン融資を受けた場合、登録免許税は以下のように計算します。
登録免許税=所有権保存登記+抵当権設定登記
=2000万円×70%×税率0.4%+住宅ローン借入額1500万円×税率0.4%
=5万6千円+6万円
=11万6千円 - ◎司法書士報酬
-
租税公課としての登録免許税とは別に、登記を代行してくれた司法書士へ払う手数料としての報酬が司法書士報酬です。
司法書士報酬の金額については、土地の売買による所有権移転登記の場合は平均4万円〜7万円、抵当権設定登記の場合は3万円〜5万円となっています。司法書士報酬の相場は、お住まいの地域によっても異なるようです。
三大都市圏の位置する関東・近畿・中部においては、その他の地方に比べてやや高めの相場となっています。
「経費・費用の計画」についても細かくサポート
3-3.印紙税
マンションを売買する際に交わす契約書には、収入印紙を貼ることが義務付けられています。
この収入印紙を購入する際の代金という形で徴収されるのが印紙税です。
印紙税は不動産の価格に応じて変化し、また経費として計上できます。
不動産売買契約において、印紙税の額は以下の通りとなっています。
| 契約金額 | 本則税率 |
|---|---|
| 100万円を超え、500万円以下のもの | 2千円 |
| 500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 |
3-4.火災・地震保険料
災害の多いわが国において火災や地震のリスクは高く、多くのオーナーがマンション取得時に火災・地震保険に加入しています。
地震保険料は火災保険のオプションとして用意されていることが一般的です。
火災・地震保険料は保険会社によって異なります。
例えば損害保険大手の三井住友海上が提供する「GK すまいの保険」の場合、火災保険の保険料は5年契約で214,800円、地震保険料をセットした場合では426,800円となります(2022年3月時点)。
火災・地震保険の保険料は、経費として計上できます。
ただし、複数年分の保険を一括契約した場合、一年度に全額経費計上できるわけではなく、一会計年度毎に一年分までの経費計上が認められています。
例えば上記した三井住友海上の「GK すまいの保険」の場合、1会計年度に経費計上できる額は、火災保険のみなら42,960円、地震保険をセットした場合は85,360円です。
3-5.(ローン関連の)事務手数料
マンション取得に要する費用について銀行から融資を受ける場合、銀行側に支払うことになるのが事務手数料です。
経費として計上できます。
事務手数料の支払額は、定額制と定率制の2種類があります。
定額制の場合、金額は3万円前後が相場です。
定率制はローンの金額に一定の率を掛けた金額を支払うもので、1%から3%が相場となっています。
例えば、融資を受ける金額が1千万円、手数料の料率が2%の場合、事務手数料の金額は
1千万円×2%=20万円
となります。
ここまで読むと「定額制のほうが金額が少なくて済む」という印象を受けられるかもしれません。
実際に、事務手数料だけに関して言えば定額制を選んだほうが手数料を抑えられるケースが多いのは確かですが、一方で定額制のほうがローンの金利が高いなど、他の条件で定率制を選んだほうが有利になる場合もあります。
3-6.(ローン関連の)保証料
保証料は、連帯保証人の代わりにローンを保証してくれる「保証会社」へ支払う料金です。
ローン関連の保証料は経費として計上できます。
多くの銀行や金融機関が、融資の条件として保証会社との契約を条件としています。
保証料の支払いには、「借入時に一括して支払う方法」と「毎月のローン返済時、返済額にローン保証料を含めて支払う方法」があります。
マンション経営の開始時に「借入時に一括して支払う方法」の場合は、借り入れるローンの額の2%程度が相場です。
3-7.物件の購入代金
物件購入の代金として支払うお金は、頭金(ローンではなく自己資金で支払う費用)、ローンで賄った分を問わず、経費として計上できません。
物件の購入に要した代金は、物件という貸借対照表上の「資産」そのものであり、すでにご説明した「資本的支出」にあたるため、経費計上が不可能となります。
3-8.(マンション購入時の)仲介手数料
マンション購入の際の仲介手数料は、不動産会社に物件購入を仲介してもらう際、手数料として支払うものです。
不動産会社を介さずに独力で物件を購入する場合、この仲介手数料はかかりません。
仲介手数料の上限は、宅建業法により「物件の売買価格×3%+6万円」と定められています(売買価格が400万円を超える場合)。
例えば、マンションを1,000万円で購入した場合、
仲介手数料の上限=1,000万円×3%+6万円
=36万円
となります。
仲介手数料は、物件購入初期にかかる費用の中でも比較的高額です。
仲介手数料として支払った金額は「費用」ではなく、「マンションの購入費用の一部」として、マンションの売買金額と合算することになります。
つまり、「資本的支出」として見なされるため、経費として計上することはできません。
経費計上できない一方で、資本的支出の一部として、以後の耐用年数にわたって減価償却される対象となります。
3-9.団体信用生命保険特約料
金融機関から融資を受けて不動産を購入する場合、「団体信用生命保険(団信)」への加入を勧められる場合があります。
団体信用生命保険は、ローンの契約者に万一の事故や病気が生じて残債を返済できなくなってしまった場合、返済義務を免除するというものです。
団体信用生命保険の掛け金は「特約料」という形で、金融機関への毎月のローン返済の際、金利に上乗せされる形で支払うことになります。
特約料の相場としては、年間の住宅ローン金利の0.2%〜0.4%程度です。
例えば500万円の融資を受けている場合、上乗せされる金利は年間で1〜2万円となります。
経費計上の可否についてですが、個人として団体信用生命保険の特約に加入する場合、特約料は経費計上することができません。
理由としては、団体信用生命保険への加入は「事業から収益を得る上で必要なもの」ではなく、「個人の身に万一のことがあった場合への備え」として見なされるので、マンション経営に必要な経費とは認められないためです。
一方で法人の場合、団体信用生命保険の保険料は経費計上することが認められます。
3-10.固定資産税清算金
固定資産税清算金とは、もともと不動産を所有していた売主が「払い過ぎてしまう税金」を売買価格に上乗せする形で、買主が負担するものです。
売主の側に「払い過ぎてしまう税金」が発生する理由は、たとえ物件を売却した後であっても、その年の1月1日時点で所有していた人(売主)がその年の固定資産税・都市計画税などを納める義務があるからです。
年のはじめに所有していた物件については、たとえ1月2日以降に売却したとしても、元々の所有者(売主)が一年分の固定資産税・都市計画税を納めなければなりません。
ゆえに、売主からしてみれば「払い過ぎ」となってしまう税金を買主との間で調整するために、「清算金」という形で売買価格に上乗せして取引する、という慣例があるのです。
この固定資産税清算金は、内容としては「税金の調整のための金銭のやりとり」でありながら、「不動産の売買価格への上乗せ」という形をとるため、経費として計上することはできません。
「経費・費用の計画」についても細かくサポート
4.マンション経営の維持にかかる費用
マンション経営開始後、マンションが耐用年数を迎えるまでの数十年間、定期的な支払いが見込まれる費用についてリストアップしました。
| 費用の名称 | 経費化の可否 | |
|---|---|---|
| 1 | 租税公課 | ◯ |
| 2 | 修繕費 | ◯ |
| 3 | 管理委託料 | ◯ |
| 4 | (入居者募集のための)仲介手数料 | ◯ |
| 5 | 広告宣伝費 | ◯ |
| 6 | 青色事業専従者給与 | ◯ |
| 7 | 給料・賃金 | ◯ |
| 8 | 水道光熱費 | ◯ |
| 9 | 通信費 | ◯ |
| 10 | 交通費 | ◯ |
| 11 | 接待交際費 | ◯ |
| 12 | 新聞図書費 | ◯ |
| 13 | 消耗品費 | ◯ |
| 14 | 地代・家賃 | ◯ |
| 15 | ローン金利 | ◯ |
| 16 | 減価償却費 | ◯ |
4-1.租税公課
マンション経営では、「固定資産税・都市計画税」、「事業税」といった税金を経費として計上することができます。
以下、それぞれの詳細を見ていきましょう。
4-1-1.固定資産税及び都市計画税
固定資産税とは、毎年1月1日時点の不動産の所有者に対し課税される市区町村税です。
都市計画税とは、毎年1月1日時点における都市計画で指定されている「市街化区域内の不動産の所有者」に対し課税される市区町村税を意味します。
固定資産税の税率は1.4%、都市計画税の基本税率は0.3%です。
それぞれの計算方法は以下のようになります。
固定資産税 = 課税標準額 × 1.4%
都市計画税 = 課税標準額 × 0.3%
出典:東京都主税局
建物の課税標準額は、固定資産税評価額となります。
例えば、評価額1,500万円のマンションを所有していた場合、固定資産税・都市計画税の計算はそれぞれ
固定資産税=1500万円×1.4%
=21万円
都市計画税=1500万円×0.3%
=4.5万円
一方で、土地については住宅用地の軽減措置が適用されるため、固定資産税評価額に一定の乗数を乗じたものが課税標準額です。
住宅用地の軽減措置が適用される住宅用地は、「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」の2つにわかれ、それぞれ固定資産税評価額に以下の係数が乗じられて課税標準額が求められます。
| 区分 | 定義 | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 住宅用地で住宅1戸につき200平米までの部分 | 1/6 | 1/3※ |
| 一般住宅用地 | 住宅用地で住宅1戸につき200平米を超え、家屋の床面積の10倍までの部分 | 1/3 | 2/3 |
※東京23区はさらに1/2
出典:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)【土地】2 住宅用地及びその特例措置について」
小規模住宅用地は住宅1戸につき200平米まで適用されますので、例えば戸数が10戸のマンションなら2,000平米の広さの土地までが小規模住宅用地の対象です。
よって、マンションの敷地では多くのケースで敷地全体が小規模住宅用地となります。
4-1-2.事業税
個人が10室以上のマンションの貸付を行った場合、「事業税」という名目で都道府県から課税されます。
事業税は、不動産所得から事業主控除額(290万円)を控除した額に標準税率5%を乗じて求めます。
事業税の計算式
事業税 = (総収入金額 - 必要経費 - 事業主控除額) × 税率
= (総収入金額 - 必要経費 - 290万円) × 5%
事業税の納付は、通常、8月と11月の年2回で、都道府県から届く納税通知書によって納付を行います。
所得税の申告内に事業税の記載欄がありますので、所得税を申告していれば事業税の申告を別途行う必要はありません。
4-2.修繕費
屋根や外壁、設備などの劣化を補うために支払った修繕費は、必要経費として計上することができます。
ただし、その年に全額経費として落とせる修繕費は、1ヵ所当たりの修繕費用が20万円未満の工事までです。
20万円以上の工事を行うと、「新たに資産を作ったもの」として扱われるので、2章でご説明した「資本的支出」として見なされます。
したがって、その年に全額を経費として落とすことができず、翌年以降に減価償却費という形で計上していくことになります。
マンション経営の中でかかってくる修繕費の中でも代表的なものは外壁塗装です。
4-3.管理委託料
管理委託料とは、所有するマンションの管理を不動産管理会社などへ、委託形式で管理を依頼する場合にしたときに発生する費用であり、経費としての計上が認められています。
マンション経営の管理委託料は、家賃収入の5%程度が相場となります。
マンションオーナーが自ら管理会社を設立している場合、経費として認められる条件は「管理料が相場の範囲であること」と「管理の実態があること」の2つです。
管理費を否認されないようにするには、通帳等で管理会社の入出金の履歴を残すことや、業務日誌を付けておくことが必要となります。
なお、サブリース形式で管理を行っている場合は、管理委託料は発生しません。
サブリースとは転貸形式(所有する物件を不動産管理会社に貸し、不動産管理会社が入居者へ“又貸し”する形式)による管理です。
サブリース形式では、サブリース会社が入居者の賃料から一定の料率分を差し引いたうえで、賃料としてマンションオーナーへお金を振り込みます。
したがって、サブリースの契約においては、管理委託料は生じないことになります。
4-4.(入居者募集のための)仲介手数料
空室が生じた際、オーナー自身が入居者を募集するのではなく、不動産会社へ募集を任せることが一般的です。
入居者の募集を仲介してもらうために不動産会社に支払った手数料は、経費として計上することができます。
入居者募集の仲介手数料として不動産会社が受け取れる金額の上限は、宅建業法により賃料の1ヶ月分と決められています。
4-5.広告宣伝費
空室の入居者募集をする際、不動産会社に広告宣伝費を支払う場合もあります。
広告宣伝費についても、経費として計上できます。
4-6.青色事業専従者給与
青色事業専従者給与とは、「青色申告者と生計を一にする15歳以上の配偶者その他の親族への給与」のことです。
青色申告をしていて、かつ10室以上のマンションである場合、「青色事業専従者給与」を経費とすることが可能です。
ただし、青色事業専従者給与は仕事に見合った給与でないと、否認されることがあります。
定期巡回や入出金管理等、実際に管理の仕事を行うことが必要です。
4-7.給料・賃金
マンション経営で従業員を雇っているケースでは、従業員への給料賃金も経費となります。
給料賃金も経費として計上することができますが、経費として認められるには相応の労働が伴っていることが必要です。
したがって、家族親類などを「名目上の従業員」に据えて、労働の実態が伴わない状態で経費計上することはできません。
4-8.水道光熱費
マンションの水道光熱費は経費計上可能です。
防犯カメラの電気代など、マンションの共用部で生じている水道光熱費が該当します。
さらに、自宅を不動産賃貸業の事務所として使っている場合は、その事務所スペース部分の水道光熱費も経費として認められる可能性があります。
4-9.通信費
マンション経営に要した郵便・電話料等の通信費も経費として計上可能です。
例えば、不動産会社との連絡にかかった電話代が該当します。
4-10.交通費
マンション経営のための視察などに支払った交通費は経費として計上することができます。
例えば、遠方にマンションを保有しており、現地のマンションを確認するために出張した場合などに要したガソリン代や電車賃等は費用にあたります。
4-11.接待交通費
マンション経営のための情報収集に使用した接待交通費は経費として計上することができます。
例えば、マンション経営の情報交換のために使った飲食費用やゴルフ代、管理会社に送ったお中元・お歳暮の費用が該当します。
4-12.新聞図書費
マンション経営のための情報収集用に購入した新聞や図書・資料などの購入代金は、費用として計上できます。
具体的には、不動産系の業界新聞の購読、マンション経営を学ぶために購入した本などが該当します。
4-13.消耗品費
マンション経営のために使用した消耗品費であれば、経費として計上できます。
消耗品費には、文房具代の他、耐用年数が1年未満もしくは取得価額が10万円未満の備品等の代金が該当します。
例えば、管理で使っているプリンターの用紙代やインク代は消耗品費にあたります。
4-14.地代・家賃
借地でマンション経営をしている場合は、地代も経費として計上できます。
また、他の人が所有するマンションを借りた上で転貸によってマンション経営をしている場合にも、支払っている家賃を経費として計上可能です。
ただし、地代及び家賃の支払いが経費として認められるためには、土地やマンションの所有者が家族などではなく、他人である必要があります。
生計を一にする親族(つまり日常的に同居している家族や親戚)から土地やマンションを借りている場合には、支払った地代や家賃は経費として計上することができませんのでご注意ください。
4-15.ローン金利
不動産投資用のローンを組んでいる場合、ローンの金利に当たる部分の返済については経費として計上できます。
ただし、金利の返済分は経費として計上できますが、「元本」の返済分は経費として計上できませんのでご注意ください。
4-16.減価償却費
減価償却費とは、建物や設備が経年劣化することによる価値の減少分を「会計上の費用」として計上することが認められているものです。
「実際のお金の出費が伴わない費用」という特殊な性質を持っています。
減価償却費を具体的に計算する方法としては、固定資産の取得に要した金額(マンション経営の場合は建物の購入価格)を、耐用年数で按分し、それぞれの会計年度ごとに「その期の費用」として計上していきます。
平成27年(2016年)4月1日以後に取得したマンションに関しては、定額法と呼ばれる計算方法で減価償却費を計上します。
定額法による減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率
定額法の償却率は、マンションの建物構造によって数値が定められています。
マンションの構造と耐用年数の関係は以下の通りです。
| 構造 | 耐用年数 |
|---|---|
| 木造 | 22年 |
| 木造モルタル | 20年 |
| 鉄骨造(3mm以下) | 19年 |
| 鉄骨造(3mm超4mm以下) | 27年 |
| 鉄骨造(4mm超) | 34年 |
| 鉄筋コンクリート造 | 47年 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 47年 |
「経費・費用の計画」についても細かくサポート
5.後期(耐用年数経過後)にかかる費用
マンションが耐用年数を迎え、売却を含めた出口戦略を検討しはじめる時期に発生する費用としては、「解体費・立退料」があげられます。
5-1.解体費・立退料
老朽化したマンションを解体し、新しい投資用マンションを建て替えるために要した解体費や、入居者に出て行ってもらうために支払った立ち退き料は、経費として計上することができます。
ただし、経費として認められるのはあくまでも「投資用のマンション建て替え」に限ります。
解体の目的が、投資用物件ではなくオーナー自身が住む自宅への転用である場合は、マンション経営により収益を生むという目的のための建て替えにあたらないため、経費として計上することは認められません。
6.マンション経営に強いハウスメーカー・建築会社を選ぶためのポイント
マンション経営を順調に行い、資産を堅実に積み重ねるためには、今回の記事で紹介したような費用の種類、そして「費用の中でどれが経費として計上できるか」を把握したうえで運営していくことが不可欠です。
とはいえ、オーナー自身がすべてを独力で判断していくのは難しいところです。
実際に、マンション経営で成果を挙げている大家さんの中にも、信頼できるハウスメーカー・建築会社から効果的なアドバイスを受けている方が多くいます。
そこで、安心して相談できるハウスメーカー・建築会社を選ぶためのポイントについてピックアップしました。
6-1.ハウスメーカー・建築会社の提示する「経営プラン」
多くのオーナーの方々はマンションを建築するタイミングで、建築にかかる費用や工法、出来上がる物件などのことばかりを気にかけがちですが、出来上がった後の収益を左右する要素として「マンション完成前・完成後の経営プラン」も非常に重要です。
各ハウスメーカーが提示しているランニングコストや収支計画をチェックすることによって「より具体的で現実性が高い計画」を掲げている会社を選ぶことが重要です。
(各社ごとに、意外なほど内容の差があるのがお分かりいただけるはずです)
6-2.評判・口コミ
ハウスメーカー・建築会社の評判や口コミについては、インターネットを活用することによって業者の立場から独立した中立な意見を拾うことができます。
特に近年では、通常のGoogle検索の他に、SNS上で情報を探すことによって「生のユーザーの声」を見つけやすくなっているので、ぜひご活用ください。
6-3.問い合わせへの対応
問い合わせへの応対が手厚い会社であれば、実際に契約を結んだ後のフォローの質にも期待できるでしょう。
気になるハウスメーカー・建築会社があれば、事前にメールで相談してみて、担当者がどれぐらい丁寧に応対してくれるかを確かめるのも一手です。
関連記事
-
- 2025.01.23
- 経営ノウハウ
-