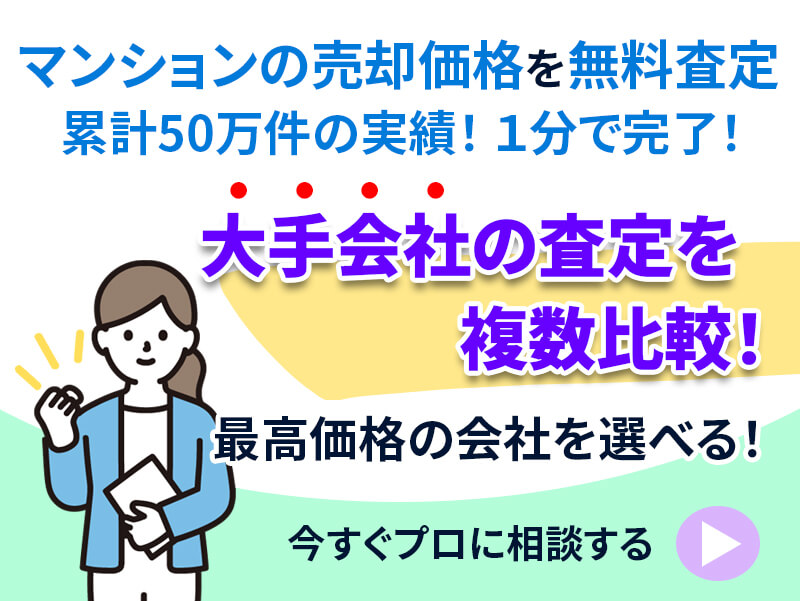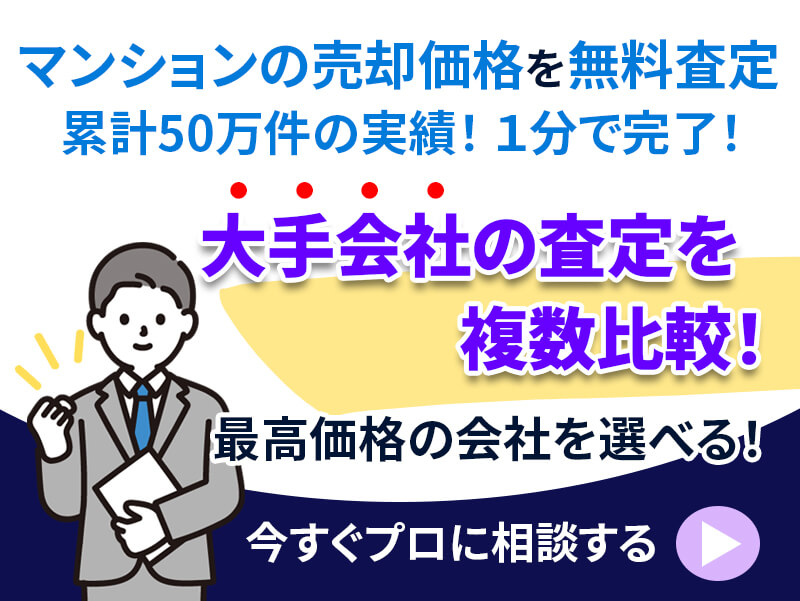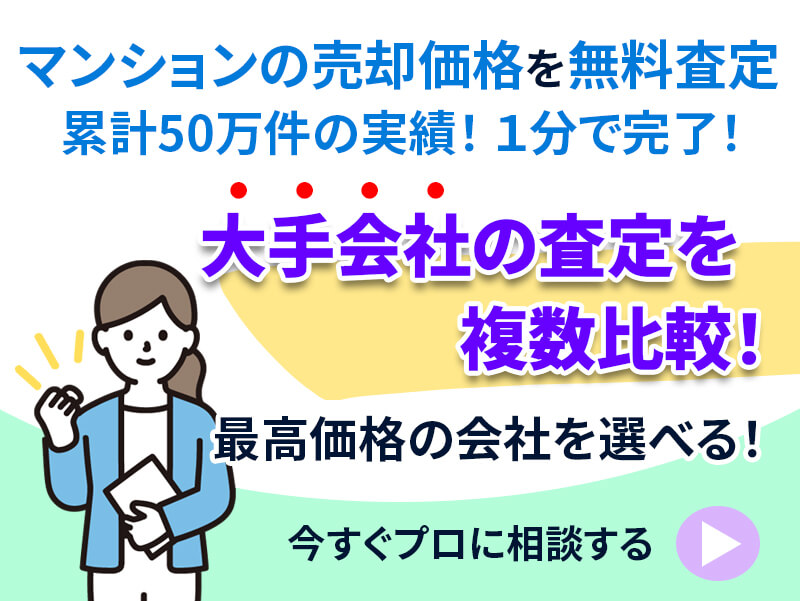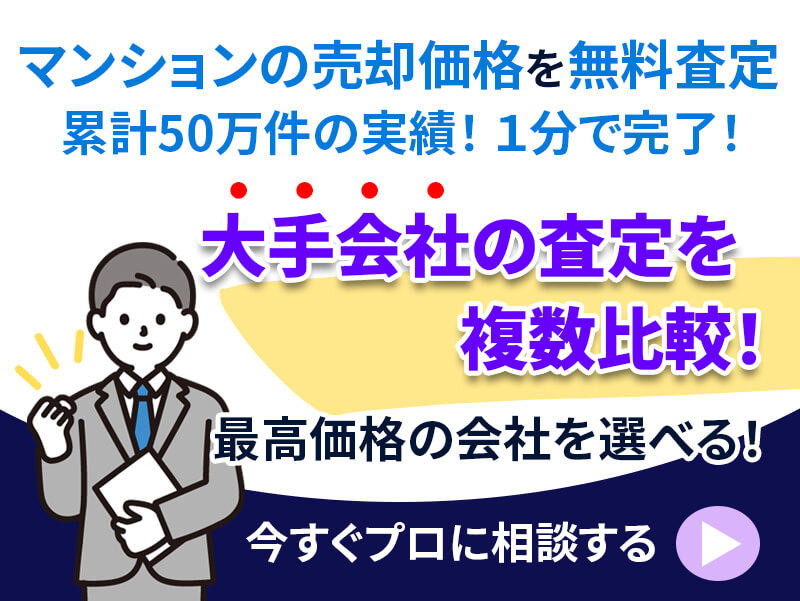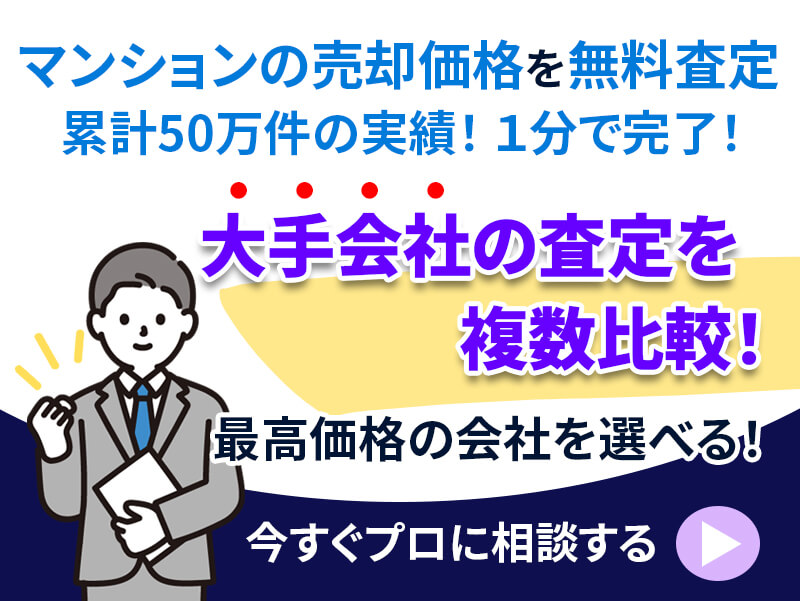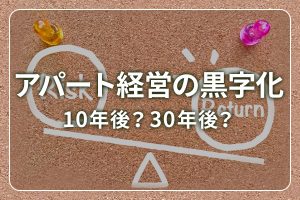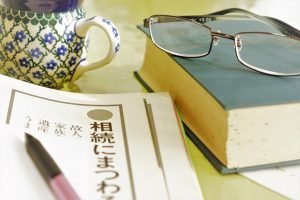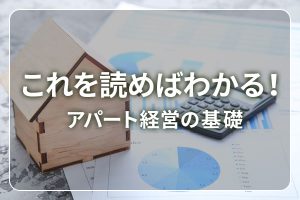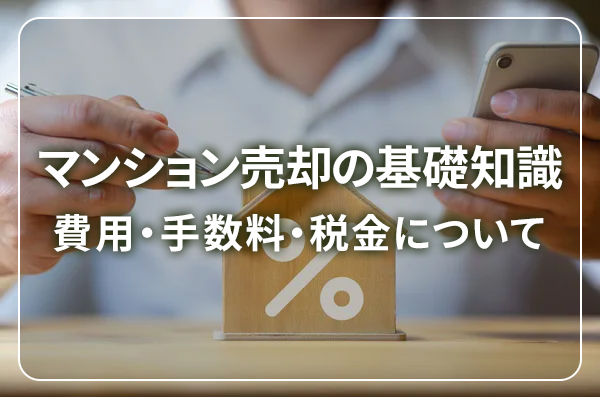
マンションの売却時には、仲介手数料(不動産会社に仲介を依頼した場合)、税金、諸費用など、費用が発生します。
そこで今回は、マンション売却で「必ずかかる費用」と、「場合によっては必要になる可能性がある費用」を解説します。
マンション売却を検討している方はぜひお役立てください。
また、以下のボタンから土地情報を入力すると、最大10社のハウスメーカーがあなたの土地に合った、建て替え総額の見積もりや、建て替え後の収益計画を無料診断いたします。
売却前に考えたい「マンションはいくらで建て替えられるの?」「建て替え後の収益予想を知りたい」という方はご活用ください。
マンション売却に有利になるようなルールはある?
マンションを売却して「利益」が出た場合に受けることができる控除は以下の3つ。
- 3,000万円特別控除
- 課税長期譲渡所得金額への軽減税率
- 特定居住用財産の買換え特例(売却後に家を買い替える予定がある場合の特例)
マンション売却で「損」が出た場合の特例は以下の2つ。
- 居住用財産買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失損益通算及び繰越控除
マンション売却の際に負担しなきゃいけない費用にはどんなものがある?
マンション売却の際、必ず負担する必要がある費用には
- 仲介手数料
- 租税公課(譲渡所得税・住民税・復興特別所得税)
- 印紙税
- 公的証明書類費用
- 司法書士費用
の5種類があります。
上記の他にもかかってくる可能性がある費用としては
- 引っ越し費用
- 住んでいたマンションの精算金
- 売却前の修理・修繕費用
- 住宅ローン返済手数料
があります。
あなたのマンションの売却価格を無料査定
詳しい解説は以下
目次
1.マンション売却費用のシミュレーション
マンションの売却時にかかる費用の総額は、以下の式で概算できます。
仲介手数料 +(売却益が出た場合の)租税公課 + 印紙税 + 公的証明書類費用 + 司法書士費用=マンション売却費用
上記のうち「(売却益が出た場合の)租税公課」については翌年以降に支払いが発生するものなので、売却時には費用がかかりません。
例えば1,000万円のマンションを売却した場合の売却時にかかる費用は、上の計算式に当てはめると以下のような形になります。
例:1,000万円のマンションを売却した場合
- 仲介手数料・・・上限額は「売買額の3% + 6万円(+ 消費税)」なので、売却額1,000万円の場合は「36万円(1,000万円 × 3% + 6万円) + 3.6万円(消費税)= 39.6万円」
→仲介手数料の詳細は「3-1.仲介手数料」で解説 - 租税公課・・・売却時は支払いなし
→租税公課の詳細は「3-2. 租税公課(譲渡所得税・住民税・復興特別所得税)」で解説 - 印紙税・・・2万円
→印紙税の詳細は「3-3.印紙税」で解説 - 公的証明書類費用・・・1,000円前後(印鑑証明書、住民票、固定資産税評価証明書を1通ずつ発行した場合)
→公的証明書類費用の詳細は「3-4.公的証明書類費用」で解説 - 司法書士費用・・・ 1万円ほど
→司法書士費用の詳細は「3-5.司法書士費用」で解説
総計・・・42.7万円
以上より、1,000万円のマンションを売却した場合はおおよそ4〜5%の費用がかかり、場合によってはこれに加えて「引っ越し費用、マンションの精算金、売却前の修理・修繕費用・住宅ローン返済手数料」などがかかってきます。
2.自宅マンション売却で使える特例控除5つ
マンションの売却では、買った時よりも高く売れて利益が出るケースと、買った時よりも安い価格でしか売れずにマイナスになるケースがあります。
マンションの売買に絡んで各種税金の支払いが発生しますが、「特例控除」を受ける条件を満たしていれば、支払う税金の額を大幅に減らすことができます。
以下、それぞれのケースに使える特例控除をまとめました。
2-1.マンション売却で「利益」が出た場合の特例3つ
まず、マンションを売却して「利益」が出た場合に受けることができる控除は3つあります。
2-1-1.「3,000万円特別控除」
マイホームを売却した場合、所有期間の長さ(5年以下・5年以上)に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円までが控除されます。
通称ですが、「3,000万控除」と呼ばれるものです。
ただし、以下の要件などを満たしていることが条件です。
条件はかなり多いのですが、マンション売却をする方に当てはまる条件を以下に記載します。
- 売却したマンションは、自分が住んでいたマンションであること
- マンションに住まなくなってから3年目の12月31日までに売却すること
- マンション売却をした前年・前々年に、この同じ特例または、譲渡損失などの特例を受けていないこと
(参考:No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)[令和2年4月1日現在法令等]) - マンション売却をした前年・前々年に、マイホームの買い換え・交換の特例を受けていないこと
(参考:No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例) - 売却したマンションの売手・買手が、親子や夫婦などの生計を共にする家族、内縁関係などにないこと
参考:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」
また、自分が使う目的のマンションでも、別荘や一時的な住処として利用していた場合も適用外です。
2-1-2.課税長期譲渡所得金額への軽減税率
マイホームとして10年以上所有していたマンションを売却した場合、譲渡所得の金額に応じた軽減税率が適用されます。
先に説明をした3,000万控除(3,000万円特別控除の特例)と併用できますので、マンション売却のタイミングが10年以上の場合は、利益があっても税率負担がかなり軽減されます。
| 課税長期譲渡所得金額 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 6,000万円以下の部分 | 10.21% | 4% |
| 6,000万円を超える部分 | 15.315% +600万円 | 5% |
参考:国税庁「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」
※所得税には「復興特別所得税」として所得税の2.1%相当が加算されています。
2-1-3.特定居住用財産の買換え特例(売却後に家を買い替える予定がある場合の特例)
現時点で、マンションを令和5年年末までに売却して、次のマイホームを買おうとお考えの方は、ある特定の条件を満たしている場合に以下の特例が適用できます。
特例を適用すると、仮に利益が出たとしても、その分の課税は、次に家を買い替える時までずっと先延ばしにすることが出来ます。(非課税にはなりません)
| 売却するマンションに関する条件 | 次に買う家またはマンションに関する条件 |
|---|---|
|
|
【参照:詳細確認先 特定のマイホームを買い替えたときの特例】
この特例の特色として、マイホームを今の家の条件よりも良いところに買い替えるという背景があります。
より大きな不動産の買い物をすることを前提に、多額の税金による将来の生活やローン負担を軽くすることで、マイホーム購入のハードルを下げ、不動産市場を活性化させることが目的です。
そのため、対象はマイホームに限定されています。
ただし、この特例は、先に説明した3,000万円控除・課税長期譲渡所得金額への軽減税率と組み合わせて適用することはできません。
どちらが得になるのかを良く検討してから申請しましょう。
あなたのマンションの売却価格を無料査定
2-2.マンション売却で「損」が出た場合の特例2つ
マイホームとして住んでいるマンションの売却をした際に、マイナスを出したときに使える2つの特例です。
2-2-1.居住用財産買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
マイホームとして使っていたマンションを売却し、新しくマイホームを購入したときに損が出た分を、その年から給与所得や他の所得と合算し、翌年以降3年間(譲渡年を含めて4年)まで繰り越して控除できる制度です。
この控除を適用すると、具体的にどんなメリットが得られるのでしょうか?
控除額を決める譲渡取得(この場合、マイナスのため、譲渡損失金額)は、下記の計算式で算出されます。
譲渡所得 = 収入金額 – (取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額
例えば、15年前にマイホームとして4,600万円で買ったファミリー向けマンションを半額の2,500万円で売却して、同じ年に売却額2,500万円と住宅ローンで新居を購入した場合について考えていきましょう。
| 収入金額:マンションの売却金額 | 2,500万円 |
|---|---|
| 取得費:マンションの購入にかかった金額 | 4,600万円 |
| 譲渡費用:売却にかかった金額 | 200万円 |
※特別控除額はないものとする
収入金額:2,500万円 -(売却金額:4,600万+ 譲渡費用:200万)
⇒ 譲渡損失金額:2,300万円
上記の場合、譲渡損失金額である2,300万円分の控除を受けることができます。控除は翌年以降の3年間(売却した年度を含めて合計4年間)の間、繰り越しの形で適用されます。
本控除の適用によって給与所得などの所得金額が打ち消されるため、会社の給与明細で引かれていた源泉徴収分は還付金として戻ってきます。
また、翌年も繰り越された控除金額が適用され、還付金として戻ります。
先ほどの例のように、譲渡損失金額が2,300万円で、所得が750万円(その他の収入はなし)の場合について考えていきましょう。
なお、住民税は前年所得によって納税金額が決まるため、売却した年度の翌年から合計4年間、控除が適用されます。
思わぬ出費につながらないように気を付けましょう。
| 売却した年度 | 翌年度 | 翌2年度 | 翌3年度 | 翌4年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 譲渡損失金額 | ▲2,300万円 | ▲約1,550万円 | ▲約800万円 | ▲約50万円 | 0円 |
| 所得金額 【給与所得など】 |
750万円 ⇒合算後0円 |
750万円 ⇒合算後0円 |
750万円 ⇒合算後0円 |
750万円 ⇒合算後700万円 |
750万円 |
| 所得税 | ⇒0円 | ⇒0円 | ⇒0円 | 相殺後、残額にかかる税金を支払う | 控除の適用なし |
| 住民税 ※翌年度から適用 |
控除の適用なし | ⇒0円 | ⇒0円 | ⇒0円 | 前年の相殺後の残額にかかる税金を支払う |
| 繰り越しとなる控除金額 | 約1,550万円 | 約800万円 | 約50万円 | ⇒0円 | ⇒0円 |
上でも述べましたが、住民税は前年所得によって納税金額が決まるため、売却した年度の翌年から合計4年間、控除が適用されます。
思わぬ出費につながらないように気を付けましょう。
この特例が適用される条件は以下の通りです。
| 売却するマンションに関する条件 | 次に買う家またはマンションに関する条件 |
|---|---|
|
|
【参照:詳細確認先 国税庁 No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき】
2-2-2.特定居住用財産の譲渡損失損益通算及び繰越控除
マイホームだったマンションを売却して損が出たときに次のマイホーム買い替えをしなくても使える控除があります。
控除を受けることができる条件は以下の通りです。
- 売却したマンションの所有期間が5年を超えているマイホームである(売却した年度の1月1日時点)
- 控除が適用される期間、各年度の所得金額の合計が3,000万円以下
- 売却相手が生計を共にする親しい親族や内縁関係ではない
- 売却日の前日、ローンが10年以上残っている
- マンションの売却代金が、ローン残高を下回っていること
- 売った年を含めて3年以内に、本特例やほかの居住用財産の譲渡に関する特例の適用を受けていない
このような条件下でマンション売却をしたとき、以下、AとBのうち、より低い方の金額を「損失額」として控除され、税務上の所得が給与などと通算されます。
その結果、この年の源泉徴収は全額還付となります。
A:(購入金額 - 減価償却費)- 売却金額 + 譲渡費用
B: 住宅ローンの残高 - 譲渡価格
ただし、2年目から控除額が低くなり、3年目から控除対象額がなくなってしまうため、税金還付がなくなります。
家の買い替えをしない場合のみ、検討しましょう。
【参照:詳細確認先 国税庁 No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき】
あなたのマンションの売却価格を無料査定
3.マンション売却時に必ず売主が負担する5つの費用
本章では、マンションを売却したときに必ずかかる5つの費用について説明します。
| 費用の名目 | 何に使うのか | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 3-1.仲介手数料 | 不動産会社に支払う仲介料 | 不動産会社の指定する%+消費税 |
| 3-2.譲渡所得税/住民税/復興特別所得税 | マンション売却で得た利益にかかる税金の支払い | ※利益の金額に応じて算出 |
| 3-3.印紙税 | 書類に使う印紙代 | ※本文表参照 |
| 3-4.公的証明書類費用 | 書類に添付する | 一種につき300~500円 |
| 3-5.司法書士費用 | 名義変更などの手続き | 1~3万円前後 |
3-1.仲介手数料
マンションの売却費用の中で、最も大きいのが仲介手数料です。
仲介手数料には、マンション売却で不動産会社が行うすべての必要経費と報酬が含まれています。
仲介手数料は一回の売却完了までの取引に対して支払われる成功報酬タイプの代金なので、売却までに時間がかかっても追加の料金などは発生しません。
ただし、マンションオーナーからの依頼で通常の営業内容以外の活動(例えば、マンションオーナーからの依頼で遠隔地の購入希望者に交渉に行くための交通費など)の実費は都度清算があります。
3-1-1.仲介手数料の内訳
不動産会社がマンション売却で行う必要経費とは以下のようなものを指します。
●広告活動全般
- 不動産流通サイト・自社サイト・その他不動産売買関連サイトネットワークへの掲載
- 売買物件の画像や紹介テキスト作成
- 配布チラシなどの作成
●営業担当者の人件費
- 購買希望者の案内や説明
- 営業用資料作成
- 問い合わせ対応
- 売主への報告業務
●売却するマンションの調査費用
●契約書などの作成費用
報酬額(仲介手数料)の上限は、宅地建物取引業法に則り、国土交通省告示によって以下の表のように定められています。
ただし、上限が決められているだけですので、不動産会社によって%には違いがあります。
| 取引した金額 | 報酬額【仲介手数料(税込)】 |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 取引額の5.5%以内 |
| 200万円を超え400万円以下の部分 | 取引額の4.4%以内 |
| 400万円を超える部分 | 取引額の3.3%以内 |
【参照:国土交通省 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額 最終改正令和元年8/30】
上記の表を参考に、例をあげて計算をしてみましょう。
(例)400万円のマンションを売却する場合の仲介手数料
【200万円以下の部分】
200万円×5.5%=110,000円
【200万円を超え400万円以下の部分】
200万円×4.4%= 88,000円
合計 198,000円(税込)
400万円のマンションを売却する場合の仲介手数料として不動産会社に支払う報奨金額(手数料)の上限は、合計198,000円(税込)となります。
また、仲介手数料の計算方法には、より簡単に計算できる「速算式」という算出方法もあります。
売買する金額からすぐに算出することができるため、とても便利です。
以下の表をもとに、先ほどの例を使って計算してみましょう。
| 売買した金額 | 報酬額(仲介手数料) |
|---|---|
| 200万円以下 | 売買額×5%(+消費税) |
| 200万円を超えて400万円未満 | 売買額の4%+2万円(+消費税) |
| 400万円以上 | 売買額の3%+6万円(+消費税) |
(例)400万円のマンションを売却する場合
・仲介手数料 400万円×3% +60,000 = 180,000円
(消費税)180,000円×1.1%= 198,000円(税込)
3-1-2.仲介手数料はいつ支払うのか
不動産売買の手数料は、売買が完了してから支払いをしますが、どのタイミングで払うかは不動産会社によって少しずつ異なります。
一般的には、以下のいずれかのタイミングで支払いを行うケースが多く見られるでしょう。
- 契約締結時点に50% 引き渡し完了後に50%
- 契約締結時点で100%
- 引き渡し完了確認後に100%
トラブルを避けるため、不動産会社と仲介契約をする前に「仲介手数料をいつ支払うのか」を確認するようにしましょう。
3-2.租税公課(譲渡所得税・住民税・復興特別所得税)
3-2-1.マンション売却の利益に対する税金の種類
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 譲渡所得税 | 土地や建物の売却で利益(所得)を得た場合に発生する税金の支払い |
| 住民税 | |
| 復興特別所得税 |
※更にマンションの売却で利益が出た場合は所得が発生するため、翌年以降に「所得税」と「住民税」が発生します。
逆に、マンション売却でマイナスが生じた場合には税金は発生しません(マンション売却と費用に関した控除については「2.自宅マンション売却で使える特例控除5つ」で詳しく解説をしています)。
3-2-2.マンション売却の利益に対する税金の計算式
以下の計算式で「売却の利益=譲渡所得」にかかる税金を算出することができます。
〔収入金額 – (取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額〕×税率
=税額
参考:国税庁「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
簡単に言い換えると、
売った価格 – (買った価格 + かかった経費) –税金控除額×税率
=払う税金
となります。
計算式に使う用語の詳細説明は以下です。
マンション売却で得た利益は「譲渡所得」といいます。
まず、計算式に用いる各用語の説明をしましょう。
●収入金額:マンションの売却金額
●取得費:売却したマンションの購入時また購入後にかかった費用の合計
- マンションの購入代金
- 購入時にかかった税金(印紙税、登録免許税、不動産取得税など)
- 仲介手数料
- リフォーム費用
- 住宅ローンの借り入れから入居までにかかった利子
(※「減価償却費」を差し引くものとする)
●譲渡費用:マンションを売るために使った費用のことです。
- 仲介手数料
- 売買契約時の印紙税
- 入居者に退去してもらうための退去費用など
- 借地上のマンション売却で地主の承諾を得るために支払った名義書換料など
●特別控除額:マンションを売却した際に特例として控除を受けた金額
参考:国税庁「No.3223 譲渡所得の特別控除の種類」
3-2-3.マンション売却の利益に対する税率について
また、譲渡所得(マンションの売却で得た利益)にかかる税率は、「不動産の所有期間の長さが5年を超えるかどうか」によって、かかる税率が変わります。
| 所有期間 (売却した年の1月1日時点の期間) |
税率 | |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 所有期間5年以下の土地・建物 | 所得税 30.63 % 住民税 9% |
| 長期譲渡所得 | 所有期間5年を超える土地・建物 | 所得税 15.315% 住民税 5% |
※所得税には「復興特別所得税」として所得税の2.1%相当が加算されています。
※なお、所有期間については売却した年の1月1日現在の期間を指します。
実際に売却した日時とは異なるため、注意しましょう。
参考:国税庁「No.3211 短期譲渡所得の税額の計算」
国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」
3-2-4.マンション売却の利益に対する税金のシミュレーション
マンションを購入したときと同じ金額で売れ、さらに特別控除は発生していないケースを想定してシュミレーションします。
| 収入金額:マンションの売却代金 | 4,000万円 |
|---|---|
| 取得費:マンションの取得費用 (購入するときにかかった費用の合計) |
マンション代:4,000万+諸経費200万円 =合計4,200万円 |
| 譲渡費用:マンションを売却するためにかかった費用 | 200万円 |
| 譲渡所得 | 4,000万円 -4,200万円-200万円 = マイナス400万円 |
| 所有期間 | 10年(→長期譲渡所得) |
上記のケースのように、マイナス利益になると税金は発生しません。
譲渡取得および所得税、住民税などの詳細な計算はインターネット上で簡単にシミュレーションできるツールがあります。
参考:カシオ計算機 マイホームの不動産譲渡所得税計算
あなたのマンションの売却価格を無料査定
3-3.印紙税について
| 費用の名目 | 何に使うのか |
|---|---|
| 印紙税 | 課税文書(契約書)にかかる税金の支払い |
印紙税とは、契約書などを作るときに国におさめる必要がある税金のことです。
マンション売買契約書に使う収入印紙という切手のようなもので支払うこととなります。
中古マンション売却額として一般的な金額範囲を抜粋しましたので、以下の表から印紙税額を確認しましょう。
| 契約書に記載した金額 | 本則税率 |
|---|---|
| 100万円~500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円~1千万円以下 | 10,000円 |
| 1千万円~5千万円以下 | 20,000円 |
| 5千万円~1億円以下 | 60,000円 |
| 1億円~5億円以下 | 100,000円 |
参考:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」
印紙税は、契約書1通につき1枚必要です。契約書は売主と買主で2枚作りますので、印紙は2枚分必要です。
ただし、ほとんどの場合は不動産会社がこの印紙を用意してくれるので、自分で購入するケースは少ないでしょう。
3-4.公的証明書類費用
| 費用の名目 | 何に使うのか | だいたいの目安 |
|---|---|---|
| 公的証明書類費用 | 書類に添付する | 一種につき300~500円 |
公的証明書類とは、契約や名義変更の際に使う以下の文書のことをいいます。
契約で必要な枚数分の費用がかかります。不動産会社から「○○を1枚」など必要な書類と枚数の指定があるでしょう。
以下は、主に必要とされる書類の発行費用の目安です。金額は市区町村によって異なります。
- 印鑑証明書 1通300円程度
- 住民票 1通300円程度
- 固定資産税評価証明書 1件400円程度 追加分100円程度
3-5.司法書士費用
| 費用の名目 | 何に使うのか | だいたいの目安 |
|---|---|---|
| 司法書士費用 | 抵当権抹消・売渡書類 | 10,000円~ ※地域や事務所によって異なる |
売却するマンションにローン残債がある場合は、売却前に完済して抵当権の抹消*を行う必要があります。
また、契約書とは別に、「売渡書類(このマンションの売買が終わりましたという証明)」のために、売主と買主がサインをして登記所に提出する書類が必要になります。
マンションの抵当権は売買するときにかならず抹消されていなければならないわけではありません。しかし、売買契約が成立して引き渡しをするときまでには抹消をしなくてはなりません。
そして、抵当権抹消と売渡書類の作成を司法書士に依頼する際に費用がかかります。
これらの費用は、地域や事務所によって値段は異なります。
費用の目安は以下の通りです。
◆登録免許税 抵当権抹消登録にかかる費用
不動産1件につき1,000円
マンションの場合、土地の上にマンション建物があるため、土地と建物で2件分が必要です。
◆売渡書類の作成
費用目安 1,000~3,000円
◆司法書士費用
司法書士に支払う報酬額は作業1件10,000円からで、地域や司法書士事務所によって多少の違いがあります。
参考:日本司法書士会連合会「報酬アンケート結果(2018年(平成30年)1月実施)」
4.マンション売却でかかる可能性があるその他の費用4つ
本章では、「3.マンション売却時に必ず売主が負担する5つの費用」で説明したもの以外にも、発生する可能性がある4つの費用を説明します。
なお、以下の費用はマンション売却をするすべての方に発生するわけではありません。
| 4-1.引っ越し費用 | 近県に引っ越しの場合、 単身:3万~6万、2~3人家族:7~20万円 |
|---|---|
| 4-2.住んでいたマンションの清算金 | なし~数万円 |
| 4-3.売却前の修理修繕費用 | 修繕箇所による |
| 4-4.住宅ローン返済手数料 | ローンの残期間による |
4-1.引っ越し費用
まず、売却するマンションに住んでいた場合は、売却と引き渡し前に引っ越しをすませておく必要があるため、引っ越し費用がかかります。
費用詳細は各引っ越し会社で見積もりをする必要がありますが、おおよその目安として近県に引っ越しで、簡単な梱包作業のみ手伝うタイプの引っ越しサービスの場合、以下の価格が相場のようです。
- 単身 3~6万円程度
- 2人家族 7~8万円程度
- 3人家族 10~20万円程度
※選択するオプション・時期・距離によって金額は異なります
参考:アート引っ越しセンター
参考:サカイ引越センター
4-2.住んでいたマンションの清算金
売却するマンションに住んでいた場合は、売却完了日時までの管理費・修繕積立金ほかを日割り/月割り(管理組合による)をして清算をします。
年払いでまとめて支払っていた場合は、退去の日から後の分を清算できます。
逆に、滞納などがあった場合は売却日までの金額を支払う必要があります。
4-3.売却前の修理・修繕費用
簡単な修理修繕を行うことで、マンション売却でなるべく値段を下げないで売る方法があります。
以下の項目を確認しておき、修理修繕を行ってみましょう。
- ドアノブが壊れてガタガタいう
- ふすまが破れていて、中身が見えている
- 壁紙が剥がれてコンクリートがむき出しになっている
- お風呂がカビだらけ
- ガラスにひびが入っている
ただし、直すのは目立つ箇所だけにして、大きなお金がかかる修繕はしないようにしましょう。
中古マンション購入を検討するかたの多くは、「こういう住居にしたい!」とご自身の理想を持っており、売却後には自分たちの希望に沿った新たなリフォームをかけることが多くあります。
リフォームにかけた費用が無駄にならないように、大きな修繕は控えておきましょう。
4-4.住宅ローン返済手数料
住宅ローンが残っている場合は、売却した金額でローンを完済するのが一般的です。
その際に、金融機関と保証会社に手数料を支払う必要があります。
全額返済申し込みの手数料は、ネット申し込みなどを行うことで金融機関によっては安価となる場合もあります。
| 銀行名 | ネット申し込み | 店頭申し込み |
|---|---|---|
| りそな銀行 | 取り扱い不可 | 変動金利 11,000円 固定金利 33,000円 保証会社への手数料 11,000円 |
| 三井住友銀行 | 5,500円 ※SMBCダイレクトでの取り扱い |
店頭 22,000円 店頭パソコン 11,000円 |
| イオン銀行 | 55,000円 ※イオン銀行ダイレクトでの取り扱い |
55,000円 |
5.自宅マンション売却後に戻ってくる3つの費用

本章では、マンション売却後に手元に戻ってくる3つの費用について説明します。
5-1.火災保険料
銀行ローンを組んだ時に、火災保険に入っている方は多いかと思います。
火災保険は、マンションを購入したときからローンの借り入れ年数に合わせた長期契約をしているケースがほとんどです。
マンションの売却をすると火災保険の途中解約をすることになり、残りの期間分の金額が戻ってきます。
火災保険料の返金は、自分で保険会社に請求する必要があります。購入時の契約書と一緒に保管しておいた火災保険契約書を確認し、解約手続きをしましょう。
また、火災保険契約書はローンを組んだ金融機関側で保管をしている場合もあるため、手元にない場合は金融担当者に確認をしましょう。
5-2.銀行保証料
住宅ローンを組んだ際に、金融機関から「保証会社」に入ることを依頼されたと思います。
上記の火災保険同様に、ローン期間に合わせた長期契約がされているケースが多く、マンション売却によって途中解約するため、残りの期間分の保証料が戻ってきます。
また同様に、売却するマンションの修繕積立金や管理費を月払いではなく年払いしていた場合は、退去後の分が払い戻しされます。
日割り計算になるか月割計算になるかは、管理組合または管理会社によって異なるため、確認しましょう。
5-3.先払いしていた固定資産税や修繕積立金
固定資産税はその年の1月1日不動産を所有していた方に課されるのですが、不動産業界の慣習上、売買が成立した日から後の固定資産税は「買主」が支払います。
そのため、1期から全額を支払っていた場合は、日割り計算で払い戻しされます。
払い戻しは、不動産会社が計算をして買主に請求します。
ほとんどの場合、売買契約のときに一緒に清算をする形をとります。
また同様に、売却するマンションの修繕積立金や管理費を月払いではなく年払いしていた場合は、退去後の分が払い戻しされます。
日割り計算になるか月割計算になるかは、管理組合または管理会社によって異なるため、確認しましょう。
6.マンション売却に強い不動産会社を選ぶポイント
マンションを売却する際にはさまざまな法律や税制度、その他のルールが関わってくるため、専門家の協力なしに独力で進めるのは困難です。
ベストな条件で売却を成功させるためには、豊富なノウハウと誠実さを備えた不動産会社を味方につける必要があります。
以下、優良な不動産会社を選ぶために必要不可欠なポイントについてお伝えします。
6-1.評判・口コミ
不動産会社の評判や口コミについては、インターネットを活用することによって業者の立場から独立した中立的な意見を拾うことができます。
特に近年では、通常のGoogle検索の他に、SNS上で情報を探すことによって「生のユーザーの声」を見つけやすくなっているので、ぜひご活用ください。
6-2.問い合わせへの対応
問い合わせへの応対が手厚い会社であれば、実際に契約を結んだ後のフォローの質にも期待できるでしょう。
気になる不動産会社があれば、事前にメールで相談してみて、担当者がどれぐらい丁寧に応対してくれるかを確かめるのも一手です。
あなたのマンションの売却価格を無料査定
関連記事
-
-
【トランクルーム経営の全知識】メリットとデメリット、失敗例を解説
- 2025.01.23
- その他活用
-
- 2025.01.28
- アパート・マンション建築