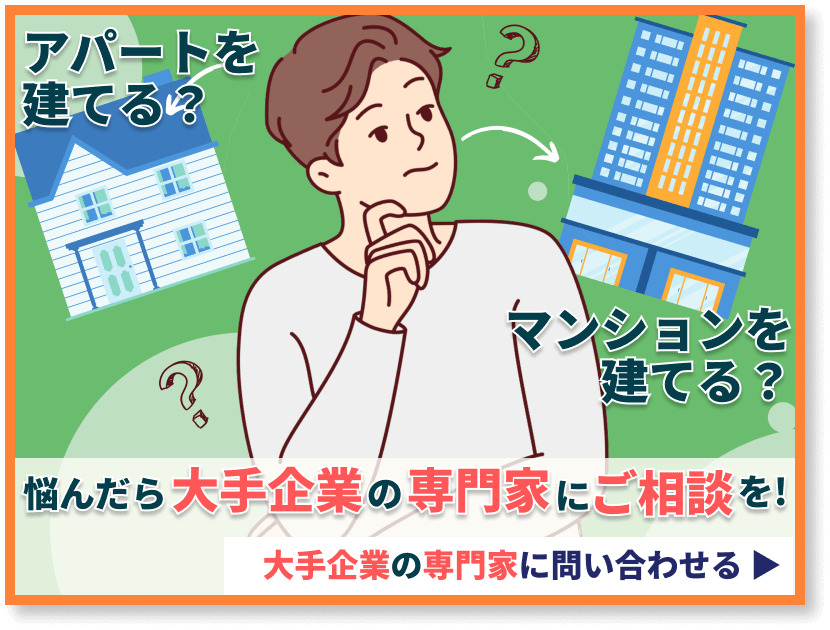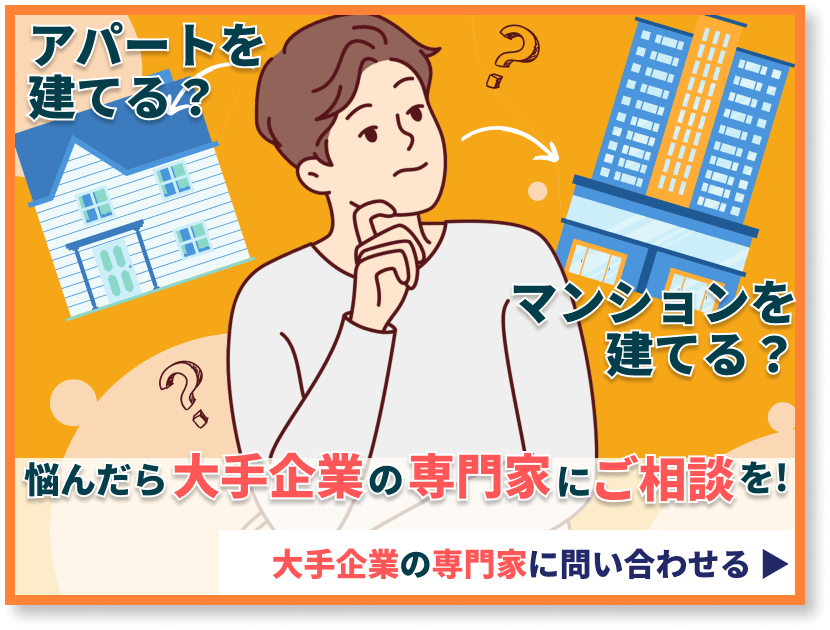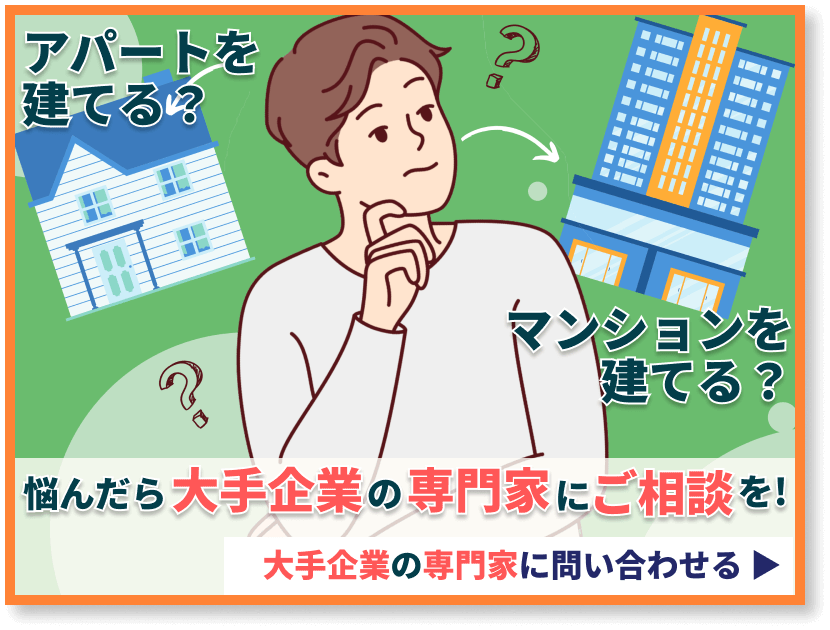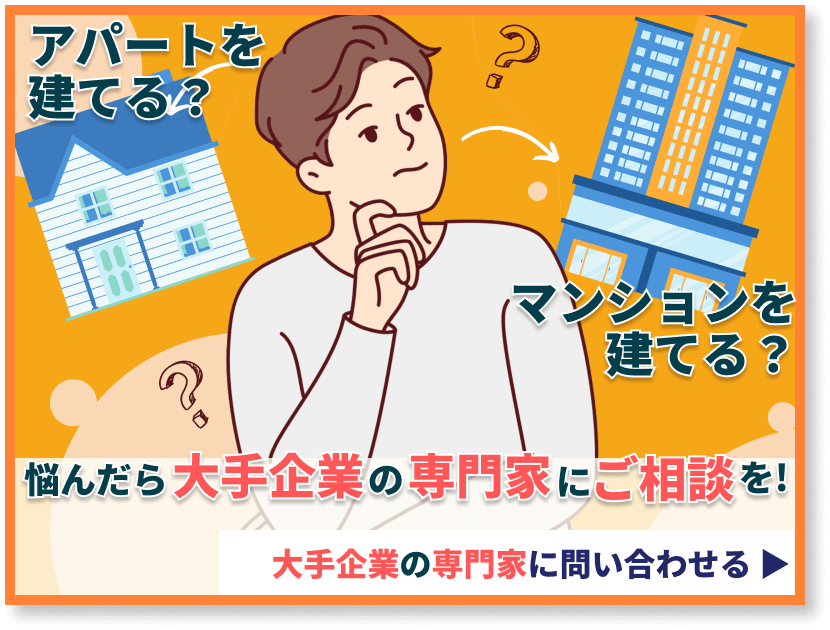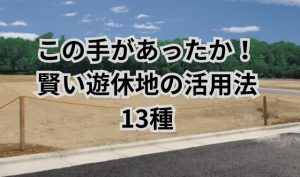【徹底解説】アパート経営とマンション経営、16の違いを徹底比較

この記事では、土地活用におけるアパート経営とマンション経営の16の違いについて解説します。
両者にはどちらも強みと弱みがあるので、どちらが自分自身に合っているか、しっかりと見極めてください。
また、「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」なら無料で土地活用提案を受けることが可能です。以下のボタンから土地情報を入力すると、最大10社のハウスメーカーがあなたの土地に合った、建物の形状や、建築費の見積もり、収支計画を無料診断いたします。
「うちの土地には何が建てられるの?」「いくら儲かるのか知りたい」という方はご活用ください。
アパート経営とマンション経営はどちらが有利?
全体的に見れば、アパート経営は少なめの資金で運営できることが利点であり、一方で資金力に余裕があるのであればマンション経営のほうが利点が多くなります。
アパート経営とマンション経営のどちらを実行するほうが有利かを「建てやすさ」や「希少性」「投資額」「収入」など全16の項目で徹底比較しています。
アパート経営に向いている人・向いていない人とは?
- アパートの経営が向いている人
自宅近くにアパートしか建てられたない土地を持っている - アパート経営が向いていない人
マンション建築に適した土地を持っている
マンション経営に向いている人・向いていない人とは?
- マンション経営に向いている人
資金力にある程度余裕がある - マンション経営に向いていない人
自己資金を多く持ち合わせていない
「アパート?」「マンション?」
詳しい解説は以下
目次
1.アパート経営とマンション経営、16の違い
マンションとアパートは同じ住居系の賃貸経営ですが、以下の16の点で違いがあります。
| アパート経営 | マンション経営 | |
|---|---|---|
| 建てやすさ | ○ | × |
| 希少性 | × | ○ |
| 投資額 | ○ | × |
| 収入 | △ | ○ |
| 耐用年数 | × | ○ |
| キャッシュフロー | △ | ○ |
| 耐震性・耐久性 | × | ○ |
| セキュリティ | × | ○ |
| 空室リスク | △ | ○ |
| 賃料下落リスク | △ | ○ |
| 管理のしやすさ | ○ | △ |
| 維持管理費 | ○ | × |
| 大規模修繕費 | ○ | × |
| リノベーションのしやすさ | × | ○ |
| 建て替えのしやすさ | ○ | × |
| 相続対策 | △ | ○ |
この章では、16のポイントについて一つずつ解説していきます。
1-1.建てやすさ
建てやすさでは「どんなエリアでも建てられる」アパートに軍配があがる
【解説】
アパートとマンションでは、建てやすさ(建てられる立地の自由度)に違いがあります。
土地には、エリアによって建築できる建物の用途や大きさに法律や条例で制限が設けられています。
アパートはほぼどんなエリアにでも建てることができますが、マンションのような高層の建物は建築できるエリアが限られてきます。
よって、アパートは建てやすく、マンションは建てにくいといえます。
1-2.希少性
建設可能なエリアが限られるマンションのほうが希少性で勝る
【解説】
建設可能なエリアが限られるマンションは、アパートに比べると供給過剰のリスクは低めです。
したがって、マンションを建てられる土地を持っているのであれば、アパートよりはマンションを建てたほうが希少性の点では有利となります。
希少性が高ければ空室リスクを下げられるので、マンションのほうが集客を安定することができる可能性も高いです。
1-3.投資額
アパートは少額で建てられるので小資本での運用にも向いている

【解説】
アパートとマンションを比べると、マンションの方が投資額は大きくなります 。
アパートは総額が1億円未満でも投資が可能です。
それに対してマンションは、1億円を超えることがほとんどです。
アパートとマンションでは、規模も違いますが、構造部材も異なります。
アパートは木造または軽量鉄骨造が多く、マンションは鉄筋コンクリート造が多いです。
木造や軽量鉄骨の方が、鉄筋コンクリート造に比べ工事費の坪単価も安いです。
坪単価が低いうえに建築規模も小さいため、投資額はアパートの方が安くなります。
例えば、自己資金3,000万円を用意できる状態で6,000万円のアパートを建てれば、自己資金の割合が50%になります。
一方で、同じ自己資金3,000万円を用意できる状態で2億円のマンション投資を行うと、自己資金割合が15%にしかなりません。
したがって同じ自己資金であれば、アパートの方が安全な投資を行いやすいと言えます。
1-4.収入
得られる家賃収入はマンションのほうが多い

【解説】
収入額で比べると、マンションのほうが賃料(家賃)が高い分入ってくる収入が多めとなります。
投資額はマンションのほうが多額の費用を要しますが、その分オーナーの手元に入ってくる収入の額も大きくなります。
ただし、「収入の額」と「収益率(投資額に対する収益の高さの率)」とは別です。
収益率の面でみれば、アパートのほうがマンションよりも勝っているケースが多いようです。
アパートはマンションに比べ投資額が低いのに対して、収入額の相場はマンションのほうが若干高いものの、一室あたりの収入額で比べた場合の差はそこまで大きくありません。
以上より、アパートはマンションより賃料が若干低いだけであるのに対して、物件の購入額には大きな差があるため、結果的にアパートのほうが投資額に対する収益率(利回り)が高いことになります。
例として、アパートの投資額が6,000万円、マンションの投資額が1億円で、家賃収入に差があるアパートとマンションを比べてみます。
| アパート | マンション | |
|---|---|---|
| 投資額 | 6,000万円 | 1億円 |
| (年間)満室時 家賃収入 |
月あたり賃料4万円×10部屋×12ヶ月=480万円 | 月あたり賃料6万円×10部屋×12ヶ月=720万円 |
| 表面利回り | 480万円÷6,000万円=8% | 720万円÷1億円=7.2% |
以上の例のように、マンションのほうが家賃収入が高かったとしても、投資額の差に開きがある分、アパートのほうが利回りが高くなる傾向があります。
1-5.耐用年数
鉄骨や鉄筋コンクリート造で作られたマンションのほうが、耐用年数が長くてローン返済の負担が軽い
【解説】
アパートとマンションでは、建物の躯体構造が違うため、耐用年数も異なります。
耐用年数とは、建物の固定資産が使用できる期間として法的に定められた年数であり、減価償却の計算期間のことを指します。
減価償却とは、使用または時の経過などによって生じる建物の価値の減少分を耐用年数に応じて、費用配分する会計上の手続きのことを指します。
耐用年数に関しては、建物の躯体構造ごとに、以下のように法律で決められています。
| 躯体構造 | 法定耐用年数 |
|---|---|
| 木造 | 22年 |
| 鉄骨造(鉄骨厚3mm以下) | 9年 |
| 鉄骨造(鉄骨厚3~4mm以下) | 27年 |
| 鉄骨造(鉄骨厚4mm超) | 34年 |
| 鉄筋コンクリート造 | 47年 |
出典:東京主税局「減価償却資産の耐用年数表(建物)」
法定耐用年数は減価償却費を計算する上で定められた年数です。
木造は22年、鉄筋コンクリート造は47年となっています。
耐用年数に関しては、銀行からローンを組む際の借入可能期間にも影響します。
一般的に銀行がオーナーへ貸し出すローンの返済期間は、耐用年数期間が上限となっています。
借入期間が長いほど毎月の返済額が少なくなるので、返済の負担が小さくなります。
特に、アパートは木造または鉄骨造であるため、借入可能期間が短くなります。
1-6.キャッシュフロー
長い目で見れば、マンション投資のほうが手元に利益が残りやすい

【解説】
キャッシュフローとは、実際にオーナーの手元に残る得られる手残りのお金のことです。
アパートとマンションでは、減価償却費を計上できる期間が異なるため、長期的にはキャッシュフローにも違いが出てきます。
キャッシュフローの計算式は以下の通りです。
キャッシュフローの計算では、実際に流出しなかった減価償却費をプラスすることになります。
しかし、耐用年数満了後は、減価償却費が計上されないので、プラスできません。
よって、耐用年数満了後は、キャッシュフローが急に悪化します。
計算式1.
- 借入金の元本返済を考慮しないキャッシュフロー
- = 税引後利益 + 減価償却費
計算式2.
- 借入金の元本返済を考慮したキャッシュフロー
- = 税引後利益 + 減価償却費 - 借入金の元本返済
実際に流出する借入金の元本返済をマイナスすることになります。
借入金の元本返済額に関しては、会計上の費用にはなりません。
(借入金は借りたときに売上にならなかったのと同様に、返しても費用とはならないというのが原則です。)
よって、借入金の元本返済は、利益には影響は与えませんが、キャッシュフローに影響を与えます。
計算式3.
- 耐用年数満了後のキャッシュフロー
- = 税引後利益 - 借入金の元本返済
減価償却費とは、「アパートなどの固定資産を購入するのにかかった費用を、購入後の年から耐用年数が終わる年までの間、按分して費用計上するものです。
実際に手元からお金が出て行くわけではないのですが、費用計上することによって課税金額を抑えるのに役立てることができます。
例えば、建築費が2,200万円の木造アパートがあった場合、毎年100万円(= 2,200万円 ÷ 法定耐用年数22年)が減価償却費として計上されます。
減価償却費は会計処理の上で発生する費用であるため、実際に支出されるわけではありません。
(毎年100万円の減価償却費と言っても、100万円が出ていくわけではないということです。)
ところが、費用として計上される以上、収入から差し引かれるため、課税の対象となる利益を圧縮し、節税に役立てることができます。
例えば、賃料収入が1,000万円、減価償却費以外の経費が300万円、減価償却費が100万円のケースを考えます。
この物件の利益は、1,000万円から減価証約費以外の300万円と減価償却費の100万円を控除し、600万円になります。
実際には700万円の利益が出ていますが、600万円に対して税金がかかるため、その分、節税効果があるのです。
(減価償却費の100万円は流出せずにキャッシュとして残ります。)
耐用年数満了後は減価償却費の節税効果がなくなるため、税引後の利益も小さくなります。
耐用年数は、木造のアパートなら22年、鉄筋コンクリート造のマンションなら47年ですので、アパートなら23年後、マンションなら48年後にキャッシュフローが悪くなります。
以上より、マンションの方が減価償却費は長く計上できるため、キャッシュフローは長持ちする優良資産であるという見方ができます。
「アパート?」「マンション?」
1-7.耐震性・耐久性
耐震性はどちらも変わらず、耐久性ではやはりマンションに分があり
【解説】
アパートとマンションでは耐震性や耐久性にも異なる影響が出てきます。
耐震性に関しては、現行の耐震基準で新築すれば、アパートもマンションも、基本的には問題ありません。
しかしながら、入居者側からのイメージとして「耐震性に弱いのではないか」と思われる可能性はあります。
耐久性についてはアパートよりもマンションのほうが優れています。
マンションは頑丈な鉄筋コンクリート造であるため、外壁材をタイルや石といった重くて硬い建材で仕上げることが可能です。
硬い素材で仕上がっているマンションの方が、見た目上の劣化が少なく耐久性があります。
1-8.セキュリティ
セキュリティ面ではマンションの一人勝ち
【解説】
アパートとマンションでは、一般的にセキュリティに大きな差があります。
マンションのセキュリティ上の特徴はオートロックが配備されている>ことであり、オートロックの設置がないアパートとは大きな差があります。
アパート経営をする方は、入居者の不安を払拭するためにも、防犯カメラや防犯センサーライトの設置をするなど、十分なセキュリティ対策を意識するようにしましょう。
1-9.空室リスク
マンションは空室にも強い

【解説】
空室リスクに関しては、物件の立地条件によって決まる部分が大きいため、一概にアパートとマンションのどちらが有利と言い切るのは難しい部分があります。
ただしマンションの方が駅から近い場所に建築されることが多いことから、総じてマンションの方が空室リスクは低い傾向にあります。
さらに、マンションには耐震性やセキュリティに関して信頼性があるため、空室リスクが低めです。
1-10.賃料下落リスク
アパートは競合の多さやアピールポイントの都合上、賃料下落のリスクがより高い
【解説】
マンションは鉄筋コンクリート造の堅牢な建物であるため、築年数による老朽化がアパートよりも目立ちにくく、さらに空室リスクも低いため、マンションのほうが賃料の下落はゆるやかです。
一方で、アパートは築年数による老朽化が目立つ上、耐震性やセキュリティ面の訴求も弱いことから、空室が発生しやすい点が弱みです。
空室が長引けば、賃料を下げて募集をせざるを得ず、結果的に賃料が下落していきます。
さらに、アパートはどこでも建築できるため、近隣に新築のアパートが競合が増える事態が起こりやすく、入居者を取り合う状況の中で賃料を下げざるをえないケースも多々あります。
入居者への訴求力が弱く、なおかつ供給過剰になりやすいアパートは、賃料下落リスクも高いと言うことになります。
1-11.管理のしやすさ
自主管理ならアパートのほうが容易
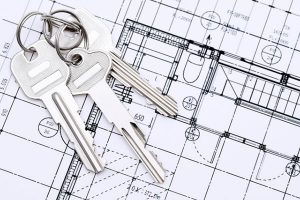
【解説】
管理のしやすさは、戸数や物件の近さが影響します。
管理会社に管理を委託してしまえば、アパートとマンションの間にオーナーが感じる負担感の違いはほとんどありません。
しかしながら、自主管理となるとマンションのほうが負担が大きくなります。
管理のしやすさに関しては、戸数が少ないという点から、アパートの方が管理が容易です。
戸数も10戸程度であるならば、自主管理も十分にこなせる規模になります。
マンションは戸数が100戸近くになることもあり、このような規模になると自主管理は非現実的になります。
戸数の多いマンションの場合には、割り切って管理会社へ管理を委託した方が良いでしょう。
1-12.維持管理費
マンションは維持管理費が高く、アパートのほうが低いコストで運営できる
【解説】
維持管理費に関しては、アパートよりもマンションの方が高いです。
マンションにエレベーターがある場合、エレベーターの保守メンテナンス費用や電気代が余分に発生します。
また条例によって管理人を設置しなければいけない規模のマンションであれば、管理人の人件費もかかり収益を圧迫します。さらに、給水ポンプや受水槽のあるようなマンションであれば、これらの設備維持費用も発生します。
マンションはアパートよりも管理人への人件費や防災設備・共用部分の設備の維持費用もかさむことになります。
1-13.大規模修繕費
マンションの修繕はより大きな額のコストがかかる

【解説】
大規模修繕費に関しては、マンションのほう方がより大きな金額がかかります。
マンションは、陸屋根(平らな屋根)の場合、大規模修繕費で屋上防水を行う必要があります。
外壁塗装に関しても外壁の面積がアパートよりも大きいため、修繕費用も大きくなります。
エレベーターは保守メンテナンス費用のための維持費がかかるだけでなく、高額な大規模修繕費も必要となります。
例えば小さな敷地で4階程度のマンションを作る場合、思い切ってエレベーターを設置しない計画とするのも一つの考えです。
1-14.リノベーションのしやすさ
大胆なリノベーションをするならマンションのほうが実行しやすい
【解説】
建物が古くなった際の空室対策のために行われるリノベーションは、アパートよりもマンションの方が簡単です。
例えば、壁を壊すような工事は鉄筋コンクリート造のマンションであれば可能ですが、柱の数が多いアパートでは不可能です。
一方でマンションの場合、2つの部屋を1つにするなどの大胆な変更もできることから、賃貸マンションをシェアハウスに変更するなどのリノベーションも実行することができます。
アパートの場合、模様替え程度のリノベーションは可能なものの、思い切って間取りを変更するなどの大胆なリノベーションは実施しにくいという点が弱みです。
1-15.建て替えのしやすさ
アパートのほうが建て替えやすく融通が効く
【解説】
マンションの方が戸数は多く、また解体費用も大きい分、建て替えが難しくなる傾向があります。
建て替えを行う際には、全ての住戸を退去させて空の状態にしなければなりませんが、戸数の多いマンションは立ち退きに多くの労力を要します。
延床面積もマンションの方が大きいため、費用の総額がより多く必要になります。
総じて見ると、マンションのほうが建て替えのあらゆるプロセスで費用が多くかかるため、建て替えのハードルは高めです。
1-16.相続対策
資金力があるならマンションを建てたほうが相続対策効果は高くなる
【解説】
相続対策の節税効果については、基本的にアパートもマンションも同じです。
アパート・マンションを賃貸として貸し出すことで、いざ相続税を計算する際の建物の相続税評価額が30%減額されます。
これを「借家権割合による評価減」と呼びます。
土地に関しては、土地の上に賃貸に供している建物が建っていることで「貸家建付地評価減の適用」を受けることができます。
通常、土地の相続税評価額は「相続税路線価」より求められたものです。
貸家建付地評価減が適用されると、土地の評価額が以下のように計算されます。
貸家建付地
= 路線価評価額 × ( 1 - 借地権割合 × 借家権割合 )
借家権割合は、全国一律で30%になります。
一方で、借地権割合は場所によって異なります。
例えば借地権割合が60%の土地であれば、路線価評価額よりも18%(= 60% × 30%)減額された価格が相続税評価額となります。
さらに、建物建築のために借入金を用いると、借入金の金額が相続財産からマイナスされます。アパートもマンションも借入金を使って建てることが多いため、2つとも相続対策効果があります。
但し、マンションの方が投資額は大きいため、一発で大きな相続対策効果を得ることができます。
アパートを何棟も建てるよりは、マンションを一棟建ててしまったほうが節税効果が高くなります。
よって、多額の現金を保有している場合には、マンションのほうが相続対策上有利です。
「アパート?」「マンション?」
2.アパート経営が向いている人
マンションよりもアパートの経営に向いているのは、自宅近くにアパートしか建てられたない土地を持っているオーナーです。
アパートしか建てられない土地とは、公法上の規制の上でマンションが建築できない土地や、マンションには小さ過ぎる土地が該当します。
元々土地を持っている方は、建物投資だけでアパート経営をすることができるので、かなり有利です。
さらにオーナーの自宅近くにある土地であれば、自主管理を選択することでさらに収益性を上げることができます。
また、アパートはマンションと比較すると必要な費用の総額が少ないため、多くの資金を有していないオーナーにとってもアパート経営の方が向いています。
3.アパート経営が向いていない人
マンション建築に適した土地を持っている方は、アパートを建ててしまうともったいないので、アパートには向いていません。
マンションが建築できるような土地は、希少性が高く、賃貸事業を開始する上でとても有利なのでぜひマンションでの活用を検討したいところです。
マンションが建築できる土地の目安としては、駅から徒歩10分圏内で容積率が200%以上で指定されているような土地です。
容積率とは建物の延べ床面積の土地面積に対する割合です。
ターミナル駅に近い土地であれば、60坪程度の土地でもワンルームマンションが建築できます。
立地条件が良く、容積率も高い土地はマンションを建てるのに適しています。
アパートでは土地のポテンシャルを活かしきれませんので、マンションを選択することをおすすめします。
4.マンション経営が向いている人
マンション経営には、資金力にある程度に余裕のある方が向いています。
現金を一棟マンションに変えると、家賃収入が得られるほか、相続税評価額を下げられるため節税対策となります 。
5.マンション経営が向いていない人
マンションは投資額が大きくなるため、自己資金を多く持ち合わせていないオーナーには不向きです。
多額の借入金によってマンション投資を行ってしまうと、その分、過剰な借入金リスクを背負うことになります。
マンションは総額が1億円を超えるような投資となるため、個人投資家が行う投資レベルとしては相当に大きな部類になります。
自己資金が不十分な方は、1棟マンション以外の小さな物件から投資を始めた方が適切です。
無理をせず、アパート経営や区分ワンルームマンション経営などから始めるのが良いでしょう。
6.アパート経営にもマンション経営にも強いハウスメーカーを選ぶためのポイント
不動産投資においては、アパート経営・マンション経営のどちらを選ぶにしても、十分な利益を確保するためには物件選びのみならず、優良なハウスメーカーを選ぶことが非常に重要です。
以下、「安心して相談できるハウスメーカー」を選ぶために必要不可欠なポイントについてお伝えします。
6-1.ハウスメーカーの提示する「経営プラン」
多くの大家さんはアパート・マンションを建築するタイミングで、建築にかかる費用や工法、出来上がる物件などのことばかりを気にかけがちですが、出来上がった後の収益を左右する要素として「完成前・完成後の経営プラン」も非常に重要です。
各メーカーが提示しているランニングコストや収支計画をチェックすることによって「より具体的で現実性が高い計画」を掲げている会社を選ぶことが重要です。(各社ごとに、意外なほど内容の差があるのがお分かりいただけるはずです)
6-2.ハウスメーカーの規模
大手ハウスメーカーのアパート・マンションはもともと施工の質が高いので、劣化しにくく、修繕費も最小限で済みます。
また手厚いアフターサービスが付いていますので、長年に渡り建物のコンディションを維持することができます。
大手ハウスメーカーで物件を建てた方の声を聞くと、決まって「アフターサービスが良い」という答えが返ってきます。
中小のハウスメーカーも「大手にはできない細やかなサービスを提供できる」というイメージを消費者に持たせようとアピールしていますが、少なくとも「大切な資産を形成する」ことを第一に考えればでは、やはり大手ハウスメーカーに建ててもらうのが安心です。
6-3.評判・口コミ
ハウスメーカーの評判や口コミについては、インターネットを活用することによって業者の立場から独立した中立な意見を拾うことができます。
特に近年では、通常のGoogle検索の他に、SNS上で情報を探すことによって「生のユーザーの声」を見つけやすくなっているので、ぜひご活用ください。
6-4.問い合わせへの対応
問い合わせへの応対が手厚い会社であれば、実際に契約を結んだ後のフォローの質にも期待できるでしょう。
気になるハウスメーカーがあれば、事前にメールで相談してみて、担当者がどれくらい丁寧に応対してくれるかを確かめるのも一手です。
なお、「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」なら無料で土地活用提案を受けることが可能です。以下のボタンから土地情報を入力すると、最大10社のハウスメーカーがあなたの土地に合った、建築費の見積もりや、経営プランを無料診断いたします。
「アパートはいくらで建つの?」「いくら儲かるのか知りたい」という方はご活用ください。
「アパート?」「マンション?」
アパート経営 基礎知識系記事一覧
- 【基礎から解説】アパート経営に必要な基礎知識一覧。検討すべき事項がすぐわかる!
- 【徹底解説】アパート経営で儲かるコツ、儲ける仕組みを大解剖
- 【徹底解説】アパート経営が儲からない理由と儲かるための10の方法
- 【事例集】アパート経営の失敗事例13種とその対策
- 【基礎から解説】アパート経営のリスク全13項目一覧&対応法
- 【徹底解説】アパート経営とマンション経営、16の違いを徹底比較
- 【徹底解説】アパート経営で老後の備え!大切な資産を活かすポイントとは
- アパート大家の主なお仕事内容8つ!管理を委託するメリット・デメリット
- アパート経営法人化のメリット・デメリットは? 相続税対策についても解説
- 土地なしからアパート経営は可能?始める方法・初期費用・条件を解説
- 土地ありで始めるアパート経営は有利!建築費用・自己資金・利回りとリスクを解説
- なぜ「アパート経営はするな」と言われる?成功に導くコツもあわせて解説
- 【徹底解説】アパート経営のメリット・デメリット!今後の動向変化と成功のポイントも解説
- アパート経営は地獄?起こりがちな失敗例7つと回避方法を徹底解説!
- 土地活用で賃貸経営!種類別メリット・デメリットや成功のポイントも解説
- アパート経営30年後に予想される10大リスクと出口戦略
- 【保存版】アパート経営を成功に導く9つの秘訣
関連キーワード