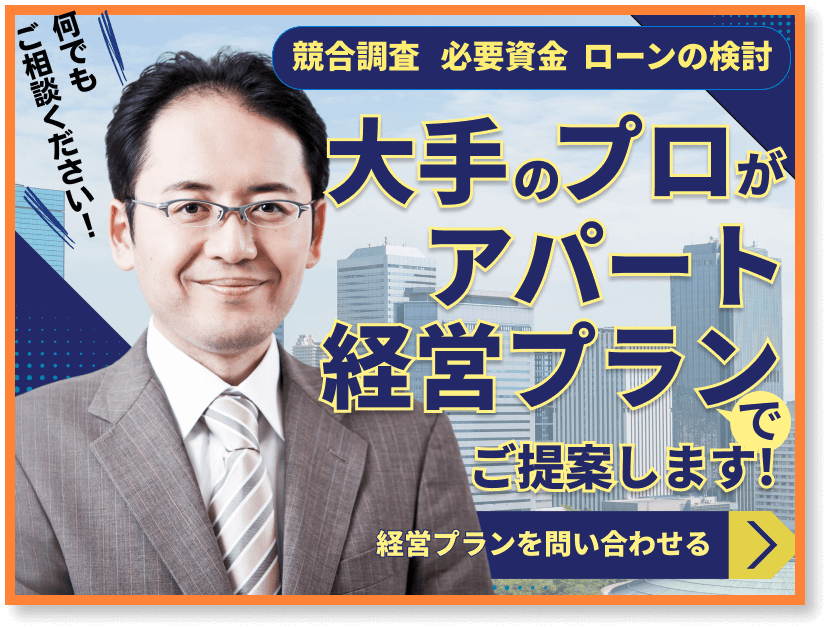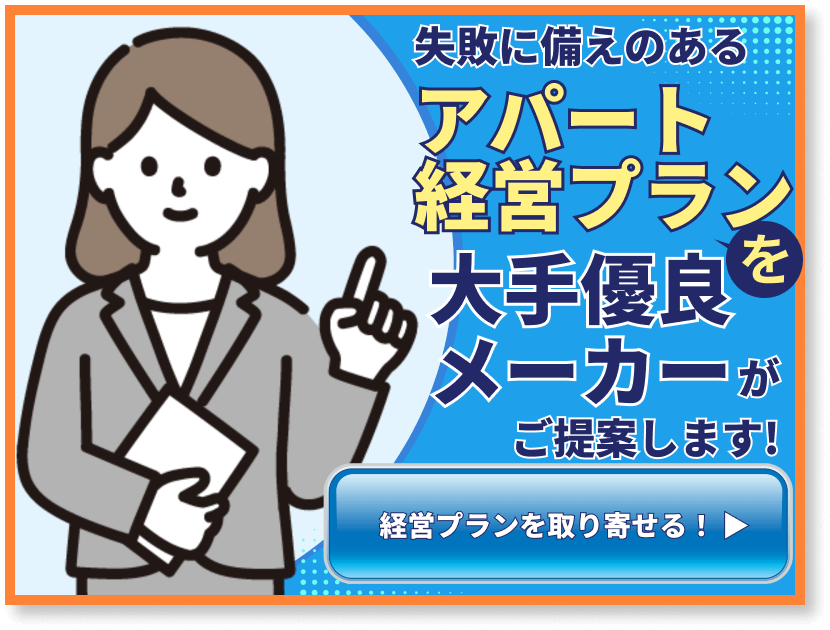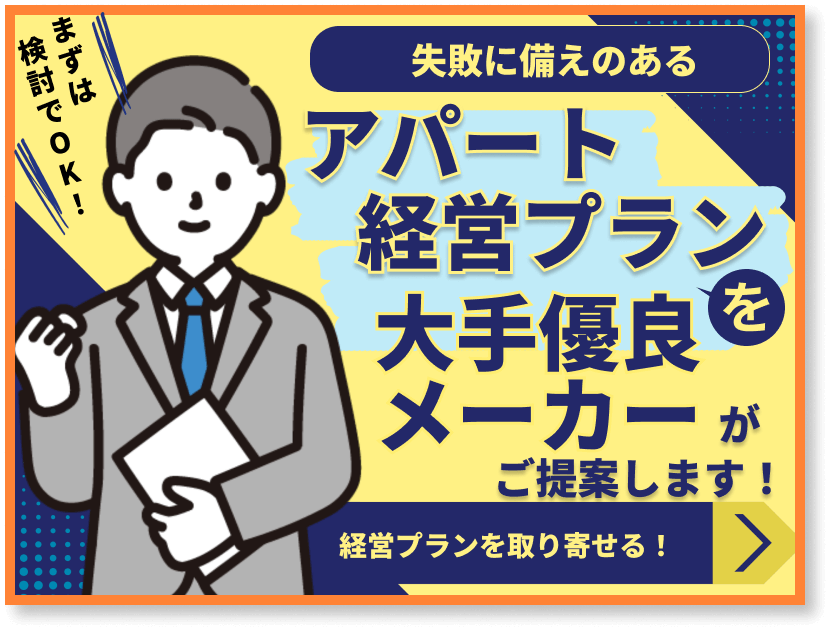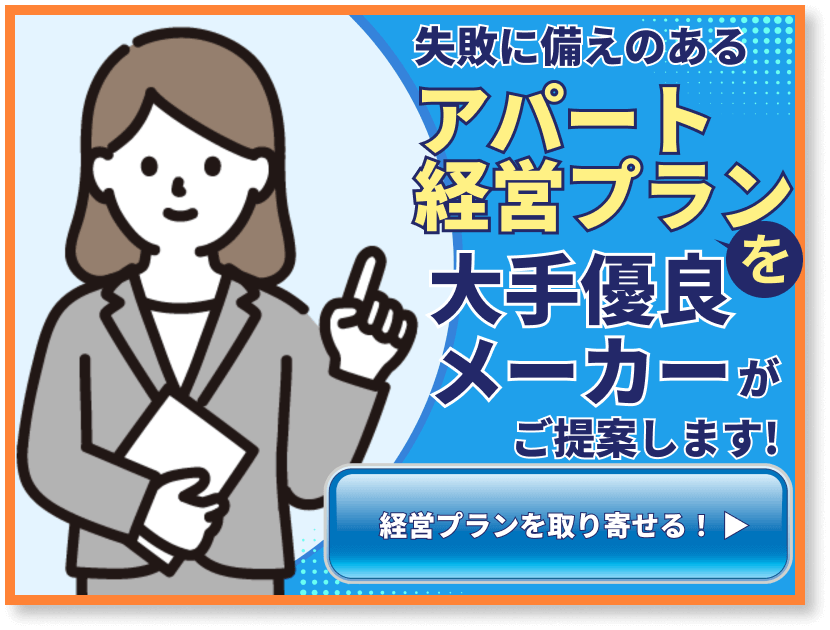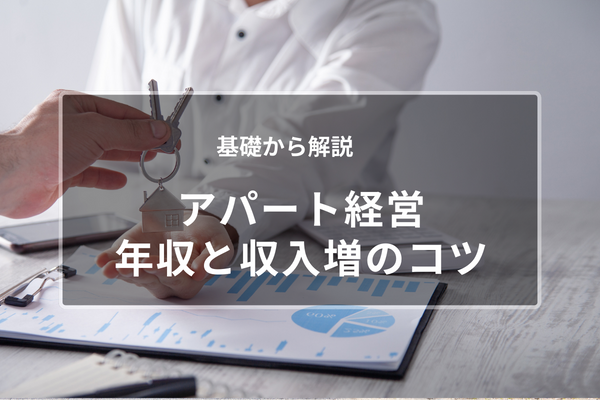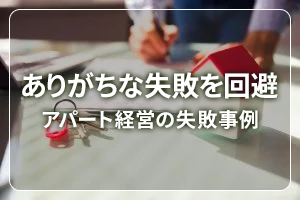
アパート経営の失敗を防ぐには、まず失敗する理由を知り、適切な対策を取りながら進めていくことが肝心です。
この記事では、失敗してしまう理由とそれぞれの対策について紹介します。
また、以下のボタンから土地情報を入力すると、最大10社のハウスメーカーがあなたの土地に合った、収支計画や、経営シミュレーションを無料診断いたします。
「うちの土地にいくらでアパートが建つの?」「いくら儲かるのか知りたい」という方はご活用ください。
アパート経営の失敗にはどんなものがある?
アパート経営の失敗にはさまざまな要因がありますが、その中でも代表的なものは以下の13種類です。
- 供給過剰による失敗
- ローンによる失敗
- 金利上昇による失敗
- サブリース契約による失敗
- 空室による失敗
- 家賃滞納による失敗
- 入居者トラブルによる失敗
- 災害による失敗
- 大規模修繕による失敗
- 家賃下落による失敗
- 老朽化による失敗
- 資産価値下落による失敗
- 立ち退きによる失敗
それぞれの失敗要因の詳細と解決策については、それぞれの章で詳しく解説しています。
アパート経営に失敗しないためにできることは?
アパート経営で失敗しないためには計画段階で検討しておきたい事項があります。以下の5つです。
- 自己資金の投じ方を考える
- 所在地のニーズを把握し建築プランを検討する
- 長期的な視野で経営プランを考える
- アパート経営をサポートできるハウスメーカーを見つける
- 良質な管理会社を見つける
「失敗しないアパート経営 」
詳しい解説は以下
目次
- 1.アパート経営が失敗しやすいタイミング
- 2.【計画時】「周りに次々とアパートが増えて入居者が集まらない…」
- 3.【計画時】「毎月の返済がきつくて、空室が出るのが心配…」
- 4.【計画時】「金利の上昇で利息が上がって返済が追い付かない…」
- 5.【計画時・経営時】「サブリース会社から想定していなかった賃料減額の要求が…」
- 6.【計画時・経営時】「空室を埋められず、支出ばかり増えていく」
- 7.【経営時】「入居者が家賃を払わず居座ってしまっている」
- 8.【経営時】「入居者から隣人の騒音クレームが。注意しても改善しない」
- 9.【経営時】「もらい火でアパート経営が続けられずローンだけが残ってしまった」
- 10.【経営時・経年時】「大規模修繕が必要なのに資金を用意できない」
- 11.【経年時】「家賃の下落で前のように儲からない…」
- 12.【経年時】「建物が古くなって入居者を見つけにくくなっている」
- 13.【経年時】「アパートの価値が下がって売ろうにも売れない」
- 14.【経年時】「建て替えのための立ち退き交渉がうまくいかない…」
- 15.【成功の秘訣】アパート経営で失敗しないための検討事項
- 16.失敗を防ぐ!アパート経営に強いハウスメーカーを選ぶためのポイント
1.アパート経営が失敗しやすいタイミング
アパート経営の失敗はリスクヘッジすることで回避しやすくなります。
しかし、リスクヘッジするタイミングはそれぞれ異なるため、適切に対策をしておくことが重要です。
解決の糸口があるタイミングは以下のように分けられます。
| 計画時 (建築時) |
経営時 | 経年時 |
|---|---|---|
|
|
|
失敗を防ぐためには、それが起こってくるタイミングと対策すべきポイントを知った上で、事前に対策を練っておくことが大切です。
2.【計画時】「周りに次々とアパートが増えて入居者が集まらない…」
まず、「供給過剰」による失敗についてみていきましょう。
2-1.供給過剰での失敗の原因
アパート経営に苦戦する理由の一つに「供給過剰リスク」があります。
新築して間を置かずに周辺にアパートが乱立し、更に家賃の面などで同じような条件の物件が多すぎると、オーナーの持つ物件の希少価値が下がり、選ばれにくくなります。
こうした供給過剰はライバル物件増加の他、当該エリアの中の人口減少によっても生じやすい現象です。
2-2.対策
- 対策1:計画時に周辺の状況と動向を調査する
供給過剰リスクを回避するには、アパートを建てようとするエリアの需要と供給のバランスはどうなっているか、向こう3年程度の見通しを調査しておくことが重要です。
このような情報は建築会社やハウスメーカーが持っています。
相談時にまず問い合わせることで、ニーズにマッチした安定性のあるアパート経営が実現しやすくなるでしょう。
- 対策2:「物件の個性」を打ち出し、他の物件との差別化を図る
例えば、「ペット可」、「女性限定」の物件として打ち出すなど、「周辺の類似物件とは異なる個性」を物件に持たせてアピールすることで、他の物件に埋もれてしまうリスクを軽減できます。
これらのような施策は、物件のルールを変えるだけで、特段大きな改装を施したりしなくても実行が可能です。
3.【計画時】「毎月の返済がきつくて、空室が出るのが心配…」

「自己資金がなくても大丈夫!」といった謳い文句を真に受けて自己資金を用意せず、フルローンでアパートを建てた場合などに陥りやすい失敗です。
3-1.ローンでの失敗の原因
アパートを建てる際に十分な自己資金が用意できていないと、金融機関からのローン借入額の割合が大きくなり、月々の返済が苦しくなるリスクがあります。
家賃収入よりもローン返済額のほうが大きい状態、いわゆる「持ち出し」が続くと、その分を自己資金や他の収入などから補填せざるを得なくなり、家計さえひっ迫させることにつながりかねません。
経営は寸分のミスも許されず、かえって非常なストレスを背負い込むことになるでしょう。
3-2.対策
- 対策:アパート建設時の資金にある程度の自己資金を投入する
借入額は出来るだけ少なくすることをおすすめします。「ローンを多く抱えるほどリスクが増える」と認識しておきましょう。
自己資金をどれだけ用意するべきかを考えるとき、まずは「これからアパートを建てる際にどれだけの初期費用がかかるか」を把握することが第一歩となります。
「競合調査」「必要資金」「ローンの検討」・・・
4.【計画時】「金利の上昇で利息が上がって返済が追い付かない…」

ローンを組んだ時より金利が上がって、最初の想定よりも銀行に払う利息が上がってしまったケースです。
4-1.金利上昇での失敗の原因
ローン契約時に「変動金利」と「固定金利」を意識せずに契約してしまうことにより、陥りやすい失敗です。
アパート経営のためにローンを変動金利で組んでいる場合、金利が上がれば月々返済するローンの利息額が上がってしまう可能性があります。
特に、借りる際に最も金利の安い設定の変動金利型を選んでいると、変動のリスクをもろに受けてしまい、返済額が増えて手残りが激減することになります。
このような金利の上昇は社会経済の変化によるので、どれだけアパートの運営自体がうまくいっていたとしても、影響を受けてしまいます。
4-2.対策
- 対策:契約時に固定金利を選択する
金利上昇のリスクを受ける可能性があるのは、ローンを受ける際に結ぶ金融機関との契約で変動金利を選択していた場合です。
固定金利を選択すれば、世の中の金利上昇の影響を受けず、契約時に決めた金利を固定的に払い続ける形になります。
固定金利は変動金利と比較すれば金利が高いものの、金利上昇のリスクヘッジとして機能するので、ある種の保険のような役割を果たしてくれます。
アパートローンの仕組みについてはこちらの記事をご一読ください。
5.【計画時・経営時】「サブリース会社から想定していなかった賃料減額の要求が…」
サブリース契約によるトラブルは多く、賃料減額の可能性があることを見落としていたというケースはよくあります。
5-1.サブリース契約での失敗の原因
サブリース契約の効力を過信してしまったことで引き起こされた失敗です。
空室時にも一定の賃料を確保するために、サブリース会社へアパートを転貸(又貸し)する「サブリース契約」ですが、たとえ家賃保証を謳っていても、契約時から満了時までずっと賃料が変わらないわけではありません。
契約から一定期間が経ったタイミングで、物件価値の減少や空室状況などを理由に「賃料の減額請求(オーナーへ支払う賃料の値下げ請求)」をしてくる場合があります。
しかし、家賃保証、一括借り上げなどの言葉が独り歩きした結果、賃料はずっと固定だと思い込んで契約内容をよく確かめておらず、減額の可能性があることを見落として、ローン返済のリスクが高まってしまったというようなケースはしばしば発生しています。
5-2.対策
- 対策1:サブリースの契約内容を確認し、通常の賃貸経営との比較をした上で経営方法を選ぶ
サブリースにはメリットもデメリットもあります。計画時に、管理会社に管理を委託して自営する方法と総合的に比較してみることをおススメします。
自営では空室リスクがダイレクトに影響しますが、サブリースでも結果的にオーナーの経営失敗につながります。
サブリース契約の効力を過信して「家賃が永久保証される」と考えるのは禁物です。
- 対策2:サブリース会社の要求に納得できない場合は、すぐに応じずに話し合いの機会を持つ
サブリース会社からの要求に対しては必ず応えなければならないというわけではありません。
理不尽な要求だと感じた場合にはすぐに応じず、まずはサブリース会社と交渉してみることをおススメします。
話し合いで解決することができなかった場合には、裁判所に仲介を依頼することも可能です。オーナー自身で全て背負い込まず、第三者の力を借りながら対処するとよいでしょう。
サブリース契約で起こりうるトラブルと回避策はこちらで詳しく解説しています。
「失敗に備えのある」アパート経営プラン
6.【計画時・経営時】「空室を埋められず、支出ばかり増えていく」
以下で詳しく解説します。
6-1.空室での失敗の原因
購入した物件に入居者が集まらず、空室を埋められないというのはアパート経営においてもっとも代表的なリスクの一つと言えるでしょう。
たとえ空室が埋まらずに家賃収入が得られなくとも、部屋を維持するためのランニングコストは必要です。
固定資産税や修繕費用などといった直接的な費用の他、空室となった部屋を埋めるための仲介手数料なども発生します。
空室を埋められない物件を保有していることは、負債を抱える失敗へとつながりかねません。
6-2.対策
- 対策1:入居者が決まりにくい「1階」を中心にした空室対策を行う
アパートの中でも最も空室となりやすいのは1階です。ですから、まずは1階の空室対策に力を入れましょう。
1階の部分は騒音の問題や防犯上の問題、害虫の問題など、不安を感じるポイントがそろっています。これらの不安点を解消することは1階への入居を促すことにつながります。
- 1階の空室対策
-
- 防音性の高い材料を使用し、防音性を高めていることをアピール
- 監視カメラ(ダミーでも可)などを目立つ部分に取り付ける
- 害虫の発生を防ぐため、こまめな草むしりなどで清潔な環境を保つ
- ガーデニングやバーベキューができる専用庭を設ける
- 1階の入居者が利用できる物置 (トランクルーム)を設置する
- 歩行者から見えないよう、垣根などを設ける
- 設計段階から1階の部屋数を少なくする
これらの対策は、アパートを建設したあとに実行するよりも、建設前から1階の空室対策を意識して建物を作り込むほうが簡単です。
設計プランを検討する際には、プロに1階の空室対策アイデアを提案してもらうことをおススメします。
- 対策2:管理会社の変更を検討する
多くの場合、アパート経営では管理や入居審査を管理会社に任せます。
空室が出てもなかなか次の入居者が見つからない、入居者募集に消極的、などといった状況が見られたら管理会社を変更することも検討するべきです。
アパートは築年数がたてばそれだけ空室リスクは高まります。
優れた管理会社であれば、状況に合った空室対策も提案してくれることでしょう。
7.【経営時】「入居者が家賃を払わず居座ってしまっている」
以下で詳しく解説します。
7-1.家賃滞納での失敗の原因
この失敗の大きな要因はマナーの悪い入居者が入って来る前の水際対策に失敗していることです。
そして、賃貸契約では「借地借家法」によって入居者の権利が守られているため、一度入られてしまうとオーナーからの立ち退き要請は非常に難しくなります。
法律上、滞納が3ヶ月以上連続しない限り契約を解除することは出来ず、3ヶ月以上滞納が続いたのちに訴訟を起こしても、実際に立ち退いてもらえるまでに半年から1年の時間がかかります。
7-2.対策
- 対策1:入居時の審査を厳格にする
家賃滞納への対策は、事前の対策が基本です。
空室を埋めるためとはいえ、どんな入居者でも入居を認めるのはトラブルメーカーを呼び込むことにつながります。
収入や職業などの基準を設けることで、家賃滞納をはじめとしたトラブルを起こしやすい入居者を事前にブロックすることも必要です。
オーナー自身が審査を行う自信がない場合は、管理会社へ任せるという手もあります。
- 対策2:敷金を預かる
敷金を預かることで、未払いの家賃に充てることができます。預かる敷金の目安としては、2ヶ月分以上預かっておくことがベストです。
- 対策3:家賃保証会社との契約を入居条件とする
家賃保証会社との契約を入居条件とすることで、いざ入居者が家賃を滞納した際に保証会社が代わりに家賃を支払う形を作れます。
家賃保証会社との契約にあたっては、入居者がオーナーへ保証料を支払う形です。
立ち退きのノウハウについてはこちらをご一読ください。
8.【経営時】「入居者から隣人の騒音クレームが。注意しても改善しない」
一部の入居者の騒音により、質の良い入居者が退出すると、新しい入居者を見つけるのが難しくなるでしょう。
8-1.入居者トラブルでの失敗の原因
入居者トラブルには、例えば以下のような例があります。
- 入居者トラブルの例
-
- ペット禁止の物件でペットを飼う
- ゴミを分別しない
- 同居や同棲をする
- 汚部屋にする
- 夜間に騒ぐ
- バルコニーでバーベキューをする
- 落書きをする
- 夜逃げする
これらは入居時の審査を厳格に実施していないことで引き起こされます。
特に家賃を安く設定しているアパートでは、トラブルを起こしやすい入居者が入ってきてしまう可能性が高くなります。
8-2.対策
- 対策:入居時の審査を厳格にする
悪質な入居者を見分けるために、審査基準を厳格にします。オーナー自身で審査を行う自信がなければ、管理会社へ代行してもらうとよいでしょう。
管理会社へ審査を依頼する場合は、賃貸仲介に強い会社を選びます。
賃貸仲介に強い会社は入居審査もしっかりしており、空室対策も積極的です。
管理会社に不安を感じたら、賃貸仲介に強い会社に切り替えることをおススメします。
9.【経営時】「もらい火でアパート経営が続けられずローンだけが残ってしまった」
隣家の火事によるもらい火の他にも、台風による水害などをきっかけに、順調だったアパート経営が暗転してしまったケースです。
9-1.災害での失敗の原因
保険料も割安で費用対効果の高い「火災保険」の重要性を見落としており、損失の補てんができなかったことが失敗の原因です。
もらい火の場合、延焼によって損害を受けたケースでも火元になった相手に損害賠償を求めるのは難しくなります。
9-2.対策
- 対策:火災保険には必ず加入しましょう。
火災保険は、特約などをつけることで火災のみならず、水害や暴風雨によるダメージも補償対象にできます。
地震保険や水害特約への加入はアパートのあるエリア次第で判断してもよいでしょう。
地震により住宅が倒壊する可能性というのは一般にイメージされているよりも低く、近年の自然災害の中で最大の被害をもたらした東日本大震災の時でさえ、被害地域におけるマンションの98%以上の被害程度が軽微あるいは損傷なしだったとされています。
(参照:平成23年 社団法人高層住宅管理業協会『東日本大震災 被災状況調査報告(PDF)』)
「失敗に備えのある」アパート経営プラン
10.【経営時・経年時】「大規模修繕が必要なのに資金を用意できない」
大規模修繕が必要なタイミングで資金を用意できず、建物の老朽化が進んでしまったケースです。
10-1.大規模修繕での失敗の原因
大規模修繕ができないという事態に陥る原因は、長期修繕計画を立てずに行き当たりばったりの経営を続けてきたことにあることがほとんどです。
アパートの場合、築10年が過ぎた頃からさまざまな箇所で修繕が必要となってきます。
具体的には外壁や屋上防水などです。
一定のスパンごとに大規模修繕を実施しないと、災害時に被害が拡大するリスクが高まり、資産価値が下落して経営に悪影響を及ぼすことになりかねません。
10-2.対策
- 対策:定期預金なども活用しつつ、時間をかけて資金を積み立てる
積み立てなどの準備をせず、修繕費用をポンと出せるだけの資金力を持つオーナーはほとんどいません。日頃から、資金を積み立てておくことが重要です。
資金を貯めることに苦手意識がある場合は、定期預金など外部の力を借りる形で資金を用意していくことで、修繕を要するタイミングに備えられます。
11.【経年時】「家賃の下落で前のように儲からない…」
新築から時間がたってアパートの賃料(家賃収入)が下がってしまい、稼働率は変わらないのに手残りが減ってしまった、というケースはどのアパートでも起こりうる失敗です。
11-1.家賃下落での失敗の原因
築年数の古さをカバーできるだけの魅力を打ち出せず、家賃の引き下げで対応することで起こる失敗です。
アパートの経年劣化、そして入居者から「築後年数が経った物件」と思われることによって、アパートが築後年数を重ねるごとに、得られる賃料は下がる傾向があります。
これが、多くのアパートオーナーを悩ませる「賃料下落」の問題です。
特に新築後の10年間は最も家賃の下落率が高く、築後20年を経過した時点で下落率が落ち着いてきます。
11-2.対策
- 対策:アピールポイントを打ち出して、物件の古さをカバーする
例えば、セキュリティ面の強化を図ったり、ペット可などルールの変更をしたりといったことでも築年数以外の魅力をプラスできます。
また、建築時に間取りやデザインを工夫することで家賃の下がりにくい物件にすることも可能です。いずれ来る家賃下落リスクに備えて建築時にプロに相談しておくのもよいでしょう。
12.【経年時】「建物が古くなって入居者を見つけにくくなっている」

経年劣化によって建物の外観が老朽化し、空室率が高くなってしまったケースです。
12-1.老朽化での失敗の原因
この失敗の最大の要因は老朽化対策のために資金を投入できていないことです。
アパート経営は数十年単位の長いスパンで運営していくものですから、老朽化のリスクとは必ず向き合うこととなります。長期の経営計画を立てることなく漫然と経営をしていくと、いずれ必要となったときに対処できずに経営難を引き起こしてしまいかねません。
12-2.対策
- 対策1:施工の質の高い建物を建てること
老朽化しやすいアパートかどうかは、建設時点である程度決まっています。新築時に適切なコストをかけ、質の高いアパートを建てることが第一の対策です。
規格アパートを持つ建築会社・ハウスメーカーであれば、コストを抑えながらも高品質のアパートを手に入れられます。規格が統一していることで、メンテナンス面でも安心です。
- 対策2:定期的なメンテナンスを実施すること
定期的に外壁塗装、排水管の高圧洗浄などの予防保全(建物が壊れる前に行うメンテナンス)を実施することで、老朽化をかなりの程度遅らせることができます。
「失敗に備えのある」アパート経営プラン
13.【経年時】「アパートの価値が下がって売ろうにも売れない」
基本的に、ローンを完済できなければ物件を売れません。資産価値が下落したことによって売却益でローンを完済できないような状態は、経営の失敗が続く状態とも言えます。
13-1.資産価値下落での失敗の原因
資産価値向上につながるリフォームを行う機会を逃しがちであることが結果的にこの失敗の原因となります。
通常、アパートにリフォームを施さないまま放置していると、築年数が経過するにつれて価値が下がっていきます。
また、建物自体が古くなるという要因以外にも、人口動態の変化などにより土地の価値が下がった影響でアパートの価値も下がるということもあります。
13-2.対策
- 対策:入居者にとって好印象となるリフォームを行う(事前にハウスメーカーと相談)
築年数が古いアパートに適切なタイミングで適切なリフォームをすることによって物件としての価値を維持・向上させることは可能です。
ただし、資産価値を上げるためのリフォームは、入居者にとって価値の感じられるものである必要があります。
価値の向上につながらないリフォームは、費用を無駄にすることになりかねません。
リフォームをするにあたっては、ノウハウも豊富なハウスメーカーへ事前に相談した上で実施するべきでしょう。
14.【経年時】「建て替えのための立ち退き交渉がうまくいかない…」
建て替えを決意して、いざ立ち退き交渉を始めたものの、一部の入居者が交渉に応じてくれないというケースです。
借地借家法では賃借人の権利を保護していることから、立ち退き交渉はきちんとした対策をとっておかないと失敗に陥る可能性が高まります。
14-1.立ち退きでの失敗の原因
立ち退き交渉のために十分な準備期間をとっていないことと、交渉の段取りを誤っていることが原因です。
アパートの老朽化は外観の問題だけでなく、防災上の危険が増すなどにつながるため、しかるべきタイミングで対処が必要です。
入居者の都合に合わせて建て替えを延期していると、その間にも老朽化が進み建物の倒壊をはじめとしたリスクが高まったり、アパートの資産価値が低下したりと大きなリスクにつながりかねません。
14-2.対策
- 対策:立ち退きの交渉は6ヶ月以上前から実施する
オーナー都合の場合、立ち退きの通知は少なくとも6か月前には行わなければならないとされています。
入居者をオーナーの都合ですぐに追い出すことは法律上不可能です。
また、立ち退き通知は時期の条件以外にも、立ち退きが正当な事由に基づいていること(老朽化に伴う防災対策等)が必須です。
オーナーの都合で入居者に立ち退いてもらいたい場合は、入居者へ「立ち退き料」と呼ばれるお金を支払うことによって解決を図るケースがほとんどです。
15.【成功の秘訣】アパート経営で失敗しないための検討事項
長く続くアパート経営で失敗しないためには、実は計画段階が非常に重要です。ここでは計画段階で検討しておきたい5つのポイントを紹介します。
- 自己資金の投じ方を考える
- 所在地のニーズを把握し建築プランを考える
- 長期的な視野で経営プランを考える
- アパート経営をサポートできるハウスメーカーを見つける
- 良質な管理会社を見つける
15-1.自己資金の投じ方を考える
初期費用の中の自己資金の割合を多くすれば、その分ローンの返済負担が軽くなります。おおよそ3割は自己資金を用意するのが望ましいとされています。
借入金を少なくできれば、審査に通りやすくなり、良い条件でローンを組める可能性も高まるでしょう。
また、返済額が多いと経営に余裕がなくなります。急な空室や自然災害で受けた損傷などリスクに対応できるだけの体力を残しておくことが重要です。
しかし、借入金を少なくしたいがために手元の自己資金を残らず初期費用に投じるのは危険です。
まだ経営が軌道に乗っていない状態でリスクにさらされる可能性もあります。こうしたときには手元に残した自己資金を投じる必要が出てきます。
15-2.所在地のニーズを把握し建築プランを検討する
アパート経営は典型的な立地商売です。所在地のニーズを無視した物件を建てたところで順調な経営はできません。
重要なのは事前の調査です。ファミリータイプかワンルームタイプか、アパートでよいか戸建て賃貸のほうがよいか、市場を調査しておきます。
しかし、こうした調査は素人には非常に難しいものです。その点、ハウスメーカーや地元密着の建築会社であれば市場の動向に敏感で、潜在ニーズを知っています。まずは、どういったかたちでの土地活用がふさわしいか、どういった建築プランが良いか、ハウスメーカーなどに相談してみるとよいでしょう。
「資金計画」「マーケティング調査」「老朽化対策」・・・
15-3.長期的な視野で経営プランを考える
アパート経営は長期的に運用することでより大きな収益を得るタイプの投資です。
長期安定を目指した無理のない運用とリスクへの事前の対応が重要になってきます。
天敵の一つに挙げられるのは経年劣化です。建築から10年もたてば大規模修繕をする必要性が出てきます。
こうしたリスク対応には大なり小なりの出費がかかるため、前もって資金を積み立てておくことが重要です。問題が勃発した時に用意できる資金がないとたちまち経営は傾き、失敗しかねません。
アパート経営では、初期の段階からリスクヘッジしておくことが重要です。
15-4.アパート経営をサポートできるハウスメーカーを見つける
アパート経営ではいかに競争力のあるアパートを建てるかが重要項目の一つになります。
ニーズにマッチした物件を手に入れるには、経営面からもアドバイスをもらえるハウスメーカーに設計と新築を依頼するのがよいでしょう。
大手の企業であれば税金対策にも詳しく、アパート建築による節税効果などのアドバイスももらえます。また、経営が始まった後もサポート体制を整えている企業もあり、強力な支援者として長期的なサポートが望めるでしょう。
15-5.良質な管理会社を見つける
経営時に勃発する多くの失敗は、良質な管理会社を見つけることで解決できます。契約内容にもよりますが、管理会社は入居者募集から建物の管理、入居者のクレーム対応まで、プロの手で対処してくれます。
特に、入居者募集や審査に関してはプロの技に頼ったほうが失敗の目を確実に摘むことが可能です。
しかし、中には所有物件のタイプの対応に慣れていないなどの理由から、良い結果を出せない場合もあります。より良い管理会社を探すには、過去の実績なども参考にするとよいでしょう。
16.失敗を防ぐ!アパート経営に強いハウスメーカーを選ぶためのポイント
ここまでご紹介してきた13種類の失敗には、ノウハウの豊富なハウスメーカーに相談することによって未然に防止できるもの、発生後でも解決できるものがいくつもあります。
したがって「安心して相談できるハウスメーカーを味方につけること」自体がアパート経営の失敗を防ぐことにつながるといって過言ではありません。
ここからは安心して相談できるハウスメーカーを選ぶために必要不可欠なポイントを紹介します。
16-1.ハウスメーカーの提示する「経営プラン」
多くの大家さんはアパート・マンションを建築するタイミングで、建築にかかる費用や工法、出来上がる物件などのことばかりを気にかけがちですが「完成前・完成後の経営プラン」も非常に重要です。
各メーカーが提示するランニングコストや収支計画をチェックすることによって「より具体的で現実性が高い計画」を掲げている会社を選ぶことが重要です。
16-2.ハウスメーカーの規模
大手ハウスメーカーのアパート・マンションはもともと施工の質が高いことが多いため、劣化しにくく修繕費も最小限で済みます。
また手厚いアフターサポートが付いていますので、長年に渡り建物のコンディションを維持できます。
大手ハウスメーカーで物件を建てた方の感想を聞くと、決まって「アフターサービスが良い」という答えが返ってきます。
「大切な資産を形成する」ことを第一に考えれば、大手ハウスメーカー・設計事務所に建ててもらうのが安心です。
16-3.評判・口コミ
ハウスメーカーの評判や口コミについては、インターネットを活用することによって独立した中立な意見を拾えます。
ただし、ネット上の評判を鵜呑みにするのは危険です。口コミから得た情報は参考程度にとどめておくとよいでしょう。
評判をもとに、一括プラン請求して自分の目で確かめる方法もあります。
16-4.問い合わせへの対応
問い合わせへの応対がしっかりしている会社であれば、実際に契約を結んだ後のフォローの質にも期待できるでしょう。
気になるハウスメーカーがあれば、事前にメールで相談してみて、担当者がどれぐらい丁寧に応対してくれるかを確かめるのも一手です。
アパート経営のノウハウが豊富な「大手アパートメーカー」
アパート経営 基礎知識系記事一覧
- 【基礎から解説】アパート経営に必要な基礎知識一覧。検討すべき事項がすぐわかる!
- 【徹底解説】アパート経営で儲かるコツ、儲ける仕組みを大解剖
- 【徹底解説】アパート経営が儲からない理由と儲かるための10の方法
- 【事例集】アパート経営の失敗事例13種とその対策
- 【基礎から解説】アパート経営のリスク全13項目一覧&対応法
- 【徹底解説】アパート経営とマンション経営、16の違いを徹底比較
- 【徹底解説】アパート経営で老後の備え!大切な資産を活かすポイントとは
- アパート大家の主なお仕事内容8つ!管理を委託するメリット・デメリット
- アパート経営法人化のメリット・デメリットは? 相続税対策についても解説
- 土地なしからアパート経営は可能?始める方法・初期費用・条件を解説
- 土地ありで始めるアパート経営は有利!建築費用・自己資金・利回りとリスクを解説
- なぜ「アパート経営はするな」と言われる?成功に導くコツもあわせて解説
- 【徹底解説】アパート経営のメリット・デメリット!今後の動向変化と成功のポイントも解説
- アパート経営は地獄?起こりがちな失敗例7つと回避方法を徹底解説!
- 土地活用で賃貸経営!種類別メリット・デメリットや成功のポイントも解説
- アパート経営30年後に予想される10大リスクと出口戦略
- 【保存版】アパート経営を成功に導く9つの秘訣
関連記事
-
不動産投資の利回りはどのくらい?利回りの種類と計算方法を解説
- 2025.01.07
- 経営ノウハウ
-
【簡単解説】マンション経営でよく失敗するポイント8つとその対策
- 2025.01.23
- 経営ノウハウ
-
-