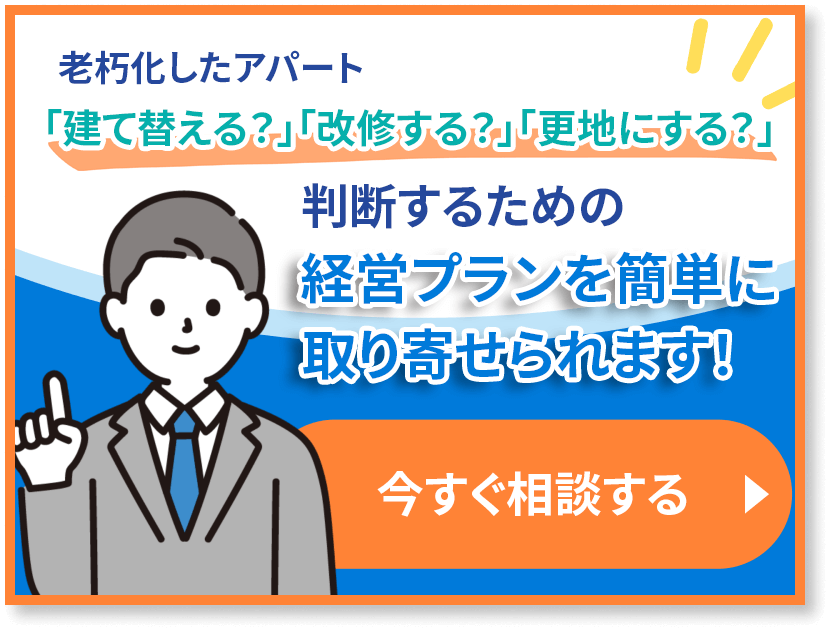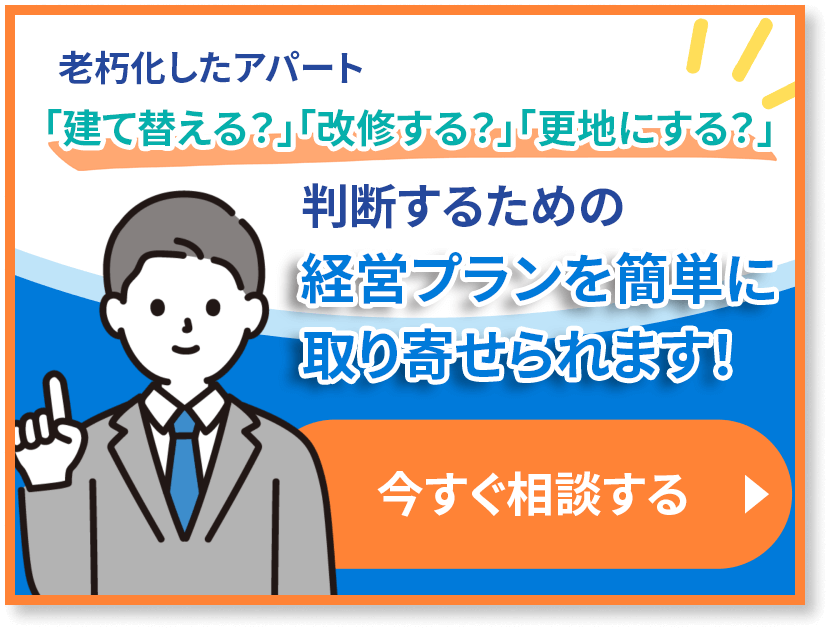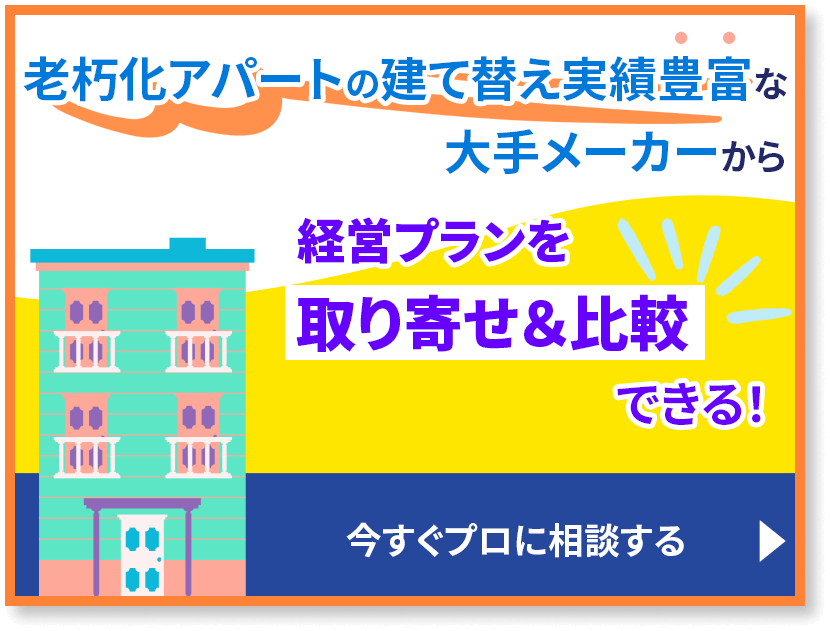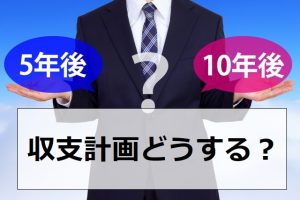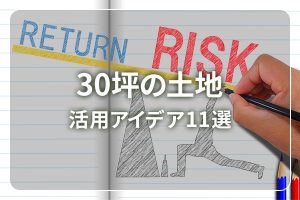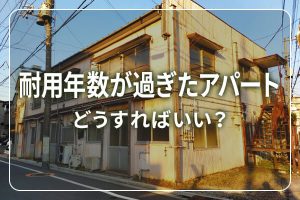【徹底解説】アパートが老朽化した際にやれること
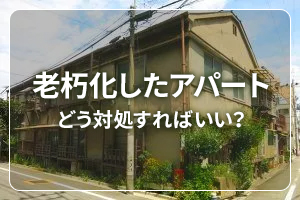
アパートの老朽化対策には、以下3つの方法があります。
- 継続利用
- 買い替え
- 建て替え
この記事では、3つの方法について、「どんな人に向いているか」「その方法を取り入れたらどうしたらよいか」などについて解説します。
また、以下のボタンから土地情報を入力すると、最大10社のハウスメーカーがあなたの土地に合った、建て替え総額の見積もりなどで修繕との将来の収益差を無料診断いたします。
「アパートはいくらで建て替えられるの?」「建て替えと修繕の将来的な収益の差を知りたい」という方はご活用ください。
マンション建築費の目安とは?
老朽化したアパートでも、入居率が5割以上ある状態であればそのまま「継続利用」するという手があります。
継続利用する上では空室対策が必須となってくるので、以下のいずれかのオプションを実行することをおすすめします。
- 管理会社の切り替え
- 募集条件の緩和
老朽化したアパートを手放して別の場所で再スタートすることもできる?
それまでのエリアを離れ、もっと賃貸需要の高いエリアで新たにアパート経営を始めるのは現実的な手段の一つです。
意識するべきポイントは「どんなエリアの物件に買い替えるか」「それまで持っていたアパートをいかに高く売るか」です。
老朽化したアパートを建て替える際に注意するべきポイントは?
建て替えの際に注意するべきポイントは以下の通りです。
- 建て替え後のプラン検討
- 資金計画
- (現在の入居者の)立退きの手順
- 取り壊しの注意点
- 一棟貸しの注意点
老朽化したアパート「建て替える?」「改修する?」「更地にする?」
詳しい解説は以下
1.継続利用
継続利用とは、「有効な空室対策を施すことで入居率を上げ、今の建物を出来るだけ長く活かす」方法のことを指します。
継続利用が向いているアパート・人は以下の通りです。
老朽化は進んでいるものの、入居率がまだ5~6割くらいあるようなアパートを保有している人。
3つの方法の中で最もコストがかからず、リスクが低いというメリットがあります。
継続利用を選んだ場合の具体的な改善方法は、以下の通りです。
- 管理会社を切り替える
- 募集条件を緩和する
以下で一つずつ解説いたします。
1-1.改善方法1 管理会社を切り替える
コストがかからず、効果が発揮されるのも早いので、老朽化アパートを相続した人の間で最もよく実施されます。
実際これだけで収益が改善することもしばしばです。
検討の際には複数の管理会社からプランを提出してもらい、プランの具体性や対応の丁寧さなどを通して優良な管理会社を選ぶとよいでしょう。
1-2.改善方法2 募集条件を緩和する
緩和の対象は、「住む人」と「お金」の2つです。実行の際にはこれらを併せ、なるべく多くの要素を取り込みます。詳しくは以下の通りです。
- 住む人の要件緩和
-
入居する人が持てる選択肢を広げることを指します。
例:「ペット可能」「事務所利用可能」「ルームシェア可能」「単身高齢者可能」「DIY可能」「楽器可能」など。 - お金の要件緩和
-
主に入居に必要なお金を少なくすることを指し、その他支払方法を柔軟に設けるといった対策も含まれます。
例:「敷金・礼金なし」「更新料なし」「管理費・共益費込み」「駐車場代込み」「クレジットカード決済可」「フリーレント」など。
2.買い替え
買い替えは、「保有している物件を売却し、新たな不動産を購入する」方法を指します。
買い替えが向いているアパート・人は以下の通りです。
30年前とは周辺環境が変わり、同じエリアでアパート経営を続けるのは厳しいと思われる状況の人。
具体的には、周辺の人口が減ったり、競合アパートが多く建てられたり、といったことがあります。
10年後はさらに厳しい環境が予想されるエリアであれば、別のエリアへの買い替えがおすすめです。
継続利用を選んだ場合の具体的な改善方法は、以下の通りです。
●都市部の収益物件に買い替える
以下で詳しく解説いたします。
2-1.都心部の収益物件に買い替える
都心部の物件であれば空室リスクが低く、賃料も高めに設定できるため、有効な選択肢の一つです。
また、賃貸物件である以上、相続税の節税効果も見込めます。土地や建物に適用される評価減のルールは、都市部も地方と同じです。
2-2.買い替えの際に活用できる特例

買い替えの際に活用できる特例として、国が設けている「特定事業用資産の買換え特例」というものがあります。老朽化したアパートを売却したときに発生する税金を抑えてくれる特例です。
保有している物件を売却した際に多額の税金が発生してしまうと、売却に消極的になるため、売却時の税金を抑えることで買い替えをしやすくしています。
必要条件として、個人が事業用の土地や建物を譲渡した後、原則「譲渡した年、またはその前年、もしくは翌年に新たな事業用資産を取得」し、取得の日から1年以内に事業の用に供することがあります。
特定事業用資産の買換え特例では、適用するために譲渡資産と買換え資産の組合せが決まっています。
中でも一番活用しやすい組み合わせは、以下の組み合わせです。
【譲渡資産】
所有期間が10年を超える土地、建物
【買換え資産】
国内にある面積300㎡以上の土地等で、特定施設(福利厚生施設を除く、事務所、事業所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、住宅等)の敷地の用に供されているもの、および建物
10種類ある組み合わせの中で9番目の組み合わせであるため、通称「9号買換え」と呼ばれています。
老朽化アパートの所有期間が10年超であれば、譲渡資産としての要件を満たすため、譲渡資産の要件として緩いという理由から、よく使われます。
通常、個人が不動産を売却した際、譲渡所得が発生すると所得税が発生します。
譲渡所得の計算式
譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用
譲渡価額は、老朽化アパートを売却したときの価格。取得費は、老朽化アパートを取得した当初の価格です。
譲渡費用は売却に要した仲介手数料等の費用を指します。
譲渡した資産の譲渡価額が買換え資産の取得価格以下で、特定事業用資産の買換え特例を適用された時の譲渡所得の計算式
譲渡所得 =( 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用 ) × 課税割合
課税割合とは、買換え資産の場所によって以下のように定義されます。
| (1) 地方(東京23区及び首都圏近郊整備地帯等を除いた地域)から東京23区への買換え | 30% |
| (2) 地方(東京23区及び首都圏近郊整備地帯等を除いた地域)から首都圏近郊整備地帯等(東京23区を除く首都圏既成市街地、首都圏金庫整備地域、近畿圏既成都市区域、名古屋市の一部)への買換え | 25% |
| (3) 上記(1)及び(2)以外の買換え | 20% |
例えば、地方の老朽化アパートを東京23区内のワンルームマンションに買い替えたとします。この場合、課税割合は30%です。
譲渡所得は以下のように計算されます。
譲渡所得 = ( 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用 ) × 課税割合
= ( 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用 ) × 30%
特定事業用資産の買換え特例を使えば、譲渡所得が発生したとしても、所得税は通常の売却の30%で良いことになります。
譲渡した資産の譲渡価額が買換え資産の取得価格を超える時の譲渡所得の計算方法
(1) 課税される収入金額
= ( 譲渡した資産の譲渡価額 - 買換え資産の取得価格 ) + 買換え資産の取得価額 × 課税割合
(2)課税される収入金額に対応する取得費と譲渡費用
= ( 譲渡した資産の取得費+譲渡費用 ) × (1) の収入金額 ÷ 譲渡した資産の譲渡価額
課税譲渡所得
= 課税される収入金額 - 課税される収入金額に対応する取得費と譲渡費用
= (1) - (2)
ここでも「課税される収入金額」を計算する上で、課税割合が登場します。
ここで使う課税割合も、上述した譲渡資産と買換え資産の場所で決まる数値と同じです。
買い替えを検討するのであれば、特定事業用資産の買換え特例を上手く活用しながら買い替えをするのが良いでしょう。
老朽化したアパート「建て替える?」「改修する?」「更地にする?」
2-3.老朽化アパートを高く売却するポイント

老朽化アパートを高く売るには、2つの方法があります。
1つは入居者を埋める、もう1つは逆に入居者を空にすることです。
前者については老朽化している状況のアパートでは実施することが難しいため、後者の「入居者を空にする」という選択肢のほうが現実的でしょう。
老朽化したアパートでも、購入者がすぐに取り壊せるような状態であれば、高く売却することは可能です。
とはいえ、今いる入居者に立退きを要求する必要はありません。
代わりの方法として、現在入居している入居者の賃貸借契約を定期借家契約に切り替えておくという方法があります。
定期借家契約とは、契約期間満了時に更新できず、必ず退去しなければならない賃貸借契約です。
入居者の賃貸借契約が、全て定期借家に切り替わっていれば、買主は購入後、しばらくしたら建物を取り壊すことができます。
定期借家契約に切り替える際は、家賃を安くしてあげる等の交換条件も必要となります。
3.建て替え
建て替えが向いているアパート・人は以下の通りです。
入居者が数戸たらずで、かつ資金的に余力のある人
入居者の立退きや取壊しといったコストも発生しますが、買い替えに比べ、今の土地を守ることができるのが最大のメリットです。
建て替えは大規模な工事を必要としますので、慎重に事を運ぶ必要があります。その際に必要なこと、注意すべきことは以下の通りです。
- 建て替え後のプラン検討
- 資金計画
- 立ち退きの手順
- 取壊しの注意点
- 一棟貸しの注意点
以下で一つずつ解説いたします。
3-1.建て替え後のプラン検討
建て替えに着手する前に、建て替え後のプランをしっかりと検討することが重要 です。
建て替え後のプランが、投資採算性が合うのであれば、建て替えを実行できますし、投資採算性が合わなければ断念せざるを得ません。
30年以上前にアパートの建築を経験した人は、特に注意が必要です。
30年前の建築費と今の建築費では単価が大きく異なり、利回りも昔に比べて感覚的に低くなっています。
加えて、周辺の競合物件の状況も異なります。
建築費などのコストを最小化するためには複数のハウスメーカーを相見積もりするのがベスト です。
建て替えの場合、今のアパートの元施工のハウスメーカーに声をかけるオーナーの方もいらっしゃいますが経験や直感だけに頼らず、 改めて計画・検討することによって建て替え後のプランを考え、収益の最大化につながる収支計画を練ることが大切 です。
3-2.資金計画

建て替え後のプラン検討と同時に必要となるのは建て替えの資金計画です。
建て替えにおいては、今のアパートを取壊して更地にするまでにお金がかかります。
更地化するまでに必要な大きな支出は「立退料」と「建物取壊し費用」 です。これらは ローンを組むことはできないので、自己資金で対応する必要があります。
また、最近は新築工事のアパートローンを組む際も、頭金を求められることが多くなりました。
銀行が求めてくる頭金は、最低でも新築工事費の10%程度 です。
アパートの立退料と建物取壊し費用の目安は以下のようになります。
- 立退料の目安
-
一戸当たり高くても100万円弱 が相場です。
内訳としては、「引越代、新しい入居先の敷金・礼金+アルファ」となります。 - 取壊し費用の目安
-
解体工事費としては、
木造アパートなら坪4~5万円
鉄骨造のアパートなら坪6~7万円
が一つの目安です。
3-3.立退きの手順
今のアパートに入居者が残っていて、普通借家契約を締結している場合には、入居者の立退きが必要です。普通借家契約は「更新」のある契約のことを指し、アパートでは多くの場合、この契約形態になっています。
立退き交渉は、弁護士法により弁護士以外の第三者である、管理会社や不動産会社等へは立退きを依頼することができないため自分で行うか、弁護士に依頼するかのどちらかになります。
普通借家契約の立退きに関しては、借地借家法第28条にルールが規定されており、賃貸人(建物所有者)から契約を一方的に解除するには、正当事由と立ち退き料が必要です。
なお、立退料は法律上のルールとして定められていますが、金額については明確なルールがありません。あくまでも本人同士の話し合いによります。
そして借地借家法は借主を強く守る法律なので、借主がひどく抵抗すれば立退料は高くなり、反対にあっさりと立ち退きに応じれば、全く発生しない場合もあり得るのです。

立退きはできるだけ入居者が減った段階で着手するのが理想的です。戸数が10戸前後のアパートであれば、残り1~2戸程度になった段階から始めることを目安にしましょう。
立退きにあたっては、まず賃貸借契約書の見直しから行います。
更新拒絶や契約解除の規定がある場合には、その規定に従い書面にて申出をすることとし、解除規定がない場合には、通常は契約期間満了の半年前から更新拒絶通知を出すことになります。
その間に交渉の妥結をし、退去してもらう運びです。
なお、次の更新時期までの期間があまりにも長すぎる場合は、期間内解約の申入れをする手があります。
(期間内解約の場合も半年以上先に解約したい旨を書面にて通知します。)
立退きは、時間に余裕をもって行うことが重要です。
最低でも6ヶ月以上前に通知を行いましょう。
また、立退きには「正当事由」と呼ばれる正当な理由が必要です。
単純に「古くなったから建替えたい」という理由だけでは正当事由として認められず、「立退料」を合わせて支払うことで、はじめて確固たる正当事由になります。
もし立退きで揉めてしまったら、早めに弁護士に相談するようにして下さい。
裁判にしてしまうと非常に長期化するうえ、借地借家法は借手の立場を守る法律のため、裁判をすると賃貸人(建物オーナー)が不利になりやすいからです。
まずは裁判に持ち込まない形で解決するにはどうしたら良いかを相談することをお勧めします。
3-4.取壊しの注意点
取壊し工事は解体現場の施工条件によって、見積もりの金額がかなり異なります。
重機が入りにくい狭い土地や、頭上に架線が通っているため作業しにくいようなアパート等であれば、解体工事費は高くなります。
また工事現場に配置するガードマンの人数も解体工事費に影響します。狭い道路をクネクネと曲がった先にあるような現場であれば、ガードマンの人数が増えるため解体工事費が上がります。
新築工事業者と取壊し業者とは別ですが、管理の手間等を考えると、解体は新築工事業者へ発注することが一般的です。
新築工事業者に取壊しを依頼すると、新築工事業者のマージンが上乗せされますが、そのまま新築工事にスムーズに移行することができるというメリットもあります。
解体工事を安くするためには、新築工事業者に十分に相見積もりを取ってもらいましょう。
3-5.一棟貸しの注意点
建て替え後にアパートの運営を続けず、老人ホームや保育園等に一棟貸し(1つのテナントに建物を全て貸すような貸し方)をする場合の注意点について見ていきます。
賃貸借の予約契約は、建物を取り壊す前に締結しておくことが重要です。
取り壊しから建物竣工までには、1年近く時間が空きます。その間に相手の気持ちが変わって、最悪の場合アパートを取り壊したのちにテナントに逃げられる、といったことがないようにするために、取り壊し前に全ての契約条件を固め、予約契約に残しておく必要があるのです。
なお、契約時のポイントとして、竣工前に契約を解除された場合の違約条項を入れておくことがあります。竣工前にテナントの一方的な都合で契約が解除された場合には、建物オーナーが今まで発生した費用をテナントに請求できるようにしておきましょう。
また、予約契約の中には本契約と同じ賃料や賃貸借契約期間も記載しておきます。テナントが後から「賃料を下げてほしい」と要求してくるのを防ぐためです。
建物が竣工すれば、本契約を締結します。
一棟貸しでは「資産区分」と「修繕区分」をしっかりと決めておく必要があります。
資産区分は、建物オーナーとテナントのどちらの資産かという区分、修繕区分は、建物オーナーとテナントのどちらが修繕するかという区分です。
一棟貸しの場合、テナントが持ち込む内装工事部分や家具等を除くと、ほとんどが建物オーナーの資産になります。
しかしながら、建物はテナントが独占的に使用するため、日常的な小修繕はテナントに任せてしまった方が管理は楽です。
後で資産区分と修繕区分を混同してしまうことがないよう、ルールを明確にしておくことがポイントです。
アパート以外の活用方法については下記の記事が参考になるはずです。
4.アパートの老朽化問題に強い土地活用会社を選ぶためのポイント
アパートの老朽化対策には、継続利用や建て替えなど複数のオプションがあるので、専門的なノウハウを豊富に備えた土地活用会社のサポートを受けることをおすすめします。
以下、「安心して相談できる土地活用会社」を選ぶために必要不可欠なポイントについてお伝えしていきます。
4-1.土地活用会社の提示する「経営プラン」
出来上がった後の収益を左右する要素として「完成前・完成後の経営プラン」も非常に重要です。
各企業が提示しているランニングコストや収支計画には、意外なほど内容の差があります。複数のプランを比較し、「より具体的で現実性が高い計画」を掲げている会社を選びましょう。
4-2.得意とする土地活用のジャンル
土地活用会社にはそれぞれ得意な土地活用のジャンルがあり、会社によっては、「トランクルームの運営ならお任せください!」といったように、特定のジャンルの土地活用に特化した会社もあります。
初めて土地活用にチャレンジするのであれば、さまざまな選択肢の中から最も適した活用方法を選んでもらうためにも、特定のジャンルに特化した会社ではなく、いくつかのジャンルを取り扱っている会社に相談するのがベストかもしれません。
4-3.評判・口コミ
土地活用会社の評判や口コミについては、インターネットを活用することによって業者の立場から独立した中立な意見を拾うことができます。
特に近年では、通常のGoogle検索の他に、SNS上で情報を探すことによって「生のユーザーの声」を見つけやすくなっているので、ぜひご活用ください。
4-4.アパート老朽化の対策で実績のある会社
アパート老朽化の対策で実績・経験のある会社を選べば、「どんな立地・どんな活用法を適用すれば、収益・費用はどれぐらいとなるか」「どのようなリスクが生じうるか」というように、さまざまな観点から情報を提供してくれます。
専門家が提供してくれるこのような情報は、事業計画を立てる上で非常に役立ちます。
「成功・失敗した経験と実績」を豊富に備え、つつみ隠さず共有してくれる会社を選ぶと後悔する事もなくなるでしょう。
信頼できる専門家や土地活用会社を探すには「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」がおすすめです。以下のボタンから土地情報を入力すると、最大10社のハウスメーカーがあなたの土地に合った、建築費の見積もりや、経営プランを無料診断いたします。
ぜひご活用ください。
老朽化アパートの建て替え実績豊富な大手メーカー
アパート経営 基礎知識系記事一覧
- 【基礎から解説】アパート経営に必要な基礎知識一覧。検討すべき事項がすぐわかる!
- 【徹底解説】アパート経営で儲かるコツ、儲ける仕組みを大解剖
- 【徹底解説】アパート経営が儲からない理由と儲かるための10の方法
- 【事例集】アパート経営の失敗事例13種とその対策
- 【基礎から解説】アパート経営のリスク全13項目一覧&対応法
- 【徹底解説】アパート経営とマンション経営、16の違いを徹底比較
- 【徹底解説】アパート経営で老後の備え!大切な資産を活かすポイントとは
- アパート大家の主なお仕事内容8つ!管理を委託するメリット・デメリット
- アパート経営法人化のメリット・デメリットは? 相続税対策についても解説
- 土地なしからアパート経営は可能?始める方法・初期費用・条件を解説
- 土地ありで始めるアパート経営は有利!建築費用・自己資金・利回りとリスクを解説
- なぜ「アパート経営はするな」と言われる?成功に導くコツもあわせて解説
- 【徹底解説】アパート経営のメリット・デメリット!今後の動向変化と成功のポイントも解説
- アパート経営は地獄?起こりがちな失敗例7つと回避方法を徹底解説!
- 土地活用で賃貸経営!種類別メリット・デメリットや成功のポイントも解説
- アパート経営30年後に予想される10大リスクと出口戦略
- 【保存版】アパート経営を成功に導く9つの秘訣
関連キーワード
関連記事
-
【徹底解説】建蔽率とは?アパートを建てる前に知りたい建蔽率の基礎知識
- 2024.12.19
- アパート・マンション建築
- ノウハウ
-
【徹底解説】アパート建て替え費用の試算と収支計画の立て方を解説
- 2025.05.01
- アパート・マンション建築
- 費用
- 経営ノウハウ
-
30坪の土地活用アイデアおすすめ11選!収益性の高い方法は?
- 2025.01.24
- アパート・マンション建築