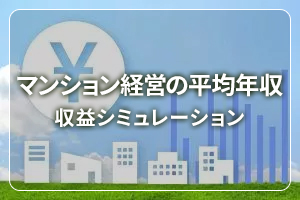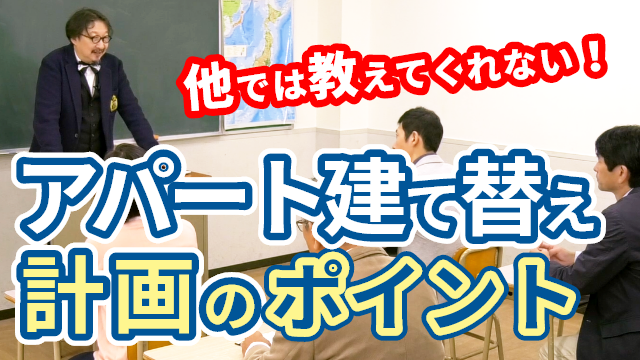【基礎から解説】土地活用の方法22選一覧|主要な活用方法を立地・目的別に網羅
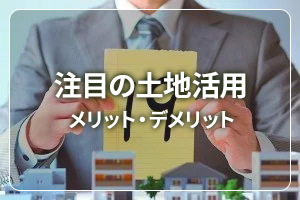
所有する土地を有効活用することで、効率的に収入を得ることができます。しかし、土地活用の種類は多種多様で、所有地にどの活用方法が合うのかを判断するのは難しいものです。
そこで本記事では、土地活用の方法22種類を網羅し、立地や目的で選びやすいカテゴリ分類をして解説します。
簡単に所有地に向いている土地活用方法を知りたい方は、以下のボタンから一括で土地活用プラン請求ができます。「どんな土地活用があるの?」「収益性はどのくらい?」など、専門家のアドバイスを受けることが可能です。
成功例の多い定番の土地活用方法は?
その他の土地活用方法の検討の仕方は?
以下の観点で、それぞれの土地活用方法について解説しています。
所有している土地の特徴や、収益の方向性にあわせて、ご検討してみてはいかがでしょうか。
目次
1. おすすめの土地活用方法22選一覧
土地を有効活用する方法はさまざまあり、目的や立地条件によって選択肢は異なります。まずは、数ある土地活用方法を目的別・立地別にまとめました。
| 土地活用方法 | 収益性 | 節税効果 | 初期費用 | 安定性 |
|---|---|---|---|---|
| アパート経営 | 〇 | ◎ | △ | ○ |
| マンション経営 | ◎ | 〇 | × | ○ |
| 賃貸併用住宅 | △ | 〇 | △ | ○ |
| 戸建て賃貸 | △ | 〇 | △ | ○ |
| 駐車場経営 | △ | △ | ◎ | ○ |
| 老人ホーム経営 | ○ | ○ | △ | ○ |
| トランクルーム | △ | △ | ○ | ○ |
| 事業用定期借地 | △ | × | ◎ | ○ |
| 太陽光発電 | △ | × | △ | ○ |
| 郊外型店舗 | ○ | × | ○ | × |
本記事ではそれぞれの土地の有効活用アイデアを向いている土地の特徴やメリット・デメリットで解剖します。目的別、立地別に分けて、まとめました。ポイントを押さえてわかりやすく紹介しますので、選択肢が見つかりやすくなるでしょう。
2. 主流の土地活用5選
数ある土地有効活用の方法の中でも、人気度の高く主流の土地活用をこちらで5つ解説します。
特に注目度の高い土地活用方法をベスト10でまとめた「土地活用ランキング」は、こちらの記事をご覧ください。
2-1.アパート経営
アパートは木造や軽量鉄骨といった構造で建築できるため、建築費が比較的安い傾向にあります。アパート経営の管理についても、管理委託や家賃保証のサブリース等のサービスが充実しているため、土地活用に知識が少ない人でも始めることができる土地活用方法です。
こうした特徴から参入障壁は低いため、競合が多い点はデメリットといえるでしょう。賃貸需要の弱いエリアでは無理に行わないという判断も必要です。
- こういう土地に向いている
-
- 生活利便性の高い立地
- 駅から徒歩10分圏内
- メリット
-
- 多くの用途地域で建築が可能
- デメリット
- 建築費用としてローンを組むため、負債を抱えるリスクが生じる
- 競合が多い
- 税金面の影響
-
- 固定資産税や相続税をはじめとした節税効果が大きい
2-2.マンション経営
賃貸マンション経営は、鉄筋コンクリート造のような建築コストの高い構造であることが多く、初期投資額が大きくなりがちです。しかし、建物自体は丈夫なため40年以上使えると考えてよいでしょう。
限られたエリアの広い土地と多額の借入金を必要とすることが多いため、参入障壁はとても高いのが特徴です。
裏を返せば、競合が少ないため、需要のあるエリアに建てれば以後、安定的な収益を期待できます。
ただし、空室リスクには注意が必要です。借入金の返済期間が長いため、空室が多くなっても簡単に取り壊すことができません。空室の発生しにくい立地の良いエリアで行うことが重要です。
- こういう土地に向いている
-
- 駅から徒歩10分圏内
- 100坪以上の広さがある
- 容積率が高い設定にある土地
- メリット
-
- 長期的な安定収入が期待できる
- デメリット
-
- 空室リスク・家賃下落リスクがある
- 多額の初期投資が必要
- 税金面の影響
-
- 固定資産税や相続税の節税効果がある
実績豊富な優良大手企業を厳選
2-3.戸建て賃貸
戸建て賃貸は、普通の家が建つ広ささえあれば可能で、用途規制の観点からもほとんどの土地で建てられます。
しかし、貸せる戸数が1戸だけのため、アパートに比べると空室リスクが高く、収益性は低めです。
一方で、競合が少ない上、ファミリー層は長期入居してくれる傾向が高く、そのまま購入につながるケースもあります。
「出口戦略」も考えられることは他の土地活用にはないメリットです。
- こういう土地に向いている
-
- 住宅街
- 学校や公的施設などが近い
- 生活利便性が高い立地
- メリット
-
- 賃貸として経営後、借主に物件を売却して手放すという選択も可能
- 広い土地の分割相続にも向いている
- デメリット
-
- アパート・マンションより収益性が劣る
- 税金面の影響
-
- 相続税と固定資産税の減税効果が高い
「戸建て賃貸について信頼のおける複数の企業の意見を聞いてみたい」というときに便利なのが、「HOME4U オーナーズ」の一括プラン請求サービスです。一度の請求で厳選された優良企業最大10社から戸建て賃貸経営プランを取り寄せられます。
2-4.賃貸併用住宅
賃貸併用住宅とは、自宅とアパートを一つの建物に併せ持つ住宅です。自宅とアパートを併用しているため、自宅だけでは広過ぎる土地に適しています。
土地の広さが200平米を超えている場合には、賃貸併用住宅として戸数を増やしたほうが土地の固定資産税は安くなります。これは、小規模宅地の特例を利用すると1戸当たり200平米までの土地評価額が6分の1になることを利用した節税効果です。
また、賃貸併用住宅は自宅の住宅ローンの一部をアパートの家賃収入で返済できるというメリットがあります。
- こういう土地に向いている
-
- 60坪以上の広さ
- 住宅街
- 駅徒歩10分圏内
- メリット
-
- マイホームを建設するためのローンを家賃収入で相殺できる
- 住宅ローンが利用できる
- デメリット
-
- 入居者トラブルに巻き込まれる可能性がある
- プライバシー確保が難しい
- 空室リスクが比較的高い
- 税金面の影響
-
- 相続税・固定資産税の節税効果が高い
賃貸併用住宅の間取りや建築費の比較検討は「HOME4U オーナーズ」を使えば、最大10社の企業から無料で建築プランが手に入ります。
2-5.駐車場
土地活用がなかなか決まらない場合には、とりあえず駐車場という手があります。土地活用としての駐車場経営は、初期投資もアスファルト舗装程度のためリスクも非常に低く始められます。
駐車場には、時間貸し駐車場(コインパーキング)と月極駐車場の2種類があります。立地が良ければ時間貸し駐車場の方が収益性は高くなります。
時間貸し駐車場は、駐車場事業者に相談することで開始できます。精算機やゲート板等の機材は全て駐車場会社の持込であることが一般的です。
- こういう土地に向いている
-
- 平面の土地
- 接道面が広くとれる土地
- 今後異なる土地活用をする可能性のある土地
- メリット
-
- 初期費用が低額で済む
- 他の用途に簡単に転用できる
- デメリット
-
- 収益性が低い
- 税金面の影響
-
- 固定資産税、都市計画税などの税制優遇が期待できない
駐車場経営の具体的な収益シミュレーションは、「HOME4U オーナーズ」を使えば、最大10社の専門企業から無料で収支プランが手に入ります。
3.収益性が高い土地活用方法3選
土地の有効活用において、活用法の収益性は重視すべきポイントです。ここでは特に高収益に期待できる土地活用方法を3つ紹介します。
3-1.シェアハウス
シェアハウスは、共同で生活するタイプの賃貸住宅です。
入居者にとっては家賃が安いという魅力があり、ワンルームマンションの家賃が高い東京では急速にシェアを拡大しています。
賃料設定が下がっても坪当たりの賃料単価は上がるため、利回りは通常の賃貸マンションよりも高くなりますが、シェアハウスは、少し郊外に離れてしまうと急速にそのニーズが減少してしまうことも特徴です。
また、管理委託費用は割高です。通常のアパートの管理委託費用が賃料の5%程度に対し、シェアハウスは7~9%程度になります。
- こういう土地に向いている
-
- 駅から徒歩10分圏内
- 単身者が多い都市部
- メリット
-
- アパートよりも多くの入居者を住まわせることができる
- アパートより空室リスクが低い
- テーマ性(「起業家のためのシェアハウス」や「国際交流ができるシェアハウス」など)を持たせることでアピールしやすい
- デメリット
-
- 入居者間のトラブルが起こりやすく、オーナー自身が介入しなければならない場合もある
- 税金面の影響
-
- 相続税・固定資産税の節税効果が高い
3-2.コンビニ店舗
コンビニは郊外の土地でも賃貸経営ができる商業系の希少な土地活用方法です。
コンビニ事業者に一棟貸しをします。賃料単価が高く、他の土地活用方法に比べても収益性は最も高いのが特徴です。
一棟貸しのため、管理も基本的には不要です。
郊外のコンビニは広い駐車場が求められるため、敷地も300~600坪程度を必要とします。郊外型のコンビニは、店舗面積は50~60坪程度が一般的です。
商業施設は、第一種低層住専用地域または第二種低層住専用地域と呼ばれる用途地域では建築できません。
コンビニは、立地さえ良ければコンビニ事業者からの出店オファーがあります。
場合によっては建設協力金と呼ばれる方式で、建築資金をコンビニ側が銀行よりも有利な条件で貸してくれることもあります。
ただし、コンビニは撤退の時期も早めです。周囲に競合店ができるとすぐに売上を落とし、撤退リスクは高まります。
- こういう土地に向いている
-
- 人通り、車通りの多い立地
- (都市部の場合)50坪程度の広さ
- (郊外の場合)300坪程度の広さ
- メリット
-
- 収益性が非常に高い
- デメリット
-
- 都市計画法などの規制により、出店できるエリアには制限がある
- 税金面の影響
-
- 商業系の建物にあたるため、税制面での優遇は受けられない
3-3.ビジネスホテル
ビジネスホテルは、ビジネスホテル事業者への一棟貸しをする土地活用です。ホテルが建築できる場所は、商業地等の一定の地域に限られます。
ビジネスホテルは敷地の広さも重視されます。客室は概ね200室程度を確保できないと、採算が合わないため、200室以上できるような広さの土地が求められます。
東京や京都では、ビジネスホテル用地は常に不足しており、激しい争奪戦が展開されます。新幹線が停車する駅もニーズがあります。
- こういう土地に向いている
-
- 商業地をはじめとした一等地
- ターミナル駅の近く
- 100坪以上の広さ
- メリット
-
- 軌道に乗れば、収益額は非常に大きい
- デメリット
-
- 相当な金額の投資が必要となる
- 限られたエリアでの宿泊客をめぐって厳しい競争にさらされる
- 競争力がないと競合に淘汰されるリスクが高い
- 税金面の影響
-
- 商業系の建物にあたるため、税制面での優遇は受けられない
4.お金のかからない土地活用方法2選
不動産投資である土地活用は、初期費用が高くなるイメージかもしれません。しかし、中にはお金のかからない土地活用方法もあります。初期投資を抑えられる活用法を2つ紹介します。
4-1.事業用定期借地
借地の中でも、契約期間満了時に確実に土地を返してもらえる借地を定期借地と言います。定期借地の中でも、資材置き場やビジネスホテルといった事業用の建物を建てるために借地するときに設定する借地権が事業用定期借地です。
事業用定期借地は、収益性はそれほど高くはありませんが、建物投資を行う必要なく地代収入が入ってくるため、リスクがとても低い土地活用です。
- こういう土地に向いている
-
- ある程度の広い土地
- 郊外でも可能な場合もある
- 都市部の場合、打診をもらえることも
- メリット
-
- 初期投資額がほとんどいらない
- 長期的に安定している
- デメリット
-
- 他の運用方法と比較して、期待できる収益の水準が低め
- 税金面の影響
-
- 初期投資額はほぼいらないが、固定資産税、都市計画税はかかる
4-2.トランクルーム
トランクルームは、区分した倉庫を建築して物置として貸し出す事業です。
現在はコンテナをそのまま置くだけでは「建築基準法違反」となるため、建築確認をしっかりとって建物として建築して貸し出すようになっています。
アパート等よりははるかに低い水準の初期投資額に抑えられることが特徴で、駐車場とアパートの間くらいにあるイメージです。
トランクルームは近年のマンションの増加によりニーズが高まっています。周囲にマンションが多いようなエリアではニーズが高い傾向です。また、トランクルームを建てられる用途地域には一定の制約があるため注意が必要です。
- こういう土地に向いている
-
- ある程度の広い土地
- 郊外でも可能な場合もある
- 都市部の場合、打診をもらえることも
- メリット
-
- 初期投資額がほとんどいらない
- 長期的に安定している
- デメリット
-
- 他の運用方法と比較して、期待できる収益の水準が低め
- 税金面の影響
-
- 相続税などの節税効果が低い
5.安定性の高い土地活用方法3選
本章では、「安定性の高い」土地活用を3つ紹介します。撤退リスクの少ない活用方法です。
5-1.保育園
保育園は建物を保育園事業者に一棟貸しします。
保育園は用途規制上、どこでも新築が可能です。ただし、国の補助金が出る認可保育園の場合、保育園が不足しているエリアでないと建築できない場合があります。
保育園は、一棟貸しであるため、管理の手間もほとんどかからず、認可保育園であれば撤退リスクも低いです。一般的な店舗よりは賃料単価は低いですが、収益の安定性という意味では抜群です。
- こういう土地に向いている
-
- 住宅街
- 駅にほど近い立地
- メリット
-
- 契約が決まれば、その後の管理はほぼ必要ない
- (認可保育園であれば)撤退リスクが低い
- デメリット
-
- 建物の修繕などを行うタイミングを図ることが難しい
- 税金面の影響
-
- 地域によっては、固定資産税や都市計画税が免税になる
5-2.老人ホーム・高齢者向け住宅
老人ホームなど介護福祉施設での土地活用は建物を老人ホーム運営事業者に一棟貸しします。老人ホームは用途規制上、どこでも建築することが可能です。ただし、敷地は300坪程度の広さが求められることもあります。
老人ホームも一棟貸しであるため、管理の手間もほとんどかからず、撤退リスクも基本的には低めです。ただし、事業者に退去されてしまうと、後継事業者が見つからない可能性もあるため、賃料の値下げ要求に対して弱い立場となります。
- こういう土地に向いている
-
- まとまった広さの土地
- 駅から遠くてもバス停から徒歩圏にある土地
- メリット
-
- (一定の条件付きで)固定資産税や不動産取得税の軽減措置を受けられる
- デメリット
-
- 施設の規模が大きいため、工事費用が大きい
- 他の老人介護施設との経営競争となり、経営を任せたサービス事業者が破綻・撤退する可能性がある
- 後から他の用途へ転用するのが難しい
- 税金面の影響
-
- 相続税・固定資産税の節税効果が高い
- 不動産取得税が最高1,200万円まで控除される(サービス付き高齢者向け住宅)
老人ホーム経営での土地活用について相談したいときは、以下のボタンから一括プラン請求できる「HOME4U オーナーズ」をご活用ください。
5-3.デイサービス
デイサービスは、通いで介護サービスや生活支援を受けるための施設で、用途規制はなく、どこでも建築が可能です。
60坪程度の敷地でも建築が可能です。建物も一戸建てのような雰囲気の物件もあります。
デイサービスでの土地活用はデイサービス事業者に建物を賃貸します。
老人ホームよりは撤退リスクは高い傾向であるものの、老人ホームやアパートにしては敷地が狭く、保育園の賃貸需要もないような場合は検討の余地があります。
- こういう土地に向いている
-
- 60坪程度の広さ
- アパートや保育園など、他の選択肢を選ぶのが難しい立地
- メリット
-
- 狭い土地でも取り組むことができ、建築場所の融通がきく
- デメリット
-
- 他の老人介護施設との経営競争となり、経営を任せたサービス事業者が破綻・撤退する可能性がある
- 税金面の影響
-
- 相続税・固定資産税の節税効果が高い
6.田舎・郊外向きの土地活用方法3選
相続などで得た田舎の土地は有効活用できないと思われがちですが、さまざまある活用方法の中には田舎の土地こそ、実行しやすい活用方法があります。
6-1.ロードサイド店舗
ロードサイド店舗は、郊外に大きな土地を保有している場合に適した活用方法です。基本的には一棟貸しであるため、管理の手間はほとんどかかりません。。
最近では郊外型の店舗は、食品スーパーやドラッグストアが併設した超大型の複合型店舗が増えてきました。こうした需要を満たすには、土地もかなりの広さが求められます。
投資額も大きく、また撤退リスクも高いことから、土地活用事業としてのリスクは相当に高めです。
- こういう土地に向いている
-
- 郊外で相当な広さがある
- 幹線道路沿い
- メリット
-
- 管理の手間が少ない
- 軌道に乗れば収益額は非常に大きい
- デメリット
-
- 投資金額が高額になるときがある
- 事業撤退などのリスクが大きい
- 税金面の影響
-
- 商業系の建物にあたるため、税制面での優遇は受けられない
6-2.倉庫
高速道路のインターチェンジに近いところに、広い土地を持っている場合は、倉庫の賃貸ニーズがあります。現在、インターネット通販が拡大していることから、倉庫の需要がとても高まっています。
倉庫は賃料も一定であり、基本的には一棟貸しのため管理の手間も省けます。
ただし、近年は求められる倉庫が大型化しており、個人向きの運用方法ではなくなってきています。
- こういう土地に向いている
-
- 高速道路のインターチェンジなどに近い
- 広い土地
- メリット
-
- 賃料が一定で、管理の手間も少ない
- デメリット
-
- 大型の敷地が必要となるため、個人での運用は難しい
- 税金面の影響
-
- 商業系の建物にあたるため、税制面での優遇は受けられない
6-3.太陽光発電
土地活用で検討するのは産業用太陽光発電です。
産業用太陽光発電は発電規模が10kW以上の施設を指し、土地活用での規模はおおよそ50kW以上となります。
収益が売電収入によるところからも土地活用につきものの空室リスク、撤退リスクと無縁であることは大きなメリットです。ただし、発電規模が大きくなれば初期費用も高額になるため、初期費用回収までには長期間の運用が求められます。
- こういう土地に向いている
-
- 周辺に建物がない
- 広大な土地
- 日当たりの良い土地
- メリット
-
- 売電収入で収益を得るため空室リスク・撤退リスクと無縁
- 少ない手間で管理ができる
- 固定価格買取制度を利用できる
- デメリット
-
- 大きな額の収益は期待できない
- 初期費用がそれなりにかかる
- 税金面の影響
-
- 税金面でのメリットはない(営農型太陽光発電を除く)
7.狭小地の土地活用3選
狭い土地ならではの土地活用方法3選を紹介します。
7-1.小規模テナント
人目に付く立地に小さな土地を所有しているなら、小規模テナントで活用する手があります。カウンタースペースのみで出店できるジューススタンドやチケットセンターなどに貸店舗として活用する方法です。
簡易的な建物を設ければ始められるため、初期費用も抑えられるでしょう。
- こういう土地に向いている
-
- 人通り、車通りの多い立地
- メリット
-
- プレハブ等なら初期投資は少なめ
- 戸建て賃貸に比べると初期費用は少なめ
- デメリット
-
- 他の運用方法と比較して、期待できる収益の水準が低め
- 税金面の影響
-
- 商業系の建物にあたるため、税制面での優遇は受けられない
7-2.バイクパーキング
駅前などであれば、バイク1台分からでも導入可能なため導入ハードルは低いことが特徴です。
初期費用は1台あたり3~5万円、屋根付きやコンテナタイプなら10万円程度が相場。月極パーキングなら、賃料は1台につき月1万円以上で設定します。
- こういう土地に向いている
-
- 都心の市街地
- メリット
-
- バイク不可のパーキングも多く、需要の高さが見込まれる
- 初期費用が低額で済む
- デメリット
-
- 収益性が低い
- 税金面の影響
-
- 固定資産税、都市計画税などの税制優遇が期待できない
7-3.自動販売機
自動販売機は、幅1メートル、奥行き70センチの最低限のスペースがあれば、はじめられる土地活用方法です。
マンションの前や、コインパーキングやコインランドリーの敷地内など他の土地活用方法と組み合わせることに向いています。
他活用方法と比べて収益性が低い点がデメリットです。
- こういう土地に向いている
-
- 人通り、車通りの多い立地
- メリット
-
- 他の土地活用方法との組み合わせに向いている
- 初期費用が低額で済む
- デメリット
-
- 収益性が低い
- 税金面の影響
-
- 税制面での優遇は受けられない
8.流行中の土地活用方法3選
資産運用の中でも長期安定性が特徴の土地活用であっても、時代の流れによって最適な活用方法のジャンルが広がったり、立地条件が変わったりします。ここではアフターコロナでも注目度の高い流行中の土地活用アイデアを紹介します。
8-1.コレクティブハウス
コレクティブハウスとは、スウェーデンやデンマークなど北欧で見られる賃貸形式です。
コレクティブハウスでは、建物を建てる前に入居者が居住者組合という組合を作ります。居住者組合のメンバーが話し合って、どういう賃貸物件にするかを決めていきます。
出来上がった後の建物はシェアハウスと似たものになりますが、シェアハウスが建物を建てた後に入居者を募集するのに対し、コレクティブハウスは先に入居者有りきで建物を建てることが一番の違いです。
土地所有者は、最終的に建物所有者になります。
居住者組合に事前に確保したい利回りを伝えておき、居住者組合が払える賃料から建築費が逆算されます。
- こういう土地に向いている
-
- 住宅街
- 学校や公的施設などが近い
- 生活利便性が高い立地
- メリット
-
- 入居者が建物の維持管理(掃除など)を自主的に行う「居住者組合」があるため、オーナーにとって維持管理の負担が少ない
- 入居者が他の入居者を呼び込む慣習があるため、空室対策になる
- デメリット
-
- オーナー自身が入居者を選べないケースが生じる
- 税金面の影響
-
- 税制面での優遇は受けられない
8-2.貸会議室・コワーキングスペース
中心市街地に土地を持っているような方にとっては、貸会議室やコワーキングスペースといった土地活用の方法もあります。
貸会議室とは時間貸しで会議室を貸す形態の賃貸です。コワーキングスペースとは、同じく時間貸しで働くスペースを提供する賃貸になります。
貸会議室運営事業者に貸す場合もありますが、自分で運営する場合もあります。貸会議室の中には、完全に無人化で営業している物件も多いため、自分で行うことも可能です。
現在、東京以外のエリアでは、オフィスの賃貸需要は軒並み縮小傾向にあり、貸会議室やコワーキングスペースの需要は増加傾向です。ただし、貸会議室やコワーキングスペースのデメリットは収入が不安定なことです。
- こういう土地に向いている
-
- 都市部・市街地
- 駅近
- オフィス街
- メリット
-
- 「無人オフィス」とすることで自動営業化も可能
- デメリット
-
- 継続利用の契約がない限り、収入が不安定
- 客が付くのに時間がかかる
- 税金面の影響
-
- 商業系の建物にあたるため、税制面での優遇は受けられない
8-3.コインランドリー
コインランドリーは、コインランドリー事業者に貸す場合と、自分でコインランドリー事業を行う場合の2種類があります。
無人営業も可能なため、自分で投資を行って営業できます。
ちょうどコンビニが抜けた後に適していますので、コンビニが抜けた後の対策として検討しておくのもよいかもしれません。
大きな布団、子どもの靴、ペットの衣服など、マンションでは干せないものや、洗濯しにくいもの等を洗うために、コインランドリーを使うケースが増えています。
昔のイメージのような銭湯の脇というのではなく、大型マンションの近くであれば高いニーズが見込めます。コインランドリー事業者に貸す場合は、通常の店舗と同じであるため、撤退も十分にあり得ます。
- こういう土地に向いている
-
- 15坪以上の広さ
- 住宅街
- メリット
-
- 運用にあたっての専門知識がほぼ不要
- 人件費がほぼかからない
- 固定客がつけば、安定的な売上が見込める
- デメリット
-
- 地域の治安状況によっては防犯上の配慮が必要となる
- 他の用途への転用が難しい
- 税金面の影響
-
- 商業系の建物にあたるため、税制面での優遇は受けられない
9.土地活用でよくある失敗例4つ
土地活用は不労収入との認識が多いものの、賃貸物件での経営にほかなりません。ここでは土地活用でよく問題となる失敗例を紹介します。あらかじめ把握しておくとリスク回避に役立ちます。
9-1.空室が増えてローン返済がままならない
土地の上に賃貸経営に利用する建物を建てる場合、初期投資として自己資金のほかに借り入れが必要になることがほとんどです。
せっかく建物を建てるからと容積率いっぱいの大きな物件を建てたり、収益性の高いワンルームタイプ住戸にこだわったりすると、ニーズが十分でない場合は空室が多く出てしまいます。
空室が増えれば、計画当初予定していた収益からの返済プランが崩れ、自己資金からの持ち出しとなります。
こうした事態を回避するには、エリアのニーズをしっかり把握することと借入額を大きくしすぎないことです。
9-2.節税効果の高いはずが逆に税金が上がった
せっかく節税のために建てた物件も、空き家が一定期間以上(近年は1か月以上)ある場合は貸家建付地評価額が上がるため、税金が上がってしまいます。
特に相続が発生した時期に空室の多い物件を相続すると、予定していたより多額の納税が必要になってしまった、ということになりかねません。
このことから、空室対策は不動産オーナーにとっての至上命題ともいえ、さまざまな施策を試みることになります。
9-3.自分の土地なのに自由に利用できなくなった
将来的に自分もしくは家族が土地を使いたいと思った時に、その土地で賃貸契約を結んでいると利用が制限されます。
特に住宅系の賃貸経営をしている場合は、借地借家法によって借主の権利が強く守られているため注意が必要です。
このようなリスクやデメリットを解消するためには、できるだけ難易度が低く、リスクの少ない方法を選択する必要があります。
9-4.建築費を抑えたら、逆に維持費がかかっている
アパート・マンションやテナントビルなどを建築しての土地活用では高額の初期費用を投じなければなりません。初期費用でも余計な出費を抑えることはその後の返済に備えても有効ですが、安さにばかりこだわると経営が失敗に陥ってしまうことがあります。
見るからに安物件になってしまうと物件が魅力的に見えず、借り手を見つけにくくなります。
また、建築費をあまりにも安く設定している企業は、アフターフォローの体制にまで行き届いていない可能性が高まります。そうなると、修繕が普通より多く必要になったり、修繕箇所が見つかっても適正な対応を受けられなかったりすることがあります。
儲かるアパートやマンションなどの建築プランは「HOME4U オーナーズ」を使えば、最大10社から無料で建築プランと建築費シミュレーションが手に入ります。
10.自分に合った土地活用方法の決め方
土地活用は、気に入った方法を自分の土地でできるとは限りません。
この章では、土地活用法を決める方法を説明します。土地活用を決める思考プロセスは「消去法」です。以下の要因から、選択肢を絞っていきます。
10-1.土地の用途規制で絞り込む

都市計画法によって、土地の用途には規制が存在しています。土地活用を検討する前に、その土地にどのような建築制限がかかっているかの確認が必要です。
一定規模の人口がいる市街地においては、どのエリアにどのような建物を建てることができるかというゾーニングが定められています。
このゾーニング規制を「用途地域」と呼んでいます。用途地域は住居系、商業系、工業系の3つに大きく分けられ、全部で13種類あります。
10-1-1.住居系用途地域の例1:第一種低層住居専用地域
- アパート
- 戸建賃貸
- 賃貸併用住宅
- 保育園
- 老人ホーム
- デイサービス
第一種低層住居専用地域は、良好な住環境を守るため厳しい建築制限が課せられています。
10-1-2.住居系用途地域の例2:第一種住居専用地域
- アパート
- 戸建賃貸
- 賃貸併用住宅
- 保育園
- 老人ホーム
- デイサービス
- 店舗
- ホテル・旅館
- 事務所
3,000平米以下であれば、店舗やホテル・旅館、事務所も建築できます。同じ住居系の用途地域でも第一種住居地域になると、さまざまな土地活用が選択可能です。
10-2.土地の広さや行政指導から決める

次に、実際にこれらの建物を建てられるかどうかについては、土地の広さが関係します。
50坪程度の敷地の場合、老人ホームのような大きな建物は選択肢から除外されますが、アパートは選択肢に残ります。
土地の広さ別の活用方法については、以下の記事でぴったりの活用方法を紹介しています。
- 狭小地の土地活用
- 20坪の土地活用
- 30坪の土地活用
- 40坪の土地活用
- 50坪の土地活用
- 60坪の土地活用
- 70坪の土地活用
- 80坪の土地活用
- 90坪の土地活用
- 100坪の土地活用
- 300坪の土地活用
また、土地の広さ以外にも、行政指導といった、選択肢を絞る要因があります。
例えば、保育園は行政がそのエリアにはすでに十分保育園があると判断しているエリアであれば、認可保育園は建てられません。
10-3.賃貸需要から決める

例えば、残った選択肢がアパートや戸建て賃貸だとします。
次に考えるべきは賃貸需要です。
駅から徒歩15分以上離れた立地であれば、単身者向けの狭小アパートは賃貸需要が弱く、リスクが高くなってしまいます。
一方で、徒歩15分以上離れていても近くに小学校がある場合、ファミリー層の賃貸需要がある可能性があります。アパートでは貸しにくくても、戸建て賃貸だと貸しやすいということであれば、最終的には戸建て賃貸を選択します。
賃貸事業は何十年も続く事業であるため、すぐに賃貸需要が枯れてしまうようであればリスクが高くなります。
土地活用の最大のリスクは空室リスクです。空室が増えると、賃料も下がり、リフォーム等の修繕費用や入居者募集費用などの費用も増加します。
賃貸需要をしっかりと把握した上で、土地活用を決めるようにするとよいでしょう。
10-4.自分の合った活用方法は土地活用会社に相談する
土地活用の重大な判断ミスを避けるためには、オーナー自身で情報を集めてある程度プランを練った上で、土地活用の専門家からも知見を集めることをおすすめします。
土地活用は長期に渡る運用を前提とする方法が多くあります。方法を選定する際、重要になってくるのは「経営プラン」の検討・比較です。
各メーカーが提示する収支計画やリスクマネジメントを比較しつつチェックすることによって「より具体的で現実性が高い計画」を掲げている会社を選ぶことが重要です。
実績を豊富に持つ企業であれば、リサーチ力も確かでより経営プランの正確性が増します。
「HOME4U オーナーズ」では、収益性までしっかり考えて提案をしてくれる土地活用に強い会社を選んで複数社紹介します。複数の土地活用会社の経営プランを一括請求することができますのでご活用ください。
土地活用の相談先については、こちらの記事でも解説しています。細かな注意点についても触れていますので、ぜひ参考にご一読ください。
土地活用関連記事、土地活用法系記事一覧
- 【基礎から解説】土地活用の方法22選一覧|主要な活用方法を立地・目的別に網羅
- 【徹底解説】23種類の地目・用途地域の調べ方と、対応する活用法
- 【プロが厳選】空き地の活用方法おすすめ10選!メリット・デメリットも解説
- 【40坪の土地活用】立地別おすすめ活用法13種類を徹底解説!
- 【徹底解説】東京の土地活用 立地別おすすめ活用法15種
- 【徹底解説】50坪の土地活用 立地・目的別おすすめ活用法13種
- 【徹底解説】大阪の土地活用 立地別おすすめ活用法15種
- 非公開: 【徹底解説】田舎の土地活用 山林・農地・宅地等、土地の種類別おすすめ活用法20種
- 【徹底解説】狭い土地の活用方法21選!狭小地のメリット・デメリット、注意点
- 【徹底解説】60坪の土地活用 立地・目的別おすすめ活用法15種
- 【徹底解説】100坪の土地活用 立地別おすすめ活用法10種
- プロに聞く土地活用の秘訣!成功する2割のオーナーが必ず行っていることとは?
- 不動産活用の方法おすすめ23種!資産の有効活用に役立つアイデア事例を解説
- 【徹底解説】300坪の土地活用方法を立地別に紹介
- 【基礎から解説】土地オーナー向け!利回りの高い土地活用法
- 非公開: 【土地活用の方法】成功するための土地活用の種類とアイデアを紹介
- 【徹底解説】短期の土地活用 立地別おすすめ活用法9種
- 20坪の土地活用アイデア16選!狭い土地でも利益を上げる活用法
- 遊休地の効果的な活用方法は?失敗しないためのコツも解説
- 【基礎から解説】田舎の土地活用で成功する方法|田舎の土地を収益化するアイデア
関連キーワード
関連記事
-
- 2025.01.22
- アパート・マンション建築
- 賃貸併用住宅
- 駐車場・駐輪場
- 戸建て賃貸住宅
-
-
- 2025.01.29
- ノウハウ