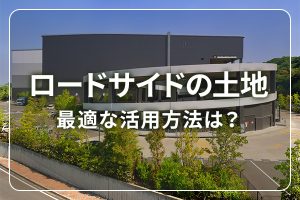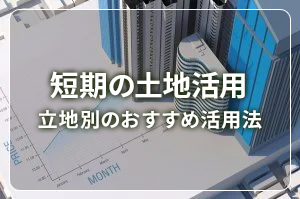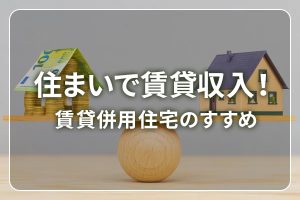「田舎の土地を相続したけど、どうすればよいかわからない」と悩む土地オーナーは案外多いものです。
特に田舎の土地は活用方法が難しく、広い発想での検討が求められます。
そこで本記事では、田舎の土地活用としておススメの方法とアイデアを紹介します。田舎というデメリットの対策方法や注意しておきたいポイントもわかる内容です。
また、最適な土地活用方法を直接プロに相談したい方は、以下のボタンから簡単に土地活用プランを入手できます。ぜひご利用ください。
田舎の土地を活用すると期待できるメリットは?
田舎の土地活用が難しい理由とは?
土地活用方法を選ぶ前に、自分の土地がそもそも活用できる土地かどうかを知ることが大切です。
田舎の土地活用が難しい理由としては、以下の3種類が挙げられます。
- 集客力がない
- 土地の用途規制にひっかかる
- 造成コストがかかる
それぞれの対策は「田舎の土地活用の3つのウイークポイントと対策」で紹介しています。
田舎に向いている土地活用方法は?
田舎の土地もさまざまです。一般的に以下のような活用方法が考えられます。
- 賃貸アパート経営
- 戸建て賃貸経営
- 老人ホーム
- 倉庫
- トランクルーム
- 駐車場
- 太陽光発電
- 産業廃棄物の中間処理施設
- 資材置き場
- キャンプ場
それぞれの詳しい解説は「【立地の特徴別】成功する田舎の土地活用10選」をお読みください。
田舎の土地活用の注意点は?
田舎で土地活用する場合に注意しておきたいポイントは3つです。
- ビジネスとして成り立つか検討する
- 複数の会社に土地活用を相談する
- お金のかからない方法を検討する
詳しくは「田舎の土地を活用する際の3つの注意点」で解説しています。
目次
1.田舎の土地を活用する3つのメリット
土地は所有しているだけで納税が必要なため、そのままにしていると毎年マイナスを生む資産です。
そんな土地もうまく活用することで収益性をつけることができ、土地にかかる固定資産税を収益から納めることも可能になります。
ここでは、田舎の土地を活用することで生まれるメリットを紹介します。
1-1.収益を得られるようになる
土地活用で最も収益性が高いのは、建物を建てて、それを人に貸すという方法です。
都会の土地活用では賃貸需要があるため、建物の賃貸で活用する方法を第一に検討します。
しかし、大半の田舎の土地では、アパートやテナントビルの需要は高いとはいえません。需要を見ながら、建物を建てる以外の土地活用も考える必要があります。
土地活用は多種多様です。中には集客力がない土地でも自力で収益を出せる土地活用もあります。
田舎でもなんらかのかたちで活用することで収益を得ることは可能です。
1-2.税金対策になることがある
不動産の所有と活用が税金対策に有効だと聞いたことがある方も多いでしょう。
相続税対策の場合、貸付地とすることで節税効果が期待できます。
これは、貸した土地の評価額に借地権割合をかけることで額を下げる効果があることを利用した節税方法です。さらに土地に貸家を建てると土地が貸家建てつけ地となり、節税効果は高まります。
また、土地の固定資産税でも活用での節税対策は可能です。
住宅用地の特例措置を活用するもので、課税標準額が1戸当たり200平米まで6分の1になります。アパート経営など賃貸住宅経営で需要が見込めるエリアであれば、固定資産税節税が可能です。
1-3.土地が荒れない
土地は放置すると雑草が生い茂って害虫を呼び込んだり、火災を引き起こしたりする恐れがあります。
土地活用は土地が荒れないための対策の一種です。例えば、アパート経営をすれば、管理会社が入るため土地も建物も定期的な手入れが入ります。資材置き場などとして土地を貸す場合でも借主の管理によって土地が良好な状態に保たれるでしょう。
また、田舎にある実家付き土地を相続した場合、実家が空き家になってしまうことがあります。空き家は放置しておくとかかる固定資産税が高くなる恐れがあり、注意が必要です。
これは「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づくものです。急速に増加している放置空き家の対策として、固定資産税の特例措置解除措置を進めています。
空き家も土地も放置しておくと、さまざまなトラブルの原因となりかねません。土地活用して管理をすることで、トラブル回避が可能です。
参考:政府広報オンライン|年々増え続ける空き家! 空き家にしないためのポイントは?
2.田舎の土地活用の3つのウイークポイントと対策
田舎の土地活用には以下の3つのウイークポイントがあります。
- 集客力がない
- 土地の用途規制にひっかかる
- 造成コストがかかる
それぞれのウイークポイントのパターンと対策を解説します。
2-1.集客力がない
田舎の土地は集客力、つまり賃貸需要が非常に限定的です。対象となる人口が少ないことから、アパート物件やロードサイド店舗などを建てても空室リスクがつきまといます。都会エリアでは収益力のある土地活用方法でも、田舎では収益力が弱い活用方法となりかねません。
2-1-1.対策
土地活用方法を検討するときにそのエリアの需要をしっかり調査することです。例えば、駐車場としてならば賃貸需要が見込める場合もあります。
また、活用しにくい土地であれば、売却や寄付、自用地としての活用を検討するのも手です。売却はある程度の売却益が見込め、毎年の固定資産税負担もなくなります。
2-2.土地の用途規制にひっかかる
田舎の土地は活用を検討する前に、自分の土地が何らかの法律の規制を受けていないかどうかの確認が必要です。
田舎では、農地や自然を守る法律が定められていることが多く、そもそも土地を活用できないという場合があります。
代表的なものが「市街化調整区域」です。市街化調整区域は開発を抑制している地域であり、新しく建物を建てることが原則できません。
また、建物を建てる、造成するとなると、許可が必要となることがあります。
田舎の土地を規制している法律は、以下のようなものです。
- 農地法
- 宅地造成等規制法
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
- 都市緑地法
- 地すべり等防止法
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
- 生産緑地法
- 森林法
- 自然公園法
2-2-1.対策
田舎では都会の土地にはかからないような法律が多いため、事前のチェックは欠かせません。
チェック後に建物が建てられないと判明した場合、土地活用としては駐車場や資材置き場など、使用貸借による活用を中心に検討します。
2-3.造成コストがかかる
放っておいた田舎の土地を活用しようとする場合、意外なところで立ちはだかるのが地形です。平地だと思っていた雑木林も、実は窪みや丘があり、利用するには造成をしなければならない地形だったということもあります。
土地の造成はコストが高く、融資がききにくいという性質を持っています。
一口に造成と言っても、整地だけのものや、伐採・抜根、地盤改良、切土、盛土等をしなければ使えないということもあるでしょう。全体的に傾斜地となっていれば、その分、工事費用もかさみます。造成費用は、平地に近いところで整地や伐採・抜根、地盤改良土等を行うと、坪4~5万円程度です。
また、宅地造成等規制法がかかっているエリアでは勝手に造成することはできません。
2-3-1.対策
造成が必要な土地の場合、自己資金を多めに用意しておく必要があります。
また、土地活用会社に造成込みで複数社見積もりをとるとよいでしょう。見積もりの比較では、造成費用を負担しても土地活用によって利益を出していけるかをしっかり検討します。
もし、造成費用の負担が大きい場合は、土地を買い替えるのも一つの手です。
所有地のポテンシャルを知りたい方は「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」をご活用ください。最適な方法について複数社から土地活用プランを手に入れられます。
3.【立地の特徴別】成功する田舎の土地活用10選
田舎の土地でも人に貸せるエリアもあれば、賃貸が難しいエリアも存在します。この章では立地の特徴に合ったおススメの土地活用を紹介します。
3-1.生活利便施設が近い立地
田舎でも駅から徒歩5分圏内だったり、学校などの生活利便施設が近い立地だったりすれば、土地に建物を建てて賃貸する土地活用が考えられます。具体的には以下のような方法です。
- 賃貸アパート経営
- 戸建て賃貸
- 老人ホーム
3-1-1.賃貸アパート経営
アパート経営は土地活用の王道ともいえる方法です。土地活用の中では収益性も高く、節税効果も期待できます。
駅から徒歩圏であったり、生活利便施設が近くにあったりといった立地でニーズが見込まれる土地活用方法です。
アパート経営の最大の敵は空室リスクです。田舎の土地では、ニーズがあってもいったん退去があると次の入居者がみつかるまで時間を要することもあります。どの程度の需要があるのかを調査したうえで、適度な規模での経営体制が望ましいでしょう。
3-1-2.戸建て賃貸経営
田舎の土地の中でも住宅街の一角に立地していれば戸建て賃貸経営を検討してもよいでしょう。アパートの立地よりも汎用性のある賃貸経営です。
戸建て賃貸は30坪程度の土地で十分始められます。広さがあれば、数棟建てて賃貸経営することも可能です。
田舎の立地の場合、バス便などは見込めないことがあります。そのため、戸建て賃貸に駐車スペースは必須です。
3-1-3.老人ホーム
老人ホームは多少交通の便が悪くとも、閑静な立地が好まれます。田舎の広い土地がある場合には検討したい土地活用方法です。
具体的には200坪程度の広さがあればよいでしょう。土地活用としては主に、建物を建てて、運営を介護事業者に委託する方法と、土地を介護事業者に事業用定期借地権で貸す方法があります。
老人ホームなどの土地活用をご検討中の方は「HOME4U オーナーズ」をご活用ください。最大10社から無料で経営プランが手に入ります。
3-2.車便のよい立地
田舎の土地には、広い道路が整備されていたり、高速インターチェンジ近くだったりして、車利用に便利な土地がたくさんあります。そうした立地であれば、以下のような土地活用が考えられます。
- 倉庫
- トランクルーム
- 駐車場
3-2-1.倉庫
高速道路のインターチェンジに近接する広い土地では、倉庫の需要がある場合もあります。
日本の物流は道路運送が多くを担っています。近年はネット通販の市場拡大もあって大規模倉庫の需要は高まっている傾向です。
大規模倉庫の場合、大型車が乗り入れできるだけの間口とスペースが必要です。前面道路があまり広くない場合は、小口の倉庫経営が向いています。
3-2-2.トランクルーム
トランクルーム経営は、住宅用に向かない土地でも成立しやすい土地活用として都会エリアでも人気が高まっています。
田舎の場合、都会のような個人向けの一間型のようなものではなく、大型のトランクルーム経営に需要を見いだせるかもしれません。ただし、以前よく見られたコンテナを設置しただけのものは現在できません。トランクルーム事業者のユニットを法律にのっとって設置する必要があります。
3-2-3.駐車場
田舎の土地での駐車場経営は月極駐車場としての活用が考えられます。事業所に一括して貸し出すなどの方法であれば、収入が安定的です。
平坦な土地、道路への出入りが楽な広い間口がとれる土地が向いています。整地が必要な場合、整地にかかる費用が借地料に見合うかどうかが問題となってきます。
田舎の場合、コインパーキング形式は稼働率が上がらず、向いていません。ただし、観光地に隣接する立地であれば高い収益が期待できます。
3-3.近隣に民家がない立地
田舎の土地の特徴を最大限に生かす活用法では、民家に隣接していないことが条件であるものも少なくありません。以下のような活用法があります。
- 太陽光発電
- 産業廃棄物の中間処理施設
- 資材置き場
- キャンプ場
3-3-1.太陽光発電
太陽光発電には住宅用と産業用があり、土地活用として運用するのは産業用太陽光発電です。土地に太陽光発電設備を設置し、設備で作った電気を売ることで収入を得ます。土地活用として事業を運用する場合、50kW以上の発電規模が望ましいでしょう。
野立てでパネルを設置する場合、反射光に注意が必要です。敷地の南側に建物があると光害をもたらす恐れがあります。
また、太陽光発電事業は長期運用で収益を得るタイプの投資のため、災害リスクが少ない平らな土地での活用がおススメです。
3-3-2.産業廃棄物の中間処理施設
民家などがない立地では産業廃棄物処理会社への借地というのも考えられます。産業廃棄物処理会社には、廃棄物を分別するための中間処理施設を作りたいというニーズがあります。しかし、中間処理施設は近隣の反対を受けると建築できないため、土地探しに苦労しているという会社が多いのが現状です。
中間処理施設は近隣に家が少ないような、田舎であればあるほど適した立地として望まれます。
3-3-3.資材置き場
資材置き場は、更地であれば初期投資が必要ない土地活用です。田舎の土地であっても、借り手がつけば長期的な安定収入が見込めます。
土地が変形地でも向いていますが、何にも使われていない土地では賃貸に出す前に整地が必要です。収益性は高くありませんが、管理の必要がなく、事業用定期借地権での契約であれば、一定期間収入を得られます。
3-3-4.キャンプ場
近年のアウトドアブームはキャンプ場の需要も高めています。自然環境を生かしながら収益を得られる方法で、田舎の活用方法として高い注目度の土地活用です。
経営方法は自営方式が一般的です。通常のキャンプ場のほか、オートキャンプ場、グランピング施設なども形態に含まれます。
キャンプ場経営には、旅館業の営業許可が必要です。また、食事を提供する施設にする場合には飲食店としての営業許可もとらなければなりません。
現在、地方都市の空き地に関しては、問題意識を持っている自治体も多く、行政が空き地の有効利用を後ろ盾している例も珍しくありません。
事例1:佐賀県佐賀市
市が中心となり「佐賀市街なか再生計画」を策定し、空き地に中古コンテナを用いた雑誌図書館を設置して有効活用を図るというような事例(わいわい!! コンテナ)も存在します。
事例2:千葉県柏市
市が土地所有者と土地活用したい市民団体等をマッチングさせるカシニワ制度を設けています。民間の商業ベースに乗らない賃貸需要も発見できるという意味では画期的な取り組みです。
また、近年では、地域資源を活かしながら地域課題の解決を「ビジネス」の手法で取り組むコミュニティビジネスというのが注目されています。コミュニティビジネスは、NPO法人や民間企業、市民団体が参画し、地域資源開発や街づくり、文化・スポーツ振興等によって、地域活性化を図ります。
例えば、地域で増加し続ける遊休農地をNPO法人が借り受け、観光農園として再生した成功例もあります。田舎の土地活用では、NPO法人が重要な借手の一人です。
4.田舎の土地が農地だった場合の対処法
田舎の土地が農地だった場合、基本的にそのままでは営農するしか活用方法はありません。しかし、営農は負担が大きく続けるのが難しいこともあるでしょう。ここでは農地だった場合に
- 農地ではなくして土地活用する
- 農地のまま土地活用する
の2つの方法を紹介します。
4-1.農地転用して土地活用する方法
土地は用途が決められており、23地目のうち田と畑に当たる農地では農地以外の利用はできない決まりです。農地法で農地減少を食い止める措置がとられています。農地としての使用をあきらめ、ほかの方法で使いたい場合は、農地転用の手続きをとらなければなりません。
農地転用は、農業委員会に農地転用許可を申請します。許可が下りたら、法務局で地目変更の手続きです。地目変更まで済んで初めて農地以外の土地活用が可能になります。
4-2.地目を変えないで活用する方法
地目を変えないで活用するなら、営農のスタイルを変えることで対応します。具体的には以下の3通りが考えられます。
- ソーラーシェアリング
- シェア畑
- 農地の貸付
ソーラーシェアリングとは、営農地に架台を設け、土地の上部に太陽光発電設備を設置することです。作物に影響のない程度に設置することで農業と太陽光発電が同時にでき、通常の営農にプラスの収益力をつけられます。
シェア畑は家庭菜園の分割貸しです。自治体に登録制を敷いているところもあるため確認しておくのがおススメです。
農地の貸付は、農業法人等に農地としての利用を条件に貸し付ける土地活用です。
5.田舎ならではの土地活用アイデア事例
田舎や都会に関わらず、土地は自分で活用するのが利益率の高い方法です。特に借手がつかないような田舎の土地の場合は自分で土地活用する方法を検討します。
ここでは、田舎の特性を生かせる土地活用のアイデアを紹介します。
5-1.地元の特産品を活用する
田舎ならではの土地活用の手法として、認知度やブランド力が高いものの力を借りるという比較的始めやすい方法があります。
例えば、地元の特産品の販売所として土地を利用します。農家の「直販所」のようなイメージです。
5-2.田舎ならではの魅力を活用する
都会に住みながらも田舎に魅力を感じている人向けに、田舎の生活が体験できるサービスを提供するという方向性もあります。
例えば、貸農園などはそのようなサービスの一例です。貸農園では、土地を小さく区画割し、数坪単位での貸し出しを行います。
ネットワークカメラを設置し、借主が作物の生育状況等が分かるようなサービスも効果的です。また、講師を招き、農業やガーデニング等の体験教室メニューを加えて付加価値を向上させるのもよいでしょう。
5-3.運営能力から考える
不動産は貸し出す空間を小さくしたり、貸し出し期間を細かく区切ったりすると、賃料単価が上がるという性質があります。1月単位で貸すワンルームマンションよりも、1日単位で貸すホテルの方が時間単価は高いのと同じ仕組みです。
例えば、「民泊」というホテル運営方法があります。
自分が運営まで関われる時間があるのであれば、民泊のような運営を伴う土地活用を考えてみるのもよいでしょう。
6.田舎の土地を活用する際の3つの注意点
田舎の土地は都会と異なる特徴に合わせた活用方法を選択することが多いため、検討時から注意しておきたいことが多くあります。ここでは、田舎の土地活用の特に注意したいポイントを3つ紹介します。
6-1.ビジネスとして成り立つか検討する
土地活用を行う際、事業計画を立てる必要があります。
まずは、その土地活用がきちんと収益を上げ続けられるかをしっかり見極めなければなりません。節税効果を期待して土地活用を始めても、収益を上げられなければ本末転倒です。事業計画はさまざまな要素を加味して実現可能なものを作成します。
田舎の土地活用で特に自営の手段をとる場合は、売上がしばらくゼロでも続けていくことのできるかが鍵です。当面、事業を継続できるだけの資金を持っておくと安心できるでしょう。
事業計画作成にアドバイスが欲しいときは「HOME4U オーナーズ」の活用がおススメです。最大10社から収支プランを含む土地活用プランが手に入れられます。
6-2.複数の会社に土地活用を相談する
土地活用はさまざまな種類があります。所有地にどの方法が最適かを見極めるには、複数の会社からプランを手に入れるのがおススメです。
土地活用の会社はそれぞれ得意分野があります。それぞれの得意分野のプランを利回りや運用計画の観点から比較することで最適プランが見極めやすくなります。
プランを手に入れるには「HOME4U オーナーズ」をご活用ください。さまざまなジャンルの土地活用会社が参画する一括プラン請求サービスです。必要事項を1度入力するだけで、最大10社から土地活用プランが手に入れられます。
6-3.お金のかからない方法を検討する
土地活用の方法には高額の初期費用を要するものも多くあります。初期費用を多くかけるのは、かけた費用を取り戻せる収益を得られるかがカギです。
田舎の土地の場合、一般的に収益性が高いといわれる賃貸住宅経営に向かない土地も多くあります。
また、放置し続けている土地には整地に費用がかかりすぎる懸念もあります。
土地活用のリスクを低くするには、借入をしないことです。
借入の返済が無ければ、事業を継続できる可能性が見違えるほど大きくなります。まずは自己資金で始められる土地活用ビジネスから挑戦するのが賢明です。
少ない資金で土地活用を始めたい方は、「お金のかからない土地活用」の記事もご覧ください。
7.田舎の土地活用を安心して相談できる土地活用会社を選ぶためのポイント
田舎の土地活用は田舎というだけで難易度が上がります。高い難易度に挑むには実績と経験のある専門家に相談することが大切です。
土地活用会社にはそれぞれ得意な土地活用のジャンルがあります。
初めて土地活用にチャレンジするのであれば、さまざまな選択肢の中から最も適した活用方法を選んでもらうためにも、特定のジャンルに特化した会社ではなく、いくつかのジャンルを取り扱っている会社に相談するのがベストです。
その中でも田舎の土地の活用で実績や経験のある会社を選べば、どんな立地にどんな活用法を適用すればいくら位儲かるか、リスクはどの程度か、しっかりした事業計画を立ててくれます。
この計画とずれがなければ、活用に失敗する事はありません。
「HOME4U オーナーズ」では、「田舎の土地活用」に強い土地活用会社を選んで複数ご紹介できます。
「HOME4U オーナーズ」は、情報サービス事業では業界最大手であるNTTデータのグループ会社「NTTデータ ウィズ」が運営している一括プラン請求サービスで、活用の種類別にプロである一流企業と多く提携しています。
ぜひ一度、「HOME4U オーナーズ」をご活用ください。
関連キーワード
関連記事
-
ロードサイドの土地活用は何がある?所有地に最適な活用法をみつけよう
- 2025.01.24
- その他活用
-
- 2025.01.29
- ノウハウ
-
【基礎から解説】マンション経営のメリット・デメリットと初期費用&始め方
- 2025.01.23
- アパート・マンション建築
- ノウハウ
- 費用
-
-
- 2025.01.24
- その他活用