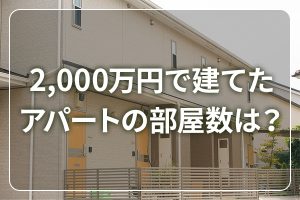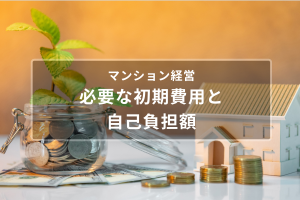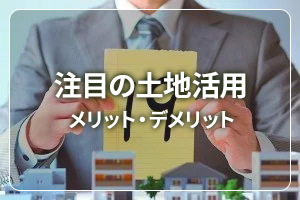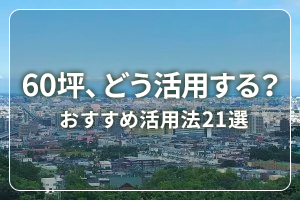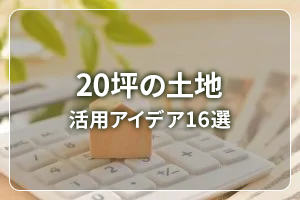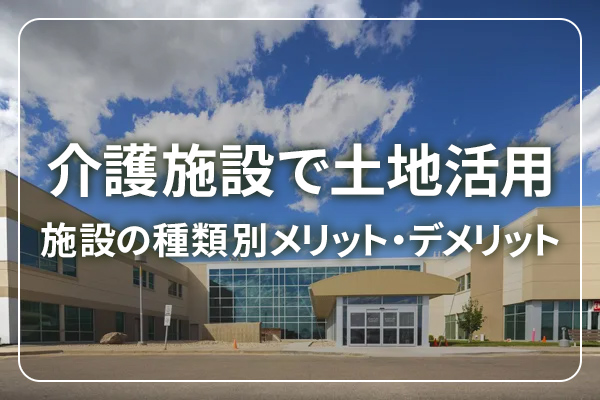
土地活用を検討する場合、地域の社会貢献にもなる介護福祉施設の経営を考えられている方もおられるでしょう。
しかし、実際にはさまざまな疑問や問題が生じることでしょう。
「所有の土地に介護福祉施設を建てたいけれど、どのような種類があるのだろうか?」
「超高齢社会で介護福祉施設は不足しているが地域での需要はあるのか?儲かるのか?」
「テナントとなる介護事業者はどのように見つければよいのか?」
この記事では、こうした土地オーナーに向けて、介護福祉施設の種類やメリット・デメリット、建築費用、収益シミュレーションなどをわかりやすく解説していきます。
また、「HOME4U オーナーズ」を利用すれば、最大10社の土地活用専門企業からあなたの土地に合った介護福祉施設の建築費の見積もりや収支計画を無料で一括請求できます。ぜひご活用ください。
介護施設で土地活用することに向いているのは?
介護施設で土地活用をすることに向いているのは、以下のような方です。
【介護施設で土地活用をすることに向いている方】
- 社会貢献、地域貢献につながる土地活用をしたい方
- 広い土地(20~30戸規模介護施設の場合、少なくとも200~300坪)をお持ちの方
- 郊外に大きな土地を持っていて活用に困っている方
- その他、所有地についてお悩みの方
介護施設で土地活用するメリットは?
介護施設で土地活用をすることには以下のようなメリットがあります。
【介護施設で土地活用をするメリット】
- 需要が大きい
- 社会貢献度が高い
- 立地を選ばない
- 補助金や税制の優遇がある
- 節税効果がある
介護施設で土地活用をするメリットについての詳しい解説は「土地活用で介護施設を経営するメリット」をご確認ください。
介護施設で土地活用をすることのデメリットは?
土地活用の手段として介護施設経営をするデメリットには以下が挙げられます。
【介護施設経営をするデメリット】
- 転用性が低い
- 初期費用が高額になる
- 運営事業者の選定が難しい
- 法改正や制度改正に経営が左右されやすい
デメリットに関する解説は「土地活用で介護施設を経営するデメリット」の中で詳しく触れています。
介護施設の土地活用の方法は?
介護施設での土地活用の手段としては2通りあります。
【介護施設での土地活用の手段2つ】
- 土地だけ貸す
- 建て貸しする
また、介護施設といっても公的な施設から民間施設までさまざまです。
どのような介護施設があるのか、住居系と居宅サービス系に分けて、施設ごとの特徴とメリット・デメリットについて説明していきます。
それぞれの方法のメリット・デメリットは「介護施設の種類とそれぞれの特徴」をご覧ください。
介護施設で土地活用を成功させるためのポイントは?
介護施設で土地活用を成功させるためには以下のようなポイントに注意が必要です。
【介護施設で土地活用を成功させるためのポイント】
- 土地の広さや立地に合わせて選択する
- 介護事業所を選ぶ上で重要なのは「人材」
- 自治体や介護事業所との打ち合わせは綿密に行う
成功へのポイントは「介護施設経営で成功するための重要ポイント3つ」で詳しく解説しています。
目次
1.土地活用で介護福祉施設を経営するメリット
土地のオーナーが介護福祉施設を建設することは、ほかの土地活用の方法とは異なるメリットがあります。
アパートやマンションなど賃貸経営とは違う介護福祉施設ならではメリットについてお伝えします。
- 需要が大きい
- 社会貢献度が高い
- 立地を選ばない
- 補助金や税制の優遇がある
- 節税効果がある
土地活用の手段として介護施設を建設してオーナーとなることには、ほかの活用法とは異なるさまざまなメリットがあります。
なぜアパートやマンションではなく、介護施設なのでしょうか。介護施設建設で土地活用をするメリットについてお伝えします。
1-1.需要が大きい
日本の65歳以上人口は、2021年(令和3年)9月15日時点の推計で総人口の29.1%となり、2042年にピークを迎えるまで、高齢者の増加傾向は続くといわれています。介護福祉施設の需要はさらに拡大し、長期的な安定経営が見込めるでしょう。
1-2.メリット2.社会貢献度が高い
社会的なニーズを満たすという意味で、介護福祉施設の経営は貢献度が非常に高く、オーナーの社会的信用にもつながります。
ニーズの高い土地活用をすることで、地域貢献にもなり、やりがいを感じることができるでしょう。
1-3.メリット3.立地を選ばない
アパートやマンションの経営が難しい郊外の土地を活用できるのも、介護福祉施設の経営の魅力の1つです。介護福祉施設の立地は、閑静な環境が好まれる傾向があります。
例えば、介護福祉施設は、主に戸建て住宅しか建てられない第一種低層住居専用地域でも建築が可能です。第一種低層住居専用地域では、店舗など事業系の土地活用ができないため、介護施設も選択肢として考えられるでしょう。
また、通常の住宅の建築許可が下りにくい市街化調整区域などでも許可が下りやすいということもメリットです。
1-4.メリット4.補助金や税制の優遇がある
介護福祉施設の不足解消のため、国や地方自治体が様々な優遇制度を設けています。介護福祉施設の種類にもよりますが、建築費の補助が受けられたり、各種の税制優遇が受けられたりするのも大きなメリットです。
ただし、介護福祉施設の数が増えるにしたがって、これらの補助金等の制度は縮小したり終了したりする可能性もあるので、これらの利用を考える場合には早めに検討することが必要です。
1-5.メリット5.節税効果がある
介護福祉施設の中でも、住居系の施設の場合には、固定資産税や相続税の節税効果が大きいのもメリットです。住宅の敷地は、建物が建っていない更地と比べて、固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1になります。
また、賃貸用の住宅の敷地の相続税評価額は、マイホーム等の敷地よりも約20%減額されます。
2.土地活用で介護施設を経営するデメリット
介護福祉施設の経営では、デメリットも把握しておかなければなりません。どのようなデメリットがあるか、確認しておきましょう。
- 転用性が低い
- 初期費用が高額になる
- 運営事業者の選定が難しい
- 法改正や制度改正に経営が左右されやすい
2-1.転用性が低い
テナントである介護事業所が万が一撤退してしまったら、次の借り手を見つけるのは非常に困難です。特殊な施設だけにほかの用途への転用も困難ですから、テナント契約はできるだけ長期で結ぶ必要があります。
また、オーナー側に「土地をほかの用途に使いたい」「土地を売却したい」という事情ができたとしても、地域に根付いた施設だけに解約は難しいでしょう。介護福祉施設の経営は、長期的に取り組む覚悟が必要です。
2-2.初期費用が高額になる
介護福祉施設は、国が定めたさまざまな要件を満たす建物にしなければなりません。そのため、住宅用賃貸物件に比べて坪単価も高くなりがちです。
初期費用の負担軽減には、リースバックや補助金などの制度を最大限に活用してください。くわしくは土地活用のプロから提案を受けることをおすすめします。
2-3.運営事業者の選定が難しい
未経験で介護福祉施設を経営することは、決して簡単なことではありません。
介護福祉施設の種類によっては、保有資格による人員配置が細かく定められています。また、介護保険制度や事業所経営に関する専門知識も必要です。
人材不足の介護業界において、何のツテもなくそれだけの有資格者と介護員を集めて雇用することは、かなりの困難を要します。そのため、土地活用の一環として介護福祉施設を建築するのであれば、運営は介護事業者に委託することを検討するとよいでしょう。
介護事業を委託する事業者を探すには、以下のような方法があります。
2-4.法改正や制度改正に経営が左右されやすい
法律や制度が変わることよって、運営のハードルが上がったり、オーナーの報酬が少なくなったりすることがあります。
代表例は、介護保険法の改正です。高齢者施設は介護事業所と提携しますが、その事業所がサービスの対価として国から受け取る「介護報酬」が減算されることがあります。
減算されると、介護事業所の収支に打撃となり、高齢者施設に提供する介護サービスの質が低下するおそれがあります。
平成27年4月の改定では、全体で2.27%の引下げとなり、同29年4月の臨時改定で1.14%引き上がっています。翌30年4月もプラス改定となりました。
介護報酬は上がることもあるのですが、下がることもあります。こうした変動リスクは高齢者施設の運営と常に隣り合わせになります。
参考:厚生労働省「介護報酬」
3.介護福祉施設経営の年収・収益は?収支シミュレーション
介護福祉施設の建築にかかる費用と賃料収入がどれくらいになるのか、土地活用に適した施設を例に挙げて見ていきましょう。
賃料はテナント(介護事業所)との協議により決定しますが、一般的な賃貸のように周辺相場を参考にすることは難しいため、ここでは期待利回りを10%として賃料設定します。
なお、介護福祉施設の種類については、「6.介護福祉施設の種類と特徴」で解説しています。
【介護施設経営の収支シミュレーション】
【グループホーム】
施設の規模:土地200坪/建物150坪
建物の建築費:約1億5,000万円
土地の評価額:約8,000万円
〈賃料〉
(1億5,000万円+8,000万円)×10%=2,300万円/年
2,300万円/12カ月=約190万円/月
【有料老人ホーム】
施設の規模:土地500坪/建物600坪
建物の建築費:約5億円
土地の評価額:約2億円
〈賃料〉
(5億円+2億円)×10%=7,000万円/年
7,000万円/12カ月=約580万円/月
【サ高住】
※30戸程度、デイサービス併設
施設の規模:土地400坪/建物400坪
建物の建築費:約3億5,000万円
土地の評価額:約1億6,000万円
〈賃料〉
(3億5,000万円+1億6,000万円)×10%=5,100万円/年
5,100万円/12カ月=約425万円/月
【通所介護事業所】
施設の規模:土地200坪/建物90坪
建物の建築費:約8,000万円
土地の評価額:約8,000万円
〈賃料〉
(8,000万円+8,000万円)×10%=1,600万円/年
1,600万円/12カ月=約130万円/月
上記の賃料に、必要諸経費分を加えた額とすることができます。
ただし、実際には介護事業所の収支計画に照らし合わせて設定するため、利回りは10%より下がる場合もあると考えておいてください。
また、リースバック方式の場合はここから建設協力金を相殺します。リースバックなどの経営方式については、次章で詳しく解説します。
4.土地活用での介護福祉施設の経営方式
介護福祉施設の経営方式には、以下の方法があることも押さえておきましょう。
- 事業用定期借地方式
- リースバック方式
- 自分で建てて貸し出す
4-1.事業用定期借地方式
事業用定期借地方式とは、事業用定期借地権を利用して介護事業者に土地を丸ごと貸し出す方法です。
いわゆる「土地だけ貸す」方式で、土地のオーナーは賃料として地代を受け取る形となり、初期費用がかからないため、低リスクで土地を活用できます。
契約期間は、10年以上30年未満、もしくは30年以上50年未満のどちらかの設定となります。
4-2.事業用定期借地方式
リースバック方式は、テナント(介護事業所)から建設協力金を預かる方式です。土地のオーナーは受け取った資金で建物を建て、それを事業者に賃貸し、土地・建物の賃料が毎月支払われます。
オーナーが預かった建設協力金は「保証金」という名目になり、毎月の賃料と相殺される形で事業者に返済されていく仕組みです。
介護福祉施設の建築では高額な初期費用が必要ですが、その負担を抑えることができ、土地と建物分の賃料でより大きな収益が見込めます。
リースバック方式については、以下の記事もご参照ください。
4-3.事業用定期借地方式
オーナーが所有地に建てた介護福祉施設の建築費用を自分で負担し、利用したい介護事業者が一括で借り上げる方法もあります。オーナーは賃料を高めに設定しやすく、収益性が期待できます。
また、建築費用の借り入れの利息や減価償却費を経費に計上できるため、所得税の節税対策にもなります。
ただし、介護福祉施設の建築には高額な初期費用がかかる点に注意が必要です。リスクが大きいため、一般的には事業用定期借地方式かリースバック方式で始めることが多いようです。
5.介護事業者を探す方法
介護福祉施設を経営するには、優良な介護事業者を見つけることが大切です。
以下に3パターンの探し方をご紹介します。参考にしてみてください。
5-1.都市部の場合
介護施設は種類ごとに用途が異なります。
介護福祉施設の土地活用をサポートするハウスメーカーやゼネコン不動産会社、コンサルティング会社に仲介を依頼する方法です。
ただし、介護事業所は経営の安定した大手であれば安心ですが、必ずしもオーナーの意向を反映できるとは限りません。
そこでチェックすべきなのは「人材」です。良い経営者のもとには良いスタッフが集まります。介護事業所の運営は「人材」あってのことなので、同業他社にリサーチするなど慎重に検討すると良いでしょう。
5-2.地方の場合
介護事業者は、企業の規模や経験・実績など、多角的に判断する必要があります。
しかし、地方の場合は情報が少ないことがあります。そこで、手広く全国で事業展開している企業に地元の介護事業所に直接コンタクトをとってみるのも1つの方法です。
また、地域密着型の小規模な事業者の中には、ほかの大手事業所で評判の良かった人が独立して介護事業所を立ち上げているケースも少なくありません。
その場合、他社のケアマネージャーとの関係もできているため、必然的に利用者も増えていきます。地域での評判などをリサーチしてみると良いでしょう。
5-3.その他(自治体で相談する)
自治体の福祉関連課へ直接出向き、相談する方法もあります(介護福祉施設の経営を行う事業者は、ケアマネージャー(介護支援専門員)や自治体との連携が必要です)。
介護福祉施設は種類もさまざまで、それぞれに必要な設備に関する基準があります。基準に該当するかどうか、建築確認に先だって自治体の関係部局への事前協議が必要となるため、計画は慎重に行ってください。
建て貸しの場合は、テナントとなる介護事業所との綿密な打ち合わせも必要です。将来的にトラブルになることのないよう、賃貸借契約書は専門家に相談の上、双方にとって納得のいくものを作成してください。
6.介護福祉施設の種類と特徴
介護施設といっても公的な施設から民間施設までさまざまで、種類や提供するサービスの内容も多岐にわたります。
どのような介護施設があるのか、住居系と居宅サービス系に分けて、施設ごとの特徴とメリット・デメリットについて説明していきます。
6-1.住居系の介護施設
まずは、老人ホームや高齢者向け住宅など、住居系の介護施設を紹介します。まずは、各施設の特徴をまとめてみました。
| 施設種類 | 特徴 |
|---|---|
| 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
•医療費控除が受けられるサービスが多いため費用が安い •長期入所が可能 •入所できるまでに数年を要する場合が多い |
| 介護老人保健施設 (老健) |
•在宅復帰を目的として入所できる施設 •機能訓練の設備が充実しており、医療ケアが手厚い •自宅生活が可能と判断されると退所となる |
| 経費老人ホーム (ケアハウス) |
•住宅型の有料老人ホームと比較すると費用が安い •個室または少人数居室なのでプライバシーを守りやすい •「自立型」は介護度が上がると退所を求められる •「介護型」は待機期間が長い |
| 有料老人ホーム |
•比較的自由が高い •介護度に合わせて援助を受けることも可能 •公共型の施設に比べると費用は割高 |
| グループホーム | •1ユニットの入所者制限があり、少人数制 •日常生活や訓練を通して、認知症の進行を緩和できる •認知症状が進行すると退所しなければならないことがある •待機期間が長い |
| サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) |
•共同生活の負担がなくマイペースに生活できる •サービス付きとは、主に「見守り」を指す •生活援助や介護サービスを提供していない場合、外部の介護事業所と契約する必要がある |
6-1-1.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
要介護3以上の在宅での生活が困難な高齢者に対し、生活援助や介護サービスを提供する施設です。施設の主な特徴は以下のとおりです。
【介護老人福祉施設の主な特徴】
- 利用サービスの多くで医療費控除が受けられるため費用が安い
- 長期入所が可能
- 待機人数が多く、入所できるまでに数年を要する場合が多い
高齢者がひとりで出歩くことのない特養は、比較的利便性を問わない施設です。郊外で活用に困っている土地でも候補となるのがメリットと言えるでしょう。その一方で、さまざまな設備やスタッフのための空間が必要となるため、ある程度の土地の広さが必要となります。
また、公的施設のため、自治体や社会福祉法人との連携は必須となることも考えておく必要があるでしょう。
6-1-2.介護老人保健施設(老健)
介護老人保健施設(老健)は、要介護者であり、在宅復帰を目指す高齢者に対して、リハビリや医療・介護サービスを提供する施設です。
老健の特徴としては、以下の内容が挙げられます。
【介護老人保健施設(老健)の特徴】
- ほかの介護施設に比べて機能訓練の設備が充実しており、医療ケアが手厚い
- 自宅生活が可能と判断されると退所となる
老健は特養と同じく公的施設となり、自己負担額が少ないため人気の施設です。また、自治体や社会福祉法人との連携が必要となる点も特養と同様です。
6-1-3.軽費老人ホーム(ケアハウス)
可能な限り自立した日常を送れるよう、生活援助や介護などのサービスを提供する施設です。
施設の特徴は以下のとおりです。
【軽費老人ホーム(ケアハウス)の特徴】
- 住宅型の有料老人ホームと比較すると費用が安い
- 個室または少人数居室なのでプライバシーを守りやすい
- 「自立型」は介護度が上がると退所を求められ、「介護型」は待機期間が長い
6-1-4.有料老人ホーム
有料老人ホームは、生活援助のある高齢者向け住居施設です。「介護付き」なら介護サービスも受けることが可能です。
施設の主な特徴は以下のとおりです。
【有料老人ホームの特徴】
- 比較的自由に生活しつつ、介護度に合わせて援助を受けることも可能
- 公共型の施設に比べると費用は割高になり、入居一時金の負担が大きい
6-1-5.グループホーム
グループホームは、スタッフのサポートを受けながら入居者が共同生活を送る施設。認知症の診断を受けた高齢者や、障害を持つ方々を対象にしたものがあります。
主な特徴は以下のとおりです。
【グループホームの特徴】
- 少人数制なので落ち着いた生活ができる
- 日常生活や訓練を通して、認知症の進行を緩和できる。ただし症状が進行すると退所しなければならないことがある
- 待機期間が長い
グループホームは社会的な需要が高く、供給が追い付いていない面があるため、長期的な需要が見込めます。また、小規模から運営でき、設備も少なく済むため、介護施設ほどの土地の広さが必要ないこともメリットと考えられるでしょう。
6-1-6.サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
見守りや生活相談などのサービスを提供する、自立した生活が可能な高齢者向け住宅のことです。施設の特徴は以下のとおりです。
【サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の特徴】
- 施設ではなく住宅なので、共同生活の負担がなくマイペースに生活できる
- 生活援助や介護サービスは義務付けられていないので、外部の介護事業所と契約する必要がある
サ高住は建築費や税金の優遇措置があり、比較的参入しやすい形態として知られています。その一方で、競合となる施設が近くにできるリスクがある点はデメリットと言えるでしょう。
6-2.居宅サービス系の介護施設
次に、高齢者が在宅で自立した生活を送ることができることを目的とした、居宅サービス系の介護施設の紹介です。以下にそれぞれの施設の特徴をまとめました。
| 施設種類 | 特徴 |
|---|---|
| 訪問介護事業所 (ホームヘルパーサービス) |
•介護生活を援助するホームヘルパーを派遣する事業所 •住み慣れた自宅で受けられる介護サービスを提供 •介護員が訪問している間にしか支援を受けることができず、訪問が負担になることもある |
| 通所介護事業所(デイサービス) 通所リハビリステーション事業所(デイケア) |
•外部との交流により、高齢者の孤立感が解消される •機能訓練や理容サービスなど、サービス内容が事業所によって異なる •事業所の送迎車で送迎がある |
| 短期入所生活介護事業所 (ショートステイ) |
•週単位の短期入所が前提 •長期的なホームの入所の準備にもなる •一時的な環境の変化に高齢者がストレスを感じることがある |
| 小規模多機能型居宅介護 |
•介護にかかるすべてのサービスが同じ施設、スタッフにより提供される •ケアマネージャーとの契約を解除する必要があるケースがある |
6-2-1.訪問介護事業所(ホームヘルプ)
介護員が自宅を訪問して生活援助・介護などのサービスを提供する事業所です。訪問看護、訪問入浴などのサービスを提供することもあります。
特徴は以下のとおりです。
【訪問介護事業所(ホームヘルプ)の特徴】
- 住み慣れた自宅で介護サービスを受けることができ、介護員がちょっとした話し相手にもなる
- 介護員が訪問している間にしか支援を受けることができず、訪問が負担になることもある
6-2-2.通所施設(デイサービス・デイケア)
日帰りで施設を訪れる高齢者に対し、生活援助や機能訓練などのサービスを提供する施設です。デイケアでは運動機能向上のためのリハビリメニューも提供します。
施設としての特徴は以下のとおりです。
【通所介護事業所(デイサービス)、通所リハビリステーション事業所(デイケア)の特徴】
- 外部との交流により、高齢者の孤立感が解消される
- 外出したくない高齢者にとっては、かえってストレスになることがある
6-2-3.短期入所生活介護事業所(ショートステイ)
要支援、要介護認定者が対象となり、短期間介護施設に入所することで、その間の生活援助サービスを提供する事業所です。
施設の特徴は以下のとおりです。
【短期入所生活介護事業所(ショートステイ)の特徴】
- 施設に慣れておくことで、介護度が上がって長期入所することになっても、抵抗感が低い
- 一時的な環境の変化に高齢者がストレスを感じることがある
6-2-4.小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、短期入所や訪問介護などのメニューを組み合わせた生活援助・介護サービスを提供する施設です。
施設の特徴は以下のとおりです。
【小規模多機能型居宅介護の特徴】
- すべてのサービスが同じ施設、スタッフにより提供されるので、安心感がある
- よい関係を築いていたケアマネージャーがいても、こちらの契約と同時に変更しなければならない
7.土地活用で介護福祉施設を経営する際の注意点
建築物を建てる際は、建築基準法で定められた用途地域の制限に従って、建築可能な建物であるかどうかを判断します。
確認が必要なポイントを以下に解説します。
7-1.用途地域を確認する
介護施設は種類ごとに用途が異なります。
- 特養(特別養護老人ホーム)や軽費老人ホームなどは「老人福祉施設」に該当し、工業専用地域以外どこにでも建築することができます。
- 訪問介護事業所はもともと事務所に区分されていましたが、2015年(平成27年)建築基準法において「老人福祉センターその他これに類するもの」として取り扱えることが明確化されました。これによって、訪問介護事業所は住居系地域を含むすべての地域に建築可能となりました。
- サ高住については、建物ごとの仕様や利用状況を踏まえて「共同住宅」「老人ホーム」「寄宿舎」のいずれかに分類されます。
最終的には特定行政庁の判断となるため、自己判断せずに所有地のある自治体へ確認してください。
建築可能な土地か調べるために必要な「用途地域」についての解説はこちら
7-2.総量規制を把握する
介護施設の中には、都道府県や市区町村が建設を制限しているものがあり、この制限を「総量規制」といいます。総量規制の対象となる介護施設は、自治体が募集しているタイミングで応募して選ばれなければ建設することができません。
総量規制があるのは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護付き有料老人ホーム、小規模デイサービス、グループホームなどです。
募集の頻度や条件については、地方自治体によって判断が分かれています。自治体が総量規制を行う理由は、経営悪化による施設の撤退を防ぐためと、自治体が負担する介護報酬の増加を制限するためです。
総量規制のある施設は、自由に建築できないのでハードルが高く、デメリットと思われがちです。でも逆にいえば、ライバルの増加が制限されており、経営が安定するので高めの賃料が設定しやすいメリットでもあります。
7-3.建築基準条件を満たしているか確認する
高齢者施設には建築基準条件があります。
例えばサ高住を建てる場合、賃貸マンションより広めの敷地面積が求められます。
理由は、
- 車椅子で移動できるだけの広さを確保しなければならない
- 各部屋に水洗便所や浴室、収納スペースを取付けた上で、床面積25㎡以上が必要
- 浴槽の深さ、出入り口の幅、廊下の幅まで細かく最低限の広さの確保が求められる
といった内容になります。
自身の土地でそれを満たせるかどうか、専門会社に見極めてもらいましょう。
7-4.土地の広さや立地に合わせて選択する
比較的立地を選ばない介護施設ですが、住居系施設か居宅サービス系の施設かによって、好ましい立地は異なります。
例えば、在宅での生活を基本とする自立した高齢者と、介護度の高い高齢者とでは行動範囲が大きく異なります。高齢者がひとりで出歩くことのない特養やグループホームとは異なり、サ高住などは基本的にアパートやマンションと同じ位置付けなので、ある程度の利便性も必要です。
土地の広さによっても建てられる施設、建てられない施設があるため、介護施設は土地の広さや立地条件などから、総合的に判断して選択してください。
8.土地活用での介護福祉施設経営はまず専門家に相談
このように、介護福祉施設のプランニングは定められた基準に従って行う必要があり、またテナントとなる介護事業所の選定などもあって、大変複雑です。
介護福祉施設での土地活用が難しい場合は、他の有効な土地活用の方法を検討してみることもおすすめします。
また、介護福祉施設の経営を決めたなら、できるだけ早い段階で介護事業者や経験実績の豊富な土地活用のプロに相談し、計画を進めていくとよいでしょう。
「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」では、所有する土地の情報と介護施設を希望する旨を入力するだけで、最適な企業をマッチングします。介護施設で収益を最大化するための建築・経営プランを最大10社まで選択し、無料で一括請求できます。ぜひご利用ください。
関連キーワード
関連記事
-
【徹底解説】アパート建築費2,000万円で建つ規模と利回りシミュレーション
- 2025.01.23
- アパート・マンション建築
- 利回り
-
- 2025.01.23
- アパート・マンション建築
- 費用
-
- 2025.01.30
- アパート・マンション建築
-
20坪の土地活用アイデア16選!狭い土地でも利益を上げる活用法
- 2025.01.23
- ノウハウ