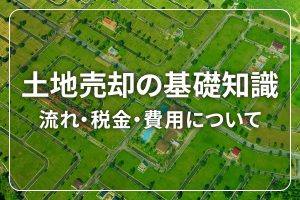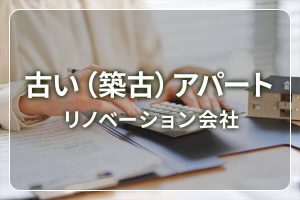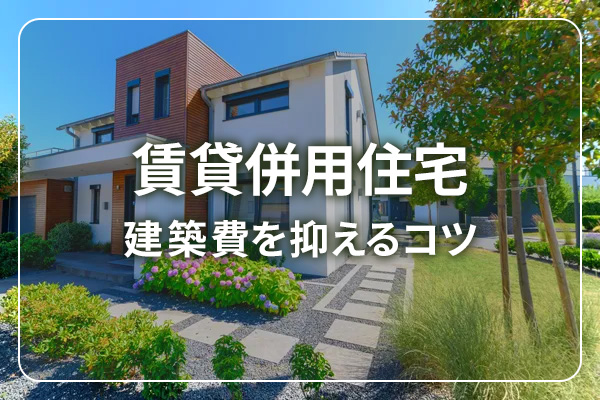
賃貸併用住宅は自宅でありながら収益物件でもあります。建築費借入の返済に家賃収入を充てることが可能です。
賃貸併用住宅の建築費は戸建て住宅よりも高額になるのが一般的です。「家賃でローンを返済したいけれど、高額の建築費に不安がある」という方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では賃貸併用住宅の建築費について、費用項目の詳細から建築費を安く抑えるコツを分かりやすく解説します。
また、以下のボタンから土地情報を入力すると、最大10社のハウスメーカーがあなたの土地に合った、建築費の見積もりや、収支計画を無料診断いたします。
「うちの土地にはいくらで賃貸併用住宅が建つの?」「いくら稼げるのか知りたい」という方はご活用ください。
賃貸併用住宅の建築費はいくらかかる?
賃貸併用住宅の建築費用は「延床面積×坪単価」の計算式で算出できます。坪単価は建築構造で異なり、構造別の坪単価の相場は以下の通りです。
- 木造:77~110万円
- 軽量鉄骨造:80~120万円
- 重量鉄骨造:90~130万円
- 鉄筋コンクリート造:100~140万円
賃貸併用住宅を建築する際にはほかにも費用がかかります。詳細は「賃貸併用住宅の建築費」でご確認ください。
賃貸併用住宅はアパートより建築費用が高くなる?
賃貸併用住宅の建築費はアパート建築よりも割高になるケースが多い傾向です。これは、自宅部分の内装材や設備に高いグレードのものを選択するために起こります。
その他、賃貸併用住宅の費用の仕組みを確認するときは「アパートや自宅との違い」をご覧ください。
賃貸併用住宅建築のコストを抑えるためにできることは?
賃貸併用住宅を建てる費用を抑えるにはいくつかのコツがあります。
- 一戸当たりの面積を40平米以上とする
- 自宅面積を50%以上にして住宅ローンを利用する
- 自宅部分と仕様を分ける
- エレベーターは4階までなら作らない
- 相見積もりを取る
コストダウンを図るコツの実践には注意点もあります。「建築費を抑える5つのポイント」で詳しく解説しています。
賃貸併用住宅建築のコストをかけるべきところは?
賃貸併用住宅では建築費をかけたいところもあります。
- プライバシー重視の設計にする
- 入居者のターゲットに応じた間取りにする
- 遮音性に優れた建材を使う
収益性にもつながる重要なポイントです。「建築費をかけるべき3つのポイント」で詳しく解説しています。

この記事を書いた専門家
(株)グロープロフィット 竹内 英二不動産鑑定士事務所および宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役を務める。不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。
1.賃貸併用住宅の建築費
賃貸併用住宅の建築費のうち、本体価格は坪単価相場から試算できます。坪単価は構造別に差があるため、構造選びでは坪単価も気にしなければなりません。
ここでは、建築費のシミュレーションと本体価格以外にもかかる諸費用の費目について詳しく解説します。
1-1.「坪単価×構造別」建築費シミュレーション
賃貸併用住宅の建築費用は、建物の構造によって差が出てきます。
構造別の建築費の目安を床面積の広さ別にまとめました。
| 構造 | 木造 | 軽量鉄骨造 | 重量鉄骨造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|---|---|---|---|
| 適した階数 | 2階建て | 2~3階建て | 3~5階建て | 3階建て~ |
| 坪単価相場 | 77~110万円/坪 | 80~120万円/坪 | 90~130万円/坪 | 100~140万円/坪 |
坪数ごとの建築費を見る
| 構造 | 木造 | 軽量鉄骨造 | 重量鉄骨造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|---|---|---|---|
| 適した階数 | 2階建て | 2~3階建て | 3~5階建て | 3階建て~ |
| 坪単価相場 | 77~110万円/坪 | 80~120万円/坪 | 90~130万円/坪 | 100~140万円/坪 |
| 30坪 | 2,310万円~ 3,300万円 |
2,400万円~ 3,600万円 |
2,700万円~ 3,900万円 |
3,000万円~ 4,200万円 |
| 40坪 | 3,080万円~ 4,400万円 |
3,200万円~ 4,800万円 |
3,600万円~ 5,200万円 |
4,000万円~ 5,600万円 |
| 50坪 | 3,850万円~ 5,500万円 |
4,000万円~ 6,000万円 |
4,500万円~ 6,500万円 |
5,000万円~ 7,000万円 |
| 60坪 | 4,620万円~ 6,600万円 |
4,800万円~ 7,200万円 |
5,400万円~ 7,800万円 |
6,000万円~ 8,400万円 |
| 80坪 | 6,160万円~ 8,800万円 |
6,400万円~ 9,600万円 |
7,200万円~ 1億400万円 |
8,000万円~ 1億1,200万円 |
| 100坪 | 7,700万円~ 1億1,000万円 |
8,000万円~ 1億2,000万円 |
9,000万円~ 1億3,000万円 |
1億円~ 1億4,000万円 |
| 120坪 | 9,240万円~1 億3,200万円 |
9,600万円~ 1億4,400万円 |
1億800万円~ 1億5,600万円 |
1億2,000万円~ 1億6,800万円[小泉2] |
※ハウスメーカーや間取りの違い等により、上記範囲外となるケースもあります。
建物構造は、建物の階数によっても適したものがありますので、何階建ての建物を建てるかで必然的に最適な構造も決まります。
また、建物建築には現況測量費や地盤調査費用、登録免許税といった初期費用も生じます。
これらの費用は、概ね建築費の5%程度が目安です。
そのため、建築費が5,000万円となる場合、諸費用も含めると5,250万円(=5,000万円×1.05)程度と想定できます。
1-2.アパートや自宅との建築費の違い
賃貸併用住宅は、アパートや自宅と比べると建築費が若干割高となります。建築費に影響を与えるポイントは以下の通りです。
- アパートより仕上げ材に良いものを選ぶことが多い
- 自宅(戸建て住宅)より住宅設備の設置箇所が増える
賃貸併用住宅では、自宅部分も含むため、外壁や内装の仕上げ材に良いものを使おうとする方が多く見受けられます。
そのため、賃貸併用住宅の建築費は、通常のアパートの建築費よりも若干高くなる傾向があります。
一方で、賃貸併用住宅は賃貸部分があるため、戸数が増えます。
戸数が多いと、その分バスやトイレ、キッチン等の住宅設備も増加します。同じ面積の建物を建てる場合で比較すれば、自宅なら住宅設備はワンセットだけですが、賃貸部分は複数セットが必要となり、その分、建築費が高くなるわけです。
そのため、賃貸併用住宅の建築費は、通常の自宅の建築費よりも高くなるのが一般的です。
以上のことから、賃貸併用住宅の建築費は、「アパートだけ」または「自宅だけ」よりも若干割高となります。
したがって、賃貸併用住宅の建築費を必要以上に膨らませないようにするには、次章で紹介するコストダウンのコツをしっかり意識することが必要です。
賃貸併用住宅建築にかかる費用が実際いくらかかるのか知りたい場合は、「HOME4U オーナーズ」の一括プラン請求サービスを使えば、無料で建築費の見積もりなど、賃貸併用住宅のプランが手に入ります。
建築費以外の賃貸併用住宅の費用についての詳細は、こちらの記事でも詳しく解説しています。
1-3.建築時にかかる諸費用
建築費以外の初期費用(諸費用)にはさまざまなものがあり、建築価格に含まれる場合とそうでない場合があるため注意が必要です。諸費用にはどのようなものがあるか紹介します。
1-3-1.ボーリング調査費用

建物の建築では建築物の規模や地盤の状況によって杭工事が必要となることがあります。杭工事が想定される場合、着工前にボーリング調査(地盤調査)費用が発生します。
ボーリング調査とは、地盤の硬い支持層が地下何メートルに存在するかを調べる調査です。
ボーリング調査費用は、1ポイントあたり80万円~100万円程度かかります。
1-3-2.設計料
賃貸併用住宅を建てる際は、設計料も発生します。
ハウスメーカーに依頼する場合であっても、設計料は発生し、請負工事契約の中で一つの費用項目として計上されます。
ハウスメーカーの設計料は、工事費に対して1~3%程度が相場です。施工会社と異なる設計事務所に依頼する場合は監理料も含め10~15%が相場と言われています。
設計料が請負工事契約の費用項目として含まれている場合には、工事費と一緒に支払うことになります。
1-3-3.印紙代
請負工事契約書には印紙を貼らなければなりません。
印紙税額は請負工事金額によって変わります。
| 契約金額 | 本則税率 |
|---|---|
| 1千万円超5千万円以下 | 2万円 |
| 5千万円超1億円以下 | 6万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超10億円以下 | 20万円 |
| 10億円超50億円以下 | 40万円 |
| 50億円超 | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
印紙代を節約したい場合、「注文書」と「注文請書」の方式で行うこともあります。
注文書とは、発注者から請負工事会社に対して発注の意思を表明する書式です。それに対して注文請書とは、請負工事会社から発注者に対して受注の意思を表明する書式となります。
注文書は、印紙税が課税される課税文書ではないため、発注者は印紙を貼る必要がありません。一方で、注文請書は課税文書となるため、請負工事会社は印紙を貼ります。
発注者としては印紙を貼らなくてよくなるため、「注文書」と「注文請書」の方式を取るケースもあります。
1-3-4.水道分担金

水道分担金(負担金)とは、水道の利用申込に際して自治体の水道局に納付するお金です。
賃貸併用住宅では、アパート部分の複数戸に水道を供給しなければならないため、引込の口径を太くする工事が発生することがあります。
現状の水道管の口径で不足している場合には、水道分担金が必要です。
水道分担金は自治体や戸数、既存の引込管の口径等によっても異なりますが、賃貸部分が4戸程度でも100万円前後になることもあります。
1-3-5.火災保険料
火災保険料は、本来、毎年発生するランニングコストですが、長期一括契約をすると金額が安くなるため、竣工時にまとめて支払うことも多くあります。
近年は、火災保険とともに地震保険にも加入する方も増えています。
地震保険は火災保険の加入が前提となるため、地震保険だけ加入することはできません。
なお、建物オーナーが火災保険に入っていたとしても、賃貸部分では借主にも火災保険の加入を義務付けることが通常です。
1-3-6.登記関連費用・司法書士手数料
登記関連費用には、「登録免許税」と「司法書士手数料」が発生します。
- 登録免許税
-
登録免許税とは登記を行うために法務局に支払う税金です。
登録免許税は、新築建物の「所有権保存登記」と「抵当権設定登記M」の2種類で発生します。 - 所有権保存登記
-
新たに生じた不動産について初めての所有権の登記。
- 抵当権設定登記
-
抵当権はローンを返済できなくなった場合に銀行が優先的に弁済を受けることができる権利のこと。
抵当権設定登記とは、抵当権が設定されていることを第三者に公示するための登記。
登録免許税は、以下の計算式で計算されます。
建物の保存登記の登録免許税 = 課税標準額(固定資産税評価額)×0.4%
抵当権設定の登録免許税 = 課税標準額(債権金額)×0.4%
- 司法書士手数料
-
新築時の登記は通常、司法書士に依頼します。司法書士はハウスメーカーから紹介してもらうことも可能です。
司法書士手数料は、建物の保存登記や抵当権設定登記を合わせると6~7万円程度です。 - 不動産取得税の基本式
- 1戸あたりの不動産取得税
- 賃貸併用住宅建築の実績が豊富
- 税金対策に詳しい
- 建築費の詳細説明がしっかりできる
1-3-7.不動産取得税
不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課す都道府県税です。建物竣工後、半年経過した頃に都道府県から納税通知書が届き、支払います。
毎年払う固定資産税とは異なり、1回のみ課税されます。
不動産取得税の計算式は以下の通りです。
不動産取得税 = 課税標準額(固定資産税評価額)×税率
ただし、各戸の床面積が「40平米以上240平米以下」であれば1戸あたりの不動産取得税は以下のように計算されます。
不動産取得税 = (1戸あたりの固定資産税評価額-1,200万円)×3%
1-3-8.入居者募集費用

賃貸物件の運用にあたっては、最初に入居者募集費用がかかります。
入居者募集費用は不動産会社に支払う賃貸仲介の仲介手数料の一種で、全戸の家賃の1ヶ月分が生じます。
一方、管理方式として家賃保証型サブリースを選択している場合、賃料の免責期間という形で入居者募集費用を負担することになります。
家賃保証型サブリースの賃料免責期間は3~6ヶ月程度となります。
2.建築費を抑える5つのポイント
建築費が必要以上に膨らみすぎないようにするために、この章ではコストダウンの5つのポイントについて解説します。
ぜひ実践して、上手に建築費を節減してください。
なお、賃貸併用住宅をローコストで建築する方法は、こちらの記事で詳しく解説しています。
2-1.一戸あたりの面積を40平米以上とする
賃貸住宅では、1戸あたりの住戸の面積を「40平米以上240平米以下」とすると不動産取得税が安くなるという特例があります。
一戸あたりの面積が「40平米以上240平米以下」の範囲内で作ると、各戸の不動産取得税は1戸あたりの固定資産税評価額から1,200万円を控除した金額に税率を乗じたものが不動産取得税となります。
【1戸あたりの不動産取得税】
不動産取得税 = (1戸あたりの固定資産税評価額 - 1,200万円) × 3%
上記の特例を使うと、木造などの賃貸併用住宅では場合によって不動産取得税がゼロになることもあります。
次に、2DKまたは1LDKといった間取りは、単身者やDINKs(Double Income No Kids)、就学前児童のいる世帯等の賃貸需要を拾うこともできます。
郊外だと賃料が安いため、単身者でも2DKや1LDKの間取りを求める傾向が見られます。2DKや1LDKは、3LDKに比べると相応に賃貸需要が高く、空室リスクも低く抑えることが可能です。
また、賃料単価を増やすために18平米程度のワンルームとした場合、必要となる住宅設備の数が増えるため、建築コストは高くなります。
需要とコストを鑑みると、40平米程度の間取りがローリスクになると言えるでしょう。
賃貸併用住宅建築にかかる費用が実際いくらかかるのか知りたいときは、「HOME4U オーナーズ」の一括プラン請求サービスを使えば、無料で建築費の見積もりや間取りプランなどが手に入ります。
2-2.自宅を50%以上にして住宅ローンを利用する
賃貸併用住宅では、自宅を50%以上にして住宅ローンを利用することもコストダウンする方法の一つです。
通常、アパート等の賃貸住宅は住宅ローンを使って建物を建てることができません。しかし、多くの銀行が、自宅部分を50%以上とすると建物の資金を住宅ローンで貸し出す条件を設けています。
住宅ローンはアパートローンに比べると金利が安いため、金利を含めた返済総額を抑えることが可能です。
その他、住宅ローンとアパートローンは以下のような違いがあります。
| 住宅ローン | アパートローン | |
|---|---|---|
| 金利の水準 | ~1%前半 | 1%前半~4%程度 |
| ローンを組める期間 | 最大35年 | 19~30年程度 (法廷耐用年数に準じる) |
| 借入の難易度 | 本人の属性が主な審査ポイント | 賃貸物件の収益性や経営方針も審査ポイントに加わる |
また、自宅部分が50%以上で、なおかつ、自宅面積が50平米以上であれば、自宅部分に対し住宅ローン控除も利用可能です。
住宅ローン控除とは、返済期間10年以上のローンを組んで住宅を購入した際、自分が住むことになった年から一定の期間に亘り、所定の額が所得税から控除される税金特例のことです。
このように住宅ローンが使える賃貸併用住宅にすれば、金利を抑え、かつ、所得税も節税できます。
50%以上の自宅確保をこだわり過ぎると上手く設計できないことも多いため、場合によっては住宅ローンを利用しないという選択肢も持っておくことをおススメします。
賃貸併用住宅の住宅ローン利用はこちらの記事で詳しく解説しています。
2-3.自宅部分と仕様を分ける
賃貸併用住宅のコストダウンを図るには、自宅部分と賃貸部分の仕様を分けることをしっかり意識することが必要です。
通常、自宅を作るときは仕上げ材や設備に自分の気に入ったものを採用するため、建築費はどんどん上がる傾向にあります。しかしながら、賃貸部分まで自宅と同じ仕様にしてしまうと、全体の建築費が上がってしまいます。
コストダウンを図るには、賃貸部分は割り切って仕上げ材や設備の仕様は下げることが必要です。
壁のクロスや床材は安いものにしておかないと、貼り替え等の維持管理費もコストアップしてしまいます。
また、賃貸住宅は贅沢に建てても、相場より高い賃料を得るのはなかなか難しいものです。逆に廉価品を使っても相場並みの賃料は十分に取れます。
2-4.エレベーターは4階までなら作らない
4階建ての賃貸併用住宅ならエレベーターは作らないというのも、コストダウンをする一つの方法です。
エレベーターは建築費だけでなく、メンテナンス費用もかかりランニングコストもアップします。将来、大規模修繕でエレベーターを入れ替える際も、多額の費用が掛かります。
そのため、4階建ての賃貸併用住宅を作る場合、思い切ってエレベーターは設置しないという判断も必要です。
4階建ての賃貸併用住宅を作る場合、自宅は最上階の4階部分とします。
エレベーター無しの賃貸物件で4階以上は、入居者を決めることがかなり難しいため、4階部分は自宅とし、3階までを賃貸で貸し出すことが無難です。
ただし、4階は、将来高齢者になったとき、階段の上り下りがきつく住みにくくなるというリスクはあります。将来に4階も貸し出せるようにプレミア住戸として高い仕様の部屋を作っておく対策も有効です。
2-5.相見積もりを取る
賃貸併用住宅のコストダウンで最も効果があるのは、相見積もりを取るということです。
ハウスメーカーはそれぞれの会社が得意な構造や工法を有していますので、ハウスメーカーを変えると建築費が変わります。
木造が得意な会社や軽量鉄骨造が得意な会社というものが存在しますので、それぞれの工法が得意な会社から見積もりを取らないと、建築費はなかなか下がりません。
そのため、各構造でベストプライスを知るには、会社ごと変えて見積もりを取り直すことが必要です。
また、ハウスメーカーは各社で時期によって「お腹の空き具合」みたいなものが違います。
受注が手いっぱいの時期にある会社に声をかけてもなかなか建築費は下がりませんが、受注がもっと欲しいタイミングにある会社に声をかけると建築費が大幅に下がることがあります。
決算期に近く目標売上になんとか近づけたいようなケースでは、他社との競争に打ち勝つために大胆に値引きした見積もりを提示してくることもあります。
賃貸併用住宅で相見積もりを取るなら、「HOME4U オーナーズ」の無料のプラン一括請求サービスの利用がおススメです。
3.建築費をかけるべき3つのポイント
賃貸併用住宅は同じ建物にオーナーと入居者が住む一種の共同住宅です。アパートや戸建て賃貸とは異なる建築のポイントがあります。ここでは、のちの収益性にも直結する建築費をかけておきたいポイントを3点紹介します。
3-1.プライバシー重視の設計にする
賃貸併用住宅ではよく賃貸部分へのアプローチに内階段がよく採用されます。
内階段には、防犯面やプライバシーの確保の観点からメリットがあります。
また、内階段を賃貸の住戸それぞれにも設置した場合、共同住宅の特徴である共用部分がなくなるため、共同住宅の建築規制や制限を適用しなくて済むということもポイントです。
しかし、それぞれに階段を設けた場合は居住スペースを減らすことになるため、戸数を稼ぎ収益性を上げられません。
それでも、プライバシー重視は賃貸併用住宅にとって、入居率を上げるポイントにもなるところです。内階段を採用して賃料アップが図れるかどうかをハウスメーカーに相談してみてもよいでしょう。
3-2.入居者のターゲットに応じた間取りにする
賃貸経営は典型的な立地商売と言われています。賃貸併用住宅を建てるエリアのニーズをしっかり把握したうえで、間取りの検討が必要です。
学校に近い、閑静な住宅地の場合はファミリータイプ、駅から徒歩圏、繁華街へのアクセスが良いエリアでは単身者用の賃貸とエリアによって需要は変わります。空室リスクを減らすにはまず需要のある間取りで考えることが重要です。
単身者用では住宅設備の設置個数が増えるため、建築費はかさみます。
しかし、賃貸併用住宅は戸数も限られるため、空室が出てしまうとたちまち経営が立ち行かなくなる可能性をはらんでいます。
エリアニーズについては、ハウスメーカーに問い合わせてみるとよいでしょう。ハウスメーカーは、不動産市場のニーズを調査するすべを持っています。調査をもとに収支プランを提示してくれるため、見通しがよくなります。
賃貸併用住宅の収益がどのくらいになるか気になったら、「HOME4U オーナーズ」の一括プラン請求サービスをご利用下さい。最大10社から無料で収支プランを手に入れられます。
3-3.遮音性に優れた建材を使う
賃貸併用住宅では、オーナー住戸の快適性もしっかり確保することが大切です。そのための手段として、遮音性に優れた建材を使って、プライバシーをしっかり確保することも必要になってきます。
遮音性を高めることによって賃貸物件としての価値も高まるため、お金をかけておきたい部分です。
大手ハウスメーカーの場合、遮音性に配慮した規格商品も多くあります。中には標準装備となっており、独自の工法で快適性を実現している商品も見られます。
4.賃貸併用住宅の建築費を相談できるハウスメーカーを選ぶポイント

賃貸併用住宅は戸建てにもアパートにもない特徴が多く、建築費に関しては、割高感があることは否めません。しかし、住宅ローンを利用できる、自宅でありながら収益を上げられる、節税効果が高いなど、高い建築費を凌駕するメリットも多くあります。
高い初期費用をかけるからこそ、収益物件は納得のいく価格でハイクオリティのものを手に入れたいものです。そこで大切なのがハウスメーカー選びとなってきます。賃貸併用住宅建築を依頼するハウスメーカー選びでは、以下のようなポイントでの比較がおススメです。
ハウスメーカーを選ぶ際は複数社からプランを取り寄せて比較します。しかし、メーカー一つひとつに請求していると少しずつ希望がずれたり、時間がかかりすぎたりすることが懸念されます。
ハウスメーカーのプラン請求には「HOME4U オーナーズ」の一括プラン請求が便利です。3分ほどの必要事項入力で最大10社に一括でプラン請求できます。ぜひご利用ください。
関連記事
-
【徹底解説】23種類の地目・用途地域の調べ方と、対応する活用法
- 2025.06.29
- ノウハウ
-
-
- 2025.01.22
- アパート・マンション建築
- 賃貸併用住宅
- 駐車場・駐輪場
- 戸建て賃貸住宅
-
- 2025.04.22
- アパート・マンション建築
- ノウハウ