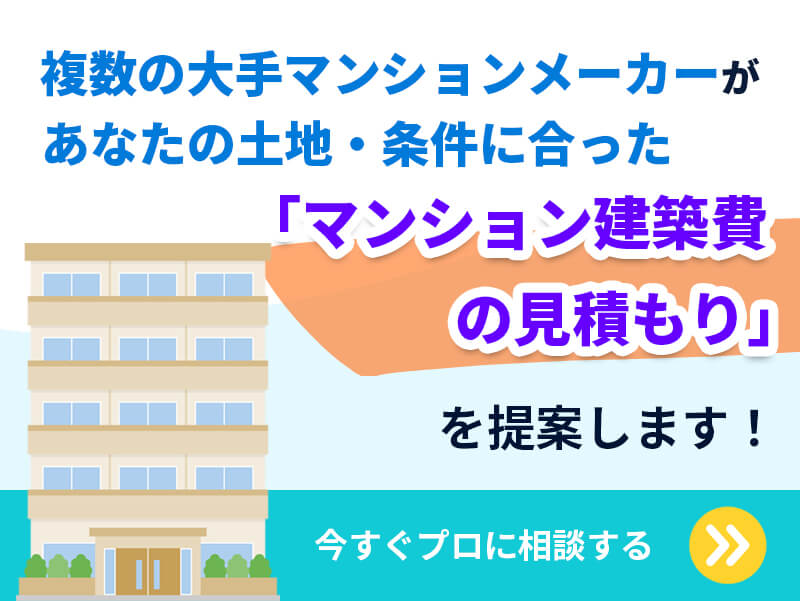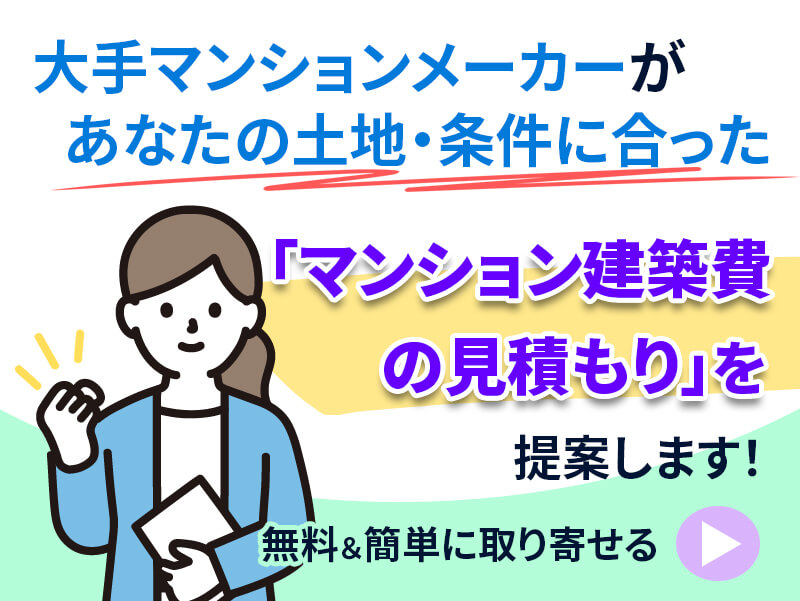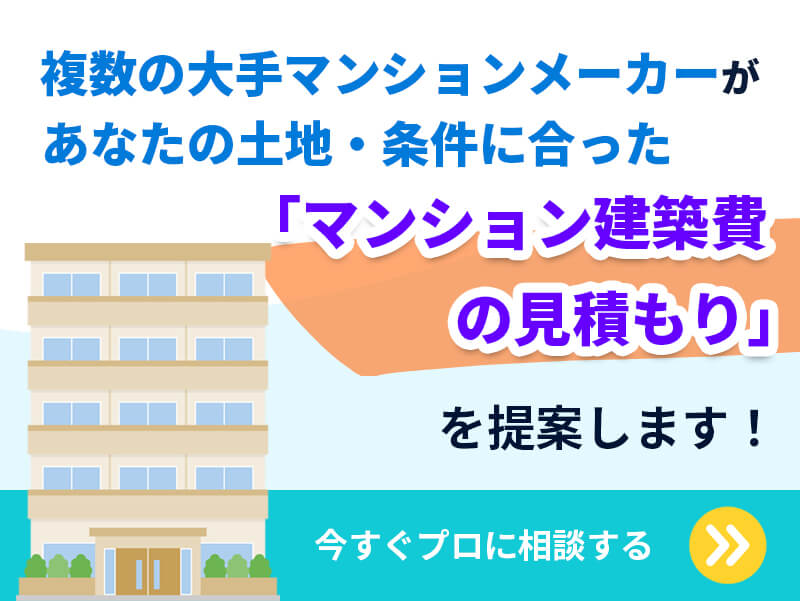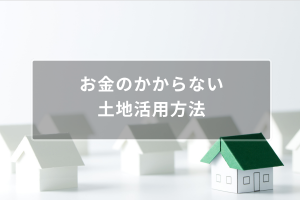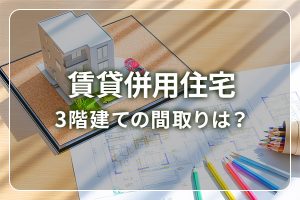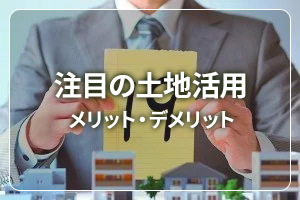【徹底解説】10階建てのマンションの建築費はいくら?見えない費用も解説

この記事では、10階建てのマンションの建築費や、それ以外に発生する費用について解説します。
また、以下のボタンから土地情報を入力すると、最大10社のハウスメーカーがあなたの土地に合った、建築費の見積もりや、収支計画を無料診断いたします。
「うちの土地にどのくらいの規模のマンションが建つの?」「いくら儲かるのか知りたい」という方はご活用ください。
あなたの土地・条件に合った「マンション建築費の見積もり」
詳しい解説は以下
1.建築費の目安
10階建てのマンションの建築費は、延床面積に対して、坪90万円前後が相場です。
安いマンションで坪75万円、高いマンションで坪130万円弱の物件もあります。
主に自動ドアの設置の有無やエレベーターの台数、外壁材や内装の仕上げ、内廊下や外廊下(解放廊下)の違いなどで差が出てきます。
建築費を下げるには、他のマンションの事例を良く観察し、仕様をどこまで割り切って落としてもOKなのか研究することが重要です。
一方で、ターゲットとする入居者層が必要としている仕様・条件まで削ってしまわないよう、注意してください。
2.「10階建て」マンション建築のポイント
この章では10階建てマンションの条件など、建築時に知っておきたいポイントを2つ解説します。
2-1.高さは31mで抑えるのが基本
建物の高さは、敷地の広さや容積率、高度地区の有無等によって決まります。
住宅で10階建て前後の建物となる場合は、建物高さは31mで抑えた方が賢明です。
なぜなら、
建物は31mの高さを超えると、建築基準法で「非常用エレベーターの設置」や「排煙設備の設置」の義務が出てきます。
また消防法においても消防性能の確保等が求められるようになります。
例えば、10階建てなら通常のエレベーターで良かったものが、11階建てとなると非常用のエレベーターの設置義務が発生し、エレベーターのコストが割高となります。
このように31mを超えてしまうと、高層建築物としての様々な規制を受けることになり、建築費が割高となってしまうのです。
マンションやアパートなどの住居系の建物の階高は1フロアあたり3mであるため、ちょうど10階建てにすると、31mの高さに抑えることができます。
10階建てマンションで建築費を抑える場合には、まずは高さが31m以下となるよう意識して下さい。
参考:国土交通省:「建築基準法制度概要集」
2-2.条例の影響を強く受ける

中高層建築物は条例の影響を強く受けます。
一般的に中高層建築物には、各自治体が建築の条例を定めています。
特に
マンションでは、通称「ワンルームマンション条例」と呼ばれる条例が存在します。
ワンルームマンション条例とは、「近隣住民および居住者のトラブル防止」や「居住環境の向上」を目的に、自治体が独自に制定するワンルームマンションの建築に関する条例です。
例えば、東京都は単身世帯数が非常に多くワンルームの賃貸需要が高いため、放っておくとワンルームマンションが乱立してしまう恐れがあります。
またワンルームマンションが増えると、住民が自治会に参加しない、ゴミ出しマナーが悪い等のクレームが自治体へ届くことも増えていきます。
そこで東京都、特に23区内ではワンルーム条例が厳しくなっており、ワンルームマンションの建築を制限しています。
ワンルーム条例は区によって内容が異なりますが、基本的には面積の広い住戸を何割か強制的に組み込ませる規制となっています。
例えば江戸川区では、15戸以上のマンションは住戸面積の平均が70平米以上としなければならないといった規制です。
住戸面積が広くなると、一戸当たりの賃料総額が上がってしまうため、賃料単価を下げざるを得ません。
賃料単価を下げれば投資採算性が低くなり、マンションが投資に見合わない建物となります。
投資に見合わなければ、結果的にワンルームマンションを建てる人が減ることになるのです。
23区では、区によってそれぞれワンルーム条例を定めているため、どのようなマンションが建てられるかは区ごとによって異なります。
建てる場所が異なれば間取りも異なり、結果的には建築費も建てる場所によって異なることになります。
このように中高層建築物の場合には、条例の影響を強く受けるため、間取りと建築費がエリアによって異なるということを知っておく必要があります。
あなたの土地・条件に合った「マンション建築費の見積もり」
3.建築費の見積り段階では見えない費用
10階建てマンションのような事業的規模の建物を建てる場合、予備費もしっかりと見込んでおく必要があります。
予備費とは、見積り段階では分からない費用に対する備えです。見込むべき予備費としては、建築費の5%程度を用意しておくのが一般的になります。
この章では、中高層建物を建築する際、どのような予備費用の支出が発生する可能性があるのかについて解説します。
3-1.杭工事は支持地盤の深さで異なる

高層建物では、杭工事が発生します。
杭工事とは、建物の荷重を地盤が支持できるように杭を打ち込む工事のことです。 杭工事を正確に見積るには、支持地盤(固い地盤)の深さを調べる必要があります。支持地盤の深さを調べる工事のことをボーリング調査と呼びます。
ボーリング調査は、土地所有者の費用負担で行います。 ボーリング調査は、マンションを建築することが概ね決まった段階で行います。 ボーリング調査の結果が分かると、それが最終見積りに反映され、請負工事の金額が確定します。 支持地盤は、周辺に比較的新しい工事現場が残っていると、周辺の工事現場の支持地盤を調査することができます。
中高層建築物の場合、ハウスメーカーやゼネコン等から見積りの提案を受けることがありますが、杭工事に関しては、当初はこの想定値の支持地盤で見積っていることが通常です。
しかしながら、実際にボーリング調査を行ってみると、支持層が思いのほか深く、杭工事の費用が高くなることがあります。 杭は支持層に杭が到達するまで打ち込むため、支持層が深いほど工事費が上がる仕組みになっているからです。
杭工事は工事費全体の1割程度を占めることが多いため、想定値からのブレは、場合によっては大きな金額となります。
建築費は、ボーリング調査を行うまで確定していないということを認識しておいてください。
3-2.埋蔵文化財包蔵地で調査費用がかかることがある
土地が周知の埋蔵文化財包蔵地に指定されている場合には、建築に先立ち埋蔵文化財の調査費用が発生します。
周知の埋蔵文化財包蔵地とは、過去の埋蔵文化財調査の結果から、役所の方で「この辺に遺跡がありそうだ」と目途をつけている土地のことになります。
埋蔵文化財包蔵地かどうかは、市役所の教育委員会等に聞くと分かります。 埋蔵文化財包蔵地については着工前に必ずハウスメーカーやゼネコンが調べてくれますが、気になるようであれば事前に自分で調べておくことをおススメします。
木造の戸建住宅や2階建てアパートなどの建築物では、杭を打つことや、地下空間を作ることがほとんどありません。 地面を掘り起こさないことから、埋蔵文化財包蔵地に指定されていても特段問題とならないことが多いです。
一方で、10階建てのマンションとなると杭工事も発生しますし、地下を掘り起こす工事も発生します。
例えば、10階建てのマンションでは通常、エレベーターが設置されます。 エレベーターを作ると基本的には地下を掘り起こす工事が発生しますが、その際、土地の中に埋まっている埋蔵文化財を破壊する可能性があるので、埋蔵文化財包蔵地で大型建築物を建築するにはまず試掘調査と呼ばれる予備調査が必要です。
試掘調査の費用は個人でも事業者負担となります。
試掘調査で何もなければ問題ありませんが、試掘調査で文化財が発掘されてしまった場合には、本掘調査が必要となります。
本掘調査には莫大な費用がかかりますが、場合によってはその費用も個人が負担する場合もあります。(自治体負担の場合もあり)
一方、事業者が法人の場合には、ほとんどの自治体で本掘調査費用は事業者負担です。 10階建てのマンションを建築する場合、法人を設立して建てるようなケースもあると思われます。 埋蔵文化財包蔵地に指定されていると大きな調査費用が発生する可能性がありますので、事前に確認した方が安心です。
参考:東京都教育委員会「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」
3-3.土壌汚染の除去費用がかかることがある

敷地内の土地に土壌汚染があると、敷地から搬出する土壌の除去費用がかかります。
土地の表層部分については、着工前に土壌汚染調査をすることによって土壌汚染の有無を把握することができますが、深い部分の調査については多額の費用がかかるため、行わないことが多いです。 すると表層部分に汚染土壌がなくても、地下を掘り返した場所で汚染土壌が見つかり、除去にコストがかかるケースがあります。
場外に搬出する土壌が汚染土壌の場合、汚染を除去してから捨てる必要が出てきます。 つまり、掘り出した土が汚染土壌がある場合には、搬出土壌の汚染除去費用が追加で発生するのです。
深いところの汚染土壌は、実際に工事を行ってみないと分かりません。
10階建てマンションの建築においては大体深く掘り起こす工事が伴うので、汚染土壌がある可能性とそれにかかる除去費用も念頭に置いておく必要があります。
3-4.近隣住民からのクレームでコスト増加することがある
中高層建築物を建築する場合、近隣住民からのクレームでコスト増加することがあります。
自治体によっては中高層の建築物について、条例で着工前に近隣説明会(近隣住民への説明義務)を課している場合があります。
近隣説明会を行うと、反対する住民が出てくることがあります。 法令の範囲内であれば土地は所有者の自由に使えるため、周辺住民に反対する権利はないのですが昨今の風潮もあり、説明会をすると反対してくる人もいることは知っておくとよいでしょう。
近隣住民との間でよくあるクレームは、新しいマンションからの「見合い」の問題です。 「覗かれるのが嫌だからどうにかしろ!」という意見が出ると、対応策を考えなければいけません。 通常、バルコニーはアルミ製の縦格子の手摺が一番安価です。 しかしながら、見合いで問題となると、バルコニーをコンクリート壁に変えるようなこともあります。 途中からコンクリート壁に変更すれば工事費は高くなります。
このように、近隣住民からの反対によっては、工事費が高くなるケースもあることを認識しておいてください。
3-5.竣工後の維持費

10階建てマンションでは、竣工後、建物維持費がかかります。
中でもランニングコストに大きく影響するのが、エレベーター保守点検費用です。 賃貸マンションのオーナーにとって維持費の判断が必要となるのは、このエレベーター保守点検に係る契約(エレベーター保守契約)です。
エレベーター保守契約には、大きく分けてFM契約(古メンテナンス契約)とPOG契約(パーツ・オイル・グリス契約)の2種類があります。
FM契約はメンテナンスの基本料金の他、部品代、修理代を全て含んだ契約になりますが、POG契約はエレベーターに関する機器の点検、給油、調整を実施し、部品代や修理費用は別料金となります。 一般的に、FM契約よりもPOG契約の方が安くなります。 またPOG契約も、エレベーターメーカーと契約するよりは、独立系のメンテナンス会社と契約した方がさらに安いです。
それぞれメリットとデメリットがありますので、ハウスメーカーと相談しながら、どの保守契約にするか決めることをお薦めします。
まとめ
いかがでしたか。この記事では、10階建てマンションの建築費と予備費について解説してきました。
- 10階建てマンションの建築費の相場としては、坪90万円程度です。
- 中高層建築物は、条例で間取りまで影響を受けるため、建築費も市区町村によって変わってきます。
- 埋蔵文化財や土壌汚染、近隣からのクレーム問題なども受ける可能性があり、建築費の5%程度は予備費を見込んでおくことが妥当です。
10階建てマンションは、個人で建築計画を立てるには難易度が高いといえます。「HOME4U オーナーズ」で様々な一流建築会社の提案をじっくり比較し、理想のマンションを建ててください。
あなたの土地・条件に合った「マンション建築費の見積もり」
関連キーワード
関連記事
-
-
【徹底解説】3階建て賃貸併用住宅の間取りは?成功例と注意すべきポイントを紹介
- 2025.01.24
- 賃貸併用住宅
-