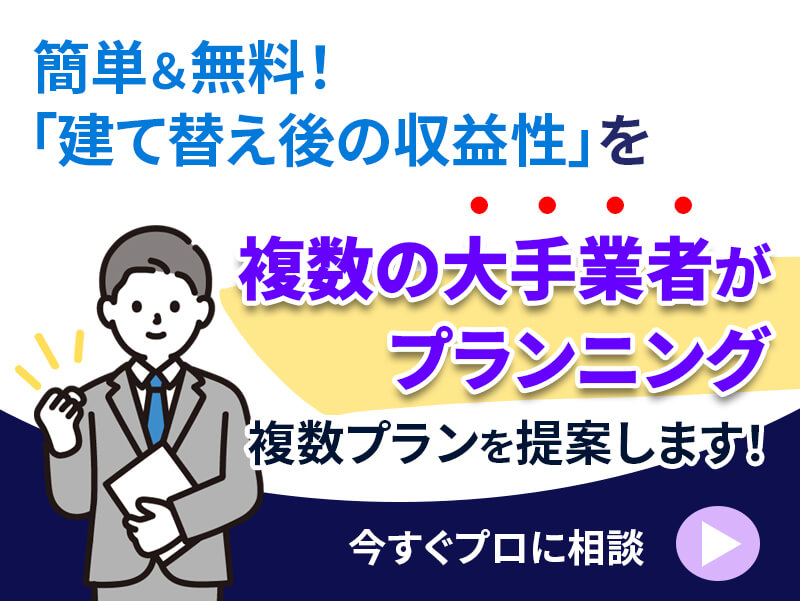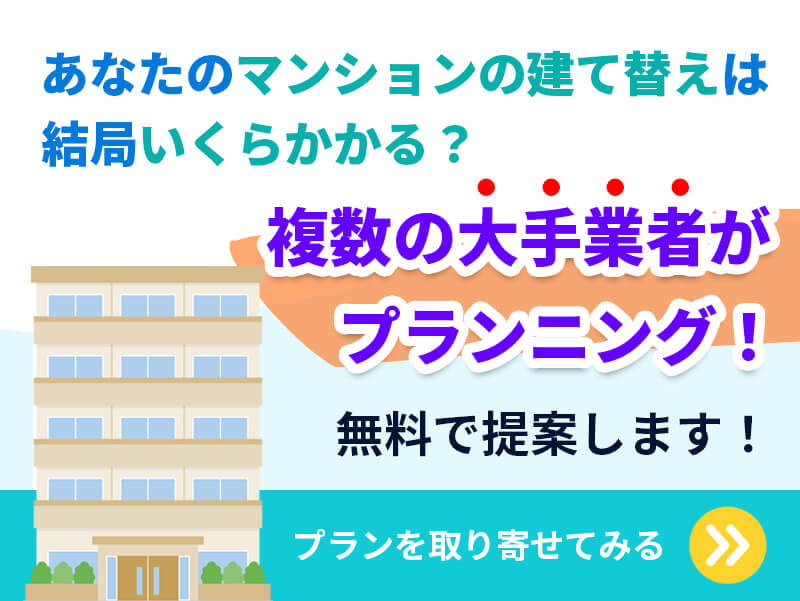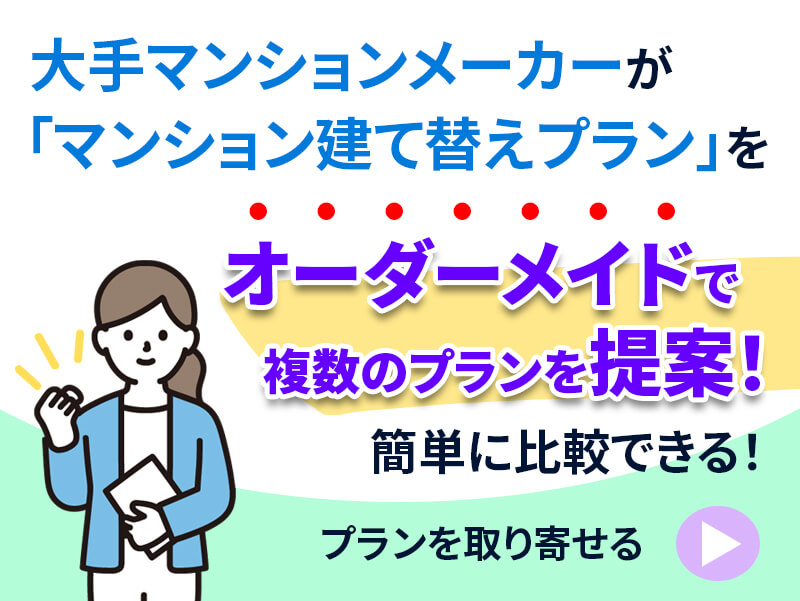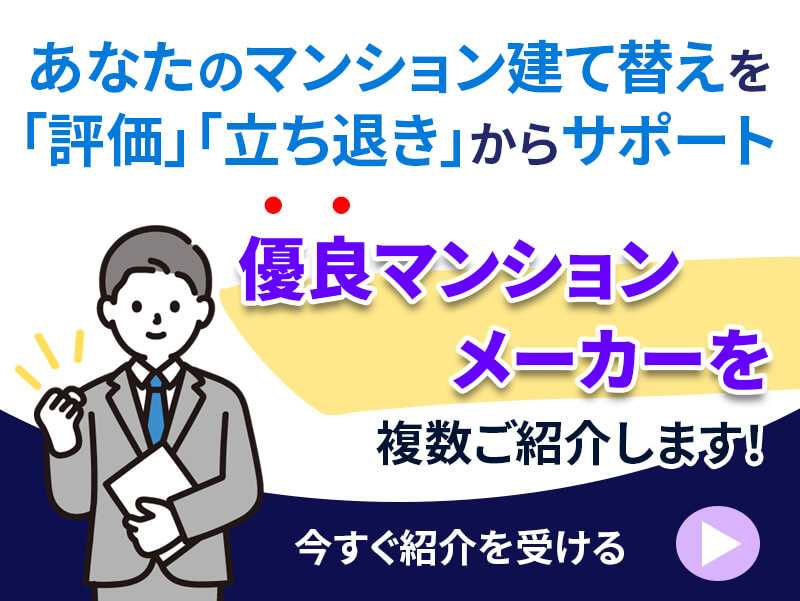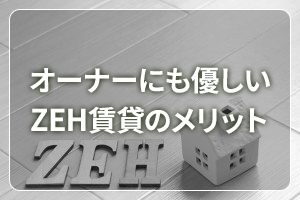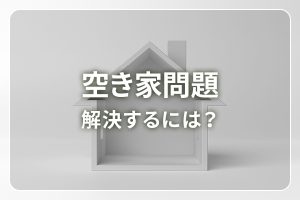【徹底解説】賃貸マンション建て替えの進め方、費用感や立ち退きの注意点といった基礎知識を解説

マンションを建て替えるには、立ち退き交渉、建て替え費用の調達など、さまざまなことを大きく動かす必要があります。この記事では、マンションの建て替えについて初心者にも分かりやすく解説します。
また、以下のボタンから土地情報を入力すると、最大10社のハウスメーカーがあなたの土地に合った、建て替え総額の見積もりや、建て替え後の収益計画を無料診断いたします。
「マンションはいくらで建て替えられるの?」「建て替えと修繕の将来的な収益の差を知りたい」という方はご活用ください。
1. マンション建て替えの流れ
最初にマンション建て替えの流れについて解説します。
【マンション建て替えの流れのイメージ図】

1-1. 建て替えの全体計画を立てる
マンションの建て替えは、まず建て替えの全体計画を立てることが基本です。
マンションの建て替えには、取壊し費用や立ち退き料等の大きな費用が発生しますので、建て替え後の収益性を確認してから着手するようにしてください。
築50年を超えるような古いマンションの場合、容積率が指定される前に建てられている建物が多いため、建て替えると今のマンションよりも規模が小さくなってしまう場合があります。
建て替えて規模が小さくなってしまうと、収入も減ってしまいます。
容積率とは、延床面積の敷地面積に対する割合です。
建築当時の法規制には適合している建物で、現在の法規制に合致しない建物のことを「既存不適格建物」と呼びます。
古いマンションでは、容積率以外でも、なんらかの規制で既存不適格となっていることが多いです。
法規制は厳しい方向に変わることが多いため、既存不適格建物は、建て替えることによって収益性が落ちてしまうことが良くあります。
そのため、古いマンションは、建て替え後、必ずしも同等の家賃収入が得られるとは限らないということを認識しておく必要があります。
一方で、仮に規模は小さくなったとしても、建て替えることで修繕費の支出を抑えることはできます。
また、
新築になれば、家賃も上がり、空室も埋まりやすくなるため、収益力は向上します。
さらに、建て替えによって生まれるのが減価償却費による節税効果です。
減価償却費とは、建物の取得原価を建物の法定耐用年数に渡り計画的・規則的に費用配分する会計の手続き上で発生する費用になります。
鉄筋コンクリート造のマンションであれば、法定耐用年数は47年です。
築47年超のマンションでは減価償却費が計上できないことから、収益は落ちているのに利益が高く、結果的に税金が増えてしまうという現象が発生します。
築47年超のマンションであれば、建て替えることで再び減価償却費を計上でき、税金を少なくすることが可能です。
よって、トータルとしてはメリットの方が大きくなるケースが多いです。
このように古いマンションの建て替えでは、しっかりと建て替え後の収支プランを知ることが重要です。
「建て替え後の収益性」プランニング
1-2. 新規入居を止める
建て替えが決まったら、次は空室部分の新規入居を止めることを始めます。
空室に新たな入居者を埋めてしまうと、立ち退きの必要が生じますので、今空いている空室は埋めないのが基本です。
管理会社に対しては、建て替えを予定していることを伝え、新規入居はストップするように指示してください。
また、現在残っている入居者の立ち退きが長期化しそうな場合には、定期借家契約を利用して入居者を埋めておくという考えもあります。
定期借家契約とは、更新規定のない契約であり、契約期間が終了すると入居者が確実に退去しなければならない賃貸借契約です。
一方で、更新がある賃貸借契約のことを普通借家契約と呼びます。
今後新たに入居する賃借人と定期借家契約を締結すれば、その入居者に対しては立ち退き料を支払うことなく退去させることができます。
定期借家契約で新たな契約をする場合、契約終了時点を同じ時期に揃えておくことがポイントとなります。
定期借家契約では、1年未満の契約期間を定めることもできます。
6ヶ月のような契約期間でも有効ですので、終了時期に近づくほど契約期間を短くするようにしてください。
ただし、定期借家契約は入居者が更新できないため、借主にとって不利な契約となります。
住宅の場合、普通借家契約が一般的なので、定期借家契約にすると大幅に賃料が落ちる傾向にあり、且つ入居者が決まりにくくなります。
また、定期借家契約で埋めてしまうと、逆に定期借家契約の終了期間までは「貸さなければいけない」という制約も生じます。
仮に残っている入居者の立ち退きが早く終わってしまえば、定期借家契約の終了期間まで取り壊しを待つことになります。
そのため、残っている入居者の立ち退きが順調で、1年以内に立ち退きが完了する見込みであれば、空室部分は割り切って空室のままとしておくことをおススメします。
1-3. 立ち退きを開始する
新規入居を止めると同時に立ち退きも開始します。
立ち退きについては、「3. 立ち退きの基礎知識」にて詳しく解説します。
立ち退きについては、実行してみないとどうなるか分からない部分があります。
相手の出方次第で難易度が変わりますので、
空室部分を定期借家契約で埋めるかどうかは、感触をつかんだうえで判断するのがポイントです。
●立ち退きは貸主側の心構えも必要
最近の傾向として、建物オーナーから立退き要請を受けると、借主側もインターネットで調べた上で対処してきます。
借地借家法では、借主の権利が強力に守られていますので、借主に理論武装されるほど、貸主の立場は弱くなります。
立ち退きを行うのであれば、貸主側も借地借家法の基礎概念を理解しておくことが重要です。
●立ち退きと建て替えのタイミングとは
マンションの建て替えは、立ち退きが大きな障壁となるため、残っている入居者が少なくなってから着手することが必要となってきます。
自然発生的に空室が増え、8割くらいが空室になった段階で立ち退きを始めていくと、戸数が絞られ楽になります。
築50年を超えていても、満室状態であれば、建て替えには着手すべきではないということになります。
入居者が多いほど、立ち退きにかかる時間と費用が膨らみます。
よって、
建て替えは、立ち退きが楽にできるような状態になってから着手するようにしてください。
1-4. 工事費を確定する
最終的に設計プランが決まったら、工事費を確定し、請負契約の締結です。
新しいマンションではセキュリティを強化することをおススメします。
新築マンションでは、エントランスに風除室(外気の流入や風の吹きつけを緩和する目的で建物の入口前に設けられた小部屋のこと)を設け、奥の扉をオートロックとし、各所に防犯カメラも設置するなど、セキュリティを強化するようにしてください。
また、4階建て以上のマンションで、エレベーターのないマンションであれば、エレベーターを積極的に設置することをおススメします。
1-5. 解体工事と新築工事を依頼する
立ち退きが完了したら、解体工事を依頼します。
建て替えの場合、解体工事は新築工事の会社にそのまま発注することをおススメします。
本来、解体工事会社と新築の建築会社は異なりますが、新築の建築会社も解体工事を請けてくれます。
解体工事は騒音と振動が激しいため、新築工事よりも近隣とトラブルになりやすいです。
解体と新築の工事会社を分けてしまうと、解体工事会社がその後の新築工事の影響を考えず、無責任な近隣対応をしてしまう可能性があります。
そのため、解体工事は新築工事への影響を見越せる建築会社に依頼した方が、全体としてスムーズに行きます。
尚、解体工事の前には、依頼主と解体工事会社で近隣に工事着工の挨拶を行うのが一般的です。
条例で解体工事の近隣説明義務の定めがない自治体であっても、トラブル防止のために挨拶は行っておくのがスムーズに建て替えるコツとなります。
解体工事も終了したら、次はいよいよ新築工事です。
月に1回程度は現場に視察に行き、工事の進捗状況を良く確認するようにしてください。
1-6. 管理方式を決める
竣工までに、管理方式を決め、契約を行います。
マンションの管理方式は、「管理委託」、「パススルー型サブリース」、「家賃保証型サブリース」の3種類です。
1.【管理委託】
管理会社に管理を委託する管理方式。
管理料の相場は、家賃収入の5%程度。
2.【パススルー型サブリース】
一棟全体を管理会社に賃貸し、各部屋は管理会社と入居者が転貸する形式の管理方式。
建物オーナーに入ってくる賃料は、入居している部屋の賃料から、約5%を差し引いた賃料が建物オーナーに振り込まれるため、収益性は管理委託と同じ。
3.【家賃保証型サブリース】
各戸の入居状況に関わらず、賃料は固定される管理方式。
建物オーナーに入ってくる賃料は、満室想定賃料から15%程度差し引いた賃料が建物オーナーに振り込まれる。
建物オーナーが締結する賃貸借契約書が管理会社との契約書1本だけで済み、かつ、収益性も高いため、立地の良いマンションであれば、パススルー型サブリースがおススメです。
管理方式は、自分の物件の状況に合わせて、適切なものを選ぶようにしてください。
2. マンション建て替えに要する主な費用
 この章ではマンション建て替えに要する主な費用について紹介します。
この章ではマンション建て替えに要する主な費用について紹介します。
- 立ち退き料
- 解体工事費用
- 新築工事費用
2-1. 立ち退き料
立ち退き料は、住宅であれば「引越代プラスアルファ」が1つの目安です。
特に値段の決りはありませんが、
1戸あたり50~80万円程度で着地すれば理想といえます。
ただし、相手がゴネ出すと金額が上がってしまいますので、予算としては1戸当たり100万円を確保しておくことが望ましいです。
2-2. 解体工事費用
マンションは鉄筋コンクリート造が多いです。
鉄筋コンクリート造の解体費用は坪7~8万円となります。
2-3. 新築工事費用
マンションの場合、新築工事も鉄筋コンクリート造が多いと思われます。
新築工事費用の相場としては、坪100~120万円程度です。
その他、新築工事では地盤調査費用や登録免許税、不動産取得税等の諸経費が発生します。
諸経費については、新築工事費用の5%程度を予備費として見込んでおくのが一般的です。
新築の工事費用は会社ごとにばらつきがあります。
ですので、
複数の会社からプランを受け取って比較検討することが、マンション建て替えの成功術になります。
マンションは規模が大きくなることが多いことから会社によって建築費はまちまちになりがちです。しっかり、竣工後の経営を見据えるなら建築費の比較検討をする必要があります。建築費の比較検討には最大10社から一括プラン請求できる「HOME4U オーナーズ」をご活用ください。
あなたのマンションの建て替えには結局いくらかかる?
3. 立ち退きの基礎知識
 この章では立ち退きの基礎知識について解説します。
この章では立ち退きの基礎知識について解説します。
3-1. 契約の種類と立ち退きの必要性
賃貸借契約には「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。
両者の違いは
更新規定の有無です。
「普通借家契約」と「定期借家契約」は、両方とも賃貸借期間が定められていますが、契約期間満了時に契約更新ができるのが普通借家契約で、契約更新できないのが定期借家契約になります。
賃貸借契約が定期借家契約となっていれば、契約満了時に入居者は退去せざるを得ないため、立ち退きの必要はありません。
一方で、賃貸借契約が普通借家契約の場合には、契約満了時に入居者が更新を申し出れば更新できてしまうため、立ち退きが必要となってきます。
契約の種類がどちらか分からなくても、とりあえず過去に一度でも入居者と更新していれば、その契約は普通借家契約ということです。
契約書の中に、「甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。」といった文言があれば、それは普通借家契約となります。
3-2. 正当事由と立ち退き料
立ち退きには、正当事由と立ち退き料が必要です。
借地借家法では、普通借家における更新拒絶について、以下のような定めがあります。
借地借家法
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第28条 建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
この規定は、賃貸人から入居者に建物の明け渡しを要求するには、正当の事由とよばれる理由と、財産上の給付を申し出ないと「することができない」と書かれています。
現実的には、建物の老朽化を理由に立ち退きを申し出ることが良くあります。
しかし、建物の老朽化だけでは、正当事由としては少し弱いです。
そこで登場するのが
立ち退き料です。
立ち退き料には弱い正当事由を補完する役割があり、「理由プラス立ち退き料」となることで、はじめて賃借人を退去させることができることになります。
立ち退き料は、法律上明記されていることですので、借主から要求されれば、立ち退き料は払わざるを得ません。
最初から概算の予算を確保した上で計画的に進めるようにしてください。
3-3. 建物用途と立ち退き料
立ち退き料は、建物用途によっても異なります。
●住宅や事務所の場合
住宅や事務所などの用途は、
「借家権価格」と呼ばれるものが立ち退き料に相当します。
立ち退き料の目安としては一般的に「引越代プラスアルファ」程度となります。
金額としては、
1戸あたり50~80万円程度です。
ただし、ごねる人もいることを考えると、予算としては1戸100万円程度も見込んでおくと安全といえます。
●店舗の場合
店舗では「借家権価格」に「営業補償」が加わるため、立ち退き料が大きな金額となります。
店舗の立ち退きは、立ち退き料の金額が極端に大きくなるため、不動産会社等にヒアリングして立ち退き料の概算値を十分に調べておくことも必要です。
店舗の場合、立ち退き料は店舗面積や店舗の売上、正当事由の強さ等によって異なります。
| 事件表示 | 立ち退き料 | 目的物 | 買主 |
|---|---|---|---|
| 東京地四五(レ)一五四 昭和四六・一一・一九判決 判時六六二-五九 |
130万円 | 店舗 | 理容店経営 |
| 東京地平二(ワ)九四三三 平三・九・六判決 判夕七八五-一七 |
700万円 | 店舗兼住宅 | ワープロ教室 |
| 東京高八(ネ)一一六三 平一〇・九・三〇判決 判時一六七七-七一 |
4,000万円 | 店舗及び住居 | 高級下着店 |
| 東京高六一(ネ)一二九一 平元・三・三〇判決 判時一三〇六-三八 |
1億6,000万円 | 店舗及び住居 | 酒類販売業 |
| 東京地五五(ワ)七〇八一 昭六一・五・二八判決 判夕六三三-一五七 |
3億4,000万円 | 鉄筋コンクリート造5階建ての1階店舗部分 | 大衆中華料理店 |
住宅や事務所は、場所が変わっても大きな影響はありませんが店舗の場合、場所が変わると売上が下がるなどの大きな影響を受けます。
そのため、店舗については立ち退き料に営業補償も含むという概念が確立されているのです。
営業補償には新規開業までの休業損失や、新店舗で客足が回復されるまでの減収分が含まれるため、金額が大きく膨らみます。
優良大手マンションメーカーの「マンション建て替えプラン」
4. 入居者対応の注意点
 この章では立退きについて入居者対応の注意点について解説します。
この章では立退きについて入居者対応の注意点について解説します。
4-1. 立ち退きは原則として賃貸人が行う
立ち退きに関しては、さらに厄介なことが1つあります。
それは、
立ち退きは、原則として賃貸人が行う必要があるという点です。
立ち退きは、法律知識が必要なうえ、お金もかかり、交渉も要することから、できれば第三者のプロに頼みたい方も多いと思います。
しかしながら、立ち退きのような紛争性の高い代理行為は弁護士法によって弁護士以外の第三者に任せることができないルールとなっています。
例えば、管理会社や建築会社など、弁護士以外の第三者には立ち退きを依頼することはできないということです。
弁護士なら代理人として立ち退きを依頼することができます。
日本における弁護士制度を定めている法律である、弁護士法の第72条では、以下のように定められています。
弁護士法
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
上記の条文によって、「弁護士以外の第三者が報酬目的で立ち退きのような紛争性の高い法律行為の代理人をしてはならない」と解釈されています。
弁護士以外の第三者が代理人となって法律行為を行うことを「非弁行為」と呼び、管理会社が立退き業務を受託してしまうと、非弁行為になるため、管理会社は立退き業務を受けることはできないのです。
仮に弁護士に依頼するとしても、借地借家法は別の法律であるため、立ち退き料が安くなるということはありません。
弁護士に依頼してしまうと、弁護士費用が加算するだけですので、立ち退きは賃貸人本人が行うことが通常です。
そのため、建物オーナーは立ち退きについて十分に勉強し、しっかり準備を整えた上で取り組む必要があります。
4-2. 裁判等は避けるようにする
立ち退きは、ちょっとしたボタンの掛け違いで、トラブルに発展することがあります。
しかしながら、
裁判等は極力避けるようにすることをおススメします。
立ち退きで裁判に発展した場合、司法の判断の根拠となるのが借地借家法です。
借地借家法は、借家人を守るための法律ですので、借地借家法が判断軸になってしまうと、賃貸人の分が悪くなってしまいます。
立ち退きで裁判になってしまうと、借地借家法に基づき、借主が手厚く保護されることが多いです。
立ち退き料で揉めた場合、多少高い程度であれば、支払ってしまい話し合いで解決した方が得です。
尚、立ち退きを成功させるコツは、誠意をもって相手と接することです。
こちらが誠意をもって誠実に接すれば、裁判になるようなことはありません。
最初から立ち退き料はしっかり支払うことを明示し、お願いベースで退去を依頼します。
4-3. 定期借家への切り替えも検討してみる
立ち退きのやり方の一つとして、残っている入居者の賃貸借契約を、定期借家に切り替えるという方法もあります。
住宅の場合、2000年3月1日以降に締結された賃貸借契約であれば、借主と貸主の合意の下、普通借家契約は定期借家契約に切り替えることが可能です。
反対に、2000年3月1日より前に締結された賃貸借契約は定期借家契約には切り替えることができないとされています。
定期借家契約の切り替えに成功すれば、立ち退き料を支払う必要もないですし、入居者の明け渡し時期も確定するというメリットがあります。
ただし、定期借家への切り替えは、入居者にとって見ると体のいい立ち退き話なので、そのままでは入居者にメリットがありません。
よって、建物オーナーから切り替えを打診する場合には、「賃料減額」の条件を提示して借主の合意を得ることが通常です。
定期借家への切り替えが難しいようであれば、その手法にこだわらず、立ち退き料を支払って退去させる方針に変更するようにしてください。
まとめ
いかがでしたか。
マンションの建て替えについて解説してきました。
マンションの建て替えには、取壊し費用や立ち退き料等の大きな費用が発生しますので、建て替え後の計画をしっかり見極めてから着手することが重要です。
費用に関しては、立ち退き料は1戸当たり100万円程度の予算を組んでおくのが無難です。
鉄筋コンクリート造なら解体費用は坪7~8万円、新築工事費用なら坪110~120万円となります。
マンション建て替えの最大のハードルは立ち退きです。
立ち退きは、借地借家法の趣旨をしっかりと理解し、立ち退き料の準備もしたうえで誠実に対応することがコツとなります。
マンション建て替えは一大事業ですので、しっかりと準備し、計画的に行うようにしてください。
「マンション建て替え」を、「計画」「立ち退き」といった段階からサポート
関連キーワード
関連記事
-
【徹底解説】ZEHの賃貸住宅は本当に有利なの?!長所短所と補助金を解説
- 2025.01.23
- 節税
- アパート・マンション建築
-
- 2025.01.24
- ノウハウ
- アパート・マンション建築
-
- 2025.01.24
- 空き地
-
-
【基礎から解説】マンション経営のメリット・デメリットと初期費用&始め方
- 2025.01.23
- ノウハウ
- 費用
- アパート・マンション建築