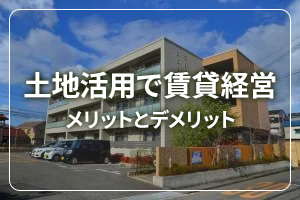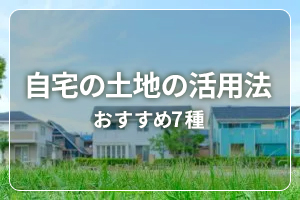
広すぎる家や土地を持て余している方は意外と多くいらっしゃいます。
「子供が独立して、部屋が余っている」「掃除や庭の手入れが大変になってきた」「自宅を相続してどうしようか迷っている」等のお悩みはないでしょうか?
せっかくの資産が逆に悩みの種になってしまうのは、実にもったいないですね。
この記事では自宅の土地活用におすすめの方法を7つ、厳選してご紹介します。
土地を活用して稼ぎたい方、なるべく手間をかけたくない方、それぞれのニーズに合わせて紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
場合によっては、自宅はそのままにして敷地の一部をうまく土地活用したり、敷地の一部を売却して自宅を建て替える方法もおすすめです。
土地活用の種類によっては、大きな節税が可能なので、なるべく多くの資産を次世代に残すためにも自宅の有効活用をおすすめします。
また、以下のボタンから土地情報を入力すると、最大10社の土地活用専門企業があなたの土地に合った活用方法や、収支計画を無料診断いたします。
「うちの土地はどんな活用ができる?」「いくら儲かるのか知りたい」という方はご活用ください。
自宅の土地活用において、稼ぎたいのか、なるべく手間をかけたくないのかによって、取るべき方法は変わってきます。
それぞれの方法によって、収益性、手間、初期投資、期間、節税効果などが異なります。
初めに、それぞれの特徴を表にまとめました。
稼ぎたい方におすすめの土地活用は?
稼ぎたい方に選ばれることが多いのは、「賃貸併用住宅への建て替え」「アパート経営」「戸建賃貸経営」の3種類の方法です。
それぞれの特徴は以下の表をご確認ください。
| 収益性 | 手間の 少なさ |
初期投資の 少なさ |
期間 | 節税効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸併用住宅 | 〇 | △~〇 | × | 長期 | 〇 |
| アパート経営 | ◎ | △~〇 | × | 長期 | 〇 |
| 戸建賃貸経営 | ◎ | △~〇 | × | 長期 | 〇 |
詳しくは、「稼ぎたい方におすすめの自宅の活用方法」の項目に記載していますので、ご確認ください。
手間をかけたくない方におすすめの土地活用は?
また、手間をかけたくない方に選ばれることが多いのは、「駐車場経営」「太陽光発電」「借地」「売却」の4種類の方法です。
それぞれの特徴は以下の表のとおりです。
| 収益性 | 手間の 少なさ |
初期投資の 少なさ |
期間 | 節税効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場経営 | △ | 〇 | 〇 | 短期~長期 | × |
| 太陽光発電 | △ | ◎ | △ | 長期 | × |
| 借地 | △ | ◎ | ◎ | 短期~長期 | × |
| 売却 | – | ◎ | ◎ | – | – |
詳しくは、「手間をかけたくない方におすすめの自宅の活用方法」の章で説明しています。
最適な方法は、土地の形状や広さ、周辺の環境により異なります。
また、土地活用で何を実現したいのかによっても変わってくるため、相談先にしっかりと要望を伝える必要があるでしょう。
信頼できる相談先を探し、土地活用のプロに総合的なプランを提案してもらうことをおすすめします。
1.稼ぎたい方におすすめの自宅の活用方法
稼ぎたい方におすすめの自宅の土地活用方法は3種類あります。
- 賃貸併用住宅への建て替え
- アパート経営
- 戸建賃貸経営
オーナーの要望や立地、土地の面積・形状によって、有利な戦略は異なります。
専門家に相談しながら、方向性を決めていくことが大切です。
なお、相談する際のコツについては「信頼できる相談先の選び方」の章でご紹介します。
1-1.賃貸併用住宅への建て替え
「土地が余っているし、自宅も老朽化している」という2つの悩みを同時に解決できるのが、賃貸併用住宅への建て替えです。
| 収益性 | 手間の 少なさ |
初期投資の 少なさ |
期間 | 節税効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸併用住宅 | 〇 | △~〇 | × | 長期 | 〇 |
賃貸併用住宅は、自宅部分と賃貸住宅部分が一体化した建物です。
建築プランは様々で、「自宅とアパートを半分ずつ」というケースも多いですが、「建物のほとんどが賃貸住宅で一部が自宅」といったケースもあります。
どのような建築プランが有利なのか、立地や敷地条件に応じて計画することが大切です。
賃貸併用住宅はどこでもおすすめできるわけではなく、賃貸需要が確実に見込める場合に検討してください。
賃貸部分はワンルームでもファミリータイプでも可能ですので、需要に合わせて選択します。
ワンルームにするほうが賃料単価は高めに設定できる傾向はありますが、単身者とオーナー家族の生活リズムの違いによる騒音トラブルに注意して、建物を設計する必要があります。
賃貸併用住宅は、音やプライバシーなどに多角的に配慮し、入居者もオーナーも快適に住めるような建物を計画することが大切です。
そのため、賃貸併用住宅の建築実績の豊富な企業に相談することをおすすめします。
1-1-1.賃貸併用住宅のメリット
賃貸併用住宅の最大のメリットは、なんといっても「住み慣れた場所に暮らしながら、賃貸収入が得られる」ということです。
その他にも、次のとおり様々なメリットがあります。
- 家賃収入をローンの返済に充てれば、ほとんど自己負担なく自宅を建て替えられる場合がある。
- 建物全体について、アパートローンより低金利の住宅ローンを利用できる可能性がある。
- 相続税や固定資産税の節税効果が高い。
- ライフスタイルの変化に合わせて、将来は賃貸部分に親世帯や子世帯を呼び寄せて独立型の二世帯住宅として利用することもできる。
- 賃貸管理を委託すれば手間をかけずに安定収入が得られる。
1-1-2.賃貸併用住宅のデメリット
賃貸併用住宅のデメリットは次のとおりです。
- 敷地全体を土地活用したほうが収益性は高い。
- 入居者とオーナーが近くに住むので、優れた設計プランを採用しないと、快適に住むことができない可能性がある。
1-1-3.賃貸併用住宅に向いている土地
駅から近い場所、周辺にアパートやマンションが多い場所、住み心地が良い人気の住宅街など。
1-2.アパート経営
アパート経営は、長期的に安定した収入が得られる手堅い土地活用ですので、多くの方に選ばれます。
ただし、賃貸需要がある場所に魅力的な建物を建てるのが絶対条件です。
| 収益性 | 手間の 少なさ |
初期投資の 少なさ |
期間 | 節税効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アパート経営 | ◎ | △~〇 | × | 長期 | 〇 |
アパート経営は、エリアによっても異なりますが、40坪くらいの土地があれば建築可能です。
利便性が高くワンルームアパートの需要が多いエリアなら、1坪あたりの賃料単価が高いため、小規模なアパートを建てても十分に採算が見込めます。
ただし、ファミリー需要の多い郊外等では、駐車場の確保も必要となり、まとまった面積でないとおすすめできないケースもあります。
1-2-1.アパート経営のメリット
アパート経営には次のとおり様々なメリットがあります。
- 徹底的な市場調査を踏まえて競争力の高い建物さえ建てれば、高収益が見込める。
- 相続税や固定資産税の節税効果が高い。
- 賃貸管理を委託すれば手間をかけずに安定収入が得られる。
- 長期的に安定収入を得られる。
1-2-2.アパート経営のデメリット
アパート経営のデメリットは次のとおりです。
- まとまった初期投資が必要。
- 入居者を集められる魅力的な物件を計画しないと、空室リスクが大きくなる。
1-2-3.アパート経営に向いている土地
駅から近い場所、周辺にアパートやマンションが多い場所など。
1-3.戸建賃貸経営
あまり聞き慣れないかもしれませんが、戸建賃貸(賃貸向けの一戸建て)を建てる土地活用は最近注目されています。
| 収益性 | 手間の 少なさ |
初期投資の 少なさ |
期間 | 節税効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 戸建賃貸経営 | ◎ | △~〇 | × | 長期 | 〇 |
ファミリー層を中心とした需要があるにも関わらず、一戸建てタイプの賃貸は非常に少ないため、差別化が可能です。
また高い入居率、定着率が見込めるため、将来性が非常に高いと言われています。
「周辺の賃貸需要は多いけれど、競合アパートと差別化したい」という場合におすすめです。
また、2棟以上の戸建賃貸を建て、そのうちの1棟に親族が住むといった柔軟な使い方も可能です。
1-3-1.戸建賃貸経営のメリット
戸建賃貸経営には次のとおり、大変多くのメリットがあります。
- 競合が少ないので高稼働が期待できる。
- 狭小な敷地や細長い敷地などに合わせた設計が可能。
- 相続税や固定資産税の節税効果が高い。
- 一棟ずつ売却、相続することもできる。
- アパートよりも建築費は抑えやすい傾向がある。
- 賃貸管理を委託すれば手間をかけずに安定収入が得られる。
戸建賃貸については、こちらに詳しく説明しています。
1-3-2.戸建賃貸経営のデメリット
戸建賃貸経営のデメリットは次のとおりです。
- 立地条件によっては、アパート経営やマンション経営のほうが収益性は高くなる。
- 賃貸用の戸建住宅の実績が少ない建築会社もあるため、メーカー選びの選択肢が限られる。
1-3-3.戸建賃貸経営に向いている土地
駅から近い場所、周辺にアパートやマンションが多い場所、ファミリー層に人気の住宅街など。
2.手間をかけたくない方におすすめの自宅の活用方法
自宅の土地活用において、あまり手間をかけられない方におすすめの方法は4種類あります。
- 駐車場経営
- 太陽光発電
- 借地
- 売却
土地の立地や面積・形状によって、最適な活用方法は変わってくるため、土地の特徴に合った活用方法を選択することが大切です。
迷ったときには、専門家に相談しながら、方向性を決めていきましょう。
2-1.駐車場経営
需要さえあれば、初期投資も少なく、短期間でも止められるので気軽に始めることができます。
| 収益性 | 手間の 少なさ |
初期投資の 少なさ |
期間 | 節税効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場経営 | △ | 〇 | 〇 | 短期~長期 | × |
駐車場経営は、1台あたり2.5m×5m程度の面積があれば始められます。
車庫入れスペース等も考慮した台数は、1台あたり7坪で概算することができます。
例えば100坪の土地なら、100坪÷7=約14台が目安です(正確な台数は土地の形状によって異なります)。
将来、お子様の家を建てるかもしれない、という理由で広い土地をお持ちの方も多いですが、駐車場はそのような土地にも向いています。
なお、コインパーキングと月極駐車場では、運営方法や、向いている立地が異なることにご注意ください。
2-1-1.コインパーキングの特徴
オーナーはコインパーキングの専門業者に土地を貸し出し、毎月一定の賃料を受け取る方式がほとんどです。
この場合は、設備投資は専門業者の負担となり、設置工事から運営管理まですべて任せることができます。
オーナーは舗装費用だけを負担するのが一般的です。
コインパーキング経営についてはこちらをご覧ください。
2-1-2.月極駐車場の特徴
オーナーが自主管理するか、地域の不動産会社に管理を委託したり、借り上げしてもらうケースが多いです。
砂利にロープを張るだけなら最もコストを抑えることができますが、場合によっては費用をかけて舗装を行ったほうが利用者は集まるので、しっかりとした調査が必要です。
アパート経営の場合は入居者の権利が強力に守られるため、オーナーが簡単に契約を解除することはできませんが、駐車場はオーナー都合での契約解除が簡単なので、短期間で土地活用を中止する可能性があっても安心です。
2-1-3.駐車場経営のメリット
駐車場経営といっても規模や契約内容は様々ですが、次のようなメリットがあります。
- 初期投資が少ない。
- 短期間の土地活用が可能で、他の用途への転用も容易。
2-1-4.駐車場経営のデメリット
駐車場経営のデメリットは次のとおりです。
- 投資額が少ないため、アパート経営等に比べると高収益は期待しにくい。
- 相続税や固定資産税の節税効果がなく、今まで自宅にしていた土地を駐車場に変えると固定資産税が上がってしまう。
- 駐車場代の滞納や、無断利用されたりするリスクがある(月極駐車場の場合)。
2-1-5.駐車場経営が向いている土地
駅・病院・観光地の近く、商業地、住宅地など。
駐車場経営についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
2-2.太陽光発電
太陽光発電は、自宅の土地に太陽光発電システムを設置して、生み出した電力を電力会社に売却し、収益を得る方法です。
| 収益性 | 手間の 少なさ |
初期投資の 少なさ |
期間 | 節税効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 太陽光発電 | △ | ◎ | △ | 長期 | × |
自宅の土地が郊外で、活用方法が限られる場合でも、ある程度の日当たりと送電線があれば土地活用が可能となるため、近年ではメジャーな方法のひとつとなっています。
日当たりがよく広い土地であれば、その分、多くの電力を発電できる可能性があるため、高収益が期待できるでしょう。
ただし、設置費用を回収するには10~15年程度かかるため、長期の土地活用方法として考えておく必要があります。
2-2-1.太陽光発電のメリット
太陽光発電には、以下のメリットがあります。
- 「固定価格買取制度」があるため、長期にわたって安定した収益が期待できる
- 政府や地方自治体からの補助金により、初期費用を抑えられるケースがある
太陽光発電は再生可能エネルギー発電となるため、国が推進している背景があります。
「固定価格買取制度」があり、一定の条件を満たせば10年~20年(※)にわたり安定した収益を得られるのもメリットと言えるでしょう。
また、政府や自治体からの補助金で初期投資を抑えられるケースがあります。ただ、設置される自治体によって制度の内容は異なるため、事前調査は必ず行いましょう。
※10kW未満で10年間、10kW以上で20年間、固定価格で買取(2022年度の場合)
経済産業省 資源エネルギー庁
2-2-2.太陽光発電のデメリット
太陽光発電のデメリットは次のとおりです。
- 初期投資を回収するのにある程度の時間がかかるため、短期の土地活用には不向き
- 天候不順が続くと発電量が減ってしまう
- 周辺に建物が建ち、日当たりが悪くなると発電量が減ってしまう
- 経年劣化による発電効率の低下や、何かがぶつかったことによる機器の破損などもリスクとして考えられる
2-2-3.太陽光発電に向いている土地
よく日の当たる土地、郊外で活用予定がない土地、広大な土地など太陽光発電について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
2-3.借地
事業者や法人、個人に土地を貸し、賃料を収益とする土地活用方法もあります。
| 収益性 | 手間の 少なさ |
初期投資の 少なさ |
期間 | 節税効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 借地 | △ | ◎ | ◎ | 短期~長期 | × |
土地を貸す際には、立地や土地の形状、面積によりさまざまなニーズがあり、以下が一例となります。
- 店舗などを運営する事業者に土地を貸し、建物を建てて営業する
- 事業者に土地を貸し、建築資材置き場や重機の保管場所として活用する
- 個人に土地を貸し、貸農園や畑として活用する
なお、土地を貸す相手・用途によって気を付けるポイントや向いている土地は変わってきますので、ご注意ください。
2-3-1.事業者に土地を貸し、事業者が建物を建てる場合
店舗などを運営する事業者に土地を貸し、事業者が建物を建てて営業する活用方法です。
この場合、オーナー自らが建物を建てるわけではありません。
「事業用定期借地権」で土地を貸した場合、契約期間を10年~50年で設定し、契約期間が過ぎると建物を取り壊し、更地にした状態で土地を返還してもらいます。
ある程度、長期の契約が必要とされるため、安定した収益が期待できるのが特徴です。
「事業用定期借地権」については、こちらをご覧ください。
2-3-2.資材置き場や貸し農園として貸す場合
資材置き場や貸し農園、畑などの用途で土地を貸す方法もあります。
活用方法が難しい郊外の土地でも、場合によっては需要が見込めるでしょう。
建物が建てられない「市街化調整区域」でも土地活用を始めることが可能です。
資材置き場であればある程度の面積や前面道路の幅員、間口の広さなどが必要となりますが、貸し農園や畑であれば狭小地でも活用できます。
2-3-3.借地のメリット
借地としての活用は、基本的に賃料を設定して貸すだけなので、費用をかけずに収益を得たいと考えている方におすすめの方法です。
土地を貸す相手や利用方法によっても変わってきますが、主なメリットは以下のとおりです。
- 賃料を設定して貸すため、定期的に安定した賃料収入を得られる
- 建物(賃貸併用住宅、アパートなど)をオーナー自身が建てるわけではなく、ただ土地を貸すだけのため、基本的に初期費用が不要
2-3-4.借地のデメリット
借地のデメリットは次のとおりです。
- 建物賃料ほどの収益は見込めない
- 土地を貸す際には定期借地契約などの形で期間を定めて契約を結ぶこととなる。そのため、自己都合で返してもらうことができない
- 契約によっては土地の拘束期間が長くなるため、地価が上がっても自由に売却できない
2-3-5.借地に向いている土地
借地として活用する場合、立地や面積により需要が変わってきます。
いずれの場合も、借地は、借り手がいて成立するもの。そのため、その土地に合った需要の借り手がいることが絶対条件となります。
2-4.売却
持っている土地をすぐに現金化したい、手間をかけたくないのですぐに手放したいという場合は、土地を売却するのも一つの手です。
| 収益性 | 手間の 少なさ |
初期投資の 少なさ |
期間 | 節税効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売却 | – | ◎ | ◎ | – | – |
土地の全体を売却する方法もあれば、一部のみ売却することも可能です。
2-4-1.敷地全体を売却する
自宅の敷地全体を売却する方法です。
このパターンでは、オーナーご自身はコンパクトなマンションやシニア向け住宅等に住み替える方が多いです。
土地を売却すれば、売却資金としてまとまったお金を得ることができ、売却後は固定資産税を支払う必要もありません。ただ、その一方で、土地活用のように継続的な収入を得ることはできません。
また、長年住んできた、思い入れのある土地を売却してしまうことをデメリットと感じる方もいるでしょう。
2-4-2.敷地の一部を売却する
最後にご紹介するのは、広すぎる敷地の一部を売却する方法です。
その売却代金を使って家を建て替えることもよく行われます。
土地を2つ以上に切り分けることを「分筆」と言います。
分筆するときの注意点の一つは、測量費用が数十万円必要となり、時間もかかること(測量費用は面積や隣地所有者の数、立地によって異なります)。
もう一つの注意点は、どのような形状・面積で分筆するか決める際に細心の注意を払わなければならないということです。
売却する部分の面積が狭すぎて高く売れなかったり、手元に残す部分が使いにくくなると残念です。
土地の一部の売却を考えるときには、どのように分筆すればいいのか、信頼できる不動産会社に相談してから決める必要があります。
2-4-3.売却のメリット
売却には次のようなメリットが考えられます。
- 売却資金としてまとまったお金を得ることができる
- 売却後は固定資産税などのコストがかからない
- 売却後は管理の手間がかからない
2-4-4.売却のデメリット
売却のデメリットは以下のとおりです。
- 仲介手数料や登記費用、譲渡所得税といった費用がかかるため、事前にしっかり計算したうえで進めることが必要
- 思い入れのある土地を手放してしまう
3.信頼できる相談先の選び方
「家が広すぎる」「家の敷地が余っている」と感じて土地活用を始めるときには、どんなことに注意すれば良いのでしょうか。
土地活用には様々な選択肢があるため、土地の形状や面積、オーナーの要望に合わせて提案してくれるプロに頼るのがおすすめです。
信頼できる相談先を見つけるための、3つのコツをご紹介します。
3-1.相談先に要望を確実に伝える
最適な解決策を見つけるためには、土地活用の相談先にしっかり要望を伝える必要があります。
できれば優先順位もつけておくとスムーズです。
具体的には、次のリストをベースに考えてみてください。
- 暮らしやすいマイホームへ建て替えたいor今の家をそのまま残したい。
- 収益性を追求したいor高収益よりも手堅い収入を優先したい
- 初期投資の許容範囲はどれくらいか
- 手間をかけたくないor退職後のライフワークとして賃貸経営に携わりたい
- 長期的に任せたいor短期で止めるかもしれない
- 固定資産税や相続税を節税したい
上記のような要望を伝えた上で、土地活用のプロに総合的なプランを提案してもらうことをおすすめします。
3-2.相続税対策の必要性について検討しておく
2015年実施の税法改正により、基礎控除の水準が引き下げられ、相続税の課税対象者が広がっています。
昔は、「相続税がかかるのは大金持ちだけ」というイメージがあったかもしれませんが、現行制度では都心に広めの自宅を持っていれば課税対象となる可能性が十分にあります。
具体的には、相続財産の総額が「基礎控除額」を超える場合に相続税の課税対象となります。
さらに、2020年4月からは、配偶者が自宅に住み続けられる「配偶者居住権」などの新制度がスタートします。
(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html)
相続税が心配な場合はあらかじめ税理士等に相談した上で、土地活用による積極的な相続税対策を検討すると安心です。
なお、不動産会社の提携税理士等に相談できる場合もあります。
3-3.活用方法は比較してから選ぶ
自宅の土地を活用する場合は、多様な選択肢があるため、コンサルティング能力の高い企業に相談することが大切です。
自宅の土地活用では、「自宅を建て替えるかどうか」「敷地の何割を土地活用に使うのか」「どんな土地活用を選ぶのか」など、総合的な解決策を検討する必要があるからです。
提案力のある企業なら、オーナーの要望と「需要と供給」「エリアの法規制」「土地の面積・形状」も踏まえて、最適な活用方法を提案してくれるはずです。
ところが悩ましいことに、大手企業に相談したとしても、その提案内容がオーナーにとってベストとは限りません。
その理由の一つは、それぞれの企業の「得意分野」を勧められる確率が高いため。
もう一つの理由は、担当者の経験値には差があるからです。
そこで、リスクヘッジのためには、複数の専門企業に相談して提案内容を比較検討し、最も優れたプランを選ぶことが大切です。
提案を比較してみると、建築費の差や、想定家賃の妥当性、節税効果などの違いが見え、どの企業の提案が最善なのか見極めやすくなります。
複数のプランを比較したいときには、「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」の一括プラン請求を利用すると、様々な特色を持つ優良企業からまとめて提案を受けられます。
各企業から提案された設計プランや事業計画について、じっくり比較検討してみてください。
関連記事
-
土地活用で賃貸経営!種類別メリット・デメリットや成功のポイントも解説
- 2025.01.29
- アパート・マンション建築
-
- 2025.01.23
- アパート・マンション建築
- ノウハウ
-
寮の経営は賃貸ニーズ高め?土地活用で寮建設をする費用と6つのメリット
- 2025.01.24
- その他活用
-
- 2025.04.22
- アパート・マンション建築
- ノウハウ