
空き地には様々な活用方法がありますが、この記事では特におすすめの10個に厳選し、それぞれのメリット、デメリット、その活用方法が向いている土地、選びかた等のポイントもお伝えします。
- 1位:賃貸アパート・マンション経営
- 2位:戸建賃貸経営
- 3位:駐車場経営
- 4位:事業用の土地として貸す
- 5位:トランクルーム経営
メリット・デメリット、「おすすめの提携企業」をそれぞれご紹介しています。6位以降とあわせて「1.空き地におすすめの活用方法:空き地活用収益率ランキングトップ10」でご確認ください。
- 固定資産税、都市計画税がかかる
- 維持費用がいかかる
- 近隣トラブルが発生する可能性がある
上記3点の詳細は「2.空き地を活用しないことの問題点」をお読みください。
目次
1.空き地におすすめの活用方法:空き地活用収益率ランキングトップ10
空き地には様々な活用方法があります。ここでは特におすすめの10の活用方法をランキング形式でご紹介します。
(※一般的に高い収益性が見込める順とする)
【空地活用収益率ランキングトップ10】
1-1.【1位】賃貸アパート・マンション経営
安定して高い収益性が見込めるに加え、大きな節税効果が期待できるのが、賃貸アパート・マンション経営です。
更地に比べると、住宅の敷地は固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1になります。さらに、相続税の節税効果も抜群です。賃貸用の住宅が建っていると、土地の相続税評価額は約20%減額され、さらに要件を満たせば200平米まで50%減額される制度もあります。
マンションはアパートよりも建築費が割高になりますが、建物の性能の高さで差別化できるので、アパートよりも高い賃料と高稼働が期待できます。周辺エリアの賃貸ニーズを見極めて、アパートとマンションどちらにするかを決めましょう。
なお、空室リスクを減らすため、入居者のニーズを満たした魅力的な建築プランを設計することが重要です。賃貸経営に手間をかけたくない場合には、専門の管理運営会社に委託すれば、入居管理等の手間はほとんどかかりません。
アパート・マンションの建築をご検討中の方は「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」を使えば、最大10社から簡単に建築プランを手に入れられます。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
| 向いている土地 |
|
以下では、実際にアパート、マンション経営・建築に実績のある企業を紹介しています。ぜひご参考ください
賃貸アパート経営(建築)に強い企業
●株式会社セレコーポレーション
他のアパートとは一味違う、独創性のある欧風の赤レンガのデザインが特徴です。また首都圏エリアを中心とした、若者向けアパートを専門としているところも強みの一つになっています。
管理面においても、自社の弁護士や公認会計士などのプロフェッショナルが土地オーナーの課題を解決します。
引用元:セレコーポレーション 公式ホームページ
※2021年2月1日現在の情報です。
●大東建託株式会社
賃貸住宅管理戸数・賃貸仲介件数・住宅供給戸数すべてに圧倒的な実績を誇っています。
東日本大震災においては、強みである2×4工法で造られた住宅に大きな被害はなかったほど、耐震性は折り紙付きです。また入居者の関心度が高い「遮音性」については、独自開発の「ノイズレスシステム」により高い遮音性を実現しています。
引用元:大東建託 公式ホームページ
※2021年2月1日現在の情報です。
●三井ホーム株式会社
「三井不動産グループ」の一員である三井ホームは、豊富な建築実績と長年にわたる賃貸住宅の管理実績から蓄積されたノウハウが特徴です。
また、震度7連続60回の揺れにも耐え抜くほどの耐震性(警察署や消防署の強さに匹敵するほどの耐震性)も特徴の一つです。
引用元:三井ホーム 公式ホームページ
※2021年2月1日現在の情報です。
賃貸マンション経営(建築)に強い企業
●朝日建設株式会社
鉄筋コンクリート造により、高い耐震性・耐火性・遮音性を実現。
建築時に使用される断熱材EPSは、極寒の南極昭和基地でも使用されており、安全性に対する技術力が高い会社です。
引用元:朝日建設 公式ホームページ
※2021年2月1日現在の情報です。
●株式会社クラスト
コスト面の安さがこの会社の特徴です。長寿命かつ、住み心地の良い鉄筋コンクリート造でありながらローコストなので、予算を抑えたいけれど安全性にもこだわりたい方におすすめです。
間取りについても、多くの入居者の声を参考に支持率の高い配置を叶えており、高入居率を実現しています。また「無料管理」という独自のサービスにより、建築計画から入居者募集、建物のメンテナンスまでも無料でサポートしてくれます。
引用元:クラスト 公式ホームページ
※2021年2月1日現在の情報です。
●生和コーポレーション株式会社
建築だけでなく、企画から経営管理までトータルでサポートしてくれるという強みがあります。
またオーダーメイドにも定評があります。
引用元:生和コーポレーション 公式ホームページ
※2021年2月1日現在の情報です。
以上が、賃貸アパート・マンション経営に強い企業のご紹介でした。
もっと詳しくアパート・マンション経営について知りたい方は、以下の記事をお読みください。
1-2.【2位】戸建賃貸経営
戸建賃貸は、最近特に注目されている活用方法です。ファミリー層を中心に、足音や子どもの声などを気にせずにのびのびと暮らせる戸建賃貸は人気です。需要に対してまだまだ供給が少ないエリアが多いので、高稼働が期待できます。
戸建賃貸はアパート等に比べると建築コストを抑えることができます。戸建賃貸・アパート・マンションの需要と供給バランスの調査をした上で、どのような賃貸物件が適しているか検討しましょう。
戸建賃貸は、手放したくなったとき、エンドユーザーに中古一戸建てとして売却しやすいのも魅力です。敷地が広ければ、土地を分割して複数棟を建てて、一棟ずつ売却する出口戦略も可能です。
戸建賃貸経営について具体的にご検討中の方は「HOME4U オーナーズ」をご活用ください。最大10社のハウスメーカーから無料で収支プランが手に入ります。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
| 向いている土地 |
|
以下では、戸建て賃貸の経営・建築に実績のある企業を紹介しています。ぜひご参考ください
戸建賃貸経営に強い企業
●ヒノキヤレスコ(東京)※首都圏中心です。
高いコストパフォーマンスが特徴の会社です。
高い耐震性と耐久性を兼ね備えており、建設資材は大手メーカー品を一括仕入れなので、高品質で低価格です。そのため、初期投資を抑えつつ、安定的な高利回りを実現できます。
管理面では、土地オーナーのニーズにあわせて、土地診断から資金計画、物件建設、さらには物件完成後の入居者募集や家賃回収、建物メンテナンスに至るまでトータルにサポートしてくれます。
引用元:ヒノキヤレスコ 公式ホームページ
※2021年2月1日現在の情報です。
●悠悠ホーム
福岡県を中心とする地域密着の不動産流通工務店です。大手にはない、地域密着という強みを生かして、入居者を集めることができます。また設計・施工・賃貸管理までオールインワン対応、すべてアドバイスしてくれます。
FFCテクノロジーを利用し、ハウスダストの発生抑制や化学物質の無毒化など、美容や健康に配慮した建築も特徴の一つです。
引用元:悠悠ホーム 公式ホームページ
※2021年2月1日現在の情報です。
以上が、戸建て建築に強い企業のご紹介でした。
もっと詳しく戸建て賃貸経営について知りたい方は、以下の記事をお読みください。
1-3.【3位】:駐車場経営
駐車場経営には、月極駐車場とコインパーキングがあります。建物を建築しにくい、長方形でない土地や狭小地でも可能です。
アパート等の建物を建てる土地活用に比べると、ローリスク・ローリターンの活用方法です。
駐車場経営の具体的な収益シミュレーションは、「HOME4U オーナーズ」を使えば、最大10社の企業から無料で収支プランが手に入ります。
以下では、駐車場経営をお考えの方におすすめの企業を紹介しています。ぜひご参考ください
駐車場経営に強い企業
●タイムズ24株式会社
駐車場設計のプロフェッショナルである一級建築士が、商業施設や自治体施設などに併設された大型駐車場を対象に、遊休地であっても最適な駐車場を提案します。
機器設置や、開設後の集金・保守・清掃・24時間緊急対応(コールセンター)などはグループ会社が行います。また、駐車場の管理・運営はパーク24グループが責任をもって行うので、手間もかからず安心です。
引用元:タイムズ24 公式ホームページ
※2021年2月1日現在の情報です。
●日本パーキング株式会社
首都圏を中心に、全国主要都市にて時間貸駐車場・月極駐車場を展開しており、特に大型立体駐車場の開発・運営は業界随一の実力を有しています。
また、空き地の管理や駐車場の経営・管理も日本パーキング株式会社が行うため、土地オーナーへの負担はほとんどありません。
引用元:日本パーキング 公式ホームページ
※2021年2月1日現在の情報です。
●三井のリパーク
三井不動産リアルティグループの総合力で、将来的な土地の活用方法など、様々なサポートを行うことができます。
時間貸し・施設型・月極など駐車場経営の種類も多く対応しており、月極駐車場などの場合は管理をすべて会社に委託することができます。
引用元:三井のリパーク 公式ホームページ
※2021年2月1日現在の情報です。
以上が、駐車場経営に強い企業のご紹介でした。
もっと詳しく駐車場経営について知りたい方は、以下の記事をお読みください。
1-3-1.コインパーキング
土地のオーナーが機械を設置して運営することも可能ですが、専門業者に土地を貸して賃料を得る方式が一般的です。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
| 向いている土地 |
|
1-3-2.月極駐車場
不動産会社等に管理運営を委託することもできますが、土地オーナーの自営方式が一般的です。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
| 向いている土地 |
|
1-4.【4位】事業用の土地として貸す
事業用の土地として貸すというのは、店舗等を運営する事業会社に土地を貸して、事業会社が建物を建てて営業する活用方法です。
「事業用定期借地権」で土地を貸せば、契約期間は10年以上50年未満で設定できます。契約期間が終わったら、建物を取り壊し、更地にして土地を返還してもらいます。
一般的な借地契約では、正当な理由がないと契約は自動更新されてしまうので、確実に土地が戻ってこないリスクがあります。定期借地契約では、確実に契約期間どおりに土地が返還されるので安心です。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
| 向いている土地 |
|
| 立地 | ニーズ |
|---|---|
| 繁華街、駅の近くの土地 | 近隣型店舗など |
| 幹線道路沿いの大きな土地 | コンビニ、ファミリーレストラン、ガソリンスタンド、クリニックなど |
| 郊外の広い土地 | 高齢者向け住宅、老人ホーム、工場、作業場など |
1-5.【5位】トランクルーム経営
近年増えてきた土地活用方法です。自営も可能ですが、トランクルーム業者のフランチャイズや一括借り上げを利用するのが一般的です。
アパートなどが建てにくい変形地や、狭小地でも活用可能です。アパート等を建てるのに比べると、設置費用も少額で、運営後も維持管理費用はほとんどかかりません。
トランクルームとして利用するコンテナは建築物に該当します。コンテナを設置するためには、建築確認が必要ですので、遵法性に注意しましょう。「低層住居専用地域」や「市街化調整区域」など、設置できないエリアもあります。
トランクルーム経営が成り立つかどうかは、収納ニーズが多いエリアかどうかにかかっていますので、充分なリサーチが必要です。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
| 向いている土地 |
|
トランクルーム経営の具体的な収益シミュレーションは、「HOME4U オーナーズ」を使えば、最大10社から無料で収支プランが手に入ります。
トランクルーム経営に強い企業
●エリアリンク株式会社
全国に約80,000室のトランクルーム「ハローストレージ」を展開。ストレージ事業No.1の店舗数を誇ります。(矢野経済研究所『拡大する収納ビジネス市場の徹底調査』2016年版/全国版(国内))
契約後の運営・管理をすべて行うので、余計な手間がかかりません。
引用元:エリアリンク 公式ホームページ
※2021年2月1日現在の情報です。
1-6.【6位】太陽光発電を設置
建物の屋根の上ではなく、空き地に発電装置を設置する方法が、「野立て」太陽光発電です。ある程度の日あたりと送電線があれば、どこでも設置できるので、近年では定番の土地活用になりました。設置費用を回収するまでに10~15年程度かかるため、短期の土地活用には向きません。
発電量(kWh)は天候によって変動しますが、発電した電気は「1kWh=●円」の固定価格で買い取りしてもらえます。
狭い土地でも設置は可能ですが、10kW未満の設置だと売電価格は10年間の固定価格になります。産業用の10kW以上を設置すれば、売電価格は20年間固定されるので、長期の安定収入になります。10kWを設置するには40~50坪の面積が必要です。
太陽光発電による土地活用は、自費で発電設備を設置する方法と、運営会社に土地を定期借地で賃貸する方法があります。運営会社に土地を貸す場合には、設置費用や運営費用は運営会社負担になります。収益性は落ちますが、低リスクの運営方法です。100坪以上の土地面積があれば、用地を探しているソーラー発電運営会社は多いので、契約内容を比較して選んでください。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
| 向いている土地 |
|
太陽光発電に強い企業
●PHOTON JAPAN 合同会社
全国各地で太陽光発電所開発の実績を誇っています。またエネルギー業界や銀行、コンサルティングファーム、重電メーカーといった、プロジェクトファイナンスに精通した企業のメンバーが参画しているため、プロジェクトの実現性を高め、土地オーナーの利益を最大化できる強みがあります。
引用元:PHOTON JAPAN 公式ホームページ
※2021年2月1日現在の情報です。
1-7.【7位】コインランドリー経営
建物を建築して、コインランドリー設備を設置し、自営またはフランチャイズで経営します。洗濯機・乾燥機等の設備は、購入方式とリース方式があります。
「周辺に住宅地が広がり、競合するコインランドリーが近くにない」など、向いている立地はある程度限られます。狭い土地でも可能ですが、車を利用する利用者が多い地域では、余裕を持った駐車スペースが必要です。
コインランドリーの利用者は、自宅に洗濯機のない単身者だけではなく、ファミリー層にも市場が拡大しています。ファミリー層の多いエリアでは大型の洗濯機を設置し、単身者が多いエリアでは小型の設備を多数設置するなど、利用者のニーズを把握することが経営のポイントです。
コインランドリー事業が成り立つかどうかは、専門業者に市場分析してもらってから判断するのがおすすめです。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
| 向いている土地 |
|
1-8.【8位】資材置き場
建築資材置き場や、重機の保管場所として、土地を貸す活用方法です。土地をそのまま貸すだけなので、初期費用や手間もかかりません。
資材置き場の需要はどこでもあるとは限りませんが、他に使い道のない郊外の土地でもニーズが見込めます。契約書には、建物の建築を認めないことを明記しましょう。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
| 向いている土地 |
|
1-9.【9位】自動販売機を設置
自動販売機の設置から、売上回収・補充・空き缶回収まで、全て設置会社に任せる方式が主流です。この場合、設置費用等は設置会社が負担し、オーナーが負担するのは、月々2,000円~5,000円程度の電気代のみです。売上の20%程度の収入が得られますが、出来高制なので、収益性は販売本数によります。
アパート経営や駐車場など、他の活用方法と合わせて、自動販売機を設置できるスペースがあるかどうか検討するのも有効です。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
| 向いている土地 |
|
1-10.【10位】貸し農園
アパートや駐車場のニーズなどが少ない郊外でも営むことができます。狭小な土地にも向いています。
10坪以下の小さな区画に区切って複数の人に貸すと収益性が高くなりますが、そのぶん契約の手間が増えます。また、区画に区切る場合には、水道・柵等の初期投資が必要になることにも注意が必要です。敷地を一括して1人の人に貸す場合には、管理も楽で、初期投資もほとんど不要です。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
| 向いている土地 |
|
2.空き地を活用しないことの問題点
空き地を活用しないで放置しておくと、収益を生まないのでもったいないのは間違いありません。
空き地を放置しておくと問題になるのは、「税金」「維持費用」「近隣トラブル」の3つがあります。この章では、この問題について説明します。
2-1.固定資産税、都市計画税がかかる
使っていない空き地でも、所有者には毎年、固定資産税や都市計画税が課税されます。郊外の土地で、税金が安かったとしても、使っていない土地に払い続ける税金の総額を考えると、決して安いとはいえなくなります。
一つ、知っておきたい知識は、空き地に戸建住宅や共同住宅を建てると、土地の固定資産税等が安くなるということです。土地活用といっても色々ありますが、住宅を建てることによる節税効果は意識しておきたい部分です。
2-2.維持費用がかかる
空き地は、活用せず所有しているだけで維持費用が発生します。
使っていない土地だとしても何も手を加えないで放置しておくわけにはいきません。除草費用、清掃費用も積み重なれば無視できない金額になります。また、不法投棄の被害にあって、多額の処分費用が発生してしまう危険性もあります。
2-3.近隣トラブルが発生する可能性がある
空き地を放置しておくと、害虫が大量発生して近所からクレームが入ることがあります。また、子どもが勝手に敷地に入ってケガをしたり、犯罪の現場になったりするリスクもあります。使っていない土地だと思われると、ペットの散歩コース、トイレ代わりに利用されることも珍しくありません。すぐに使う予定がない土地でも、あまり気分のよいものではありません。
特に住宅街の中の空き地は、景観がよくないため、ご近所からの印象も悪くなりがちです。空き地の有効活用は、無用なトラブルに巻き込まれないための自衛手段といえるでしょう。
3.田舎の空き地活用の注意点
田舎の空地活用の注意点は以下3点です。
3-1.農地転用の必要があるか
土地活用を検討している土地の「地目」が「農地」の場合で、農地以外の活用を検討している場合は、転用許可を得る必要があります。
農地には複数の種類があり、下表のように「転用できない農地」と「転用できる農地」が定められています。
| 種別 | 定義 | 許可の方針 |
|---|---|---|
| 農用地区区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備区域内において農用地区域とされた農地 | 原則不許可 |
| 甲種農地 | 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等の特に良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可 |
| 第1種農地 | 10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等の良好な営農条件を備えている地域 | 原則不許可 |
| 第2種農地 | 鉄道の駅が500m以内にある等の市街地化が見込まれる農地または生産性の低い小集団の農地 | 周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可 |
| 第3種農地 | 鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域または市街化の傾向が著しい区域にある農地 | 原則許可 |
「地目」は登記や、固定資産税の納税通知書に同封されている「課税明細書」もしくは「評価明細書」にて確認ができます。
3-2.管理ができる距離にあるか
土地活用の種類によっては、維持・管理のために定期的に訪問する必要があります。管理ができる距離かどうかも検討内容にふくめましょう。
3-3.固定資産税を賄えるか
土地活用の方法により、収益性が変動するため、事業計画の段階で、固定資産税額を賄えるかをシミュレーションする必要があります。
固定資産税の試算方法については、以下をご確認ください。
田舎の空き地活用については、こちらの記事でも解説しています。ぜひ参考にご一読ください。
4.お金のかからない空き地活用アイデア
1章で紹介した空地活用収益率ランキングトップ10以外にも「お金のかからない」空地活用アイディアが2つあります。
- 空き地のまま貸す
- 建設協力金方式で賃貸事業
4-1.空き地のまま貸す
空地のまま貸すという選択肢もあり、以下のメリット、デメリットがあります。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
4-2.建設協力方式で賃貸事業
もう一つの選択肢は「建設協力金方式」という方法です。
コンビニやロードサイド店舗等の商業系の建物で採用されることが多い手法で、ざっくり言うと、テナントからお金を借りて、完全所有の建物をテナントに建ててもらう事業方式です。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
5.空き地活用する際に確認しておくこと
空地を活用する際に確認しておくべき「3つの観点」について説明します。
5-1.法規制を確認する
土地活用を決める大前提となるのが、その土地の法規制です。代表的な法規制は次の3つです。これらの法規制を踏まえて、合法的な活用方法の中から、どれがいいか考えます。
5-1-1.「市街化区域」か「市街化調整区域」か?
市街化調整区域は基本的に建物を建てられないエリアです。ただし、条例によって、コンビニ等の特定の建物が建てられる場合もあります。
5-1-2.「用途地域」
その土地に建てられる建物の用途を定めたもの。用途地域は12種類あります。
例えば、「第一種低層住居専用地域」は低層住宅のための地域なので、店舗は建てられませんが、小規模なお店を兼ねた住宅は建てることができます。
「商業地域」は飲食店や銀行などが集まる地域ですが、住宅や小規模の工場も建てられます。アパート等の住宅が建てられないのは「工業専用地域」だけです。
【参考:「東京都都市整備局「用途地域による建築物の用途制限の概要」】
5-1-3.「容積率」「建ぺい率」
その土地に建てられる建物の大きさの上限を定めたもので、エリアによって、建築可能な建物の大きさには、かなり違いがあります。
- 容積率:敷地面積に対する延床面積の割合
- 建ぺい率:敷地面積に対する建築面積の割合
5-2.周辺ニーズ を確認する
次に、重要なのが、周辺ニーズを踏まえた土地活用を考えることです。
例えば、法令上はアパートが建てられる土地でも、競合アパートが多すぎる場合は、駐車場として土地活用する方が高収益を見込めるケースもあります。同じ用途の競合物件がどれくらいあるのか、周辺の需要と供給のバランスを考慮することが大切です。
周辺ニーズについては、地域に精通した不動産会社や、専門業者(トランクルーム運営会社、コインランドリー運営会社など)の意見を聞いてみるとよいでしょう。
5-3.土地活用の目的を確認する
最も重要なことは、「あなたに合った土地活用方法であるか?」という点です。あなたは土地活用に何を求めますか?
- 初期投資をしてもいいので、高収益を得たい
- 初期投資費用を抑えたい
- 手間をかけたくない
- できるだけ長期間、安定運用したい
- 10年だけ土地活用したい
- 相続対策がしたい
- 親族が使うかもしれないので、いつでもやめられる活用方法を探している
人によって、土地活用に求める目的や考え方が違うはずです。これらの土地オーナーの意思を反映した活用方法でなければ、ベストの選択肢とはいえません。手段が目的にならないよう、目的の再確認をしましょう。
6.空き地活用は複数のプランの比較検討が成功のカギ
空地の土地活用を検討する際には、はじめから一つの会社に決めてしまうのではなく、複数のハウスメーカーや建築会社の建築プランをできるだけ数多く入手し、内容を比較してから、納得いく会社を探し出すようにします。
複数プランを比較・検討するには、日本全国のハウスメーカーや建築会社の中から、一度の入力で最大10社まで絞り込んで相性の良い会社を提案してくれる「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」の一括プラン請求をご利用ください!
土地活用に関する実績と経験が豊富なハウスメーカーや専門企業などから提案を受けることで、思いもよらなかった活用方法が見つかる場合もあります。
土地活用関連記事、土地活用法系記事一覧
- 【基礎から解説】土地活用の方法22選!パターン別のおすすめ活用法
- 【徹底解説】23種類の地目・用途地域の調べ方と、対応する活用法
- 【プロが厳選】空き地の活用方法おすすめ10選!メリット・デメリットを解説
- 【40坪の土地活用】立地別おすすめ活用法13種類を徹底解説!
- 【徹底解説】東京の土地活用 立地別おすすめ活用法15種
- 【徹底解説】50坪の土地活用 立地別おすすめ活用法13種
- 【徹底解説】大阪の土地活用 立地別おすすめ活用法15種
- 非公開: 【徹底解説】田舎の土地活用 山林・農地・宅地等、土地の種類別おすすめ活用法20種
- 【徹底解説】狭小地の土地活用 立地別おすすめ活用法21種
- 【徹底解説】60坪の土地活用 立地別おすすめ活用法15種
- 【徹底解説】100坪の土地活用 立地別おすすめ活用法10種
- プロに聞く土地活用の秘訣!成功する2割のオーナーが必ず行っていることとは?
- 不動産活用方法おすすめ23種類を解説!資産有効利用に役立つ事例とは
- 【徹底解説】300坪の土地活用 立地別おすすめ活用法9種
- 【基礎から解説】土地オーナー向け!利回りの高い土地活用法
- 非公開: 【土地活用の方法】成功するための土地活用の種類とアイデアを紹介
- 【徹底解説】短期の土地活用 立地別おすすめ活用法9種
- 20坪の土地活用アイデア16選!狭い土地でも利益を上げる活用法
- 【徹底解説】遊休地を活用するには?おすすめ活用法13種
- 【基礎から解説】田舎の土地活用で成功する方法|田舎の土地を収益化するアイデア


















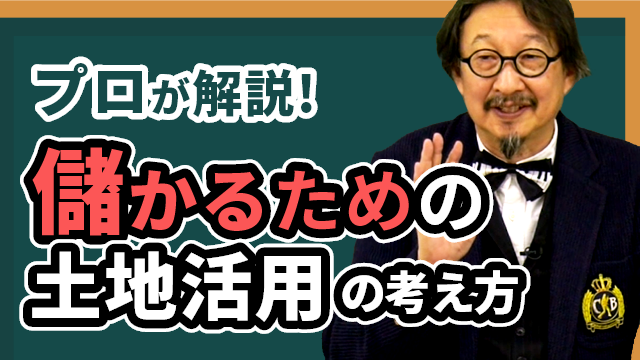

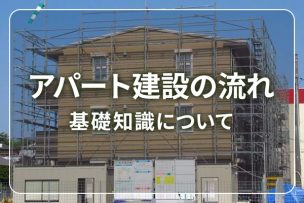

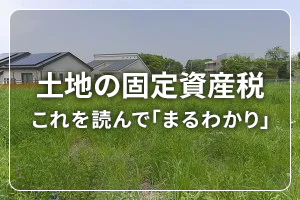




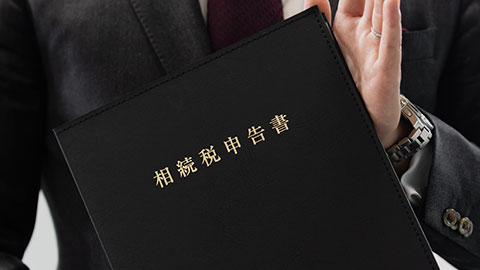













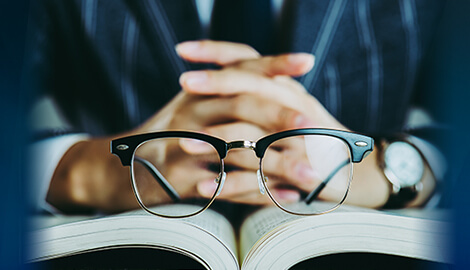






この記事のカテゴリトップへ